
【読者参加型】
コンゲツノハイクを読む
【2023年6月分】
ご好評いただいている「コンゲツノハイクを読む」、2023年もやってます! 今回は11名の方にご投稿いただきました。ご投稿ありがとうございます。(掲載は到着順です)
清明の大空仰ぐものわすれ
山尾玉藻
「火星」2023年5月号(通巻1000号)より
清明は二十四節気のひとつで、4月5日ごろ。万物が清らかで生き生きとしている季節だ。上五中七の「清明の大空仰ぐ」という気持ちのいい措辞からの、下五の「ものわすれ」で読者は仰天する。空を仰いだのは、思い出したいことをなかなか思い出せないときの、あの中空を見上げる仕草だったのだ。ひらがな「ものわすれ」によって、認知症という言葉を連想するような深刻さからは遠く、加齢を穏やかに受け入れている雰囲気を感じる。おおらかで、すこやかで、かつ面白い一句だ。
(千野千佳/「蒼海」)
花の下皮一枚の嬰眠り
岡辺明代
「南風」2023年6月号より
花の下に嬰が眠っています
乳幼児のみずみずしく透き通る肌を皮一枚と表現した力技
ここで句の様相は一転しました
皮と言うことで、骨、肉、流れる血が想像されます
グロテスクといえば、そうかもしれません
けれども、それが生の命です
穏やかな幸福感に満ちた光景に、すっと剃刀を走らせたかの中七が、「即物」の中身を現出させました
その上で、この句の湛える品位に打たれます
皮一枚への驚きは敬意になり感謝になり、やはり愛情へ帰結しているのです
(土屋幸代/「蒼海」)
差しで飲みレシート長し春の雨
竹本光雄
「鷹」2023年6月号より
コロナの間会えず仕舞の旧友と、二人で昼の居酒屋へ。三年も溜まった話題堰を切り、世界情勢、温暖化。果ては己の病気自慢。取り敢えずビールで始めポッピーの中身・外身と杯重ね。シロ、カシラ、ハツ、ナンコツと果てしなく。あっという間に時は過ぎ、尽きぬ話題もそろそろ尽きて、気づけば既に夜も更けて。奢る奢らぬ争いで勘定書を奪い合い、予定調和の割り勘に。店を出てみりゃ春の雨。「春雨じゃ濡れていこう!」と洒落込んで、傘もささずに梯子酒。明ければ酷い二日酔い。後には長いレシートが、悔いの証と残される。
「竹本」さんの句なので義太夫風に語ってみました。
(種谷良二/「櫟」)
人上手くよけられぬ日や涅槃西風
飛田小馬々
「稲」2023年5月号より
狭い歩道を我が物顔で歩く人たち、猛スピードで歩道を走る自転車。歩くことより、人を上手くよけない人をよけるのに疲れる。歩いて出かけるときには、遠回りになっても人通りの少ない歩道を歩こう。そうすれば、人を上手くよけられない日はない。そんなことを考えていた。その考えていたことが俳句になって現れた。なんという偶然。ひりひりする読後感。これを書いているのは六月。季節外れの涅槃西風が吹いてきた。インターネットの最深部と西方浄土は繋がっているのかも知れない。
(高瀬昌久)
煙草くさく香水くさく酒くさく
佐藤知春
「楽園」第3巻第1号より
東京には臭いがない。いや、実際にはあるのだろうが、それらは私の生活から注意深く排除されている。体臭、尿臭、腐敗臭……。人が生きたり病んだり死んだりすれば当然漂ってくるであろうそれらを、あたかも無いものであるかのように、違う世界のものであるかのように、私も含め多くの都市生活者は考えている。しかし時々、そのような異様なまでの無臭にも一種の息苦しさを感じ、程よくにおいのする空間へ出て行きたくなるのだろう。本気で「臭い」とまでは行かないけれど適度に「くさい」、煙草と香水と酒のにおいの漂う空間へと。
(西生ゆかり/「街」)
書込みの多き古本春の月
久保千恵子
「稲」2023年5月号より
大学が神田の古本屋街の近くだったので、古本屋にはよく通った。大学一年生の時に、文庫本と新書本の専門の古本屋で、初めて、古本を買った。値段が安かったので、本を開くと線を引いたところや書込みがたくさんあった。最初は不快だったのだが、本を読み終えて、線が引かれた部分や書込みを読むと、以前の持主の思いを慮り、彼(彼女)と対話している気分になってきた。こういうあえやかな交流には、春の月がふさわしい。
(加瀬みづき/「都市」)
ガラスペンポップな青の浅き春
竹岡俊一
「ホトトギス」2023年6月号より
ガラガラスペン ペンポップ
青の浅きペンポップ
ガラススペスペ ラスペンポ
ラスペンポップ ペンポップ
ポップな青の浅き春
ガラスペンペン ペンポップ
ポップな青の浅き春
あおのあ あさきあ はるはるはる
あおのあ あさきは はるはるはる
あおのあさきは はるはるはる
あおの あさあさ
朝来 あぁ春
ポップな青の浅き春
ガラガラスペン ラスペンポ
ガラスペンペン ペンポップ
ガラスペン ポップな青の浅き春
(月湖/「里」)
受験票鉛筆五本大試験
山本依子
「円虹」令和5年6月号より
大試験会場の机の上を想像した。受験番号が見えるように受験票、その横に鉛筆が五本揃えて置かれている。緊迫した試験会場の空気が漢字のみの表記から伝わる。また、単語をぽんぽんぽんと並べた句のつくりからは、大試験に向けて最終チェックをしている様子も浮かんだ。忘れ物はないか、声に出して確認する。私も外出の際は「携帯財布鍵PASMO」と呪文のように唱える。自然と七五調になってしまうのは、日本で生まれ育った身体に染みついているリズムだからだろうか。馴染みのリズムで心を整えれば、きっと大切な試験も普段通りに全力を出し切れることだろう。
(笠原小百合/「田」)
顔のないわたしが産んだ無人島
月波与生
「楽園」第3巻第1号より
顔のないものが無人島を産むのなら、顔のあるものが産むのは有人島であろうか。
人は基本的には自分の顔を知らないものだとして、自分の顔がどんなものかは他者がいることでわかる、或いは他者によって定まる、と言えるのではないだろうか。
乱暴であるかもしれないけれど、他者がいなければ顔がないと言ってしまえるのではないか。
つまり「顔のないわたし」が既にして無人島なのである。
無人島が産むのはやはり無人島なのだ。
そして顔のないものは名前も持たないだろう。
誰も知らない本当の孤島の無人島。
人喰い島の可能性もあるだろうか。
産むではなく「産んだ」がよい。
そこにはもはや母親さえも、顔を与え名を与えてくれる母親という他者はいない。
(田中目八/「奎」)
うすらひのつかれゆすられ忘れらる
森あおい
「南風」2023年6月号より
薄氷の観察句として、もちろん成立している。人は薄氷を見つけたら、最初は目新しくて踏んでみたり、つついてみたりする。人の悪戯に薄氷は疲れを感じているかもしれない。さんざん弄んだのに、人はやがてそれぞれの場所に向かう。そこに薄氷があったことなんて歩いているうちにすっかり忘れられてしまうのだろう。ら行のひらがなの調べが、やがて水へと還る薄氷の心許ない様子を想像させる。
「つかれ」「忘れらる」という言葉から、薄氷に自分自身の憂いを投影しているようにも思える。倦怠感、不安感が妙に気になった。寒さの残る春にほんの一瞬過った、ちょっとした春愁であろうか。
(藤色葉菜/「秋」)
一つ一つ貌見て薯を植ゑにけり
新治 功
「南風」2023年6月号より
種薯を手に取り、指の腹にその肌合や固さを確かめ、くるりと返してそれを目視する。丁寧な仕事ぶりがユーモアと共に伝わって来る。なんと言っても掲句の肝は「貌」だ。面と向かっている人と人の如く、そこには意思の疎通があるのだろう。そしてその境地に到るまでの「薯」と人との関わりの長い歳月までも感じ取られる。豊かな実りと、このような関わりが未来永劫に続いて行くことへの祈りのこめられた一句だと思う。
(加能雅臣/「河」)
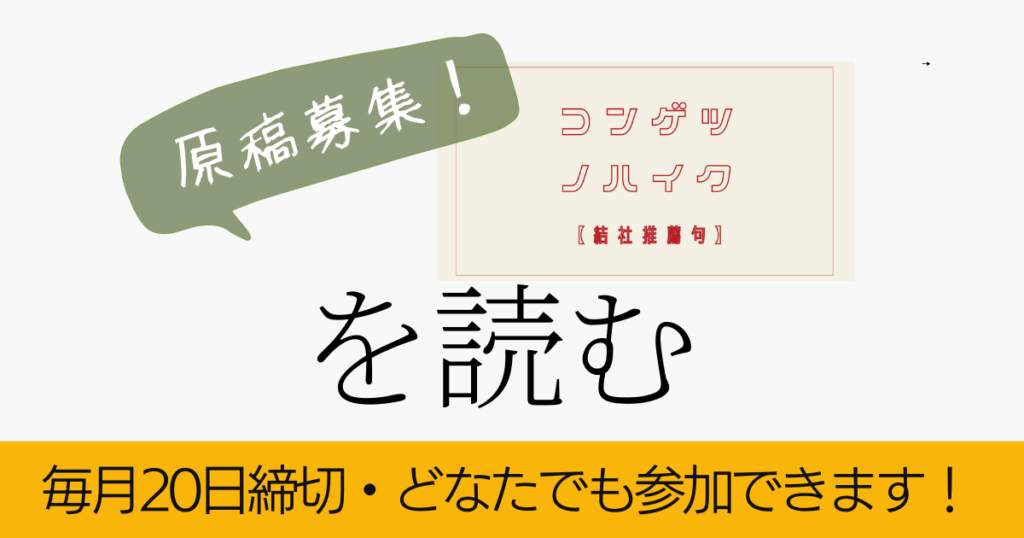
【セクト・ポクリット管理人より読者のみなさまへ】
