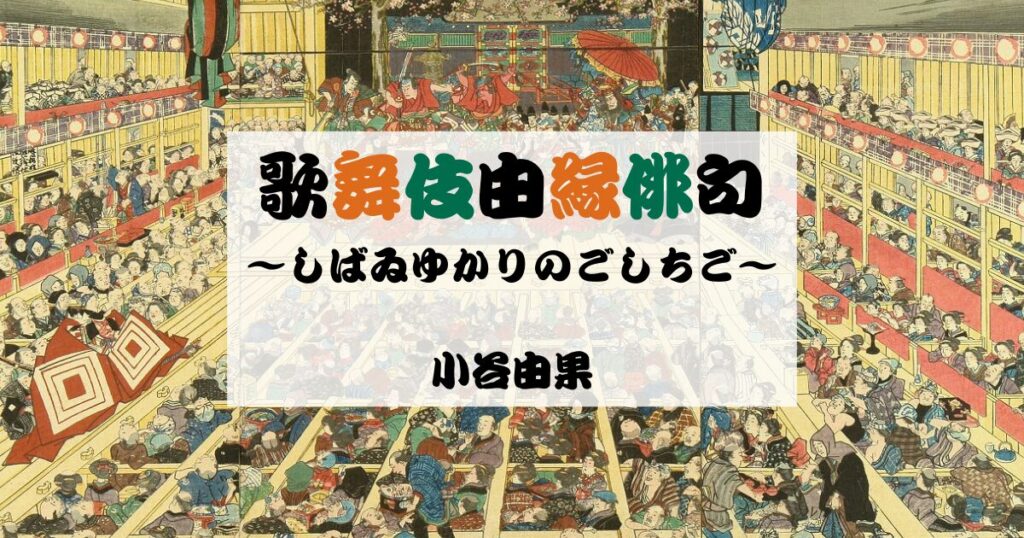
【第13回】
『義経千本桜』の和歌と俳句

(2025年10月1日 歌舞伎座『義経千本桜』初日)
今月10月は、1日から歌舞伎座で『義経千本桜』が上演されている。
『義経千本桜』は、通常各幕が見取り狂言として別々に上演されることが多いが、今年2025年は松竹創業130周年記念として、歌舞伎の三代名作である『仮名手本忠臣蔵』『菅原伝授手習鑑』『義経千本桜』を一挙に通し上演しており、今月はその最後を飾る『義経千本桜』の通しである。
『義経千本桜』とは
『義経千本桜』は、平安時代末期、源平合戦で平氏一門を滅ぼした源九郎判官義経が、兄頼朝から謀反を疑われ都落ちしていく流転を軸に、実は生き残っていた平家の武将や、義経の恋人の静御前、その静御前の守護を託された義経の家来の佐藤忠信(実は源九郎狐)など、幕ごとに異なる主人公をドラマチックに描く歴史ロマンである。
初演は延享4年(1747年)11月の竹本座で、約280年を経た今も、各家の型(澤瀉屋型・音羽屋型)や役者の藝が継承工夫されて上演されており、非常に人気のある演目である。
あらすじは以下の通りである。
義経が平家を討伐し、後白河法皇に報告すると、法皇の側近から褒美に「初音の鼓」を与えられるが、そこには鼓の両面を兄弟になぞらえ、兄頼朝を「討て」との謎がかけられており、それが兄弟同士討ちの企みと察した義経は鼓を打たずに持ち帰る。しかし兄頼朝から謀反の疑いをかけられ、義経は都落ちして西国へ向かう。その際、形見として恋人の静御前に「初音の鼓」を与え、家来の佐藤忠信には静御前の守護を託して自らの鎧と姓名「源九郎義経」を与える。静と忠信は、初音の鼓と鎧を携えて義経が匿われている吉野山の川連法眼の館に向かう。その川連法眼の館で、佐藤忠信は実は「初音の鼓」の皮にされた夫婦狐の子で、親恋しさから佐藤忠信に化けて静についてきたことを白状し、義経は狐に初音の鼓を与える。狐は喜び、義経を討ちに来た衆徒を通力で退治する。これが静御前と佐藤忠信(実は源九郎狐)が主人公の幕「鳥居前」「吉野山」「川連法眼館」のあらすじである。
一方、義経はここまでの道中で、大物浦の船問屋「渡海屋」の主人になりすました平知盛から、平家一門の恨みを晴らすべく戦いを挑まれ、知盛は敗色が濃くなり、平家再興を断念して自害。その船問屋に匿われていた安徳帝は乳母の典侍局からともに入水をすすめられるが、これを義経一行が引き止め、典侍局が自害すると、安徳帝は義経が守護し、帝の母である建礼門院に預け出家させる。これが知盛と安徳帝が主人公の幕「渡海屋・大物浦」のあらすじである。
しかし、この他の幕「木の実・小金吾討死」「すし屋」には、義経は登場しない。平維盛の隠れ住むという高野山に向かう維盛の妻子と家来の小金吾、維盛の父・重盛に恩のある釣瓶鮓の弥左衛門とその息子の“いがみの権太”をめぐる物語。弥左衛門の息子の権太は、ならず者で勘当されて家出をしており、小金吾の金をゆすったり、家に来て母にお金をせびったりしていた。権太は弥左衛門が帰ってくるのを見て母からせびった金を鮓桶に隠した。一方弥左衛門は、すし屋の下男・弥助として実は維盛を匿っており、小金吾が追手に捕まり討たれると、その首を維盛の代わりに鎌倉方に差し出そうと首を持ち帰り鮓桶に隠した。そこへ偶然維盛の妻子が尋ねてきて、権太の妹お里は、恋仲の弥助の正体が維盛と知り、維盛と妻子を逃す。権太は鮓桶を持って後を追う。その後鎌倉方の梶原景時がすし屋に来たので、弥左衛門が鮓桶を開けると、金があるばかり。そこへ権太が維盛の首と維盛の妻子を携えて現れ、褒美をもらいたいと言うと、弥左衛門は怒りで権太を刺す。しかしその首は実は小金吾で、妻子は権太自らの妻子であった。権太も弥左衛門の企みに気づいていた。梶原が権太に褒美として渡した頼朝の陣羽織の襟裏には、「内や床しき、内ぞ床しき」と書いてあり、陣羽織の縫い目の内を見ると、袈裟と数珠。頼朝も維盛を出家させ逃がそうとしていた。維盛は出家し、権太は改心遅く絶命する、というあらすじである。
『義経千本桜』に登場する和歌
この『義経千本桜』には、重要な場面で3首の和歌が登場する。
1つ目は、「渡海屋・大物浦」の場で安徳帝が詠むこの歌である。
今ぞ知る御裳裾川の流れには浪の底にも都ありとは
知盛の敗色が濃くなり、知盛に匿われていた安徳帝は乳母の典侍局からともに入水をすすめられ、この歌を詠む。
御裳裾川とは、伊勢神宮の五十鈴川の別名で、皇統の流れに譬えたもの。「天照大神の流れを汲む天皇の身として、波の底にも都があるなどということを今初めて知った。こういう悲しい最期になろうとは、今まで気づかなかった」という意味である。
今回、坂東巳之助の子である守田緒兜(7歳)が初お目見得でこの役をつとめ、立派に詠み上げお見事であった。
なお、この歌は「長門本平家物語」には、安徳天皇の祖母である二位尼の辞世として載っている。
2つ目の歌は、「すし屋」の場で、維盛の科白として登場する。
雲の上はありし昔に変わらねど見し玉簾の内や床しき
維盛(実は小金吾)の首への褒美として、梶原景時が権太に渡した頼朝の陣羽織の襟裏に、「内や床しき、内ぞ床しき」と書いてある。すると維盛は、
「この歌は小町が詠歌、雲の上はありし昔に変わらねど、見し玉簾の内や床しき、とありけるを、その返しとて、人も知ったるこの歌を、物々しゅう書いたるは心得ず。ことに梶原は和歌に心を寄せし武士、内や床しき、内ぞ床しき。ムゝ、この羽織の縫目の内ぞ床しき。」
と言って、襟の縫い目を切りほどくと、内には袈裟念珠。そして羽織の裏を切りほどくと、浄土の袈裟衣、水晶の数珠が出てくるのである。
なお、科白の中では「小町が詠歌」とされているが、謡曲「鸚鵡小町」では、陽成天皇が小野小町に送った歌とされ、小町はその下の句の「内や床しき」を「内ぞ床しき」と一文字だけ改めて返歌を「鸚鵡返し」した、とされている。
「宮中は昔と変わらないけれど、見慣れた御簾の内側が恋しくはありませんか?」という意味である。
3つ目は、「吉野山」の場で静御前と忠信が掛け合うこの一首である。
春立つといふばかりにやみ吉野の山も霞みて今朝は見ゆらん
忠信が「春立つといふばかりにやみ吉野の」と詠みかけると、静が「山も霞みて」、そして両人で「今朝は見ゆらん」。これは『拾遺和歌集 巻第一』に収められている壬生忠岑の歌である。この場面では吉野の桜が咲き誇っているが、歌自体は立春の頃を詠んでいる。まだ雪深い吉野の山も、暦の上で立春というだけで今朝は霞んで見えるようだ、という意味である。
『義経千本桜』にまつわる俳句
『義経千本桜』の中に俳句は登場しないが、歌舞伎役者や俳人が詠んだ『義経千本桜』にまつわる俳句がある。
忠信と靜の汗のおびただし 中村吉右衛門
役者が役者を観察している珍しい視点の句。少し艶っぽさも感じるので、忠信と静の道行「吉野山」の場を想像したが、「鳥居前」「吉野山」「川連法眼館」のどの場のことかは書かれていない。いずれの場でも衣裳を何重にも着ている忠信と静。照明も当たる舞台の上で、汗はおびただしく出るだろう。特に忠信は、肉襦袢を着たり踊ったり、早替りのために何枚も衣裳を重ね着したり激しい動きのケレンや宙乗りまであり、かなり汗をかく。実際、今月の忠信の市川團子も、汗で白粉が溶けて白い汗が衣裳に滴り落ちるほどで、光が当たって輝いていた。
また、「すし屋」の場を詠んだ水原秋櫻子の句がいくつか残っている。
鮎鮓や吉野泊りは夜の長き
維盛が鮓桶になふ葛の花
鮓桶を抱へし見得や月落ちて
鮎のぼる噂を聞けり釣瓶鮨
いずれも明治座や歌舞伎座の筋書に掲載された句。「鮓」も季語なので全句季重なりだが、舞台上の「すし屋」の鮓自体は季感がないものとして扱っている。舞台を詠む際の季節は、舞台上の季節か実際の今の季節かを悩むものだが、この句群では舞台を見た時の季節を充てている。秋櫻子は歌舞伎好きで歌舞伎俳句も多く残しているが、『義経千本桜』についての句は「すし屋」しか詠んでいない。好きな場だったのかもしれない。
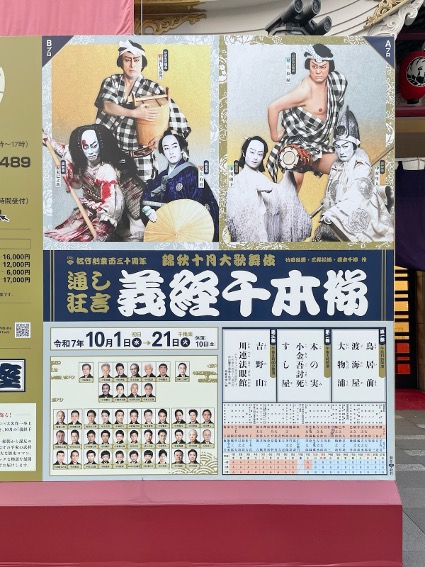
(歌舞伎座前の看板)
さて、今月の『義経千本桜』で特に話題になっているのが、「鳥居前」と「川連法眼館」の場で佐藤忠信(実は源九郎狐)を初役で演じる市川團子。特に「川連法眼館」の場は、原作全五段の四段目の切に当たり通称「四の切」と呼ばれ、四の切の狐忠信は、市川團子の祖父である二世市川猿翁が、宙乗りの演出を復活させライフワークとして最も演じてきた当たり役の一つ。その「澤瀉屋型」の四の切を、21歳の若き團子が初役として演じるとあって、大きな注目を集めている。
私は、記念すべき初役初日の1日に花道横の最前列、4日に宙乗り“お迎え席”の3階で観たので、舞台上の表情に加え、宙乗りの姿も近くで観ることができた。猿翁が残した詳細で膨大な映像や資料をみっちり研究し稽古を重ねた團子は、狐忠信の独特な「狐詞」の科白まわしやしぐさ、ケレンや宙乗りまで、初役とは思えない出来。團子の持ち味である真っ直ぐさや可愛さも狐忠信の姿に表れていて、宙乗りで桜吹雪を全身に浴びる表情から、演じることが心の底から嬉しく楽しそうなのが伝わってきた。全身全霊をかける情熱が汗となって光り輝き、瑞々しさが眩しい、胸を打たれる舞台だった。

今月の歌舞伎座『義経千本桜』は10月21日まで。10月11日以降はAプロからBプロへ役者が入れ替わるので、前半後半どちらも楽しみである。(気になる方は「歌舞伎美人」をご参照ください!)
<参考文献>
『名作歌舞伎全集 第二巻 丸本時代物集 一』(昭和43年、戸板康二ほか監修、東京創元社)
『義経千本桜』(平成3年、原道生編著、白水社)
『歌舞伎歳時記』(昭和33年、戸板康二著、知性社)
『中村吉右衛門定本句集』(昭和30年、中村吉右衛門著、便利堂)
『芝居の窓』(昭和61年、水原秋櫻子著、東京美術)
(小谷由果)
【執筆者プロフィール】
小谷由果(こたに・ゆか)
1981年埼玉県生まれ。2018年第九回北斗賞準賞、2022年第六回円錐新鋭作品賞白桃賞受賞、同年第三回蒼海賞受賞。「蒼海」所属、俳人協会会員。歌舞伎句会を随時開催。
(Xアカウント)
小谷由果:https://x.com/cotaniyuca
歌舞伎句会:https://x.com/kabukikukai
【PR】松竹株式会社様にご監修・図案提供を賜り、奈良墨工房 錦光園様に製造をいただき、筆者がディレクション・デザインをさせていただいた、香る奈良墨「隈取香墨」を販売中。

https://kinkoen.shop/?mode=grp&gid=3014590