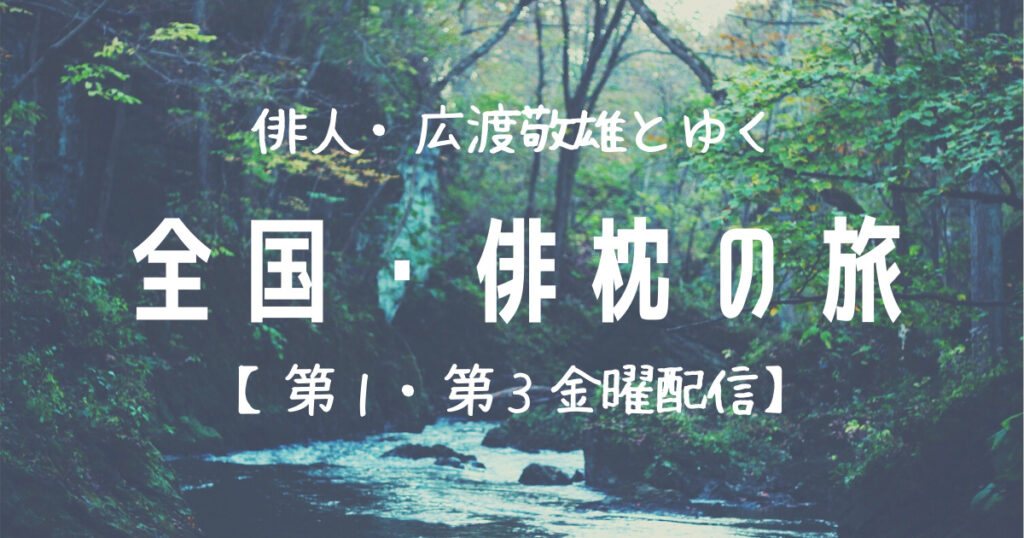
【第69回】
東吉野村と三橋敏雄
広渡敬雄
(「沖」「塔の会」)
奈良県東部の東吉野村は、台高山脈の北辺、高見山の西側に位置し、神武天皇ゆかりの伝承の史跡(鳥見霊畤)であり伊勢街道、紀州藩参勤交代の道として発展してきた。
幕末一八六三年 に大和国五条で挙兵した勤皇・天誅組が当地鷲家口で幕府側彦根藩兵と戦い、総裁の吉村寅太郎らが死亡し、天誅組は壊滅したが、明治維新の先駆けと言われる。日本最後の「ニホンオオカミ」が捕獲され、現在は大英博物館で標本になっている。

又当地小には、「ホトトギス作家」で「鹿火屋」主宰となった俳人原石鼎の上京前の旧宅(石鼎庵)があり、村をあげて俳句誘致に努め「俳句の里」として多くの俳人の句碑巡りが楽しめ、「深吉野賞俳句大会」も開催され、「天好園」も俳句の宿として知られる。(※は村が建立した句碑)

絶滅のかの狼を連れ歩く 三橋敏雄※
頂上や殊に野菊の吹かれ居り 原 石鼎※
鷹舞へり青嶺に隠れ現れて 右城暮石
日の神が青嶺の平ら照します 山口誓子※
霊地にて天降るしだれざくらかな 能村登四郎※
千年の杉や欅や瀧の音 草間時彦※
おのづから人澄む水の澄める里 後藤比奈夫※
深吉野の闇かきわけて蛍狩 鷹羽狩行※
〈絶滅の〉の句は、第二句集『眞神』収録、ちなみに眞神は狼の古称で、敏雄の代表句として広く愛唱されている句。「明治三十八(一九〇五)年、現在の奈良県東吉野村鷲家口で捕獲された一頭の若い雄の狼が最後の日本狼となったとの記録を読み、一挙に同地を訪ねたいと思ったが、永い間果たせない思いが積もるうち、想像の世界にまぼろしの狼をとらえた。いつしか私は一頭の狼を連れて、かの地深吉野の山中を歩いていた」と自註にあり、当地の名勝七瀧八壺に句碑がある。

「掲句の狼は、三橋の心象のそれであり、祖先たちが神と呼び、畏怖し崇め、共に生きとし生きて来たものへの追悼、寂寥の句」(松谷富彦)、「三橋の生き方として、狼的なものを常に心に置いており、俳句に置いて〈一匹狼〉の様に、独自のものを追求する匹狼、群れに属さない批判精神の表れ」(荒木みほ)、「この絶滅の狼は、豊かに稔ったとは言い難い新興俳句の喩えであろうか。敏雄は忘れない男である。幻の狼を連れ歩く姿がこんないしっくり似合う俳人はいない」(池田澄子)の鑑賞があり、〈狼を詠みたる人と月仰ぐ 茨木和生〉、〈狼も詠ひし人もはるかなり すずきみのる〉〈おおかみに蛍が一つ付いていた 金子兜太〉の句も知られる。

1 / 3