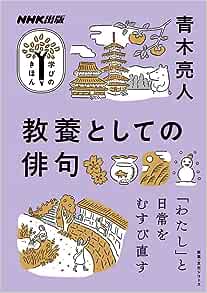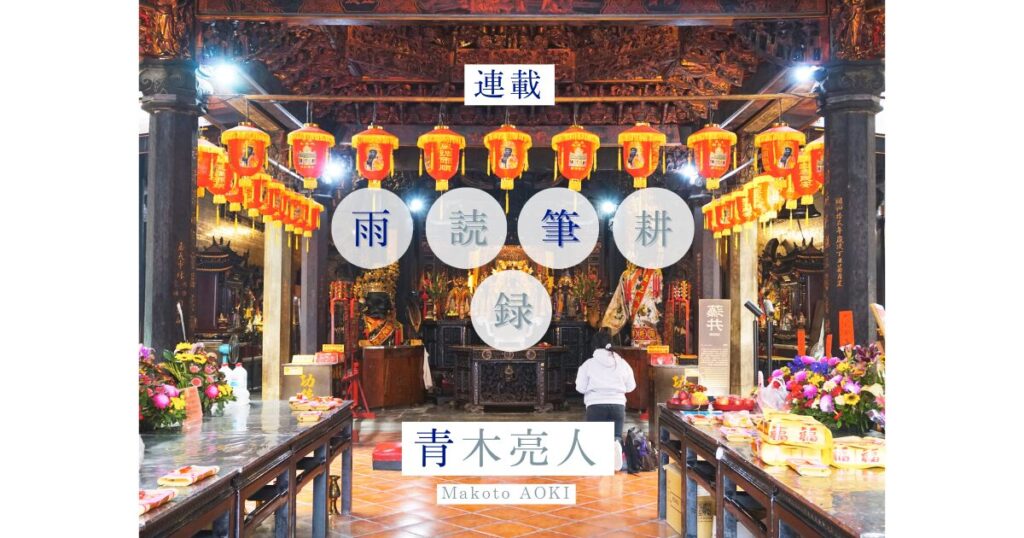
【#1】
台湾東部、花蓮市の小籠包(1)
今回から、「雨読筆耕録」として主に台湾文化や歴史に関わる随筆をまとめてみよう。新タイトルの「雨読筆耕」は「晴耕雨読」と「筆耕」を混ぜた造語で、何となく漢字文化圏の雰囲気漂う題にしてみた。
もちろん、今までのように趣味や写真等の随筆も折に触れてまとめることができればと考えているが、さしあたり台湾文化のあれこれについて書き綴ってみたい。まずは台湾東部の花蓮市での食事から筆を起こしてみよう。
∴
台湾東部の三移民村(吉野、豊田、林田)の調査を終え、花蓮市に車で戻った時にはすでに日が暮れていた。同行して現地を案内してくれた李さんと晩食を摂ることにし、私たちは地元の住民に人気という「周家小籠包・蒸餃」に向かった。

店に着くとすでに多くの人で賑わっていたが、奥の席が空いているという。夕食を摂る人々の卓を通り抜けて奥の席に座った私たちは、メニューを見ながら料理を決めていった。看板料理は小籠包と蒸餃子とのことなので、まずは小籠包と韮の蒸餃子、そして高麗菜の水餃子を頼んだ。主食を決めた後、日本でお目にかかれない副菜を食したい旨を李さんに相談すると、李さんは金針花という花と筍のスープの「金針筍片湯」や、豚の新鮮な血を固めたスープの「猪血湯」等を勧めてくれた。
他にもいくつか頼み、しばらくすると料理が次々と運ばれてくる。湯気を立てた蒸餃子や小籠包、スープ等……さっそくいただくと、どの料理も洗練されていることに驚いた。クセがなく、しつこくない味で、地元の人がよく訪れるのも頷ける気がした。


興味深かったのは、小籠包が想像と異なっていたことだ。小籠包といえば小ぶりで、薄皮の中に肉汁がたっぷり入っているイメージだったが、 小籠包は饅頭――日本の餡が入ったマンジュウではなく、中華圏の主食にあたるマントウ――に具が入っている案配で、日本の肉まんに近い。

一口食べてみると皮が厚く、滑らかというより粗さを残した歯触りで、新鮮な食感だった。中の具は豚肉や生姜等で、日本の肉まんより肉汁がやや多めだが、一般的な小籠包のようにスープが豊富に入っているわけではなく、皮も厚いために脂分のしつこさを感じない。厚皮の食感も含めて全体のバランスが取れており、想像以上の美味しさに驚いたものだ。猪血湯等のスープも含めてどれも美味しく、大満足の晩食だった。
それまでも台湾各地で様々な料理を食する機会があり、翌日以降も引き続き色々な土地で食事をいただいたが、花蓮市の「周家小籠包・蒸餃」で食したような厚皮の小籠包は他で出会ったことがなく、あの厚皮の食感の美味しさは今でも残っている。
そんな風に「周家小籠包・蒸餃」の小籠包を時折思い出すのだが、ふと思ったことがあった。台湾に小籠包はいつ渡来し、どのように定着したのだろう、と。
小籠包の発祥は中国の河南省に端を発するといわれており、やがて浙江等や上海――いわゆる華中地域――の名物料理になったという。小ぶりで皮が薄く、具とスープが包まれた小籠包は次第に中華文化圏に広まり、台湾にもいつしか定着した。台湾の小籠包で有名なのは、台北の鼎泰豐(ティンタイフォン)だろうか。

ただ、台湾の小籠包は蒸籠で蒸した包子全般を指す語でもあり、スープの有無にかかわらず蒸籠蒸しの包子を小籠包と呼ぶ店もあるという。小籠包がスープ入りの小ぶりの包子なのか、肉まんのようなスープなしの種類も含めるのかは地域や店によって異なるらしく、スープ入りの小籠包を明示する際には「湯包」と表記する場合が多い。
もっとも、これは台湾特有の話ではなく、中国でも各地域で小籠包の定義が異なり――上海や華中ではスープ入りの確率が高いが、華北や他地域では蒸籠で蒸した包子を小籠包と呼ぶ場合も少なくないらしい――、台湾の状況と近い地域もあるようだ。
従って、花蓮市の「周家小籠包・蒸餃」では蒸籠で蒸した包子を小籠包と呼び習わし、それで私たちの卓にもスープなしの包子が運ばれてきたのだろう。

青木亮人(あおき・まこと)
昭和49年、北海道生まれ。近現代俳句研究、愛媛大学教授。著書に『近代俳句の諸相』『さくっと近代俳句入門』『教養としての俳句』など。
【もう読みましたか? 青木亮人さんの『教養としての俳句』】
日本の伝統文芸として、数百年ものあいだ連綿と受け継がれてきた俳句。その愛好者は1000万人ともいわれている。にもかかわらず、私たちはその知識をどこでも学んでこなかった。そこで本書では、数々の賞を受けてきた気鋭の評論家が、日本人として最低限おさえておきたい俳句のいろはを解説。そもそも俳句ってどうやって生まれたの? 季語ってなぜ必要なの? どうやって俳句の意味を読みとけばいいの? 知識として俳句を知るための超・入門書。
俳句は、日本のリベラルアーツだ。