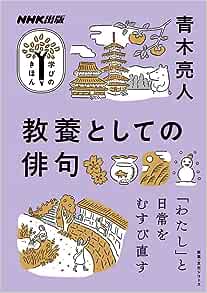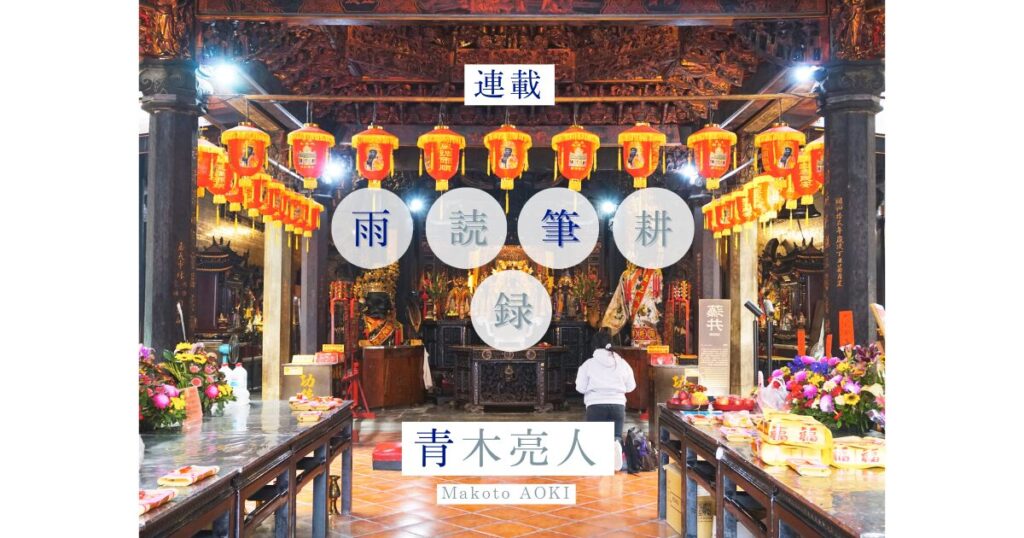
Mogwai(モグワイ)というバンドについて
2000年頃に知り合いからMogwai(モグワイ)というグループを教えてもらった後、よく聴くようになった。
春の明るい陽ざしが窓から射しこむ日や、夏の白雨が上がった後のむせるように蒸し暑い夕方のひととき、あるいは開け放った窓から金木犀の香りが流れこむ秋の朝や、師走の曇り空から雪片が降り始めた寒々しい午後……季節を問わず、時間を問わず、その頃の私はのめりこむようにモグワイの様々な曲を聴き続けたものだ。
モグワイはスコットランドのグラスゴー出身のバンドで、ポスト・ロックと呼ばれるジャンルに属し、インストゥルメンタル中心の曲が多い。ポスト・ロックは主に1990年代にデビューしたグループの括りとして用いられ、従来のロックのような曲構成ではなく、ドラムとベース、ギターを中心にSoundscape(音の風景)的な質感を目指すグループを指す。アメリカやカナダから大きな影響を及ぼすグループが現れたが、モグワイはイギリスを代表するポスト・ロックの雄と目されるようになった。
なお、ポスト・ロックというのは入り組んだ用語であり、実は1970年代後半にすでに流通していた。ニューヨークとロンドンに出現したパンク・ロックが一世を風靡した際、セックス・ピストルズのフロントマンだったジョン・ライドンが「ロックは死んだ」と宣言してP.I.Lを率い、従来のロックを解体するような曲を挑発的に発表するなどして、いわゆるNew Waveと称される潮流が70年代後半に流行する(実際はP.I.L以外にも多彩なジャンルのグループが関わったが、今回は割愛)。ポスト・ロックは、そうした戦後版のダダイズム的な音楽活動を括る合言葉として70年代後半に流通していた。
その後、1980年代に入るとポスト・ロックという括り方は影を潜めるようになったが、1990年代に別の文脈やグループを指す用語として再び人々の口端に上り始め、スコットランド出身のモグワイもその一例と目されたのである。
ただ、私がモグワイを聴きこむようになったのは、ポスト・ロック云々よりもケルト音楽の雰囲気が漂っているように感じられたためだった。アメリカやカナダ、ドイツその他のポスト・ロックグループとモグワイでは主旋律の捉え方が異なっており、その要因はグラスゴー出身のモグワイにケルト音楽の感性が流れこんでいるためでは、といった感覚をいつしか抱くようになった。
モグワイの曲はほぼ全て聴いたが、一時期よく聴いたのは”2 Right Make 1 Wrong”(2001)という曲だ。20代から30代にかけて頻繁に流し続け、例えば学術論文が佳境に入った時に延々と聴いた時期もあった。40代になって評論やエッセイの原稿を日常的に書き始めた頃も聴きこみ、原稿をまとめる際の定番曲の一つとして飽きずに聴いたものだった。それこそ季節を問わず、時間も問わず、曲に没頭しながら原稿を書き続けたものだ。
かくも聴き続けた”2 Right Make 1 Wrong”だったが、ある時期から聴く回数が減り始め、やがて潮が引くように聴かなくなった。かつてあれほど流し続け、飽きずに聴いた曲だったが、今ではごくたまに流し、どこか懐かしい気分に浸る程度だ。
ある時、久しぶりにこの曲を聴き直した時、不思議な感慨を抱いたことがある。
以前にあれほど聴き続けた時期があったのは、孤独にうまく慣れていなかったためでは、という感覚だった。物を書き続ける孤独にうまく馴染めず、何か支えや頼りになるものが欲しかったのかもしれない、という根拠のない感慨である。
無論、答えは分からないままであり、結論があるかどうかも分からない。ただ、仮にそうとすれば、ある時期の私はモグワイの”2 Right Make 1 Wrong”に助けられていたのかもしれない、と感じるようになった。
グラスゴー出身のバンドが奏でる電子音に甦るケルト音楽の気配が、極東の片隅でささやかな文章を書いている人物の孤独を和らげたかもしれないという説はいささか不思議で、荒唐無稽な感じがしないでもないが、物を書き続ける孤独を慰めるためだった可能性があるというのは分かる気がする。
当時は、何のために、なぜ書かねばならないのか、ほぼ分かっていなかった。そういう時期に最も相応しい曲の一つが”2 Right Make 1 Wrong”だったのだろう。
下のリンクは、Youtube公式アカウントの”2 Right Make 1 Wrong”。
青木亮人(あおき・まこと)
昭和49年、北海道生まれ。近現代俳句研究、愛媛大学教授。著書に『近代俳句の諸相』『さくっと近代俳句入門』『教養としての俳句』など。
【もう読みましたか? 青木亮人さんの『教養としての俳句』】
日本の伝統文芸として、数百年ものあいだ連綿と受け継がれてきた俳句。その愛好者は1000万人ともいわれている。にもかかわらず、私たちはその知識をどこでも学んでこなかった。そこで本書では、数々の賞を受けてきた気鋭の評論家が、日本人として最低限おさえておきたい俳句のいろはを解説。そもそも俳句ってどうやって生まれたの? 季語ってなぜ必要なの? どうやって俳句の意味を読みとけばいいの? 知識として俳句を知るための超・入門書。
俳句は、日本のリベラルアーツだ。