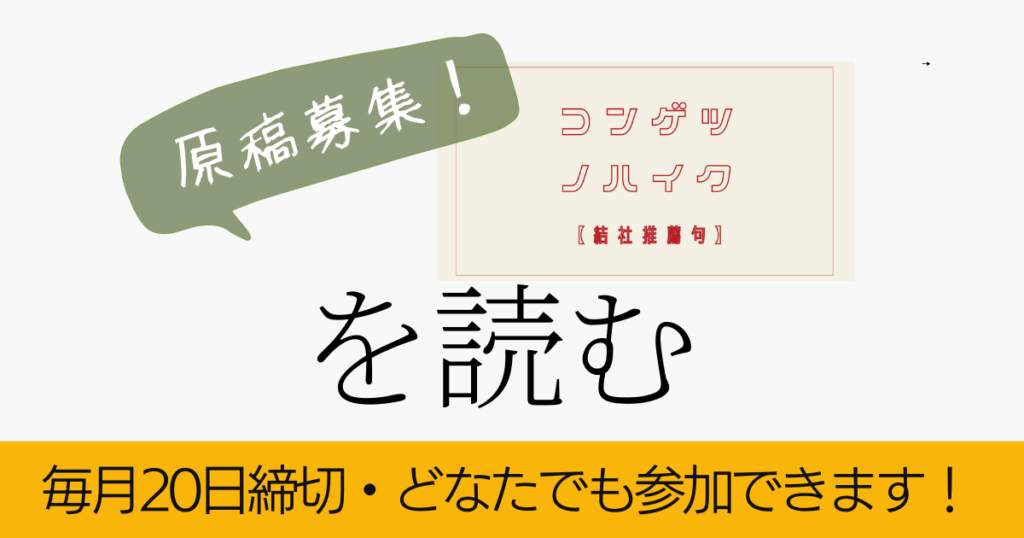【読者参加型】
コンゲツノハイクを読む
【2022年1月分】
ご好評いただいている「コンゲツノハイク」は毎月、各誌から選りすぐりの「今月の推薦句」を(ほぼ)リアルタイムで掲出しています。しかし、句を並べるだけではもったいない!ということで、一句鑑賞の募集を行っています。まだ誰にも知れていない名句を発掘してみませんか? どなたでも応募可能できますので、お気軽にご参加ください。今回は11名の方にご投稿いただきました!(掲載は到着順)
輪切りしていつまでを海鼠と呼ぶか
橋本喜夫
「銀化」2022年1月号より
クリスマスに鶏の丸焼きを見て、これは「1羽」なのか「1つ」なのかどっちだろう? と疑問を抱いたことを思い出した。しかし、鶏は焼かれてもあくまで鶏。海鼠の場合は、より話が根源的になる。輪切りされたそれは、いつまで海鼠で、いつから非・海鼠になるのだろう。日付変更線のように「ここを切ったら非・海鼠になる」という線があるのだろうか。海鼠に断りもなくそんな線を決めて良いのか。おかしいような、恐ろしいような、海鼠に申し訳ないような、そんな一句。(西生ゆかり/「街」)
生田筋トーアロードと秋惜む
森田純一郎
「かつらぎ」2021年12月号より
センター街を三宮から歩いている句ですね。通りの名前を2つ並べて秋を惜しんでいるだけなのに、さんちかタウン、生田神社、南京町、待合せの阪急の改札等々とともにいろんな思い出が湧き上がってきます。震災の2~3年後に一度、センター街を歩きましたが、戻ってきていない店もあり、ちょっと寂しかったですね。そんなことがなくても、神戸には秋が似合います。2つの通りの名前だけで胸に迫る郷愁に駆られました。(小原千秋/「櫟」)
フルーツサンド葡萄断面四つ並び
森下秋露
「澤」2021年12月号より
これは私が詠みたかった! 人気のフルーツサンド、これ自体は昔からありましたが、最近は「映え」を意識して断面を「魅せる」ものが当然、の世界になってきました。季語の「葡萄」の断面(シャインマスカットではなく巨峰かピオーネの方が断面が「映える」気がする)を読者に見せて、しかも「四つ並び」と、パンの大きさと葡萄のバランス、それに字数まで過不足なく合わせているところが見事。(鈴木霞童/「天穹」)
幼子にへびと呼ばれて蜥蜴去る
中村たま実
「蒼海」2021年14号より
へびと呼ばれても、何の反応も見せずに去ったという蜥蜴は、自分だと思った。自分が蜥蜴だったら、へびと間違われたくらいでは、それを正すのが面倒で黙っていると思うから。それに、この相手は幼子、説明しなくてもそのうちに、へびと蜥蜴の差は学ぶはず。面倒くさがってばかりいる自分ですが、穏やかに生きてこられた気がしています。蜥蜴は黙って坦々と生息しています。悪くないです。(フォーサー涼夏/「田」)
蜩や大教室に忘れもの
窪田千滴
「蒼海」2021年14号より
ドラマチック。そう云うときのドラマとは、世に放映され享受される物語作品という意味でドラマチックな句ですね。記号的な青春詠だと申したいわけでは、なく。〈大教室〉を備えるような場、大学でしょうか、その経験が読み手の側に有ろうと無かろうと、一つの印象深い場面を喚起される句だと申したい。「体験したことの無い物事をまざまざと思い出す」。そういう味わいを蔵している。だからドラマ的。これはいわゆる共感とも違う手触りだと感じられます。(平野山斗士/「田」)
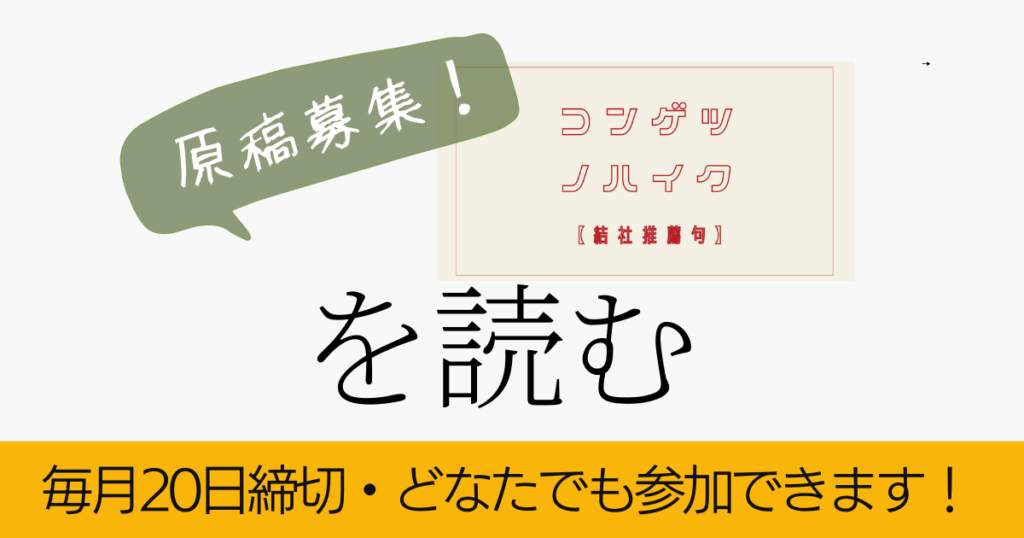
古書店の値札褪せたり晩夏光
髙嶋 静
「橘」2021年11月号より
古書店の店先で、「この箱の中どれでも一冊100円」といった形で、色褪せた値札と共に往年の名作が売られているのをよく見かける。昔はバイトで苦労して貯めたお金を叩いて買った本が、今では安売りされており、時代の変化/時の移ろいの早さへの驚きが、「褪せたり」という措辞から一つの諦念と共に伝わってくる。下五の「晩夏光」という季語も、草田男の「晩夏光バットの函に詩を誌す」同様、存念の青春性として、掲句の“許され”としてしっかりと機能している。青春よ永遠なれ。(琲戸七竈/「森の座」)
星飛んで谷にケーナの調べ降る
新谷壯夫
「鳰の子」2021年12月・2022年1月号より
なんと美しい句であろうか。ケーナは南米の縦笛。「コンドルは飛んでいく」の旋律をとるあの楽器である。その音色には哀愁が漂う。そんなケーナの音が、流星が消えた夜空の静寂に聴こえてきたというのだ。流星の静かな余韻と一筋の残像は、その音色によって増幅された。時に音は、静けさの純度を高める。「調べが降る」という措辞について。通常降るならば、流星の尾の粒か満天の星空だろう。それをケーナの調べに言い換えたことで、星の谷の夜は極まった。不思議と、奏者が住む小さな村の営みも気配として感じられる。(松村史基/「ホトトギス」)
喪中とあるゴリラの檻にいぼむしり
村上喜代子
「いには」2022年1月号より
昨今動物園では動物が死ぬと檻に「喪中」の掲示をしているそうだ。旭川の旭山動物園が平成16年頃に始めたもので、明るい話ばかりでなく動物たちの「死」もしっかり見てほしいという趣旨からだそうだ。当初は反対も多かったようだが、現在では全国の動物園のスタンダードになっているとか。
さて、掲句。ネット検索ではどこの動物園か特定はできなかったが、とにかくどこかの動物園でゴリラが亡くなった。「喪中」の掲示の掛かった空の檻の中では、青くて太ぶととした蟷螂がこちらに斧を振り上げていた。作者はそこに「死」と「生」のコントラスト、生きとし生けるものの定めを見たのであろう。(種谷良二/「櫟」)
湯上りの下駄や線香花火買ふ
塚本武州
「ホトトギス」2022年1月号より
湯上がりに、宿の名前の入った浴衣を着て、下駄を履いて、温泉街を散策。通りがかりのお店で線香花火を買ってみた、と想像した。下駄を履くことも、セットではない単品の線香花火を買うことも、現代の生活ではなかなかしない。まるで古き良き時代にタイムスリップしたかのようだ。「湯上り」と「下駄」の文字に隠れた「上」と「下」の言葉遊びが粋。そして句またがりのリズムは、下駄を履いて散策するときの不規則で楽しげなリズムを思わせる。今年の夏はこんな温泉街への旅ができたらいいなと思う。(千野千佳/「蒼海」)
虫の名にもモドキ・ダマシや夏盛ん
角谷昌子
「磁石」2021年11月号より
昆虫図鑑を眺めていると「◯◯モドキ」「◯◯ダマシ」という名を見かけることはそう珍しくない。「似て非なるもの」という意味だが、もう少し違う言い方はなかったものかと思う。タテハモドキ、ゴミムシダマシなど。他にはニセコルリクワガタという名も。しかしそのような名をつけたのは人間であり、虫たちが自ら望んで名乗っているわけではない。名をつけた人間側の思考や思惑が虫の名から感じられ、そういった角度から改めて昆虫図鑑を読んでみるとまた面白い。自分がなんと呼ばれているかなどお構いなしに、虫たちはその命を夏へと捧ぐ。(笠原小百合/「田」)
柿吊す選挙対策本部かな
橋本小たか
「秋草」2022年1月号より
およそ風情のない「選挙対策本部」が俳句になるのかと驚きの一句。「柿吊す」とするだけで、地元の後援会や婦人部などの群像劇が目に浮かび、そこに一瞬の静けさを生み出す柿の存在感が温かく感じられました。(曽我晶子/「天穹」)
→「コンゲツノハイク」2022年1月分をもっと読む(画像をクリック)

【セクト・ポクリット管理人より読者のみなさまへ】