
【読者参加型】
コンゲツノハイクを読む
【2024年2月分】
ご好評いただいている読者参加型コーナー「コンゲツノハイクを読む」、2024年も続いてます。今月は6名の方にご投稿いただきました。ありがとうございます(掲載は到着順)!→2024年2月の「コンゲツノハイク」はこちらから
たくさんの聖菓売り終へひとつ買ふ
安倍真理子
「ふよう」2024年1月号より
ケーキ屋の横に長机を置いただけのクリスマスケーキ引換場があり、そこに安っぽいサンタクロースの衣装を着たバイトが立っているところを思い浮かべた。この日のために用意したケーキは種類を問わずどんどん売れてゆく。すべてを売り終えるころにはすっかり真夜中になっている。バイトは取っておいたひとつのケーキを買って帰る。この句は最後が「貰ふ」のではなく「買ふ」のがよい。売り手から客に変わるところをしっかりと描写している。クリスマスの労働を描いた句として出色の出来だと思う。
(千野千佳/「蒼海」)
雪晴風天よつかまるものがない
村一草
「雪華」2024年2月号より
雪晴風は「ゆきはらし」と読むようだ。初めて見た言葉だが雪晴に風吹く光景がよく分かる。よく分かるというのは北国で育った筆者(私)の体感であり記憶があるからだ。雪晴の眩しさと冷たい風に目を細めて立っている者が天に呼びかけている。「つかまるものがない」と。「理屈」で読めば強風に煽られているのかもしれないが、筆者としては「感覚」で読みたい、というかこの句の言葉が筆者の中に呼び起こす五感の記憶はどちらかというと弱い風で、雪が降ったあとの光に満ちた風の中にいてふわりと昇天しそうな心地なのだ。思わず天に呼びかけてしまう心地なのだ。つかまって己の体を地に繋ぎとめておくようなものは何もない、むしろ何もなくていい、そんな浮遊感。魅惑。日常生活の異次元または異次元の日常。
(小松敦/「海原」)
蜩を纏えば響く僕の骨達
高木水志
「海原」2024年1・2月号より
蜩を纏うとは蜩の鳴く只中に身を置くことだろう。
その鳴き声、音は当然空気の振動であるので、その中に身を置けば確かに鼓膜以外に身体全体も振動を受けているはずである。
蜩は他の蝉と違って合唱する。
その合唱の中に居るのは恐らく僕一人なのだろう。
そこに身を置くことの薄絹を纏うような心地よさ、肌から肉を伝って骨に響くことの恍惚さえ感じるようである。
僕の骨達という字余は賛否あるかと思う。
しかし敢えてこう書くことによって、逆に骨という身体を構成するものではなく、身体を共有している者達として客体化されているように感じるのだがどうだろう。
蜩の合唱に骨達も合唱をしているイメージが浮かぶと同時に自身の身体へ深く潜ろうとする眼を感じさせる。
( 田中目八/「奎」)
夜半の秋こびとが踊る古時計
加藤剛司
「伊吹嶺」2024年1月号より
洋館のようなこの家にも
おじいさんの古時計
特別な古時計
百年立っても動いてる
夜半の秋の満月の一日前に
古時計のこびとが躍る
おじいさんを思い出して!!
おじいさんが亡くなった日は
夜半の秋の満月の一日前
そして、おじいさんが生まれ変わった日は
夜半の秋の満月の日
その日も古時計のこびとが躍る
夢の中で
おじいさんは言った
おじいさんは大丈夫
一度死んだらもう死なない
だからおじいさんは大丈夫
(月湖/「里」)
寝室に飾ったままの春の銃
故・らふ亜沙弥
「海原」2024年1・2月号より
消灯後の四人部屋のベッドで半身を起こす。化学療法の副作用で薄闇の間仕切りカーテンが黄色く淀む中、一丁の拳銃が、こればかりは冴冴(さえざえ)と鋼(はがね)の光沢を灯す。と見るや、煌々たる紫色の車が滑り込み、全身紫づくめのドライバーが紫のマニキュアでその拳銃をつんつんとつつくと、「まだまだ青いわね」。口紅も声も紫だ。「もっと熟させなくっちゃ」
ジャッとカーテンリングが轟いて「おはようございまぁす」と看護士が踏み込んで来る。スマホの旧暦カレンダーの今日は12月25日。でも立春。そこではたと思い出す。去りがてのエンジンをふかしながら紫夫人が言ったことに、「私の春は紆余曲折10年ほどで闌(た)けたの。壁の銃も最期にはえも言われぬ紫色に熟したわ。あなた、これからが大変なのだ」
(生倉 鈴/「楽園俳句会」)
背後の人同じ吊革摑む残暑
長谷川照子
「澤」2024年1月号より
満員電車でやっとたどり着いた吊革ほど安心するものはない。吊革はその下に立つ人専用のつかまるものであるはず。なのに、背後から覆いかぶさり、吊革の舳の部分につかまってくる人がいる。吊革の輪を勢いよく奪われたこともある。わたしを筆頭に、身長の低い人ならば、特にこの不快感に激しく共感するだろう。こちらの句の季語の斡旋、字余りは、背後の人物の体温、湿度、息遣い、不快感全部を見事に表現していると思う。いつまでも終わりの見えない残る暑さへの嫌悪も重なって、わたしの吊革から手を放せと、満員電車で無駄に右に左につかまれた吊革を揺らすことを、きっとこの先もやめられない。
(藤色葉菜/「秋」)
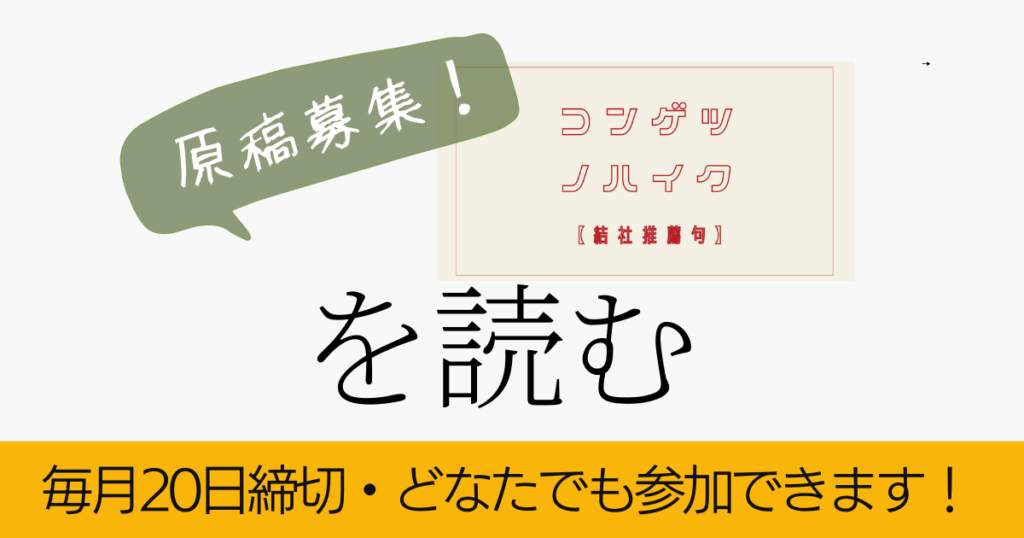
【セクト・ポクリット管理人より読者のみなさまへ】
