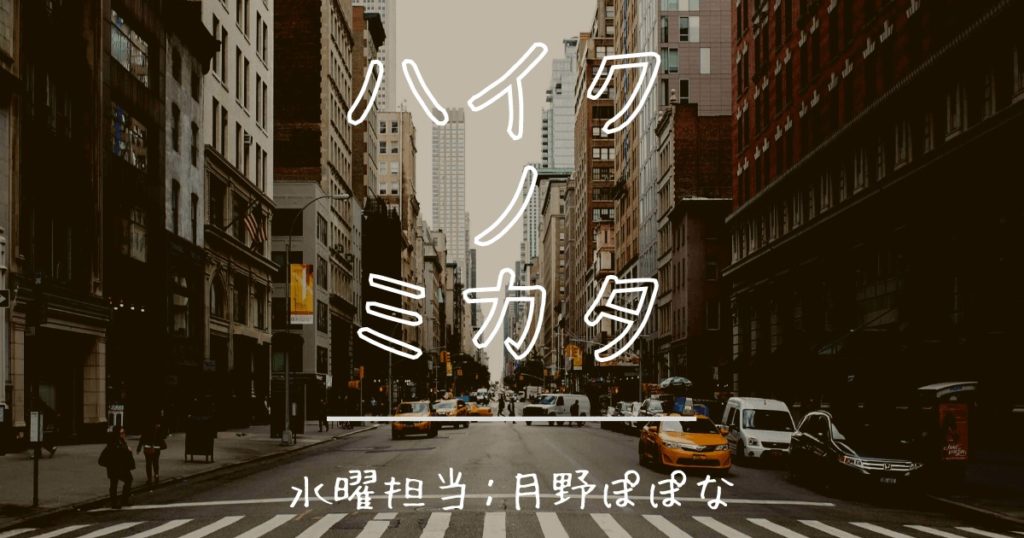
とび・からす息合わせ鳴く小六月
城取信平
〈小六月〉は、新暦の10月下旬から12月上旬にあたる、旧暦10月の異称。立冬をすぎてもすぐには厳しい寒さは訪れず、雨風が少なく、春を思わせる暖かい日和の続くところから小春ともいう。
ぴーひょろひょろ
かぁかぁかぁ
トンビ(鳶)とカラス(烏)。この特徴的な鳴き声を持つ、種類の違う鳥が、仲良く息を合わせて鳴いているように聞こえてくるという。そんな穏やかさが、初冬の陽光に溢れた日和にとてもよく合っている。
トンビの声は高い空から、カラスの声は、比較的、人に近い低い空から響き合い、空の深さが見えて来る。そして空の広さも。
ぴーひょろひょろ
かぁかぁかぁ
作者は、筆者の故郷でもある、信州伊那谷に住む。ここは長野県南部、西を木曽山脈に、東を赤石山脈に挟まれ、天竜川に沿って南北に伸びていて、谷、といえども、広い平坦部が多いため、伊那平とも呼ばれる。
そのため、谷、という言葉からイメージされるだろう、その空より伊那谷の空はずっと広い。平坦部には、天竜川が形成した河岸段丘と呼ばれる、いくつかの段差面があり、段丘一つ登るたびに視界が開けてゆく。遠くの山並みと、その山並みが縁取る空が美しい。
ふと、この伊那谷をこよなく愛した俳人のことを思った。
江戸時代末期、突然伊那谷に現れた井上井月。後世には、その晩年の風態から「乞食井月」として知られる向きが強いが、書が上手く俳諧の道に長けていた井月は、当時、文化人として人々から歓迎された。その後約30年間、人々に、慶事や弔事に際して挨拶句を贈ったり、詩文を揮毫しては、酒食や宿、金銭などの接待を受けつつ、伊那谷を放浪し続けた末、66歳でこの世を去った。
井月も仰いだであろう、伊那谷の空。
何処やらに隺の聲きく霞かな 井上井月
明治20年3月10日(旧暦2月16日)、死の2時間前に、この句を書いたという。
「霞のなかどこやらから鶴の鳴声が聞こえてくるなあ」。彼の心に最期まで、伊那谷の空に響く鳥の声があった。
1 / 2