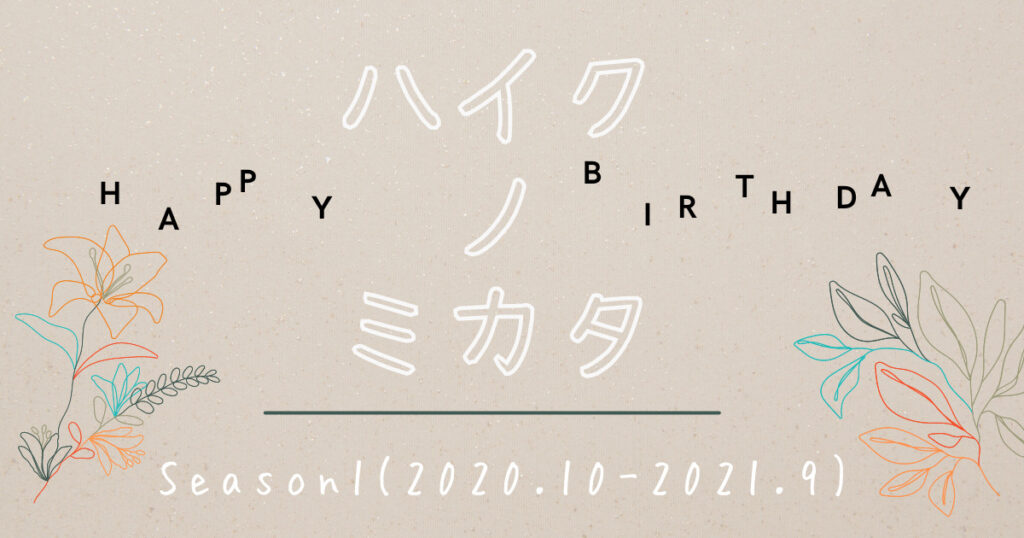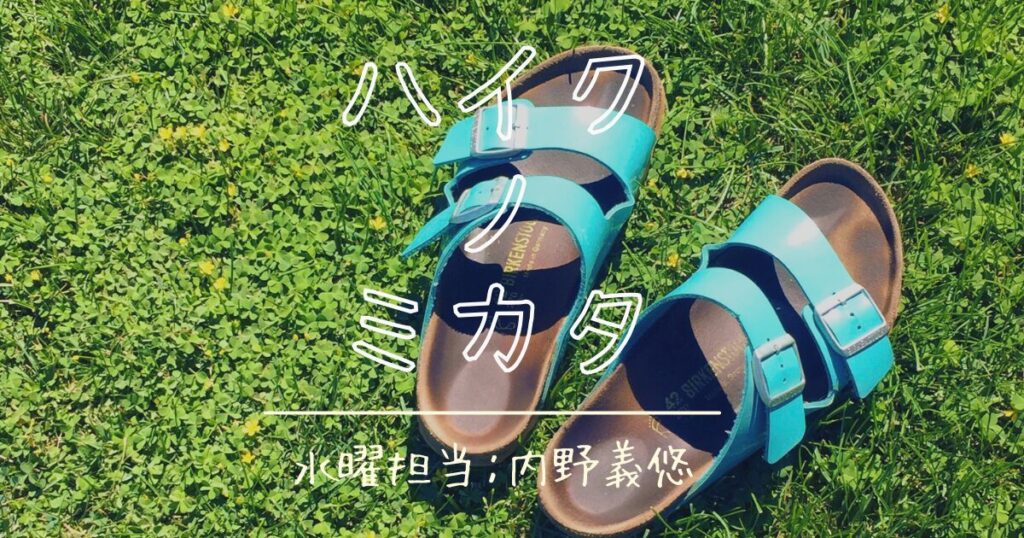
青梅の最も青き時の旅
細見綾子
『伎藝天』より
旅をしていると、さして重要でもないありふれた一場面の方が、その時々のメインイベントよりも記憶に深く焼き付いているということがままある。
たとえば、有名な観光地を訪れたりご当地名物のグルメを食べたことよりも、ぼおっと休んだ道の駅の駐車場のだだっ広さや、路地裏にたまたま見つけた古びた町中華の下ろされたシャッターの方が眼裏にくっきり浮かんできたりする。
そんなどこにでもあるような景色を記憶してもしょうがないのに、何故このようなことが起きるのか考えてみた。
たぶん、「自力で拾い上げた景色」の方が明確な輪郭を持って記憶に残るのだと思う。その景色の価値の有無は別として。
それぞれの土地の代名詞であるだけに、観光地やご当地グルメには多くの人が群がりいつも賑やかだ。
その代わり、みんなが同じものを観て同じような行動をする。そこには「こう振る舞わなければ損」というような無意識の同調意識も生じているように思う。
そうすると記憶に置換される時に、どこか色が薄まり輪郭がぼやけている気がする。その間の行動の主体性が弱まっているからかも知れない。
その点、人が気にも留めない無名の景色や対象は地味ではあるが誰にも邪魔をされない。誰かとイメージを共有することは難しいかも知れないが、自分の脳裏にはいつでもすぐに甦ってくる。
今回鑑賞する一句も、そのような種類のささやかな一場面を一つの旅の象徴として捉えている。
青梅の最も青き時の旅 細見綾子
句集では「不破の関 六句」の前書が付されている。
綾子の所属した結社「風」の吟行で中山道の不破の関を訪れた時に詠まれた、掲句はその冒頭句である。
吟行句というと、どうしてもその土地特有の景を詠みたくなるのが人情であろう。特に不破の関という歴史的背景の色濃い土地なら尚更だ。
その中で綾子は「青梅」というどこにでも実る自然物に着眼した。そしてその「青さ」の絶頂を鮮烈に切り取ったのだ。まさに「季」そのものの流れゆく様を、そのまま抱くように詠んだ旅吟と言えよう。
一連の吟行句の冒頭に置かれたことも相まって、綾子が眼にした不破の関の様々な景色それ以上に、この「青梅の青さ」がこの吟行旅行の象徴となったように思える。
小さな対象から、旅全体を包み込むような大らかな時間性をも引き出した、広がりを感じさせる佳句である。
さきに「無名の景色や対象は誰かとイメージを共有することは難しいかも知れない」と書いたが、それが季語(青梅)となると話は別で、仮託された綾子の明るく楽しげな心持ちが読み手にも容易に想像できる。
このあたりは、やっぱり俳句という文芸っていいよなぁ、と思える所以でもある。
今回引いた掲句の初出は『伎藝天』という句集に収録されたものだが、ぼくは『細見綾子の百句』(山崎祐子著・ふらんす堂)に収められたものの中からこの句を知った。
よって今回は、『伎藝天』のみならず綾子の句業全体の中から他にも数句紹介してみたいと思う。
いずれも晴れやかな伸びやかさ、瑞々しさを纏っているところに綾子らしさを見出すことができる。
百里来し人の如くに清水見る 細見綾子『桃は八重』
九頭竜の洗ふ空なる天の川 同『桃は八重』
能登麦秋女が運ぶ水美し 同『雉子』
枯野電車の終着駅より歩き出す 同『和語』
門を出て五十歩月に近づけり 同『牡丹』
綾子は1907年(明治40年)の生まれ。俳句に出会う以前のその前半生は苦難に満ちており、22歳の若さで最初の夫を病で喪い、立て続けに実母も亡くした。同時期に自らも肋膜炎を発病し、療養生活に入る。この時の主治医に俳句を勧められ、その縁から「倦鳥」に入会、松瀬靑々に師事することとなる。「倦鳥」では晩年の靑々の供をして、京都や奈良などを吟行で何度も訪ねた。
やがて後の夫となる俳人・沢木欣一と出会い、交際。しかし、ここでも太平洋戦争下という時代背景もあり、欣一の出征など苦しい時間を過ごした。
終戦を迎え、無事に戦地から生還した後欣一が創刊した「風」の同人となり、昭和22年には結婚。
その後は子宝にも恵まれ、自身の病も癒えて、ようやくその人生に安寧が訪れる。
掲句もそのような平穏な時期に詠まれた句。
凝縮されたような「青」の鮮やかさに、「生」への喜びや賛嘆の情があふれている。
心にゆとりがあるからこそ拾い上げられるささやかな景色の美しさを見落とさないように、日々を生きていきたいと思った。
(内野義悠)
【執筆者プロフィール】
内野義悠(うちの・ぎゆう)
1988年 埼玉県生まれ。
2018年 作句開始。炎環入会。
2020年 第25回炎環新人賞。炎環同人。
2022年 第6回円錐新鋭作品賞 澤好摩奨励賞。
2023年 同人誌豆の木参加。
第40回兜太現代俳句新人賞 佳作。
第6回俳句四季新人奨励賞。
俳句同人リブラ参加。
2024年 第1回鱗kokera賞。
俳句ネプリ「メグルク」創刊。
炎環同人・リブラ同人・豆の木同人。
俳句ネプリ「メグルク」メンバー。
現代俳句協会会員・俳人協会会員。
馬好き、旅好き。
【2025年5月のハイクノミカタ】
〔5月1日〕天国は歴史ある国しやぼんだま 島田道峻
〔5月2日〕生きてゐて互いに笑ふ涼しさよ 橋爪巨籟
〔5月3日〕ふらここの音の錆びつく夕まぐれ 倉持梨恵
〔5月4日〕春の山からしあわせと今何か言った様だ 平田修
〔5月5日〕いじめると陽炎となる妹よ 仁平勝
〔5月6日〕薄つぺらい虹だ子供をさらふには 土井探花
〔5月7日〕日本の苺ショートを恋しかる 長嶋有
〔5月8日〕おやすみ
〔5月9日〕みじかくて耳にはさみて洗ひ髪 下田實花
〔5月10日〕熔岩の大きく割れて草涼し 中村雅樹
〔5月11日〕逃げの悲しみおぼえ梅くもらせる 平田修
〔5月12日〕死がふたりを分かつまで剝くレタスかな 西原天気
〔5月13日〕姥捨つるたびに螢の指得るも 田中目八
〔5月14日〕青梅の最も青き時の旅 細見綾子
【2025年4月のハイクノミカタ】
〔4月1日〕竹秋の恐竜柄のシャツの母 彌榮浩樹
〔4月2日〕知り合うて別れてゆける春の山 藤原暢子
〔4月3日〕ものの芽や年譜に死後のこと少し 津川絵理子
〔4月4日〕今日何も彼もなにもかも春らしく 稲畑汀子
〔4月5日〕風なくて散り風来れば花吹雪 柴田多鶴子
〔4月6日〕木枯らしや飯を許され沁みている 平田修
〔4月8日〕本当にこの雨の中を行かなくてはだめか パスカ
〔4月9日〕初蝶や働かぬ日と働く日々 西川火尖
〔4月10日〕ヰルスとはお前か俺か怖や春 高橋睦郎
〔4月11日〕自転車がひいてよぎりし春日影 波多野爽波
〔4月12日〕春眠の身の閂を皆外し 上野泰
〔4月15日〕歳時記は要らない目も手も無しで書け 御中虫
〔4月16日〕花仰ぐまた別の町別の朝 坂本宮尾
〔4月17日〕殺さないでください夜どほし桜ちる 中村安伸
〔4月18日〕朝寝して居り電話又鳴つてをり 星野立子
〔4月19日〕蝌蚪一つ落花を押して泳ぐあり 野村泊月
〔4月20日〕人體は穴だ穴だと種を蒔くよ 大石雄介
〔4月22日〕早蕨の袖から袖へ噂めぐり 楠本奇蹄
〔4月23日〕夜間航海たちまち飽きて春の星 青木ともじ
〔4月24日〕次の世は雑木山にて芽吹きたし 池田澄子
〔4月25日〕ゆく春や心に秘めて育つもの 松尾いはほ
〔4月26日〕山鳩の低音開く朝霞 高橋透水
〔4月27日〕ぼく駄馬だけど一応春へ快走中 平田修
〔4月28日〕寄り添うて眠るでもなき胡蝶かな 太祇
〔4月29日〕造形を馬二匹駆け微風あり 超文学宣言
〔4月30日〕春の夢遠くの人に会ひに行く 西山ゆりこ
2020年10月からスタートした「ハイクノミカタ」。【シーズン1】は、月曜=日下野由季→篠崎央子(2021年7月〜)、火曜=鈴木牛後、水曜=月野ぽぽな、木曜=橋本直、金曜=阪西敦子、土曜=太田うさぎ、日曜=小津夜景さんという布陣で毎日、お届けしてきた記録がこちらです↓