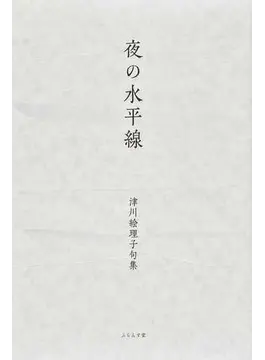いつもとなりに
――津川絵理子『夜の水平線』(ふらんす堂、2020年)――
話題となった句集にいまさらつけ加えることなんて、あるだろうか。本書は、津川絵理子の第三句集にあたり、2020年末にふらんす堂から刊行されたもの。手触りがよく、温かみのある、白いシンプルな型押しのある表紙。すでに書評もいくつか書かれているし、著者宛には山ほどの手紙が届いただろう。先日は、第61回俳人協会賞を受賞したので、これにより、さらに多くの人に読まれることになるはずだ。
本書は、2012年から2019年までの8年間の作品を収録している。これは津川が、村上鞆彦とともに「南風」の主宰を共同で務めていた時期にほぼ重なっている(現在は村上が単独で主宰)。たしか家族の事情で辞退したという話をどこかで読んだ覚えがあるが、詳しくは知らない。その件は、句集にも一切触れられていないし、そもそも句集の「あとがき」は4行しかなく、しかもうち2行は、過去の二句集につづき装釘を担当された画家の戸田勝久氏と、「家族、わが家にやってきた鳥や虫たち」への感謝の言葉に当てられている。
わたしみたいに不要なことをべらべらと喋り続ける、きっと津川はそんな人ではないのだろう。きっと謙虚で礼儀正しく、節度ある人なのだろう。それは、装幀やあとがきから十分に読み取れることだし、句からも想像ができる。津川の句は派手ではないが、味わいがある。小津の映画のようだ。
思ひ出すために集まる春炬燵
万緑や礼をするとき目をつむり
マンションの木々みな若し愛鳥日
吾を映すあたらしき墓洗ひけり
映画のカットには、たとえそれが他愛のない日常の場面であったとしても、それぞれ意味がある。会話しているときの外の天気、車の色や車種、机の上のコーヒーを映す角度など。見事なカットをつくる映画監督の目は、やはり普通とは微妙にちがう「角度」をもっている。津川の句集を読んでいても、同じことを感じる。礼をするときに目をつぶるのは、自分であろうが他人であろうが、簡単に見えるものではない。久保田万太郎の「叱られて目をつぶる猫春隣」とは、ドラマの作り方が根本的に異なっているのだ。
このような津川の魅力については、「ものごとの順序」という観点からも説明できる。たとえば、一句目、「春炬燵」がすでにあるところに、集まってきて思い出話をしている、というのが平凡な捉え方である。津川はそれを逆転させている。三句目も現実は、若い木々をマンションに施工業者が植えただけのこと。「マンションの木々みな若し」と断定することで、マンションも新築で、かつ初夏の鳥たちの眩しさまでもが伝わってくる。四句目も「あたらしき墓」に「吾」が映っているところを、「吾を映すあたらしき墓」と形容することで、「吾=墓」という未来や、「吾―洗う」という再帰性が、ユーモアをもって立ち現れる。結果として、作者の目=発見がよく伝わってくるのだ。
そのような技巧と無関係ではないかもしれないが、津川の句では、季語が「主役」になることはあまりない。ゼロではないが、季語そのものを一物仕立てで詠んだ句は少ない。しかしかといって、「取り合わせ」と呼びたくなるほど、季語は離れたところにはない。こう言ってよければ、多くの句において、季語は〈となり〉にある。
橋桁は水にあらがふ夏燕
帰路はよく話す青年韮の花
花梨やひとりに開く美術館
冬薔薇満場一致とはしづか
一句目、「夏燕」はどこにいるかというと「橋桁」の〈となり〉にいる。「韮の花」は、「青年」の〈となり〉にある。「花梨」は「美術館」の、「冬薔薇」は「満場一致」の〈となり〉にある。そして残りの部分、いわゆる目の効いた措辞で「発見」を伝える。橋桁にぶつかる水の勢い。それは夏燕の旋回と響き合う。「韮の花」の地味さは、「青年」の二面性と重なる。「梨の花」は、地方の「美術館」ののどかさを暗示する。「冬薔薇」のきりりとした感じは、会議で議決をとるときの無言をいっそう際立たせる。
再構成されているのは、津川自身の生活や経験であるのに、おしつけがましさは一切ない。おそらく、作者自身が、作者自身の生にすべてを還元されることを、望んでいないのだろう。俳句は日記でもなければ、私小説でもない。だから、そこに私性、キャラクター、境涯性、何と呼ぼうが、〈個人的なもの〉は排除されるべきであると、作者が考えているようにも感じられる。少なくとも、この句集の読者はそのような読み方を促される。
多くの俳人は、へそまがりだ。しかし津川はちがう。「まっすぐ」であることを厭わない。そして、わたしたちに「隠された真実」をこっそりと教えてくれる。
初蝶やスカートのなか脚うごく
人を待つコートの中の腕まつすぐ
寒晴や後れ毛のなきバレエの子
立春や腕より長きパンを買ふ
ポケットの木の実の中の鍵探す
津川の有名句に〈主婦となるセーターの腕ながながと〉という句があるが(『はじまりの樹』所収)、「立春」の句を読むとき、脳裏にその句もちらついて、笑ってしまう。一方で、「スカートのなかの脚」や「コートの中の腕」は、外面からは見えていない部分に注目している点が面白い。それは「ポケットの中」に「木の実」があり、「木の実の中」に「鍵」があるという入れ子構造によって、さらに複雑化する。「寒晴」の句は、飯島晴子の〈寒晴やあはれ舞妓の背の高き〉に少し似ているが、シニョンヘアを「後れ毛のなき」と表現したところが、先の「満場一致」のように、木々が葉を落として裸木となる冬の感じと響き合う。
句集を読んでいて感じるのは、津川にとって俳句とは、日常そのものであるということだ。日常の「なか」に俳句があるのではない。そうではなく、ふとある気づきが、気づかれてしまうのだと思う。スカートの中で脚が動いていること、コートの中の腕がまっすぐであること、満場一致とはしずかであること――そうした小さな気づきが、この『夜の水平線』ではさらに進化/深化しているという感じがある。俳句をつくるにしても、季語を無理やり探したり、ましてや意外性を求めてすげ替えたりすることはないのだろう。なぜなら、季語は気づきの〈となり〉にあるからだ。
興味深いのは、この句集に「顔」というワードが頻出するということである。
断面のやうな貌から梟鳴く
時雨るるや新幹線の長きかほ
初電車しみじみ知らぬ顔ばかり
甘露煮の醜きかほや春の暮
永き日の桶をあふるる馬のかほ
噴水に照らされ父の顔となる
津川は、顔をよく見ている。おそらく、顔は変化するものだと思っている。朝の顔と夜の顔が異なるように、人間も馬もフクロウも、おそらく春の顔と冬の顔はちがう。それらを同じものにしてしまうのは、「名」のもつ暴力性である。名付けは、Aの時間的変化を無視して、AをいつまでもAであることにしてしまう。本当は、Bになっているかもしれないし、Zになっているかもしれないというのに。日々の「変化」を素直に受け入れる柔らかな知性と感性。それが津川の最大の魅力だ。
作者の実生活に沿うなら、子育ての最中であり、ビルのある街に住み、ギターよりはウクレレが好きで、しばしば墨で書をしたため、古きよき日本映画を愛し、鳥を飼っていて、本が好き――そんな作者像が浮かぶが、それはあくまで本書の副産物にすぎない。
史実からいえば、『夜の水平線』の8年間のあいだには、「南風」主宰を2004年まで務めた師・鷲谷七菜子(1923-2018)、そして七菜子のあとを次いで主宰継承をした山上樹実雄(1931-2014)の両氏を失っているが、集中に明らかな追悼句はない。強いていえば、2016年の〈蜻蛉すいと来て先生の忌日かな〉は、8月6日に亡くなった山上に寄せた句であろうか。「2017年」最後の句である〈病院の廊下つぎつぎ折れて冬〉は、大病院に入院した師を見舞ったときの句かもしれないが、そこにわかりやすい感情は示されておらず、むしろ前へ前へと進まざるをえない人生を思う。
たどりつくところが未来絵双六
古暦日の差して部屋浮くごとし
ちよつと腰浮かす挨拶シクラメン
オリオンの広き胸ゆく明日も晴
どちらかといえば、『夜の水平線』は、ほんのりとしたユーモアが漂う明るい句集だ。「南風」はもともと、水原秋櫻子の弟子である山口草堂(1898-1985)によって、「馬酔木」の大阪支部を母体としてつくられた結社であり、「抒情」と「美意識」を前面に押し出した作家も多い。実際、津川も〈寒紅を濃くひく我をおそれけり〉のような句が、かつてはあったが、この句集には主観語の使用は差し控えられている。自分を見つめる句を作るとしても、〈吾を映すあたらしき墓洗ひけり〉という「寸止め」の表現になっている。
鷲谷七菜子の第三句集『花寂び』は、1977年に牧羊社の「現代俳句女流シリーズ」から刊行されている。
老僧の眉がうごきて遠ざくら
山河けふはればれとある氷かな
みづうみのこまかきひかり佛性会
このような師の句は、その着眼も美学も、そして控えめさもすべて、津川のそれと重なり合っている。『花寂び』を刊行した年、鷲谷は55歳。一方、1968年生まれの津川は、今年(2022年)54歳を迎える。ひとつ違うのは、鷲谷七菜子が俳人協会賞を受賞したのは、その数年後に刊行した第四句集の『游影』(1983年)だったということだが、40代後半から50代にかけて、自身の「名」に要約されえない多彩な俳句世界を生み出す円熟期に到達しつつあるというのは、同じだろう。
『夜の水平線』は、版元の電子書籍プロジェクトの一環で、1000円で入手することも可能だが、この小鳥のように軽やかな句集は、〈となり〉に置いておいても損はないだろう。以下は蛇足になるが、筆者が10句に絞るなら、という難問を受けた場合の回答であるが、無理だった。どんなに頑張って絞っても、20句になってしまった。そういう句集なのである。
二の腕のつめたさ母の日なりけり
黙考の大金蠅は打ち難し
マネキンにひとつ灯残る夜長かな
初電車しみじみ知らぬ顔ばかり
止り木に鳥の一日ヒヤシンス
あたたかやカステラを割る手のかたち
菜の花や釣人の来る喫茶店
押入れの空気出てゆく菊日和
ひと言に血のめぐりだす竜の玉
鳥籠に青菜絶やさず文化の日
ちよいちよいと味噌溶いてゐる桜どき
雲の峰サンドバッグに音溜まり
祖母の声飛んで来さうな青蜜柑
口のなか舌浮いてゐる鰯雲
人を待つコートの中の腕まつすぐ
ものの芽や年譜に死後のこと少し
眼鏡掛け替へてこの彩菊膾
薬草といふ冬萌に目を凝らす
春風や弾力で立つ竹箒
鹿の声ひそかに水の湧くところ
この書評では、「夜の水平線」という謎めいたワードが、いったいどんな句から引かれているかは、触れなかった。というよりも、その楽しみを読者から奪ってしまうような書評は、最低の部類だろう。やっと順番が回ってきた友人のカラオケを、間違ってイントロで消してしまうくらい最低だ。というわけで、まだお読みでない方は、ぜひ「夜の水平線」というタイトルがどんな句に由来するのか、ぜひお楽しみに。
【執筆者プロフィール】
堀切克洋(ほりきり・かつひろ)
1983年生まれ。「銀漢」同人。第一句集『尺蠖の道』にて、第42回俳人協会新人賞。第21回山本健吉評論賞。2020年9月より「セクト・ポクリット」を立ち上げて、不慣れな管理人をしております。
【セクト・ポクリット管理人より読者のみなさまへ】