
【連載】
もしあの俳人が歌人だったら
Session #17
管理人引っ越しのため、しばしお休みをいただいたのち、先月より再開しております。気鋭の歌人のみなさんに、あの有名な俳句の作者がもし歌人だったら、を想像(妄想)していただくコーナー。今月のお題は、高濱虚子の〈遠山に日の当りたる枯野かな〉。ユキノ進さん・野原亜莉子さん・三潴忠典さんの御三方にご回答いただきました。
【2022年11月のお題】

【作者について】
高濱虚子(1874―1959)は現・松山市生まれ。地元で正岡子規に兄事し俳句を教わる。子規没後は、「ホトトギス」の経営を引き継いで、大正期には俳句普及に大きな貢献をした。1954年、文化勲章受章。1959年4月8日、永眠。2000年、疎開先旧宅である小諸市の「虚子庵」に小諸高濱虚子記念館が開館。同年4月、兵庫県芦屋市に虚子記念文学館が開館した。
【ミニ解説】
明治33年(1900年)11月25日、虚子庵例会で詠まれた句です。世紀の境目に虚子は、「師」の病状の悪化と、生まれ来る我が子の胎動に立ち会っていました。この前月の子規庵における句会例会は中止、この翌月に長男・年尾が生まれることになります。このとき虚子、27歳。
この句が描く情景は、実にシンプルです。遠くに山が見え、そこに冬日が当たっています。その手前には、蕭条とした枯野。連体形の「たる」によって、遠山と枯野を半ば強引につなぎあわせ、ひとつの絵のなかに収めているわけです。
冬の季語である「枯野」で思い出すのは、何と言ってもまず、松尾芭蕉の〈旅に病で夢は枯野をかけ廻る〉でしょう。芭蕉が臨終を迎えたのは、元禄7年10月12日申の刻、新暦でいえば同年11月28日の午後4時頃のこと。
芭蕉が息を引き取ったころと同様に、枯野に当たっている日は、いまにも没しようとしているのでしょう。しかし、太陽がいまにも沈まんとしているところで、あたたかく照らしています。そのような初冬の入日の「あたたかさ」は、子規にせよ芭蕉にせよ、〈大いなる師〉の最期を思わせもします。
虚子自身は若いころ、枯野の句がそれほど好きではなかったようです。みずからの身に老いを感じるにつれて、自作の見え方が変わっていったのかもしれません。後年、虚子は遠山の句を「もっとも気に入っていた自作句」として公言するほどでした。事実として、20世紀前半を通じ、虚子もまた〈大いなる師〉になったわけですが……。
明治20年代は、かつて柄谷行人が『日本近代文学の起源』(1980年)のなかで「風景の発見」の時代なのだ、と喝破したことも思い出されます。当時、子規や虚子が注目したのは、画家でもあった蕪村の客観的で印象明瞭な「描写」でした。
てら/\と石に日の照る枯野かな 蕪村
むさゝびの小鳥喰み居る枯野かな 同
与謝蕪村(1716〜1784)は、いまでこそ芭蕉・一茶と並ぶ江戸の俳人として知られていますが、当時はまったく忘れ去られていた存在。その名を復興させたのが、子規の『俳人蕪村』です。
「一事一物を画き添えざるも絵となるべき点において、蕪村の句は蕪村以前の句よりもさらに客観的なり」と書きながら、子規は上の「枯野」の句も挙げています。そして蕪村には、こんな句もあります。
山は暮て野は黄昏の薄かな 蕪村
俳句が風景を詠むようになったといっても、幾何学的な意味での消失点があるわけではなく、蕪村の時代からこのような写実的な「遠近法」は実践されていました。この句は、虚子の「枯野」とは、日の向きこそ違いますが、やはり当時の虚子が蕪村から吸収したものは大きそうです。晩秋から初冬にかけての午後4時。それは、俳句において特権的なひとつの時空となっているのかもしれません。
火を焚くや枯野の沖を誰か過ぐ 能村登四郎
よく眠る夢の枯野が青むまで 金子兜太
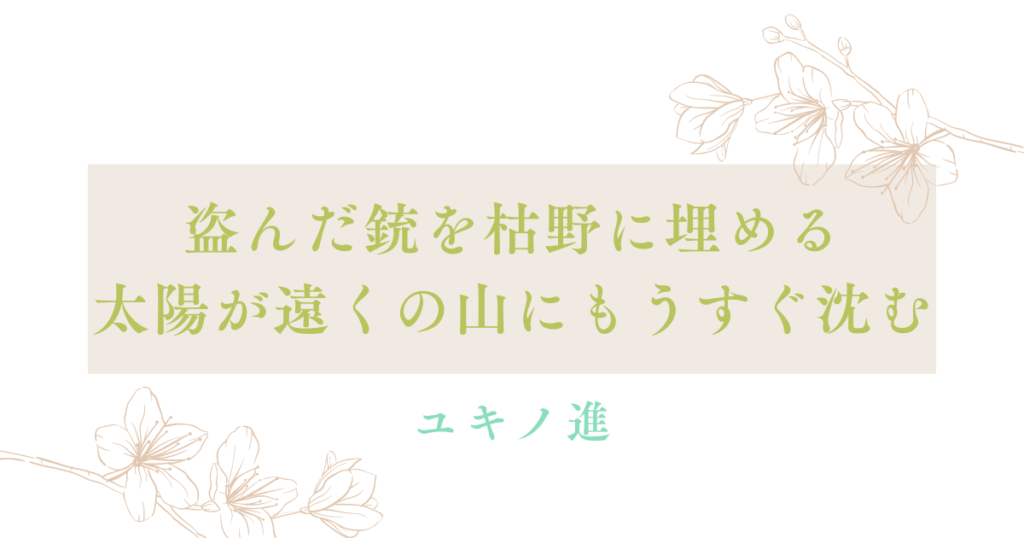
「いい写真なんだけど」クライアントの担当者は申し訳なさそうに言った。「これ、どこの山かわからないですよね」
僕たちは海外のある国への観光誘致のWeb記事の初稿をチェックしていた。記事の最後には雰囲気のある夕暮れの風景の写真。丘の上からのアングルで、手前にあかりの灯りはじめた町がありその向こうに山並みのシルエットが広がっていた。いわゆるマジックアワーの美しい風景だ。でも確かにそれはどこの景色かはわからない。旅行の広告企画には合わない写真だ。その写真は差し替えることになった。
山はそれぞれ印象的な姿を持っている。多摩川を散歩している時に見える富士山はもちろん、福岡の実家の窓の向こうの脊振山、新潟で営業車から見た弥彦山など山並みはそれぞれのアイデンティティを持ち土地の記憶と結びついている。しかし夕方、日が暮れ始めると山は徐々にその姿を失い始める。くっきりとした山肌は薄暗い大きな影になり、やがて地平線に溶けてゆく。それぞれの個性が消え匿名の風景となっていくのだ。だから夕暮れの遠い山を見たとき、僕たちは居場所を失うのではないか。それはここではなく、昔見た別の山かもしれない。いつか将来訪れる遠い場所の予感かもしれない。そうして不安な気持ちで消えていく山の端を見上げるのだ。
(ユキノ進)
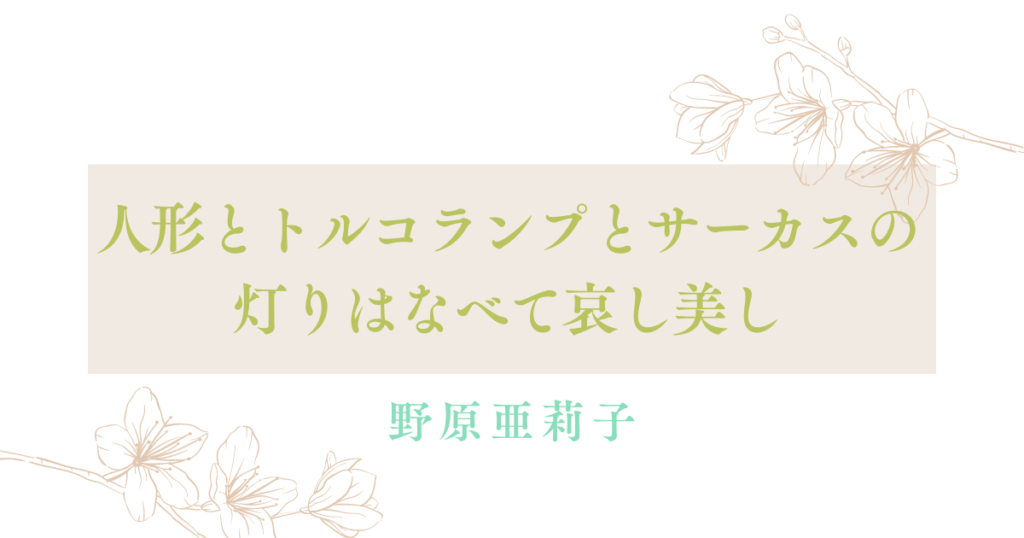
家にこもって人形ばかり作っているので、たまに外に出ると世界が美しくてびっくりする。空の色、葉っぱの色、光の色。立ち止まってゆっくり写生できたらどんな絵が描けるだろう。見える場所に山も枯野もないが、身の回りの小さな緑に光が差している様子や、人の手によって作られた灯りの暖かな美しさに感動してしまう。
印象派の画家たちは自然のなかの光を画面に写し取ろうとした。百年以上前の木漏れ日や池の面に揺れる光が今もわたしたちを魅了するのは、光というものがすぐに消えてしまうことを知っているからだ。戦争は印象派の画家たちにも暗い影を落とした。
少年・少女の肌は内側から光を放っているように明るい。そんな人形を作りたいと思う。いつ消えてしまうか分からない光や幸福な瞬間をそのまま留めたい。文学でもアートでも、たぶんそれが人としての最後の願いだと思うから。
(野原亜莉子)

秋になると市内の山裾を歩き回る。といっても、残念ながらハイキングではない。耕作をされなくなって荒れ果てた、かつて田や畑であったであろう土地だ。山隘を開墾して作られた田んぼや畑の所有者の名義は、今や其処には住んでいない都会在住の相続人である。
たまに手入れされた農地がある。しかしながら、農作業をしているのは若くても七十過ぎの人で、八十代というのは珍しくない。十年もしないうちにその田んぼも放棄地となり、たちまちのうちにセイタカアワダチソウに覆われるだろう。もしくは何処ぞか分からない都会の法人がソーラーパネルを敷設することであろう。
自宅からは二上山や葛城山が見えるが、あの山裾はどうなっているのだろう。ちょっと散歩をすれば、畝傍山、耳成山、香具山という大和三山があり、これらは国の名勝ということもあって手入れされている。国有地には民間の発電設備を設置されることもないので少しばかり安心、ではある。
(三潴忠典)
【今月、ご協力いただいた歌人のみなさま!】
◆ユキノ進(ゆきの・すすむ)
1967年福岡生まれ。九州大学文学部フランス文学科卒業。2014年、第25回歌壇賞次席。歌人、会社員、草野球選手。2018年に第1歌集『冒険者たち』(書肆侃侃房)を刊行。
Twitter:@susumuyukino

三潴忠典(みつま・ただのり)
1982年生まれ。奈良県橿原市在住。博士(理学)。競技かるたA級五段。競技かるたを20年以上続けており、(一社)全日本かるた協会近畿支部事務局長、奈良県かるた協会事務局長。2010年、NHKラジオ「夜はぷちぷちケータイ短歌」の投稿をきっかけに作歌を始める。現在は短歌なzine「うたつかい」に参加、「たたさんのホップステップ短歌」を連載中。Twitter: @tatanon (短歌なzine「うたつかい」: http://utatsukai.com/ Twitter: @utatsukai)
◆野原亜莉子(のばら・ありす)
「心の花」所属。2015年「心の花賞」受賞。第一歌集『森の莓』(本阿弥書店)。野原アリスの名前で人形を作っている。
Twitter: @alicenobara



【セクト・ポクリット管理人より読者のみなさまへ】
