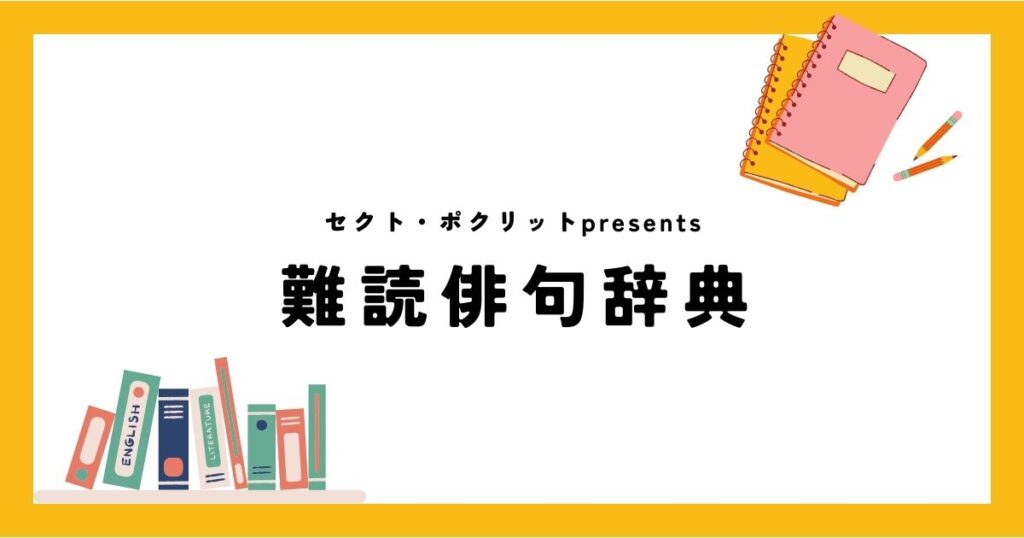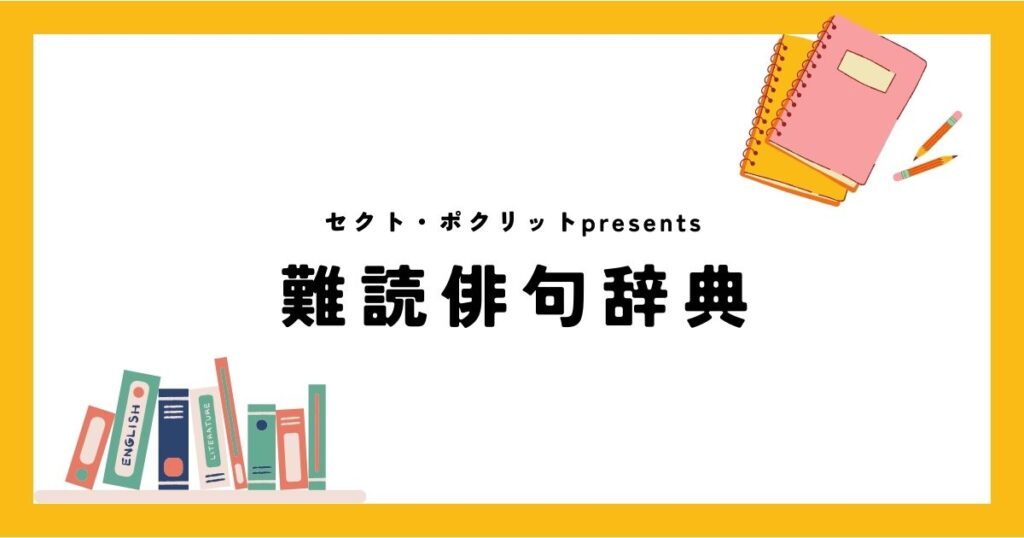
象
レベル ★★★★
使用頻度 ★☆☆☆☆
<ジャンル> 動物
【例句】
募集中
【解説】俳句で「象」といえば、この句がすぐに思い浮かびます。
象潟や雨に西施がねぶの花
象潟は、秋田県にかほ市にあった無数の小島が点在する入り江で、芭蕉が「松嶋は笑ふが如く象潟はうらむがごとし」と述べていた場所。奥の細道の「北端の地」としても知られますが、「ぞうがた」ではありません。「きさがた」と読みます。動物の「象」は昔の日本で「きさ」と呼ばれていました。
象潟の語源は、細かな入江が「刻まれて」いるからだとか、「蚶貝」がたくさんとれるから「蚶方」と呼ばれていたからだとか、言われるのですが、入江のかたちを「象牙」に見立てたという可能性もありそう。いずれにしても、この地に8世紀ごろ、蚶方法師という僧がお寺を建てたとのこと。
象の存在は、仏典を通じて日本でも昔から知られていましたが、生きているゾウが日本へ渡来したことが確認できる最も古い文献記録は、室町時代のもの(1408年7月15日)。若狭国小浜へ入港した南蛮(東南アジア)の船にゾウが積まれていたというもので、第4代将軍・足利義持への献上品だったそうです。
『萬葉動物考』によれば、「象」を「きさ」と呼ぶのは、象牙の横断面に橒(=木目の文)があるためであるそうです。ということは、大昔から大陸から象牙は輸入されていたというわけですね。
昔見し象の小河を今見ればいよよ清けくなりにけるかも 大伴旅人
「象の小川」は、吉野川に注ぐ川のひとつ。吉野山の青根ヶ峰や水分神社の山あいに水源をもっています。おそらく光眩い水面には「木目の文」のような、たくさんの線が見えることから、その名がついたのではないでしょうか。
「象」と漢字で書けば、おそらくほぼ100パーセントの人が「ゾウ」と読むでしょうから、現在「きさ」と読ませたければ、ふりがなに頼るほかないでしょうが、俳人のうんちくとしてひとつ、頭に入れておいてもよいかもしれません。最後に「象」でもっとも有名な句をひとつ。
月光の象番にならぬかといふ 飯島晴子
【「難読俳句辞典」バックナンバー】
>>【第9回】「蹼」 >>【第8回】「眴」 >>【第7回】「半月」 >>【第6回】「後妻・前妻」 >>【第5回】「蹇」 >>【第4回】「毳」 >>【第3回】「象」 >>【第2回】「尿」 >>【第1回】「直会」