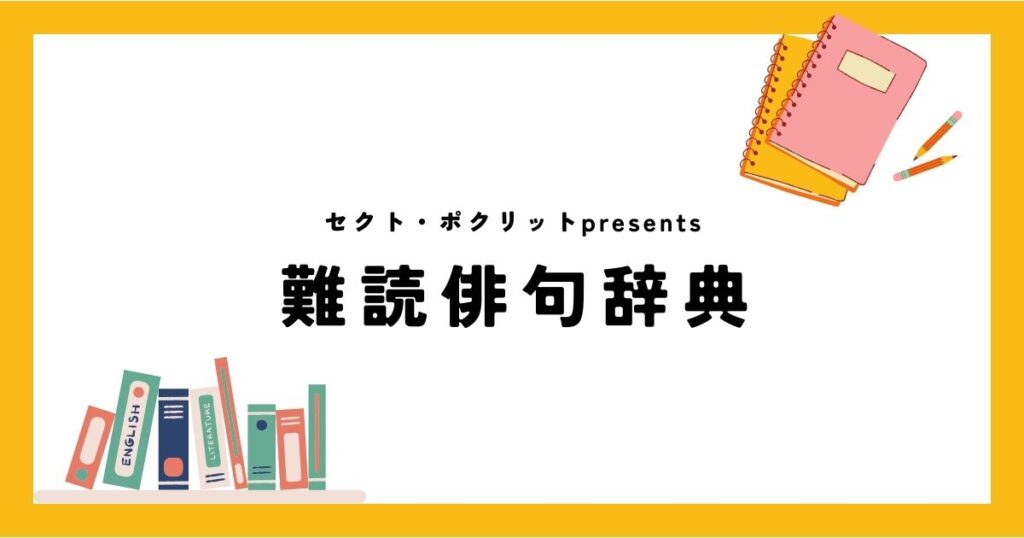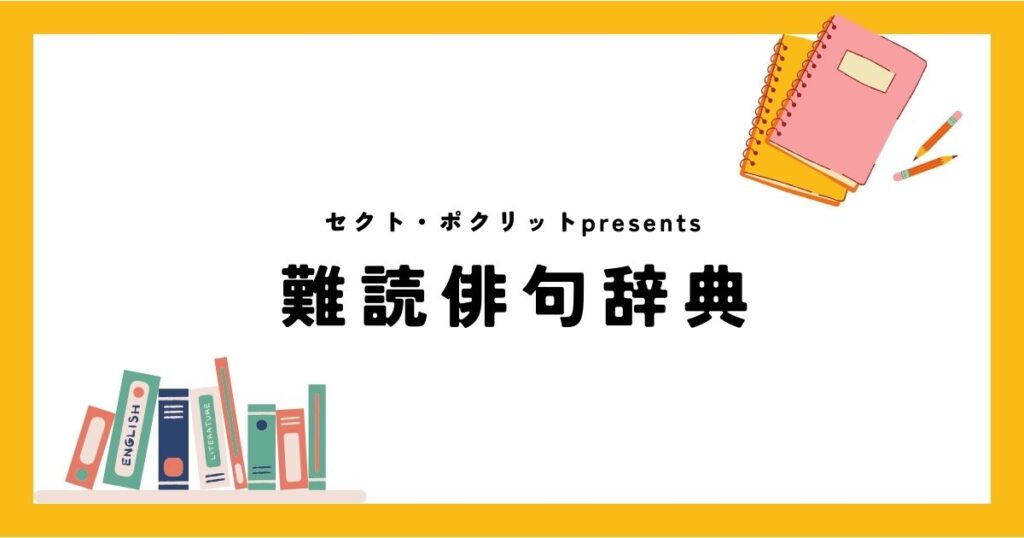
尿/尿
レベル ★★★☆☆
使用頻度 ★★★☆☆
<ジャンル> 生活・身体
<類語>おしっこ、小便、小水、ゆまりなど
【例句】
蚤虱馬の尿する枕もと 松尾芭蕉
枯るる貧しき厠に妻の尿きこゆ 森澄雄
天高し風のかたちに牛の尿 鈴木牛後
【解説】俗を愛する俳句において、「小便」をたくさん詠んだのは、小林一茶かもしれません。〈小便の滝を見せうぞ鳴蛙〉〈ちる霰立小便の見事さよ〉〈小便の穴だらけ也残り雪〉のように、数多くの小便俳句を詠んでいます。ためしに、一茶の俳句データベースに「小便」と打ち込んで検索してみると、「49句」もの小便俳句がヒットします。
誰もが毎日せざるをえない排尿行為は、日常であれば「おしっこ」と呼ばれていますが、俳句で「おしっこ」といえば、さすがに幼児的な印象を与えざるをえません。そこで、そのような印象を与えずに「おしっこ」を詠むための方法が、この「しと/いばり」です。2音にも3音にも対応しているスグレモノです。
「この宮に御しとにぬるるは、うれしきわざかな」――これは、紫式部日記「若宮誕生」の場面ですね。「殿」こと、藤原道長が赤ちゃん(若宮)を抱っこして、「お漏らし」の被害に遭うところ。こういうのもかわいいよねえ、といいながら、火にあぶって服を乾かしていることもあった、という紫式部目線の描写です。
たぶん、「しっこ」に「お」をつけるように、「しと」に「御」をつけて「おしと」。高級感のある排泄物です。間違っても子供にそんな名前つけてはいけません。
「おしっこ」は、あまりに日常的であるがゆえに、出そうになるときに「おしっこ!」と言ってみたり、つまり行為そのものを指すことがありますが、「尿」はあくまで排泄された液体を指す言葉。ちなみに汗や涙や雨でぐっちょぐちょに濡れるのは「しとど」です。
体のなかから排泄されたおしっこは、「お湯」のようにほかほかです。そして排泄行為のことを昔のことばで、「まり」といいます(うんちが時に「鞠」のようなかたちをしているからでしょうか?)。そこから、おしっこのことを「ゆ+まり=ゆまり」あるいはそこから音が変わって「ゆばり」「いばり」と言うようになりました。
「伊弉諾尊、乃向大樹放尿。此卽化成巨川」――これは『古事記』の国産み神話。こちらは、行為としての「おしっこ」に近く、「放尿」という感じが当てられています。
これを、やまとことばとして言うなら、「ゆまる」となり、排泄された液体は「ゆまり」となります。いまはもう誰も『古事記』や『日本書紀』を読まなくなってしまいましたが、ある程度の年代までには、了解されている言葉だったのでしょう。西東三鬼には、
女立たせてゆまるや赤き旱星
という変態句があります。
【「難読俳句辞典」バックナンバー】
>>【第9回】「蹼」 >>【第8回】「眴」 >>【第7回】「半月」 >>【第6回】「後妻・前妻」 >>【第5回】「蹇」 >>【第4回】「毳」 >>【第3回】「象」 >>【第2回】「尿」 >>【第1回】「直会」