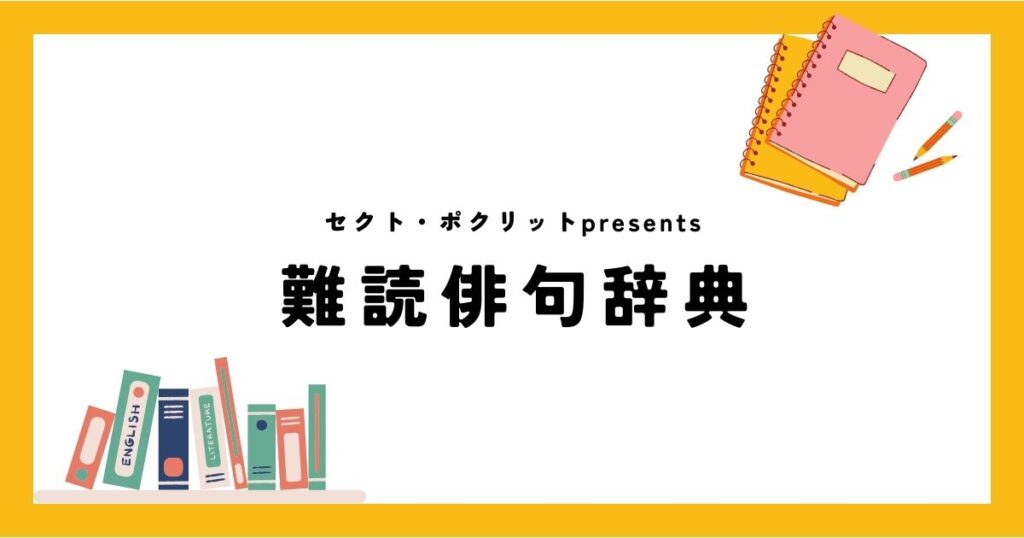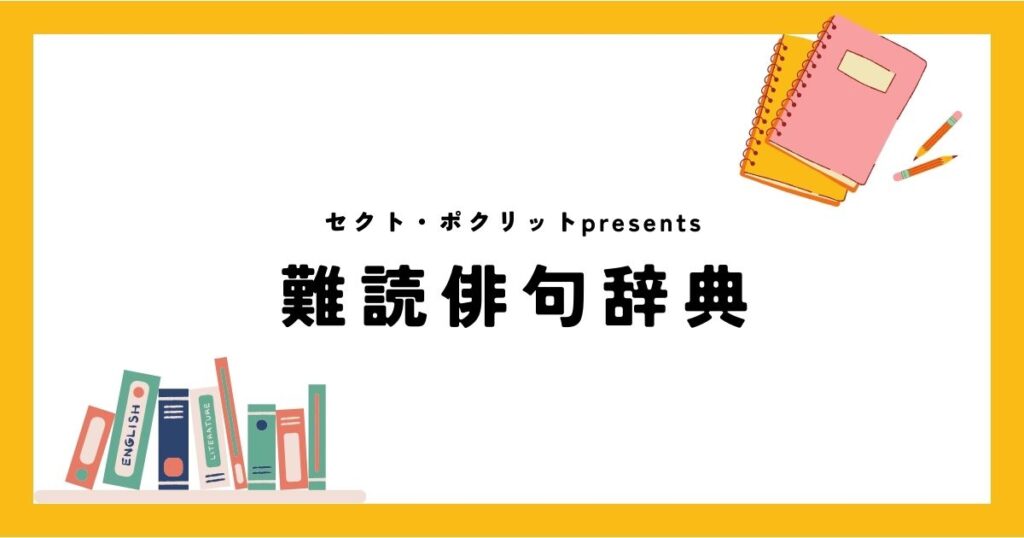
眴
レベル ★★☆☆☆
使用頻度 ★★★☆☆
<ジャンル> 動作
<類語>めまじ・めまぜ(目交)
【例句】
火恋し鳰に眴せしたのちは 市場基巳
初猟の眴せで舟うごきけり 小野寺清人
ひさしぶりの記事なので(サボっていてすみません)、今回はわりと簡単な漢字をひとつ。一般に「目配せ」と書くこともある「めくばせ」ですが、本当は「眴」という漢字が用いられます。この漢字はもともと(中国では)「まばたき・またたき」のことを意味していたところから、「目を動かして合図をする」という意味に(ちょっとだけ)拡張されて使われるようになりました。
では、「めくばせ」の歴史を少し。平安時代には、目で合図をすることを「めをくはす」といっていました。「くはす」は「食はせる」ということ。これが「めくはす」と助詞が落ちて動詞として使われるようになり、たとえば伊勢物語には、
世をうみのあまとし人をみるからにめくはせよともたのまるるかな
の用例があります。歌意は、「海で海女として暮らしている人だとお見うけするので、お目にかかると海藻を食べさせてもらいたいと心まちにしてしまう」という次第。ちなみに、「うみ」は倦みと海、「あま」は尼と海女、「みるからに」は見るだけでと海藻の海松、「めくはせよ」は目で合図をなさいと海藻の布(め)をたべさせよの掛詞のオンパレード。
その後、中世末に「めぐはせ」も登場、江戸時代になると「めくばせ」が出てきて、現在に至っているわけです。
動詞としても「めくはす」は濁音化して「めくばす」へ。もともと「食はす」というハ行活用の動詞に由来しますので、現代日本語ではワ行に転じていますが、歴史的かなづかいでは、「ハ行・バ行」で活用することになります。意味的には、「〜を食わせる」という使役のニュアンスがあるため、四段活用ではなく、下二段活用となります。つまり、完了の「り」には接続せず、「眴せり」は誤り。
「眴煥」は「目をひくほど鮮やかなさま」を表す漢語で、「けんかん」と読みます。
【「難読俳句辞典」バックナンバー】
>>【第9回】「蹼」 >>【第8回】「眴」 >>【第7回】「半月」 >>【第6回】「後妻・前妻」 >>【第5回】「蹇」 >>【第4回】「毳」 >>【第3回】「象」 >>【第2回】「尿」 >>【第1回】「直会」