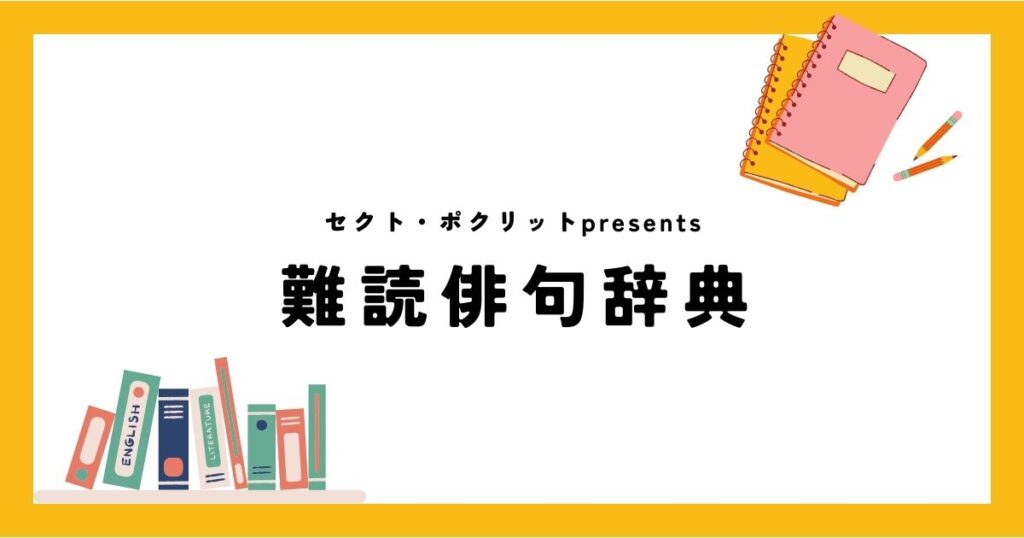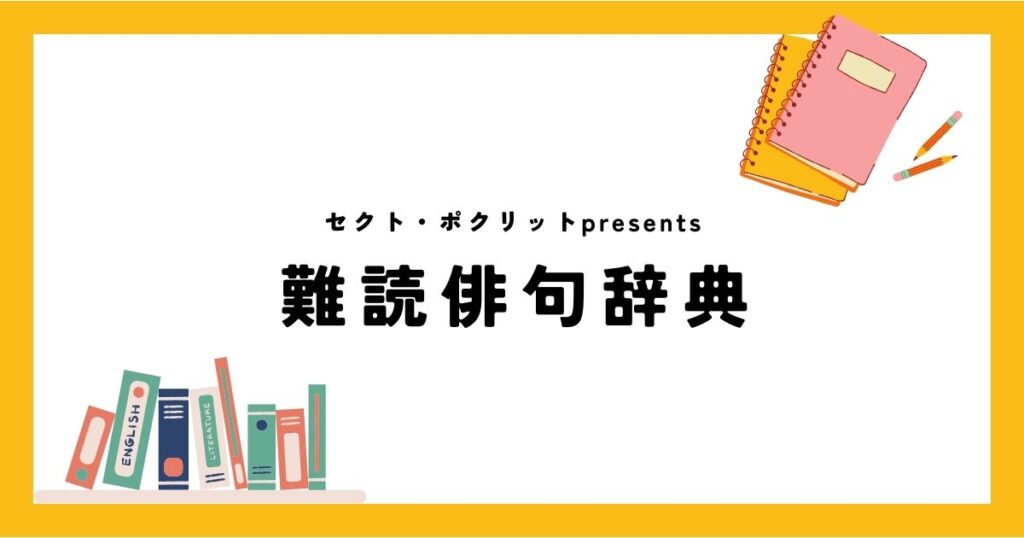
蹼
レベル ★★★☆☆
使用頻度 ★★★☆☆
<ジャンル> 身体
【例句】
夜濯や蹼のこる指の股 高橋睦郎
蹼のうごき止まざる涅槃西風 有住洋子
蹼の吾が手に育つ風邪心地 奧坂まや
蹼のたどりつきたる草の花 石田郷子
桜餅指に蹼ありしころ 相子智恵
カエルや水鳥などに見られる指と指のあいだの膜。あれは「水を掻く」ためのものなので「水掻き」。そのまんま、なのですが、中国語では「蹼」というそうで、この漢字に「みずかき」という訓を当てることもあります。漢字一字で書くと、動作性が少し後ろに退いて、「もの」としてのミズカキが独立性をもつような印象を受けます。
科学的にいうと、多くの哺乳類で「蹼」がないのは、酸素濃度と関係しているそうです。酸素が濃いところでは、指の間で「細胞死」が起こって、「蹼」ができなくなる。足に水かきのある両生類のアフリカツメガエルのオタマジャクシを、高濃度の酸素を入れた水槽で育ててみると、成長するなかで、本来は起こらない細胞死によって「蹼」がなくなるのだとか。
こうした「蹼」の研究をリードするのが、東工大の田中幹子先生。
山陰中央新報デジタル ー 科学スコープ「生き物の四肢」 水かき、手足…なぜ多様? 指間細胞死の有無が関係
たしかに手足の指のかたちは、生物でさまざま。そこに「指間細胞死」というシステムが横たわっているというのは、面白い話ですね。進化とは何なのか、という考え方が変わるきっかけになるかもしれません。
ところで、水泳選手には「蹼」がある……そんな話を聞いたことがある人も多いのではないでしょうか? そんな短期間に身体って「進化」するの?と半信半疑な方もいると思いますが、これは科学的にはウソ。一説によれば、ソウルオリンピックで金メダルをとった鈴木大地選手が、「私の手には、水かきがついている」と発言していたことが影響したのだとか。
その影響なのか、俳句でもしばしば人間に「蹼」がある、という句を目にすることがあります。
【「難読俳句辞典」バックナンバー】
>>【第9回】「蹼」 >>【第8回】「眴」 >>【第7回】「半月」 >>【第6回】「後妻・前妻」 >>【第5回】「蹇」 >>【第4回】「毳」 >>【第3回】「象」 >>【第2回】「尿」 >>【第1回】「直会」