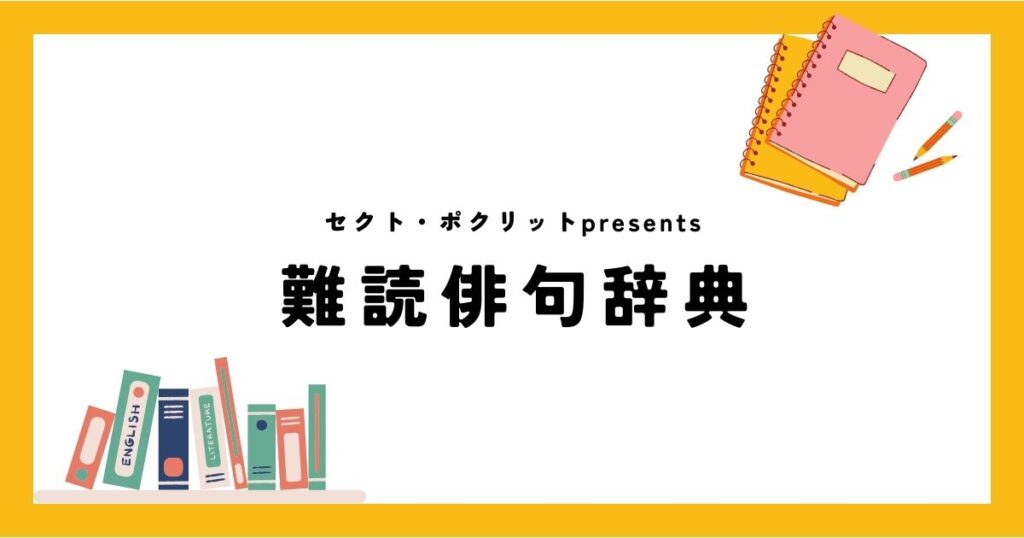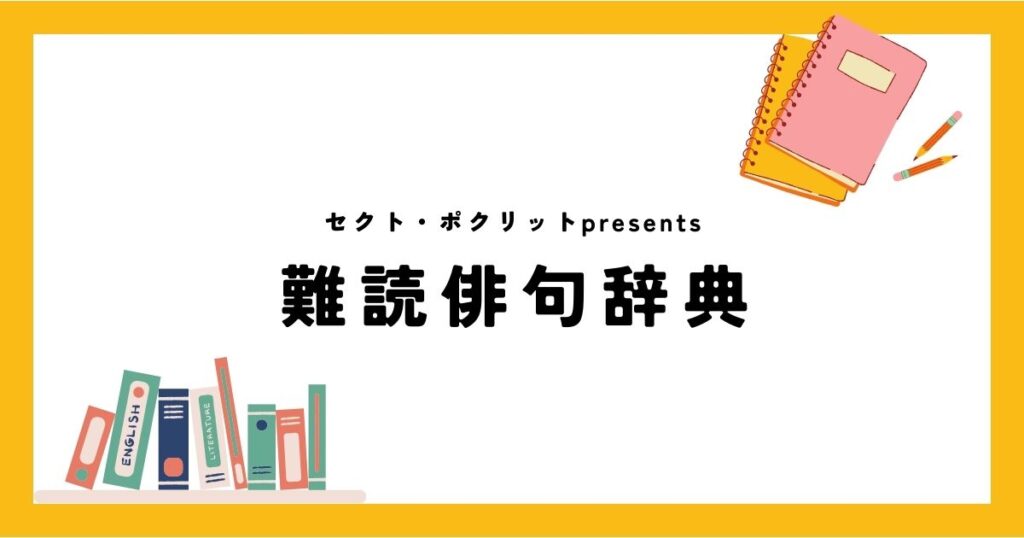
蹇
レベル ★★★★★
使用頻度 ★☆☆☆☆
<ジャンル> 身体・動物
<類語>歩行困難、肢体障害、下肢機能障害など
【例句】
曳猿の蹇すなるあはれなり 後藤夜半
凧揚げて蹇が夢はぐくめり 阪東英政
蹇が霜夜の妻を哭かしゐて 小林康治
【解説】身体障害にかかわる言葉は、差別との関わりが強いため、時代の要請を免れませんが、「蹇」という言葉は、大昔から使われてきたがゆえに、いまでは忘れ去られている言葉のひとつかもしれません。
もともと、日本語に「あしなへ」という言葉があり、これは文字通り「足が萎える」ということ。足が不自由になること、足がいうことをきかなくなることを、かつては「蹇へぐ」「蹇ふ」と言いました。人間以外にも使われてきた言葉で、「四河入海」という17世紀の文献には、「あしなへたる羊なんどが…」という用例が見られます。
ちなみに、「蹇」という漢字の音読みは、漢音で「ケン」です。
そう、これってもしかして「けんけんぱ」や「けんけんで歩く」の「けん」なのではないでしょうか?
漢音の「蹇」という字は、もともと「足の不自由なさま」という意味が第一義で、そこから「行動が遅いさま」(蹇緩)や「お金がなく苦しんでいること」(窮蹇)などの意味が派生しました。「跛蹇」というのは、不自由な足をことばで、それは漢字のかたちにも表れていますね。「蹇足」という言葉もありますが、「蹇跛」あるいは「蹇歩」という言葉もありますから、そこから「けんけんぱ」という遊びにつながっているのではないかと考えられます。
ちなみに、ほぼ同様の意味をもつ「跛」という漢字にも「あしなへ」という読みを与えてきましたが、同時にこの漢字には、「びっこ」や「ちんば」といった、現在では差別的用語として使用を差し控えることがコンセンサスとなっている言葉も読みとして与えられています。
すべての人が五体満足というわけではなく、いつ誰もが病気や事故で足の機能を損傷/喪失するかは、わかりませんから、「足が萎えている」くらいで、ハンデを被らないような互助的な社会をつくることを、わたしたちは常に念頭に置いておく必要があるのでしょう。
【「難読俳句辞典」バックナンバー】
>>【第9回】「蹼」 >>【第8回】「眴」 >>【第7回】「半月」 >>【第6回】「後妻・前妻」 >>【第5回】「蹇」 >>【第4回】「毳」 >>【第3回】「象」 >>【第2回】「尿」 >>【第1回】「直会」