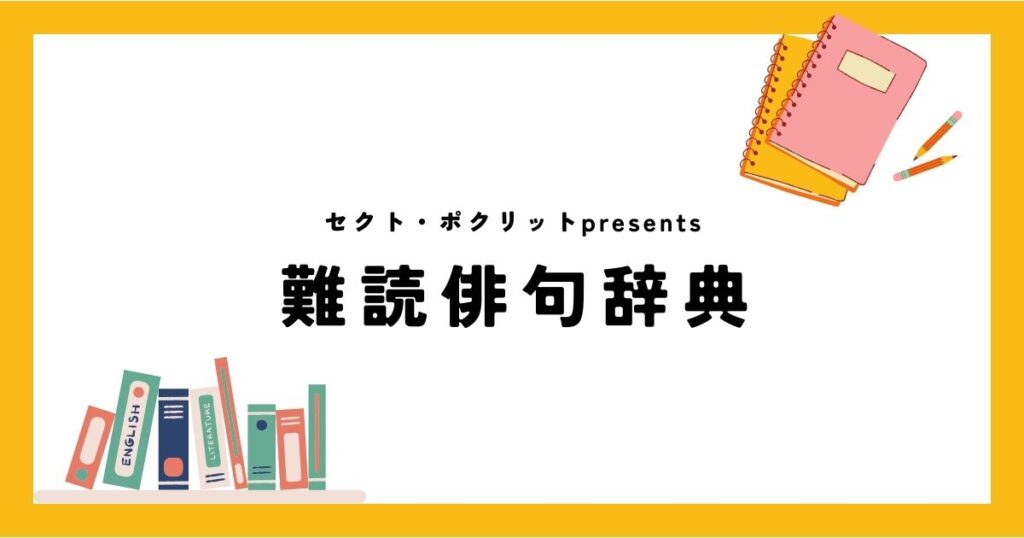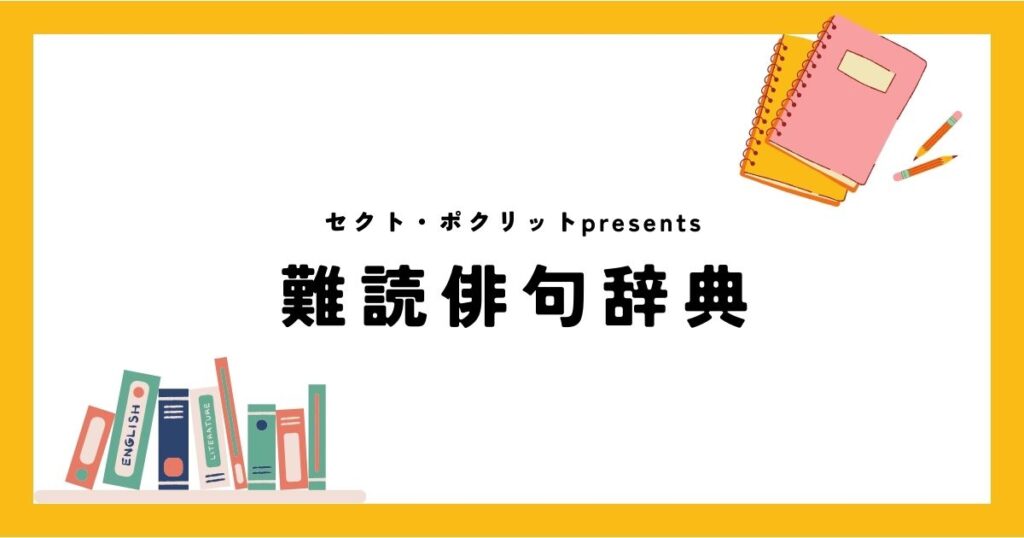
毳/毳/毳立つ
レベル ★★★★★
使用頻度 ★★☆☆☆
<ジャンル> 身体・動物
<類語>産毛、和毛、柔毛など
【例句】
けだものに生まれ瞼にさえ毳 長岡裕一郎
生乳の毳立つほどに春めける 中村和弘
みちのくの毳立つ茅の輪くぐりけり 矢島渚男
【解説】やわらかい毛のことを「和毛」と書いて「にこげ」と読みます。というか、もともと「にこげ」という言葉があって、それに「和毛」という漢字を当てています。たまに「毳」という漢字を当てることがあり、この一字で「毳」と読ませるのですが、訓読みだと「毳立つ」となります。
きっと「けばだつ」は普通、漢字で書くなら「毛羽立つ」と書かれる方が多いのではないでしょうか。もともと、「毳」は、獣の細かい毛を意味しており、そこから毛皮や毛織物、フェルトなどの製品を指すようになりました。古代中国では、「冕服」といって、ハイソな人たちが粗めの毛織りの衣服を身につけていたので、「毳衣」というのは礼服や僧服のことを意味していました。
そのような経緯から、「にこげ」ないしは「むくげ」、あるいは「けば」という訓を当てたというわけです。
つなげる糸に蜩の啼 其角
瓢箪の毳のうちは葉がくれて 神叔
青木神叔は、江戸前期の俳諧師のひとりで、上の句は『萩の露』(1693)に収められています。「むく」というのは、「毛がふさふさとしていること」を指す言葉で、「尨」という漢字を当てるのが、一般的。瓢箪の果実は、最初皮に細かい毛がありますが、成熟すると毛が落ちて、つるつるになります。
だから厳密にいえば、「むくげ」と「にこげ」はニュアンスが少し違います。「にこげ」は、鳥のお腹のあたりの毛のイメージ、「むくげ」は犬の体毛のイメージです。昔のことばで、毛がふさふさしている犬のことを「むくいぬ」や「むくげいぬ」などと言いましたが、漢字で書くと「尨犬」となります。
【「難読俳句辞典」バックナンバー】
>>【第9回】「蹼」 >>【第8回】「眴」 >>【第7回】「半月」 >>【第6回】「後妻・前妻」 >>【第5回】「蹇」 >>【第4回】「毳」 >>【第3回】「象」 >>【第2回】「尿」 >>【第1回】「直会」