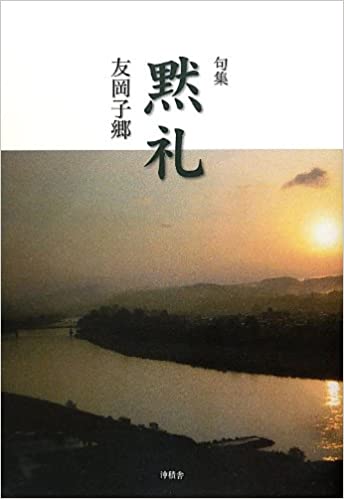【連載】
「震災俳句を読み直す」第9回
加島正浩
震災を語る方法の「二極化」にあらがう
――友岡子郷『翌』・照井翠『龍宮』
阪神淡路大震災で被災した俳人のひとりに友岡子郷がいる。〈倒・裂・破・崩・礫の街寒雀〉の句をご存じの方も多いだろう。
その句を収める友岡の句集『翌』(ふらんす堂、1996年9月)には、―句集の後半に〈かの惨の日々うすれゆく吾亦紅〉という句もあり、被災直後を除いては、震災を頻繁に詠んでいるわけではないため、それほど多くはないが―阪神淡路大震災被災直後の句が収録されている。
目を惹くのは、友岡の句の「まぶしさ」である。
着の身着のままにまぶしき寒卵
焦げし木に懸けまつさらのランドセル
寒塵のきらきら立てり死者運び
その「まぶしさ」は被災直後の現実と対照されており、特に2句目の〈まつさらのランドセル〉と〈焦げし木〉の対照、きらきらと立った塵が「死者」を運んだときのものを示す3句目の対照はわかりやすく、〈被災〉と〈日常〉の対照が鮮やかに示されているといってよいだろう。そして対照的な〈被災〉と〈日常〉の様子が一句に収まることにより、〈被災〉と〈日常〉は地続きにつづいていること、〈被災〉のなかにも〈日常〉の生活があること、〈被災地〉にも「まぶしい」ものが存在していることを、鮮やかに示すことに成功していると考える。
ただそのように友岡の句を読むとき、対照的な俳人を思い出してしまう。第1回、第8回でも取り上げた俳人、照井翠である。岩手県釜石市で津波により被災した照井の句は、友岡とは対照的に「暗い」。第1回でも取り上げた『龍宮』には、〈津波より生きて還るや黒き尿〉、〈朧夜の泥の封ぜし黒ピアノ〉、〈春昼の冷蔵庫より黒き汁〉など「黒色」を強調した句が収められている。また堀切克洋の巻頭言では、照井の『泥天使』が「泥」がライトモチーフに世界観を深めていることが指摘されているが、『龍宮』にもそのような深まりまではないものの「泥」は多く登場する。〈泥の底繭のごとくに嬰と母〉、〈御くるみのレースを剥げば泥の花〉、〈冥土にて咲け泥中のしら梅よ〉などが挙げられるが、ここでは友岡の句との対比で〈喉奥の泥は乾かずランドセル〉という句に着目したい。
友岡は「焦げた木」と「まっさらなランドセル」をひとつの句のなかで対照させることで、〈日常〉へとつづいていく(あるいは戻っていく)〈被災地〉の姿を描いているが、照井は、泥とともにあるランドセルを詠むことで、〈被災〉した時点で時間が止まっている〈被災地〉を描いている。
もちろん友岡も〈寒夜また火を曳き走る夢に覚め〉のような〈被災〉した瞬間に引き戻されるような句を詠んでおり、照井にも〈死の川の底に緑の差し初めぬ〉のような時間の経過を思わせるような句は存在するが、概して言えば、友岡の『翌』は〈被災〉後の〈日常〉へと戻っていく場面をとらえた句集であり、照井の『龍宮』には〈被災〉の瞬間で時間を止めてしまったような光景が広がっているとまとめることができるだろう。
私はそのような概括をすることで、友岡が未来志向で楽観的だとか、照井が悲観的であるなどと言いたいわけでは、当然ない。俳人の個性の違いはもちろんあるだろうが、私が考えているのは、阪神淡路大震災と東日本大震災というのは(想像以上に)全く違う災害だったのではないかということである。
東日本大震災以後、阪神淡路大震災の教訓を踏まえた災害対応が行われた。阪神淡路大震災時に避難所生活で高齢者のストレスが高まり、孤独死などがみられたことを踏まえ、避難所に交流スペースを設け、震災以前の地域コミュニティを極力崩さないように避難所への入居を進めるなど、阪神淡路大震災の教訓を踏まえることで効果をあげた事例は、私が知る限りでも多々ある。また人文学の領域でも、阪神淡路大震災と東日本大震災を(その差異も踏まえつつ)つなげて考えようとする研究書の出版が多々みられた。
私も阪神淡路大震災を踏まえて、東日本大震災を考えることが「文学」研究においても有効であると素朴に考えていた。しかし本当にそうだろうかと悩まざるをえない。たとえば友岡は東日本大震災以後に出版した句集『黙礼』(沖積舎、2012年8月)にて以下の句を詠んでいる。
だれにでも朝日はとどく松の芯
「3・11東日本大震災。以後このこと念頭を去らず。われにも震災の句あれば。」と但し書きのついた一連の句のなかに上句は収まっており、東日本大震災を踏まえて(おそらくは「被災者」に向けて)詠んだ句ではないかと判断できる。〈だれにでも朝日はとどく〉と記す友岡には、それが「希望」であるとの思いがあるのだろう。しかし照井の『龍宮』には以下の句がある。
春光の影となるものなかりけり
津波で何もなくなってしまった場所には春の光がそのまま差し込んでしまうのである。つまりそこでの太陽の光は、〈被災〉を思い出させるものでしかなく、再度〈被災者〉を「絶望」に突き落とすものであるのかもしれない。友岡と照井で日光の意味が反転しているのである。
このことから私は、友岡が東日本大震災の〈被災地〉のことを何もわかっていないなどと糾弾したいわけではない。ただ私は友岡の句を読むことで、阪神淡路大震災の〈被災〉の経験から、東日本大震災への〈被災者〉や〈被災地〉へと接近することはできないか、一般化すれば、ある災害や過酷な経験を基に、別の災害や過酷な経験を〈想像〉することは可能なのかを考えてみたかったのである。
短絡的に結論を出すのは控えたいが、今回私はその可能性を見出すことはできず、むしろ「阪神淡路大震災」と「東日本大震災」は別の災害であり、それぞれ異なる〈被災の現実〉に直面したという「事実」が明確になった。しかし、避難所運営や災害対策を考察するマクロの視点で両災害がつなげられることで、見えなくなってしまうふたつの災害の差異を明らかにするのが、「文学」や俳句の仕事でもあるだろう。マクロの視点からは、〈被災〉した個人の「経験」や思いは見えにくくなってしまうため、それに明確な形を与えるのが「文学」や俳句の形式であるといえるかもしれない。
しかしそうであるのならば、考えなければならないのは〈被災地〉を離れて俳句を詠むことは可能なのかということである。連載の第4回で長谷川櫂の『震災句集』を扱ったが、『震災句集』が大変な不評を買ったことはご存じの方も多いだろう。その批判の力点は「被災地を一度も訪れることなく」震災を詠んだことにあった。
もちろん〈被災地〉から離れて詠むことで、〈被災地〉の現実とはかけ離れたことを詠んでしまう恐れはある。友岡は朝日が希望であることを示したが、照井はそれが必ずしも希望ではないことを詠んでいた。そのことは〈被災〉した〈被災者〉にしかわからないことかもしれない。だからこそ〈被災者〉が詠んだ俳句に教えられることは非常に多い。
しかし東日本大震災発災から10年以上が経つにもかかわらず、〈被災者〉以外がーあるいは〈被災地〉を訪れて、〈被災者〉や〈被災地〉のことを徹底的に知ったうえで書くこと以外に―震災を語る/詠む/書く方法がないのではないかと私は考える。
私は、〈被災者〉の言葉と〈被災地〉の現状を基に、「震災」を書き、東日本大震災以後の「文学」研究を進めるという方法を取ってきた。それは、文学研究/評論界隈では定着した感のある「震災後文学論」という東日本大震災以後を研究する枠組みが〈被災者〉と〈被災地〉の現実の一切を排除していたからである。〈被災者〉と〈被災地〉の現実を切り捨てて、「震災」の何を研究したことになるのか、と私は問うているつもりではある。
しかし最近は、それだけでは不十分だとも考えている。一方の極に〈被災者〉と〈被災地〉の現実を一切排除した「文学研究」のやり方があるのだとすれば、もう一方の極が私のような〈被災者〉の言葉と〈被災地〉の現状を踏まえた研究のやり方だということになるだろう。それは両方とも「極端」なのである。
そのため両方の研究に限界がある。私自身の研究方法では、震災を語る新たな枠組みを創出することが困難なのである。
2021年11月現在、〈被災者〉でないものが震災を語る方法は、〈被災地〉や〈被災者〉を無視するか、あるいは徹底的に〈被災地〉や〈被災者〉のに寄り添うか。そのふたつしかないように思う。その「両極」のあいだで、語る方法を創出しなければ、やはり忘却は進んでいくように思う。一方は〈被災地〉は眼中になく、もう一方は〈被災者〉から〈被災地に詳しい専門家〉に代わっただけなのだから。
「文学」や俳句が、それが「作品」であるという枠を超え、語りがたい思いに形を与えるものであるとするならば(そのために独特の形式が備わっていると考えるならば)、それを研究することで、新たな語り方を考案することはできるのではないかと思う。
〈被災者〉だけが震災で心を痛めたわけではない。〈被災者〉だけが震災のことを気にかけているわけではない。「震災後」の影響を被ったわけでもない。しかし、それは十分に語られてきておらず、それを十分に語ることができる「形式」を確立することもできていないと考える。
〈被災地〉で起こっていることが忘却にさらされ、無視され続けている現状では、私は今まで通り〈被災地〉を踏まえた研究を継続していくつもりではあるが、震災や〈被災〉の語り方のバリエーションを増やす試みも行っていきたい。
なぜなら日常の言語では語りにくいことを語るために、「文学」や芸術、そして俳句の仕事はあると私は考えているからだ。そしてそうであるならば、震災の「語り方」を考えるのも「文学研究」の仕事であるはずだからだ。
様々に領域を横断しながら、奮闘していきたい。
【執筆者プロフィール】
加島正浩(かしま・まさひろ)
1991年広島県出身。愛知淑徳大学ほか非常勤講師。主な研究テーマは、東日本大震災以後の「文学」研究。主な論文に「『非当事者』にできること―東日本大震災以後の文学にみる被災地と東京の関係」『JunCture』8号、2017年3月、「怒りを可能にするために―木村友祐『イサの氾濫』論」『跨境』8号、2019年6月、「東日本大震災直後、俳句は何を問題にしたか―「当事者性」とパラテクスト、そして御中虫『関揺れる』」『原爆文学研究』19号、2020年12月。
【「震災俳句を読み直す」バックナンバー】
>>第8回 「喪失」から遠く離れて
―青眼句会合同句集『フクシマ以後』・照井翠『泥天使』
>>第7回 「忌」ではない別の表現を
―『浜通り』浜通り俳句協会
>>第6回 書く必要のないこと
―小野智美編『女川一中生の句 あの日から』
>>第5回 風と「フクシマ」
―夏石番矢『ブラックカード』・中村晋『むずかしい平凡』
>>第4回 あなたはどこに立っていますか
―長谷川櫂『震災句集』・朝日新聞歌壇俳壇編『阪神淡路大震災を詠む』
>>第3回 おぼろげながら浮かんできたんです。セシウムという単語が
―三田完『俳魁』・五十嵐進『雪を耕す』・永瀬十悟『三日月湖』
>>第2回 その「戦場」には「人」がいる
―角川春樹『白い戦場』・三原由起子『ふるさとは赤』・赤間学『福島』
>>第1回 あえて「思い出す」ようなものではない
―高野ムツオ『萬の翅』・照井翠『龍宮』・岡田利規「部屋に流れる時間の旅」
【セクト・ポクリット管理人より読者のみなさまへ】