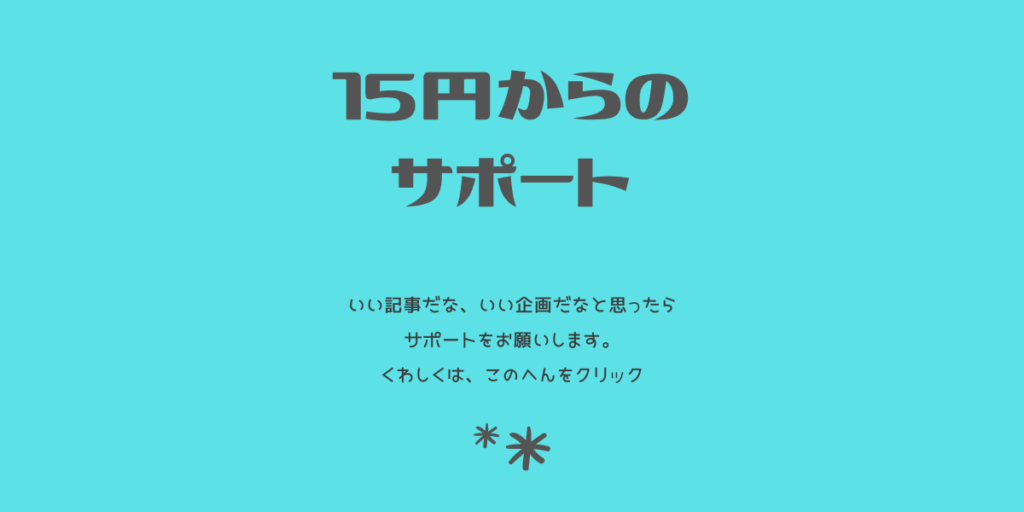菜の花や月は東に日は西に
与謝蕪村
いま東京のマンスリーマンションで「帰国者の自主隔離」に挑戦している。知らない土地で、マンションにこもっているのって辛い。家のまわりを散歩するくらいは許されているものの、公共交通機関をつかったり、喫茶店やレストランに入ったりと、人と接触するのは駄目といわれている。
この連載を書こうにも本がないので、頭の中にある句を引用することになる。それでわかったのは、わたしの頭の中には句が入っていないという事実だ。うーんと考え込んでいたら、中学校で習った、
菜の花や月は東に日は西に 与謝蕪村
が浮かんだ。摩耶山を訪れたときの句らしい。芭蕉や一茶とくらべて、蕪村って近代的でおしゃれな人だなあ、と感動した記憶がある。じっさい芭蕉、蕪村、一茶とならべた場合、俳句を知らない人にも好かれる(つまりわかりやすい)のは蕪村にちがいない。
蕪村の句は伝統を重んじつつも、実験的な手法を自在に駆使し、しかも都会的でおしゃれである。〈菜の花や〉における古典とはなにかというと、膨大な数にのぼる「日と月」の対句表現だ。なかでも蕪村の座右の書であった陶淵明の雑詩〈白日は西の阿に淪(しづ)み、素月は東の嶺に出づ、遥々たり万里の暉、蕩々たり空中の景〉は、日と月を天にかかげた蕩遥たる望景が描かれる点で、光景的にも心象的にも〈菜の花や〉とぴったりあっている。きっと摩耶山から地上を見渡したとき、しぜんと陶淵明の詩が思い起こされたんじゃないかしら。
ここから蛇足。蕪村の句は絵画的と言われることが多いけれど、これは芭蕉の句が写実的だと言うのと同じくらい眉唾だ。もちろん〈菜の花や〉は絵画的にも完璧で、わたし自身も絵みたいだと感じるけれど、当の蕪村がまったく違うイメージを抱いていた可能性は否定できない。なぜなら〈菜の花や〉は広大な自然空間と天文とをあつかった句ゆえ、瞬間ではなく二物の運動を捉えたとみなすと句柄の雄大さがより光ってくるし、そもそも「日と月」の対句表現は、陶淵明の詩にかぎらず時の流れを含意するのがふつうでもあるからだ。そういえば、蕪村にはこんな句もある。
月光西にわたれば花影東に歩むかな 与謝蕪村
月光が西にわたるにつれて花影が東に歩んでゆくよ、という意味だ。見れば見るほど破天荒でじわじわくる。この句には「花影上欄干、山影入門など、すべてもろこし人の奇作也。されど只一物をうつしうごかすのみ。我日のもとの俳諧の自在は、渡月橋にて」の前書きがある。あれやこれやといった中国のすばらしい詩があるが、動いているものは一物だけ。それとくらべて我が日本の俳諧は自在なものだよ、と言うのだ。一物ではなく二物をうつしうごかし、俳諧の自在を実演してみせた蕪村。運動を描写するのみならず、この句自体が俳諧の自在さを体現した実験的な「動く俳句」に思えるのはわたしだけだろうか。
(小津夜景)
【執筆者プロフィール】
小津夜景(おづ・やけい)
1973年生まれ。俳人。著書に句集『フラワーズ・カンフー』(ふらんす堂、2016年)、翻訳と随筆『カモメの日の読書 漢詩と暮らす』(東京四季出版、2018年)、近刊に『漢詩の手帖 いつかたこぶねになる日』(素粒社、2020年)。ブログ「小津夜景日記」
【セクト・ポクリット管理人より読者のみなさまへ】