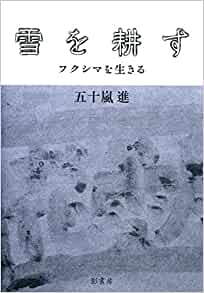【連載】
「震災俳句を読み直す」第3回
おぼろげながら浮かんできたんです。セシウムという単語が
―三田完『俳魁』・五十嵐進『雪を耕す』・永瀬十悟『三日月湖』
加島正浩(名古屋大学大学院博士課程)
三田完『俳魁』(角川書店、2014年2月)という小説がある。
定期的な原稿料を俳句の連載コラムで得る程度のさほど有名ではない小説家である玄という男を中心人物に小説は展開する。小説内で俳壇の重鎮とされている窪島鴻海という人物が、なぜかうだつの上がらない作家である玄に関心を寄せている。鳴海は石巻市の出身で、俳人としては広島の原爆詠で名を上げた人物である。
ある時、玄は俳人であった母の遺品を整理しているときに鳴海と母が師弟関係にあったことに気が付く。そして鳴海の句とされている俳句の原型が母の句にあることに気がつき、俳人であった自らの母が鳴海と師弟を越えた「特別な」関係にあったのではないかと玄は疑問を抱く。そのようななか、鳴海が震災後の故郷石巻を詠むことになり、その同伴者に鳴海は玄を指名し、ふたりは石巻に赴くことになる。
『俳魁』は、「色」気が多く、結社が色恋の人間関係の網目でがんじがらめになっており、句会が愛人に会う口実に用いられるテクストの表現に苛立つ方もいらっしゃるかもしれないが(パワハラ・セクハラの温床になりやすい師弟関係を含む場であるからこそ)その点は一度わきに置く。
ここで問題にしたいのは、窪島鳴海という俳人が詠んだ俳句を東日本大震災後に読むというテクストの仕掛け、また原爆詠で世に出た俳人の出身地が石巻であるという設定である。
彼が詠んだ句は以下のようなもので、それを東日本大震災後に読む玄は以下のような感慨を抱いている。
一閃の朝・蝉黙す街となる
饐ゆる飯すらなし女性徒ら死屍またぐ
黒き雨刺す広島の朱夏原爆を受けた直後の広島、すべてが巨大な火の塊に灼きつくされた街を詠んだ鳴海の句に、どうしてもここ数日のニュースで眼にする風景を重ねてしまう。家々が根こそぎ津波に吞み込まれた三陸の港町、あるいは水素爆発であばら骨をさらす原子力発電所の建物を。
『俳魁』、45頁
原爆を詠んだ俳句に東日本大震災および原発「事故」以後の風景を重ねてしまうのは、それが「正しい」行為であるかどうか(さらにその「正しさ」を「問う」ことができるかどうかも)別として、震災後に俳句を触れる人間の態度として理解できるものではある。ただ鳴海が原爆を詠んでいたという設定は、原爆を詠んだ句に東日本大震災を重ねて読んでしまう以上には生かされず、震災後の故郷石巻に詠む際に原爆詠で世に出た俳人という来歴が小説内で生かされてはいない。
俳句の読み手が、原爆を詠んだ句に震災後の風景を重ねて読んでしまう様子を描き、原爆詠と石巻の出身という設定を施したのであれば、原爆と津波で被災した石巻とを俳人は繋ぎ得るのかどうかは問うて欲しかったように思う。
そしてこれは小説を離れるが、原爆(過去の災厄)を詠んだ句に、東日本大震災(現在の災厄)を読んでしまうことは、同時代にも多く行われていたように思うが、東日本大震災から原爆へと至る回路はどの程度あったのか、またそれはどのように可能なのかを今後は考えていく必要があるかもしれない。それは私の課題としても今後取り組むつもりである。
ただ、いまは、原爆を詠んだ句に東日本大震災以後の風景を読んでしまう話題に戻る。大きな災厄(人災)が起こった際に、過去の災厄(人災)を参照点にすることは、過去に学ぶという意味でも大きな意義がある。今回東日本大震災と原爆がつなげられる、その理由としてまず想定されるのは「放射性物質」の問題であろう。
玄自身も「留年の痛みマイクロシーベルト」(49頁)、「放射線に匂ひはあらず風薫る」「ベクレルと知つたかぶりを焼穴子」(87頁)、「風薫る甚振られたる国土とて」(89頁)などと震災後の「日常」には、これまでと変わらない日常を過ごしていても、そこには見えない放射性物質が付帯していることを示している。
それは現実の俳人にも、たとえば神野紗希が「暁・鴉・睡魔・マイクロシーベルト」(『俳句』2011年5月号)と、おそらく阪神淡路大震災時に友岡子郷が詠んだ句「倒・裂・破・崩・礫の街寒雀」を踏まえて詠んでいる試みがある。「放射性物質」のために、日常に変化が無いように思えても、確実に震災後「日常」は変化したのである。
そして福島県においては、その変化を鋭敏に捉えた俳人がいる。
五十嵐進がその人である。五十嵐の『雪を耕す』(影書房、2014年12月)には、五十嵐の俳句のみならず俳句論や、震災後の福島で生活することを綴った随筆などが収められている。彼は以下のような俳句を詠んでいる。
あゝ以後は放射能と生きていくのかあやめ
月光の無音γ線の波頭音
弥勒よ水立ち上がる草をセシウム
セシウムの産道くぐる野辺の目よ
キノコよ柿よ腐って還れ不許出荷
αβγか奴めこの身に棲みつくか
汚染藁焼く日本の夜と霧
もちろん五十嵐にはまだ多くの句があり、挙げたものはその一部であるが、震災後の福島で生きる人間は「放射性物質」の飛散を意識して生きていかなければならないことが明瞭に示される。「あゝ以後は放射能と生きていくのかあやめ」はまさにその思いを率直に吐露した句であり、ここで述べられる「以後」は、自らが生きているあいだは放射性物質との「付き合い」が終わらないことを見据えているかのようにも捉えられる。
放射性物質と「付き合う」ということは、「汚染」や「被曝」と付き合うということでもあるが、以下のような現実にも向き合わされるということでもある。
すでに報道済みなのでご存じであろうが、出た、出てしまった。二本松市の米から食の暫定基準値500ベクレル/kgと同数値のセシウムが検出された。(中略)その検出の報道は、新聞によっては「福島県産米から検出」という見出しだったので私などはなんと心ない報道かとなさけなくなった。とうとう、あるいは、ついに、という思いと同時に、そう思った。日本で3番目に広い面積をもち、気候も異なる三つの地域をもつ福島県である。県産米とひとくくりにできるはずがないのに、との思いからである。自分のペン先によって福島県産の米がどのような扱いになってしまうのかという配慮がまったく働かないのだ。ペン先の倫理というものがあろうではないか。
『雪を耕す』、28-29頁
北海道、岩手県に次ぐ面積をもつ福島県をひとくくりに語ることはできず、福島が「汚染」されているという安易になされた報道に傷つけられた方は多い。それに反発するように歌を詠んでいる歌人に齋藤芳生がおり、彼女の主張や歌も看過されるべきものではない。
しかし一方で、放射性物質は飛散する。いわゆる放射線量が高い「ホットスポット」が、原発「事故」以後福島県ならず多くの地域に点在していることや、空間線量のみならず、内部被曝や土壌汚染の問題、放射線は浴びないに越したことはなく、この値以下であれば絶対に安全だと言い切れる「しきい値」も存在しない。そのためそれぞれの場所で生活を営んでいる人が、自身の置かれた様々な状況から、個人的に居住/避難の選択を選ばざるを得なかったのが原発「事故」以後の現実でもある。
(上記の問題に関しては、中村征樹編『ポスト3・11の科学と政治』(ナカニシヤ出版、2013年1月)尾内隆之、調麻佐志編『科学者に委ねてはいけないこと―科学から『生』をとりもどす』(岩波書店、2013年9月)、佐藤嘉幸・田口卓臣『脱原発の哲学』(人文書院、2016年2月)などを参照のこと)
そのため、特定の地域のみが原発「事故」の影響を強く被り、高い放射線量を計測し続けていると語ることにも、それ以外の地域では放射性物質による影響がないかのような印象を与えるため、それだけでは不十分であるはずである。それは郡山市から避難した森松明希子さん(https://www.bungeisha.co.jp/bookinfo/detail/978-4-286-21793-2.jsp)や、仙台から宮崎へと避難した歌人の大口玲子、東京から京都へと避難した詩人の中村純、沖縄へと避難した俵万智や白井明大などの強制避難区域外避難者の存在を無視することになり、三田や神野がマイクロシーベルトを含んだ俳句を詠んだ意味も理解できなくなるだろう。
そのような意味で問題があると考えるのが、永瀬十悟の震災詠である。
ここでは『三日月湖』(コールサック社、2018年9月)の「第一章・第二章」を中心に考えてみる。第一章では帰還困難区域に指定されてしまった地域を、第二章では放射線量が高い地域の様子を詠んでいる。
廃屋となりたる牛舎燕来る
村はいま虹の輪の中誰も居ず
原発事故それからの日々夕かなかな
一山の除染袋に雪降り積む
村ひとつひもろぎとなり黙の春
しづかだねだれもゐないね蝌蚪の国
朽ちてゆくばかりの家や梅真白
しろつめくさ廃炉への道渋滞す
除染土に咲くあれこれや明日葉も
さへづりの真ん中にある線量計
避難区域の柵越しに見るさくらかな
汚染土も土なり蝉の羽化はじまる
炎天のマウンドに積む除染袋
夏草やスコアボードはあの日のまま
滴りの行き着く先の汚染水
保育所に靴がそのまま秋桜
陽炎や日本に永久の仮置場
廃屋となった牛舎や、帰還困難区域となった村に誰もいない様子、そのため家が朽ちていく様子や「あの日」のまま放置されてしまったスコアボードなどが詠まれ、汚染土や汚染水、廃炉がなかなか進まない様子、フレコンバッグや線量計が設置され、原発「事故」以後変わってしまった地域の様子にも触れられ、帰還困難区域や居住困難区域などの現状が詠まれているといえる。また「陽炎や日本に永久の仮置場」の句は、最終処分先が決まらない除染土や使用済み核燃料の様態を的確に詠んでおり、個人的には名句であるように思う。
しかし、気になる点もある。たとえば「村ひとつひもろぎとなり黙の春」「しづかだねだれもゐないね蝌蚪の国」に注目してみるが、村はひもろぎとなったわけでもなく蝌蚪の国となったわけでもない。「事故」によって沈黙させられ神籬のように、おたまじゃくしの国のようにさせられたのであり、村が「あの日」から沈黙させられてしまった根本の原因に永瀬は触れることを避けているようにみえる。「原発事故それからの日々夕かなかな」も原発「事故」以後に過酷な生活を送らされた/つづけている人々のことを思うとき、のどかなひぐらしの鳴き声に「それからの日々」を回収できるようには思えない。してはならないとも思う。
(余談だが、多くの人が思うように私も、原発は「事故」ではなく、人災であると考えるため、新城郁夫『沖縄に連なる―思想と運動が出会うところ』(岩波書店、2018年10月)で、一貫して原発「事故」と表記されているのを読んで以来、私も原発「事故」と一貫して表記している。俳句で「」を使うことは難しいかもしれないが、原発事故と素直に言葉にしているところにも、私はやや引っ掛かりを覚える。)
そして五十嵐の句と比較して気が付くのは、『三日月湖』は「放射性物質」の名前を出さないのである。もちろん『三日月湖』を読んでいれば、おぼろげながら詠まれた地域にセシウムが漂っていることを読み取れはする。しかしそれが「あの日」をもたらした根本の原因にどこか言及することを避けている印象をもたらしていることも事実であり、より問題であるのは、放射性物質に言及しないことで、放射性物質による汚染の問題が、フレコンバッグや線量計が置かれた、特定の地域の問題であるかのように読めてしまうということである。
放射性物質は飛散するのである。風に乗り、各地にホットスポットを作り出し得るのである。放射性物質による汚染の問題は、特定の地域に限られるものではない。五十嵐は「汚染藁焼く日本の夜と霧」と詠んでいた。原発「事故」の問題は、福島県に限られるものではない。というよりも、福島県に限り、福島県(→浜通り→相双地区→双葉…)の問題として矮小化し、問題を押しつけてはならない。「汚染」の問題が特定の地域の問題であるかのように読める俳句は、問題を矮小化する態度を醸成することにつながりかねないのではないか。
窪島鳴海は「黒き雨刺す広島の朱夏」と詠んでおり、黒い雨が刺したのは確かに広島である。長崎でもある。ただ放射性物質の飛散は福島に留まらないのである。その点を踏まえると、原爆詠と原発「事故」詠を単純に結ぶことはできないように思う。原発「事故」を単純に原爆に重ねることはできない。ただし、しなくてよいとも思わない。
75年以上、『文学』や芸術は、あるいは人文学の研究は原爆に向き合ってきた。
その蓄積と東日本大震災、原発「事故」を結ぶことで、双方が見落としてきたことを見いだせたり、新たに深く考えることのできる問題を浮上させたりすることはできるはずである。
東日本大震災、原発「事故」に留まらず、原爆やチェルノブイリや阪神淡路大震災…などと関連づけて考えていくということが、求められている課題のひとつであると私は考える。これについてはまた回を改めて考えたい。
【執筆者プロフィール】
加島正浩(かしま・まさひろ)
1991年広島県出身。名古屋大学大学院博士後期課程在籍。主な研究テーマは、東日本大震災以後の「文学」研究。主な論文に「『非当事者』にできること―東日本大震災以後の文学にみる被災地と東京の関係」『JunCture』8号、2017年3月、「怒りを可能にするために―木村友祐『イサの氾濫』論」『跨境』8号、2019年6月、「東日本大震災直後、俳句は何を問題にしたか―「当事者性」とパラテクスト、そして御中虫『関揺れる』」『原爆文学研究』19号、2020年12月。
【セクト・ポクリット管理人より読者のみなさまへ】