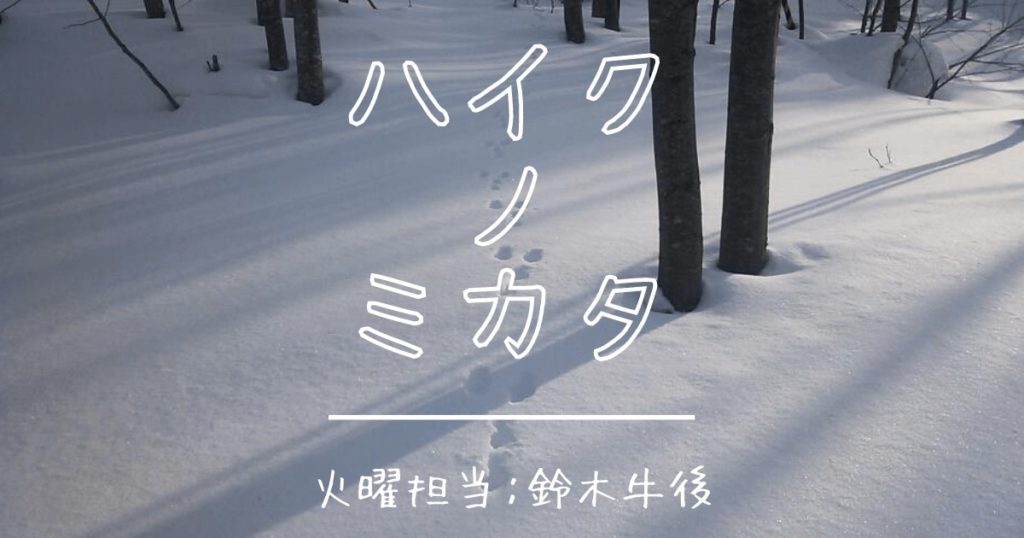
牛乳の膜すくふ節季の金返らず
小野田兼子
季語は「節季」。講談社日本大歳時記の解説には、「本来は、季の節、即ち各季節季節の終わりのことであるが、転じてお盆や年の暮の商売上の勘定期を言うようになり、句の季題としては年の暮のそれに当てられている。(…)現代では、盆暮の総勘定などということは実際には殆どなくなっていよう(…)」とある。確かにこの季語はもう使われることはほとんどないだろう。実際に、夏井いつき「絶滅危急季語辞典」(ちくま文庫)にもちゃんと掲載されている。
しかし現代でも農業経営では年末が決算期で、勘定を締めることは必須だ。多くの農家は春に種子や肥料を「ツケ」で買い、秋の収穫の代金で精算する。そうすることで無事年を越すことができるのである。
だが収入が落ち込んだり、予期せぬ支出があったりすると、その「ツケ」の分は払えなくなる。どうしても年末には精算しなくてはいけないシステムになっているので、不足分は正式に借用書を書いて金を融通してもらうことになる。そうすると、翌年はその借金(もちろん利息付きだ)を返した上に通常の利益を上げねばならず、なかなか厳しい状況が待っているということになってしまう。
牛乳の膜すくふ節季の金返らず
掲句は商人の立場で詠まれたものだろう。「ツケ」で売った代金が返って来なかったのだ。牛乳を沸かした際に張る膜を掬うという、はなはだつまらない、そして余計とも思える行為に、その口惜しさが投影されている。
一方で、牛乳を売って生計を立てている私にしてみれば、捨てられる膜といえども販売代金の一部であり、その膜の部分くらいが利益ということもありそうだ。そう考えると、掲句の哀感がいやおうなしに増すように思えてくる。
「講談社 新日本大歳時記」(1983年)より引いた。
(鈴木牛後)
【執筆者プロフィール】
鈴木牛後(すずき・ぎゅうご)
1961年北海道生まれ、北海道在住。「俳句集団【itak】」幹事。「藍生」「雪華」所属。第64回角川俳句賞受賞。句集『根雪と記す』(マルコボ.コム、2012年)、『暖色』(マルコボ.コム、2014年)、『にれかめる』(角川書店、2019年)。