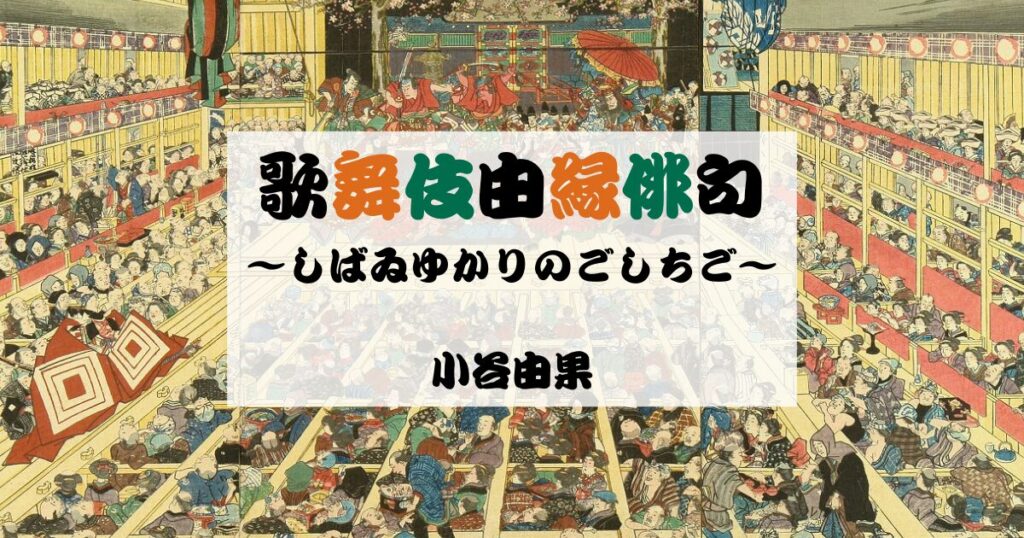
【第12回】
『菅原伝授手習鑑』の和歌と俳句

今月9月の歌舞伎座では、『菅原伝授手習鑑』が通し上演される。
今年2025年は松竹創業130周年記念として、歌舞伎の三代名作である『仮名手本忠臣蔵』『菅原伝授手習鑑』『義経千本桜』を一挙に通し上演する。『仮名手本忠臣蔵』は3月、『菅原伝授手習鑑』は9月、そして『義経千本桜』は10月で、3月に続き9月もすでにチケットが好調に売れており、特に昼の部は完売が続出している。理由は明確で、菅丞相を演じる人間国宝の片岡仁左衛門が出演なさるのが昼の部のみで、かつその菅丞相はAプロで片岡仁左衛門、Bプロで松本幸四郎がWキャストで演じ、幸四郎は初役で仁左衛門から菅丞相役を“伝授”されるとあって、昼の部は特に見逃せないからである。(気になる方は今すぐ「歌舞伎美人」のご確認を!)
『菅原伝授手習鑑』とは
『菅原伝授手習鑑』は、平安時代を舞台に、帝(醍醐天皇)を補佐する右大臣の菅原道真公(菅丞相)と、帝位略奪を狙う左大臣の藤原時平、そして帝の弟である斎世親王に、それぞれ分かれて仕える菅丞相の家臣白太夫の三つ子、梅王丸(菅丞相舎人)・松王丸(藤原時平舎人)・桜丸(斎世親王舎人)、そして菅丞相の旧臣かつ愛弟子の武部源蔵、菅丞相の子息である菅秀才たちが、運命に翻弄される様子を描いた物語。『菅原伝授手習鑑』という外題の意味は、“菅原”道真公が“手習”(筆法)を“伝授”する“鑑”(手本)のこと。菅丞相は筆法(書道)と詩歌に優れ、その筆法を愛弟子の武部源蔵に伝授する「筆法伝授の場」が外題の由来。初演は1746年8月の大坂竹本座で、約280年を経た今なお、その綿密な脚本と人間模様のドラマを演じる役者の伝承藝が心を打つ名作である。
『菅原伝授手習鑑』に登場する和歌
菅原道真公は、詩歌と筆法に優れていたことから現代でも「学問の神様」として親しまれ、京都の北野天満宮を総本社とする天満宮は全国に約1万2000社も存在している。
この『菅原伝授手習鑑』にも、3首の和歌が登場する。その中で最も重要なのはこの歌である。
梅は飛び桜は枯るゝ世の中に何とて松のつれなかるらん
この歌は、四段目の「天拝山の場」と「寺子屋の場」の2回登場する(「天拝山の場」は今回上演されない)。
梅、桜、松はどれも菅丞相が屋敷で愛でていた庭木で、梅は「飛梅伝説」で有名なように菅丞相のもとへ飛んできた。桜は主を失い悲しみのあまり枯れてしまった。松は「なぜ松はつれないのだろう(いやそんなはずはあろうか)」と詠まれたわけである。
梅は梅王丸、桜は桜丸、松は松王丸のことも指している。梅王丸は、都から太宰府へ左遷された主の菅丞相のもとへ飛んで馳せ参じ、桜丸は、この菅丞相左遷のきっかけとなる斎世親王と菅丞相の養女・苅屋姫との密かな恋仲の逢瀬を手引きし駆け落ちさせてしまったことへの申し訳として切腹。しかし松王丸は菅丞相の政敵藤原時平の舎人であるため、世間の人にはつれない、薄情だとそしられている。
「天拝山の場」では、安楽寺へ飛んできた菅丞相の愛樹の梅と、その寺へ詣でた菅丞相のもとへ馳せ参じた梅王丸に、菅丞相がこの歌を詠みかける。
「寺子屋の場」では、武部源蔵が匿っている菅丞相の子息・菅秀才の命が狙われた際、松王丸が我が子の小太郎を身代わりにし、菅丞相への忠義を立てる。そこで松王丸は、松の枝へつけた短冊を投げ込み、源蔵が取って見て「梅は飛び桜は枯るゝ世の中に」と読むと、松王丸が「何とて松のつれなかるらん。女房喜べ、伜はお役に立ったわやい。」「菅丞相には我が性根を見込み給ひ、何とて松のつれなかろうぞとの御歌を、松はつれない/\と、世上の口に、かかる悔しさ、推量あれや源蔵殿。伜がなくばいつまでも、人非人と言われんに、持つべきものは子でござる。」と言うのである。
2つ目は、有名なこの一首である。
東風吹かばにほひをこせよ梅の花主なしとて春な忘れそ
こちらも「天拝山の場」に登場するため、今回は上演されない。「東風が吹いたなら、私がいる太宰府まで匂いを送ってよこしておくれ、都の我が家の梅の花よ。私という家の主人がいなくとも、春を忘れてはならないよ」という意味である。『菅原伝授手習鑑』の中では、菅丞相が太宰府に左遷されて1年が経った頃に詠んだ設定になっているが、1006年頃に編纂された『拾遺和歌集』では、この歌に「流され侍ける時、家の梅の花を見侍て」と添えられており、菅丞相のモデルとなった菅原道真が実際に詠んだのは、道真が都を去る際とされる。
3つ目は、「道明寺の場」の幕切れに詠まれるこの一首である。
鳴けばこそ別れを急げ鶏の音の聞こへぬ里の暁もがな
太宰府への船の汐待の間、菅丞相は伯母覚寿のいる河内・土師の里へ暇乞に行く。覚寿は、帝の弟斎世親王と駆け落ちした菅丞相の養女・苅屋姫の母である。
夜明けの一番鶏の鳴き声を合図に迎えが来て菅丞相は出発することになっており、とうとう迎えが来た時、菅丞相を泣きながら送る覚寿と苅屋姫に「鶏が鳴いてしまうからこそ、別れを急ぐことになってしまう。夜明けにその声が聞こえない里であればどんなによいであろうか」とこの歌を詠みかけ、幕切れとなる。「鳴けばこそ」には、鶏だけでなく覚寿と苅屋姫の泣き声も掛かっているのである。1679年に出版された『河内国名所鑑』の「道明寺」の項目には、この歌が詠まれた後、「此里に鶏をかずと申伝ふる(この里では鶏を飼わなくなったと伝えられている)」と記述されている。
『菅原伝授手習鑑』にまつわる俳句
『菅原伝授手習鑑』の舞台は平安時代であり、俳句は江戸時代に俳諧連歌の発句が独立し明治時代にその発句が俳句と名付けられたため、『菅原伝授手習鑑』の中に俳句は登場しない。俳人が詠んだ『菅原伝授手習鑑』や菅原道真公にまつわる俳句は存在する。
土師の里遠世のさまに霞みけり 水原秋櫻子
水原秋櫻子が歌舞伎座と明治座の筋書に寄稿していた句を集めた『芝居の窓』(昭和61年、東京美術)に掲載。前書に「道明寺懐古」とある。昭和39年5月作。菅丞相からの視点のように思える。覚寿のいる土師の里から一番鶏を合図に早朝に旅立つ菅丞相。遠く太宰府に流される心境が「遠世のさまに霞みけり」に表れている。霞むのは、涙のせいもあるだろう。
菅原道真公にまつわる俳句の季語としては「北野菜種御供」があり、傍題は「北野御忌日」「天神御忌」「梅花祭」「梅花御供」「道真忌」「菜種の神事」「菜種御供」。2月25日、菅原道真公の忌日に京都市の北野天満宮で行われる祭である。下記は直接歌舞伎に関係はないがこれらの季題を含む句である。
曇りより雨となりたる菜種御供 森澄雄
かたくなに枝垂れぬ柳道真忌 竹下しづの女
ともしびの洩れくる菜種御供の森 加藤三七子
菜種御供尼の身内のあつまりて 中村若沙

さて、今月の歌舞伎座『菅原伝授手習鑑』は9月2日から24日まで。通しでかかることは珍しいので、気になる方はぜひ歌舞伎座でご観劇を!
<参考文献>
『名作歌舞伎全集 第二巻 丸本時代物集 一』(昭和43年、戸板康二ほか監修、東京創元社)
『芝居の窓』(昭和61年、水原秋櫻子著、東京美術)
『文化デジタルライブラリー』菅原伝授手習鑑(日本芸術文化振興会)
(小谷由果)
【執筆者プロフィール】
小谷由果(こたに・ゆか)
1981年埼玉県生まれ。2018年第九回北斗賞準賞、2022年第六回円錐新鋭作品賞白桃賞受賞、同年第三回蒼海賞受賞。「蒼海」所属、俳人協会会員。歌舞伎句会を随時開催。
(Xアカウント)
小谷由果:https://x.com/cotaniyuca
歌舞伎句会:https://x.com/kabukikukai
【PR】松竹株式会社様にご監修・図案提供を賜り、奈良墨工房 錦光園様に製造をいただき、筆者がディレクション・デザインをさせていただいた、香る奈良墨「隈取香墨」を販売中。

https://kinkoen.shop/?mode=grp&gid=3014590