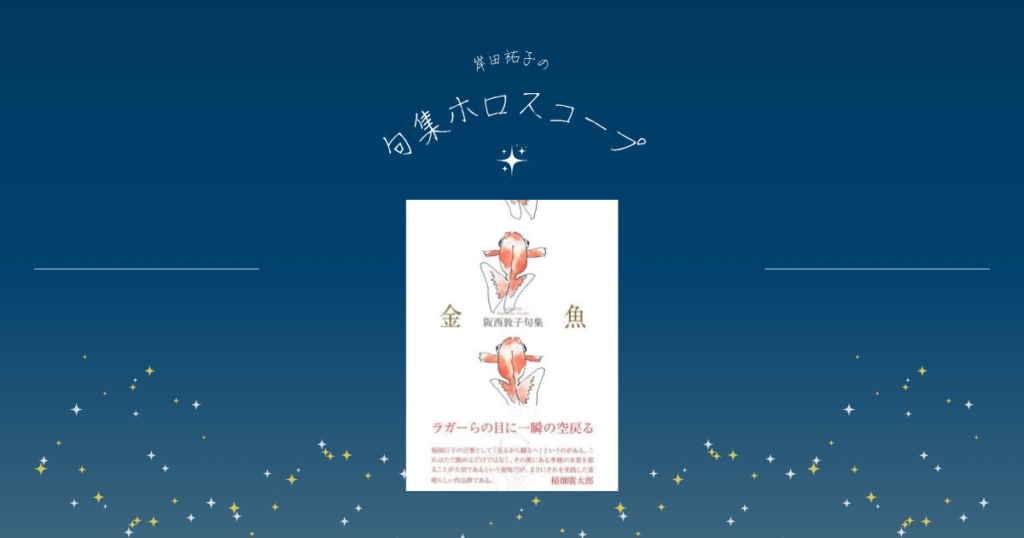
<はじめに>
星占いといえば、一度くらい、1月4日生まれは、山羊座です、といようなことを聞いたことがあるのではないでしょうか。これは太陽が山羊座の位置にある時に生まれましたという意味で、山羊座とは、天体の位置のことを示しているのです。また、星占いでは、太陽、月、水星、金星、火星、木星、土星、天王星、海王星、冥王星の10個の星を使います。太陽は山羊座にいても、月は水瓶座の位置で、金星は獅子座にいるというように星はいろいろな位置に散らばっています。それらの星の位置関係を一枚の図表にしたものがホロスコープで、チャートとも言います。星占いは、このホロスコープを読み解くことで持って生まれた特性やテーマ、課題、運勢などを予測します。大抵の場合、占う対象は人であることが多いですが、国や会社など人以外を占うこともできます。
星や星座には「シンボル」として、先人たちが見出した意味が割り当てられています。同様に星と星が作る角度(アスペクト)にも意味を持たされています。この「シンボル」を読み解いてゆくことがホロスコープを読むということです。
心理学者のユングは「占星術とは五千年の歴史を持った心理学」という言葉を残しました。星の配置がなぜ人の心や世の中の動きに連動しているのか、連動しているように感じるのかは、よくわかっていません。
元をたどると西洋占星術、いわゆる星占いは「天の徴(しるし)が地上の出来事の前兆を示す」と考えた古代メソポタミアに起源を持ちます。その後、天体観測の知見が蓄積され惑星運動には秩序があって、季節や気象との相関関係があることが分かるようになり、ヘレニズム文化が栄える中で、初めて本格的にホロスコープを用いる占星術に発展しました。私たち、ひとりひとりの小さな営みも季節や気象と深い関わりがあります。そこで、人が生み出した俳句の作品をとどめた句集に向き合う一つのアプローチ方法として、西洋占星術の手法を用いてみたいと思います。
この連載では、著者自身が句集に込めたテーマやメッセージを探るということではなく、句集そのものが生まれた瞬間に授かったテーマを西洋占星術の手法で探ります。奥付にある発行日を句集のお誕生日とすることにし、出生時間は正午、出生地は出版社の所在地といたします。
1 / 2