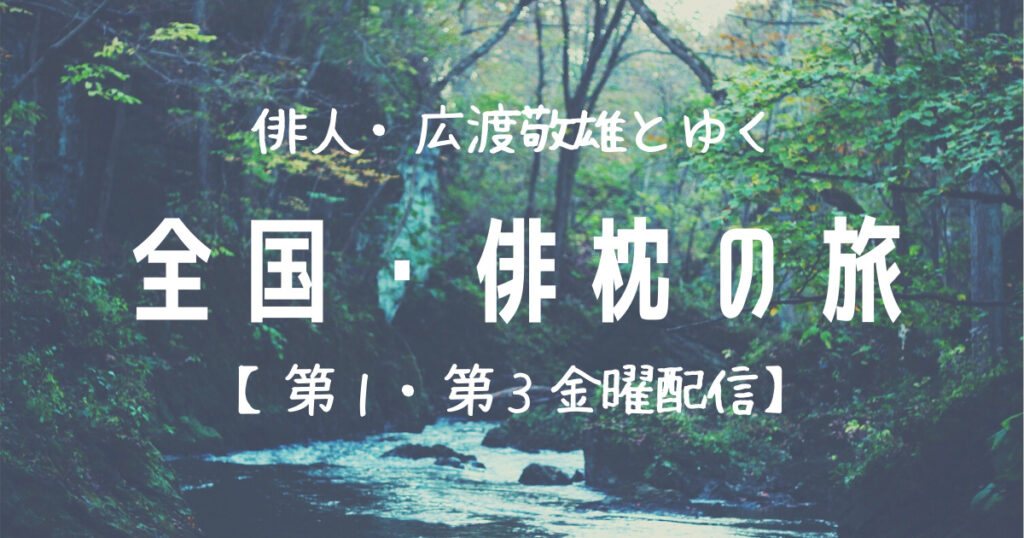
【第35回】
英彦山と杉田久女
広渡敬雄(「沖」「塔の会」)
英彦山は、大分県と接する福岡県の最高峰で1200メートル、大峰山、羽黒山と並び日本三大修験道場(山岳信仰の霊山)。

明治2年の神仏分離令で、僧坊三千超の宿坊も激減し隆盛を失った。入口の銅鳥居と奉幣殿は国の重要文化財である。遠賀川の源流で、山頂付近は、山毛欅、大杉が繁茂し、裏手の豊前坊(高住神社)を経て、名勝耶馬渓へ行ける。
谺して山ほととぎすほしいまゝ 杉田久女
英彦山の夕立棒の如くなり 野見山朱鳥
霧厚し土の鈴より土の音 沢木欣一(英彦山土鈴)
砥のごとく厚く畦塗り比古の田は 向野楠葉
雪沓に替へ上宮へ英彦の禰宜 江口竹亭
鬼杉のうしろの真闇夜鷹鳴く 豊長みのる
秋扇をひらけば水の豊前坊 黒田杏子
〈谺して〉の句は、英彦山の前書きがあり、昭和6(1931)年40歳の折の作で『杉田久女句集』に収録。久女の代表句として名高く奉幣殿に句碑あり、大阪毎日新聞等主催の「日本新名勝俳句」で十万余句から選ばれた最優秀二十句帝国風景院賞(金賞)の作品。同時作〈橡の実のつぶて颪や豊前坊〉も銀賞に輝いた。
ちなみに金賞は、〈啄木鳥や落葉をいそぐ牧の木々 水原秋櫻子〉〈滝の上に水現れて落ちにけり 後藤夜半〉〈さみだれのあまだればかり浮御堂 阿波野青畝〉等後世に残る名吟ばかりである。「ほととぎすは、谷から谷へと鳴き、実に自由に高らかにこだましていた。ほしいまゝが見つかるまで五六度足を運んだ」と自解する。「女性らしからぬ雄渾な句で、作品に掛けた久女の生命、作家魂である」(山本健吉)、「ア音・オ音が主律のしらべと下五が霊山たる深山幽谷の新緑の大景を活写し艶麗にして雄渾な句である」(鷹羽狩行)、「やって来るまで辛抱強く待つこと(苦吟)の果てに「ほしいまゝ」の五文字を感得した久女の喜びはいかばかりか」(清水哲男)、「英彦山の精の様なほととぎすが、あたかも自分だけに鳴いてくれる至福の時間」(小島健)等の鑑賞がある。
-1.jpg)
1 / 3
