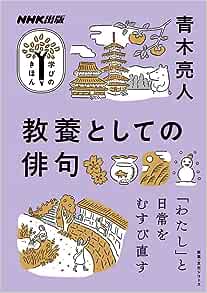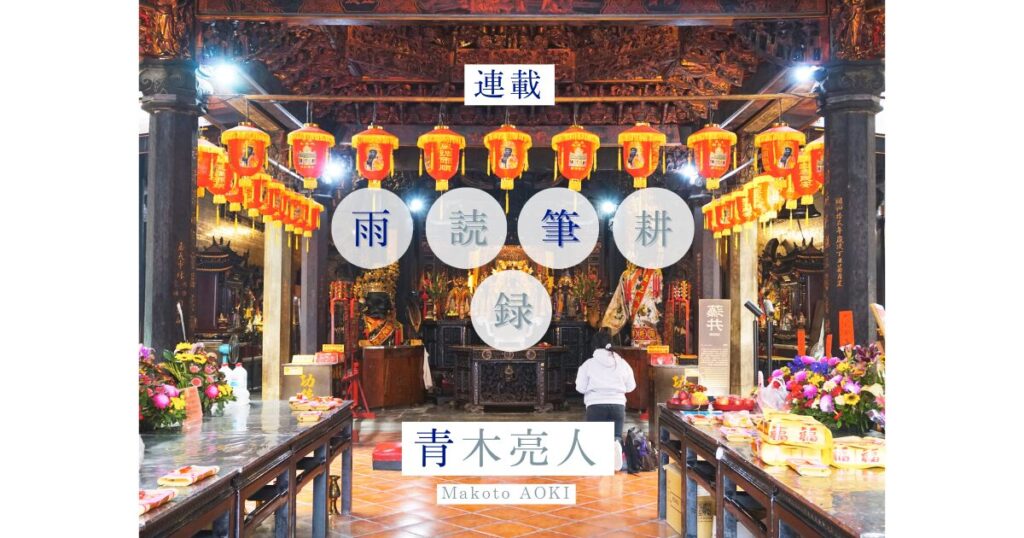
台湾東部、花蓮市の小籠包(2)
それにしても、台湾に小籠包が広まったのはいつ頃からなのだろう。清朝時代に大陸から渡った漢人が持ちこんだように思われるが、清朝期に移住した漢人は福建や広東といった華南出身者が多く、上海近辺の華中から大挙して移住したわけではないはずだ。無論、清朝時代の華南地域にも小籠包がすでに浸透し、その食文化を移住者が持ちこんだ可能性もあるが、判然としない。
今一つ引っかかるのは、薄皮でスープ入りの小籠包は手間暇がかかり、庶民が気軽に作る料理としては時間と技術を要する点である。つまり、小籠包のような料理は自然に広まったというより、何か特別な文化や宗教、歴史や政治的な理由が背後にあるのでは……そういったことを何となく考えていたある日、蕉桐著『味の台湾』(川浩二訳、みすず書店)を読んでいると次の一文に出会い、なるほどと得心したことがあった。
台北には美味な小籠包が多いが、その名が天下に響くようになったのは歴史的な偶然といえよう。
一九四九年に、突如としてあれほど多くの外省からの新たな移民がやって来たことで、言うなれば中国の八大料理大系が台湾に集まったわけで、特に江蘇・浙江一帯の料理は盛んに発展した。小籠包は国共内戦後に取り入れられ、宣揚されたものなのだ。(『味の台湾』)
日本の敗戦後、中国大陸では共産党と国民党の内戦が勃発し、やがて敗北した国民党の蒋介石は1949年に一党を引き連れて台湾へ渡った。政治家や軍人、民間人その他を含めて百万人を軽く超える膨大な中国人が大挙し、彼らは台湾出身者と区別する意味で外省人と称される(台湾出身者は本省人)。
新たな支配者たる国民党の頂点に立つ蒋介石は、強大な浙江財閥――華中の江蘇・浙江にまたがる巨大財閥――の創始者を父に持つ宋美齢と結婚し、上海を中心とする文化圏と縁の深い軍人である。
つまり、台湾に小籠包が広まったのは外省人が大挙した1949年以降の可能性が高く、そして小籠包は蒋介石ら外省人の高官にとって懐かしい食事だったためにもてはやされ、浸透していったのではないか。
台北にスープ入りの美味しい小籠包の店が多いのも、政治経済の中心地たる台北に国民党上層部が多数移住してきた歴史的な背景が影響しているのかもしれない。
台湾の個々の料理には様々な文化や歴史的背景を湛えていることが多いが、何気なく入った花蓮のお店の小籠包に出会うことで、今や「台湾料理」として著名になった小籠包もまた台湾独特の歴史的背景を持った料理かもしれないことに思い至った体験は、大仰にいえば台湾の歴史に少しだけ触れたような実感があり、なかなか印象的だった。
そういう風に考えていると、花蓮市の「周家小籠包・蒸餃」の創業者はいかなる人生を歩み、どのように商売を始め――最初は屋台だったのかもしれない――、小籠包や蒸餃子のどの点にこだわりがあったのだろう、とも感じるようになった。実はそこにも文化や歴史的背景があったのもしれず、意外にそこまでではないのかもしれないとも思いながら、あの厚皮の粗い、独特の食感を湛えた花蓮の小籠包を思い出すのだった。
-1024x717.jpg)
青木亮人(あおき・まこと)
昭和49年、北海道生まれ。近現代俳句研究、愛媛大学教授。著書に『近代俳句の諸相』『さくっと近代俳句入門』『教養としての俳句』など。
【もう読みましたか? 青木亮人さんの『教養としての俳句』】
日本の伝統文芸として、数百年ものあいだ連綿と受け継がれてきた俳句。その愛好者は1000万人ともいわれている。にもかかわらず、私たちはその知識をどこでも学んでこなかった。そこで本書では、数々の賞を受けてきた気鋭の評論家が、日本人として最低限おさえておきたい俳句のいろはを解説。そもそも俳句ってどうやって生まれたの? 季語ってなぜ必要なの? どうやって俳句の意味を読みとけばいいの? 知識として俳句を知るための超・入門書。
俳句は、日本のリベラルアーツだ。