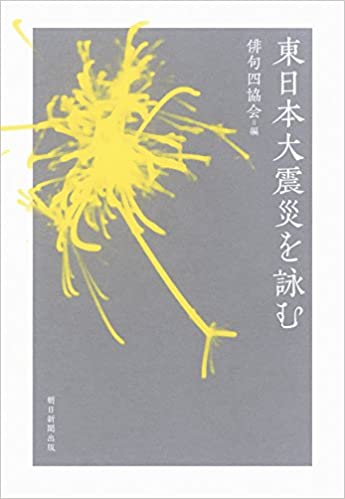【連載】
「震災俳句を読み直す」第10回(最終回)
加島正浩
遅れて届く言葉を信じる
俳句四協会が編集した『東日本大震災を詠む』(朝日新聞出版、2015年3月)は、全国各地から東日本大震災を詠んだ俳句を募集し、投句された句を全て収録している点で資料価値が高い。一般的に旭俳壇などの新聞の投句欄では類句は取られないと思われるが、『東日本大震災を詠む』は類句も排除することなく全て収めているため、俳人が震災の何に関心を持ち、何を詠もうとしたのかが、量的に把握できる。
収録されている句には〈三月の何をどこまで詠ふやら〉(東京 伊藤類)、〈大震災花を詠む気の失せにけり〉(鹿児島 藤岡香代子)、〈海色の地震来て春の失語症〉(福井 水上啓治)というような、震災を(前に)詠うことが困難になっている素直な気持ちを吐露したものもある。地震・津波・原発「事故」と複合的に絡まった東日本大震災をどのように詠むかというのは依然決着のつかない(というよりも永遠に研究課題として探求されうる)問題であるが、私の関心は詠うことが困難であるにもかかわらず、なぜ人は詠ってしまうのかというところにある。ただこれも(残念ながら)答えを見出すのが難しい問いである。しかし、詠ってしまうがゆえに、犯してしまうものはあるように思う。
復興の明日へ光となる桜 大阪 河辺さち子
初桜生くる限りは希望もて 北海道 清水里美
だとしても菜の花は咲くすみれ咲く 東京 須川久
私はすでに本連載の第6回で、小野智美編『女川一中生の句 あの日から』を取り上げ、小野が中学生の俳句からは読み取ることのできない「希望」を解釈に付与していることを、「糾弾」ともいえるような勢いで激しく指摘した。「なぜ執拗に小野氏は「前に進ませようと」するのか。なぜ嘆き悲しみ、生きることに絶望することを中学生に許さないのか。「前に進まなければならない」と誰かが他人に強いたとすれば、それは暴力である」と私は記した。同様のことを私は2011年に詠まれた上記3句に感じる。「光」や「希望」を語ることは、絶望している者にそれ以外の感情の表出を妨げるし、「だとしても」と語ることが、語った相手のどのような感情を抑圧してしまっているのか想像できているとは私は思えない。
福島市在住のある方から『バハールの涙』という過激派組織IS女性だけで構成された武装部隊との闘いを描く映画に、「ひとびとは夢や希望ばかりに向かう。悲惨には関心がない」というセリフがあることを踏まえて、同様のことが福島在住のある詩人の評価にも関わっているのではないかというメールをいただいたことがある。悲惨に目を向けることは苦しい。悲惨で苦しんでいる人がいるのを知りながら、のうのうと暮らしている自分を意識することはつらい。後ろめたい。それは事実である。ただその後ろめたさから逃れるために、「希望」を語るのであれば、それは自らが安心するためだけに紡がれた大いなる欺瞞である。花が咲くからなんだというのだ。
残念ながら、目の前で進行する悲惨な出来事に対して言葉は無力である場合が多い。言葉が仕事をできるのは、往々にして「事後」である。津波で家が浸水したとき、「文学」なんて何の役にも立たなかったという言葉を攻撃的な意味合いで投げかけられたことがある。それは、事実である。言葉が、「文学」ができる仕事は悲惨な出来事が過ぎ去った後なのだとしても、目の前で進行している悲惨な出来事に対して言葉は、おそらく無力である。言葉は現実を変換することができる。傷つかないように現実を捻じ曲げることができる。存在しない「希望」を言葉のうえで、描くことができる。しかしそれはただの文字であり、それが現実を覆い隠すのであれば、欺瞞である。
悼むとは目をつむること椿落ち 東京 長峰竹芳
口結ぶことも詩なり花萱草 宮城 浪山克彦
祈りとは白き日傘をたたむこと 宮城 渡辺誠一郎
悲惨な出来事の最中で言葉にできることはないのかもしれない。言葉にできることはないと言葉にすることが、言葉を使うものが悲惨な出来事の最中にいるときのギリギリの「倫理的」な態度であるのかもしれない。決して言葉だけが悼みや祈りや「詩」を構成するわけではない。私もそれに同感する。私たちは、東日本大震災に関して、「うるさすぎる」ほどに言葉を発し、「無音を聞いてきた」ような気がするのである。
瓦礫より音声菩薩雁渡し 東京 安西篤
身に入むや津波に失せし子等の声 鹿児島 五反田加代
盆の海沖に数多の声溜る 長野 根橋久子
いとうせいこうの『想像ラジオ』などを基に、死者の声を聞こうとする問題と、死者の声を無性に聞こうとする前にまずは生きている者の声を聞くべきであるという指摘はすでになされている(坪井秀人「生者と生きる―〈ポスト3・11〉の死者論言説」坪井秀人ほか編『世界のなかの〈ポスト3. 11〉』新曜社、2019年3月)。
私も同感である。本連載の第1回では、照井翠『龍宮』の〈芋殻焚くゆるしてゆるしてゆるしてと〉、〈花吹雪耳を塞いでゐたりけり〉という句や岡田利規「部屋に流れる時間の旅」などを取り上げ、悲惨な震災後の現実を「忘れたい」人に〈おぼえてるでしょ?〉と投げかけるのが「文学」の仕事であると述べた。照井が聞いている死者の声や「部屋に流れる時間の旅」で男が聞いている死者の声は、生き残った自らを責め立てる「聞きたくない」死者の声である。「聞きたくない」にもかかわらず「聞いてしまっている」のである。「身に入むや」などと詠めるはずもない許しを乞うしかない死者の声である。
死者の声を「聞く」とき、無意識に自らの「安全」を揺るがすことのない危険のない声を想定しているのではないか。なぜ震災で亡くなった死者が、震災以後を生き残った者を恨んでいないと想定できるのか。自らを不安に貶めることのない安全地帯で死者の声を「想像」するのであれば、それはやはり死者への暴力であり、欺瞞である。同書には〈父母呼べば波音返る秋の浜〉(岩手 舞田公子)という句も収められている。本当に聞きたい声は、聞こえないのである。
最初の問いに戻ろう。私は「なぜ人は詠ってしまうのか」に関心があると述べた。ひとつの答えは、悲惨な現実や自らの後ろめたさを覆い隠し、「安心」したいがためだと述べるしかない。そういうことも言葉には可能なのだということを認めるしかない。その大前提をもってしても、一線を犯しうるのが「書く/詠む」という行為である。
ただし「書く/詠む」ことは暴力的だからやめるべきだなどと安直なことを主張するつもりはない。答えは出せないが、「書く/詠む」ことが何かを犯しうるものであることを前提に「それでもなぜ書く/詠む」必要があるのかを考えたいのである。
連載第2回で歌集ではあるが、三原由起子の『ふるさとは赤』を取り上げた。連載では原発「事故」以後の歌にのみ触れているが、本歌集は三原が16歳から33歳までに詠った歌が収められており、原発「事故」以前の歌も多い。〈「聞いてみる」差し出されたウォークマンこれが君の好きなメロディ〉、〈「今日は一緒に帰らないの」と聞くわたし高飛車だってわかっているけど〉などの恋愛の歌が多くならび、〈(わたし結婚するの聞いてよ結婚をするの)レジまで「ゼクシィ」持って〉の歌によって私は、ところどころに黄色い紙の付箋が貼られ、偶然忘れられたかのように装われ、放置されることで何らかの無言の圧力を演出する武器としか思っていなかった「ゼクシィ」の本来の意味を受け取り、「本来は」しあわせの象徴なのだなと認識を改めたりもした。もちろんここで重要なのは、私が実生活でそのような「ゼクシィ」攻撃を受けていたかどうかではなく、恋愛をストレートに詠む歌と原発「事故」後の様々な葛藤や思いが、時に言い淀むかのような歌も含めて、三原の歌集に同居しているということである。
原発「事故」がなければ、おそらく三原は恋愛を中心とした自らの感情を率直に吐露する歌で一冊の歌集を編んだのではないかと思う。それが原発「事故」によってかなわなくなったのである。つまり原発「事故」は、自らの感情を積極的に詠んでいくという歌人としてのひとつのあり方を三原から奪ったのである。そのことを、原発「事故」前後の歌が同じ歌集に収められていることで、1冊の歌集から読み取ることができる。もちろん、そのようなことを三原が記しているわけではない。歌集の構成からそのような読み方もできるということである。
言葉は言葉だけで意味を持つのではなく、それがどのような文脈で発せられたのかによっても意味が付与される。句や歌の場合、それは句集/歌集の構成ということになるのだろう。まとめることで、一句のみでは感じ取れなかった意味を読み取ることができるということが句集を刊行する意味のひとつなのだと思う。であるならば、ある地点で詠んだ句が、句集に収められることで、後々別の意味を持つということも考えられるだろう。言葉は遅れて届くということがある。なぜ「書く/詠む」必要があるのかはわからないが、それを重ねていくことで、後々わかるということはあり得ると思う。
『東日本大震災を詠む』には以下のような句がある。
三月や揺れもないのに揺れている 東京 圍喜江
2013年に詠まれた句である。なぜ「揺れもないのに揺れている」のか。「揺れもないのに揺れている」ということは、一体東日本大震災は「何を揺らした」のか。明確な答えは未だない。結局私は未だに何もわかっておらず、私が書いていることが自己欺瞞でないと、あれだけ強く批判をしておきながら、言い切る自信もない。欺瞞だと指摘されれば、振り返って考えるしかない。しかしそれでも書くことを積み上げることで、何らかの「答え」を私が見つけることができるかもしれないし、誰かが見つけ出してくれるかもしれない。書くことに即効性はなく、今現在進行する出来事に対してはおそらく無力である。しかし、言葉は多義的であるため、そのなかにある意味のいくつかは、書き手にも、読み手にも遅れて届くことがある。
私にとって本連載は、様々な点で学ぶ機会を与えてくれた。この連載にお付き合いくださった方々にとっても何らかの点で益するものがあれば、大変にありがたい限りである。しかし、実際のところ、私がこの連載で何を述べることができたのか、当人にはよくわからない。述べることができなかったことも多くあり、そもそも俳句読んだことになっているのか、私には全く自信がない。ただもう少し時間を置き、初回から連載を読み返したとき、私のなかで、連載の持つ意味が少しは明らかになるかもしれない。そのときに、次の課題であったり、新たに述べるべきことであったりも出てくるであろうと思う。
連載は完結するが、それで震災と俳句について書き終えたわけでは当然ない。またいずれ何か別のかたちで、お会いすることができればと思う。
最後になりますが、毎回締め切りぎりぎりか、今回のように締め切りを過ぎて拙稿をお送りするにもかかわらず、毎回丁寧にコメントをくださり編集してくださったセクト・ポクリット管理人の堀切克洋さん、TwitterなどのSNSでご宣伝くださったみなさま、最後まで連載にお付き合いくださったみなさまに、深くお礼申し上げます。誠にありがとうございました。
【執筆者プロフィール】
加島正浩(かしま・まさひろ)
1991年広島県出身。愛知淑徳大学ほか非常勤講師。主な研究テーマは、東日本大震災以後の「文学」研究。主な論文に「『非当事者』にできること―東日本大震災以後の文学にみる被災地と東京の関係」『JunCture』8号、2017年3月、「怒りを可能にするために―木村友祐『イサの氾濫』論」『跨境』8号、2019年6月、「東日本大震災直後、俳句は何を問題にしたか―「当事者性」とパラテクスト、そして御中虫『関揺れる』」『原爆文学研究』19号、2020年12月。
【「震災俳句を読み直す」バックナンバー】
>>第9回 震災を語る方法の「二極化」にあらがう
――友岡子郷『翌』・照井翠『龍宮』
>>第8回 「喪失」から遠く離れて
―青眼句会合同句集『フクシマ以後』・照井翠『泥天使』
>>第7回 「忌」ではない別の表現を
―『浜通り』浜通り俳句協会
>>第6回 書く必要のないこと
―小野智美編『女川一中生の句 あの日から』
>>第5回 風と「フクシマ」
―夏石番矢『ブラックカード』・中村晋『むずかしい平凡』
>>第4回 あなたはどこに立っていますか
―長谷川櫂『震災句集』・朝日新聞歌壇俳壇編『阪神淡路大震災を詠む』
>>第3回 おぼろげながら浮かんできたんです。セシウムという単語が
―三田完『俳魁』・五十嵐進『雪を耕す』・永瀬十悟『三日月湖』
>>第2回 その「戦場」には「人」がいる
―角川春樹『白い戦場』・三原由起子『ふるさとは赤』・赤間学『福島』
>>第1回 あえて「思い出す」ようなものではない
―高野ムツオ『萬の翅』・照井翠『龍宮』・岡田利規「部屋に流れる時間の旅」
【セクト・ポクリット管理人より読者のみなさまへ】