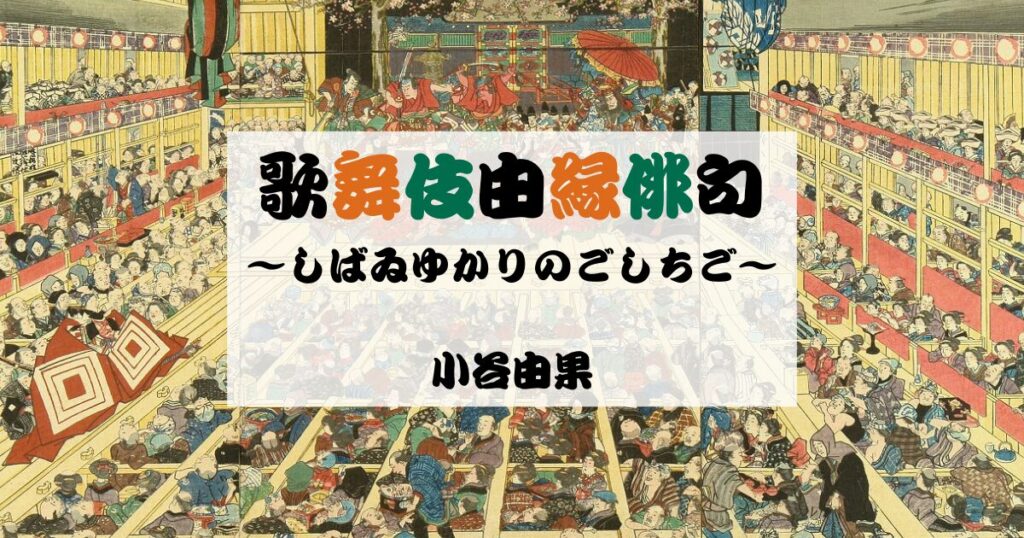
【第10回】
近松門左衛門と俳句

映画『国宝』が空前のブームである。吉田修一の小説『国宝』(2018年、朝日新聞出版)を原作とし、李相日が監督した作品。任侠の一門に生まれながらも、歌舞伎役者の家に引き取られ、歌舞伎に人生を捧げた主人公・喜久雄の50年を描いた一代記。歌舞伎指導は、人間国宝・四代目坂田藤十郎を父に持つ四代目中村鴈治郎が行い、鴈治郎は出演もしている。吉田修一はこの作品を書くために、鴈治郎に付いて全国の劇場を回り、約3年間も黒衣姿で取材したという。
この作品の中には、歌舞伎の演目がいくつか登場する。『関の扉』『連獅子』『二人藤娘』『二人道成寺』『曾根崎心中』『鷺娘』。この中で唯一『曾根崎心中』は世話浄瑠璃の心中物で、他は全て舞踊。この『曾根崎心中』は、浄瑠璃・歌舞伎作者の近松門左衛門の代表作である。
近松門左衛門とは
近松門左衛門(1653〜1725)は、松尾芭蕉・井原西鶴とともに“元禄の三大作家”と称され、“日本のシェイクスピア”とも呼ばれる日本の代表的な劇作家である。
近松は、越前の武士・杉森信義と越前藩医岡本為竹の娘の次男として、承応2年(1653年)に誕生。本名は杉森信盛。10代半ばの頃に父が浪人となり、一家は京都に移った。
延宝3年(1675年)、京都に古浄瑠璃の宇治座が誕生。信盛(のちの近松)が仕えていた公家のひとりである正親町公通が、宇治座の創設者である宇治加賀掾の浄瑠璃の愛好者で、信盛は正親町公通の使いとして加賀掾を訪ね、やがて信盛は加賀掾の元で作者修業を始めた。
近松が作者になった当初、浄瑠璃や歌舞伎の作者の立場は低いもので、加賀掾は正本への近松の署名を認めていなかった。近松の作品への署名が最初にみられるのは、貞享3年(1686年)竹本座初演『佐々木先陣』の正本であるが、実際には宇治座初演作の中に近松の初期作品が多く含まれる。しかし署名がないことから、どれが近松の作品かははっきりとわからなくなっている。
天和3年(1683年)9月に宇治座で初演された『世継曽我』は、近松作と認められている最も古い作品である。この宇治座で近松と出会った竹本義太夫が、貞享元年(1684年)に竹本座を創設し、その旗揚げ公演で『世継曽我』を上演。義太夫の回想文にこの『世継曽我』が近松作と書かれている。近松31歳の時のこの作品が人気を得て、出世作となった。貞享2年(1685年)、近松は義太夫と提携し、貞享3年(1686年)竹本座初演『佐々木先陣』の正本で初めて「作者 近松門左衛門」と署名。以後竹本義太夫は作者を尊重し正本に近松の名を記した。
近松門左衛門と坂田藤十郎と中村鴈治郎
近松は元禄時代(1688〜1704)を中心に歌舞伎作者としても活躍。京都の都万太夫座の座付作者となった。この都万太夫座の座本が、初代坂田藤十郎である。
初代坂田藤十郎(1647〜1709)は、元禄時代を代表する名優で、上方歌舞伎の始祖の一人。近松は藤十郎の芸風を活かす作品を数多く執筆し、藤十郎は近松の脚本を尊重。しかし藤十郎の健康問題から近松は歌舞伎を離れ、再び浄瑠璃作者に戻った。
歌舞伎作者時代の近松は、庶民の周りで起こった身近な事件を数日のうちに芝居に仕立てて上演する「世話狂言」も執筆していた。
この歌舞伎の「世話狂言」の手法を活かし、元禄16年(1703年)4月7日に現在の大阪市北区曽根崎2丁目の露天神社で起こった実際の心中事件を元に、浄瑠璃作品『曾根崎心中』を執筆。実際の事件からわずか1か月後の元禄16年(1703年)5月7日、竹本座で『曾根崎心中』が上演され、大当たり。これをきっかけに竹本座の座付作者となった。
『曾根崎心中』は、これを皮切りに起こった心中物の流行とともに実際の心中事件が多発したため、江戸幕府により享保8年(1723年)に上演を禁止され、以後長く再演されないままであったが、近松生誕300年の1953年(昭和28年)、歌舞伎狂言作者の宇野信夫が脚色を加え復活。徳兵衛を二代目中村鴈治郎、お初を二代目中村扇雀が初演し、新橋演舞場で上演され、「扇雀ブーム」が社会現象となるほどの大成功を収めた。
お初を当たり役とした二代目中村扇雀は、のちの四代目坂田藤十郎。今回『国宝』で歌舞伎指導を行った四代目中村鴈治郎の父であり、人間国宝である。
1 / 2