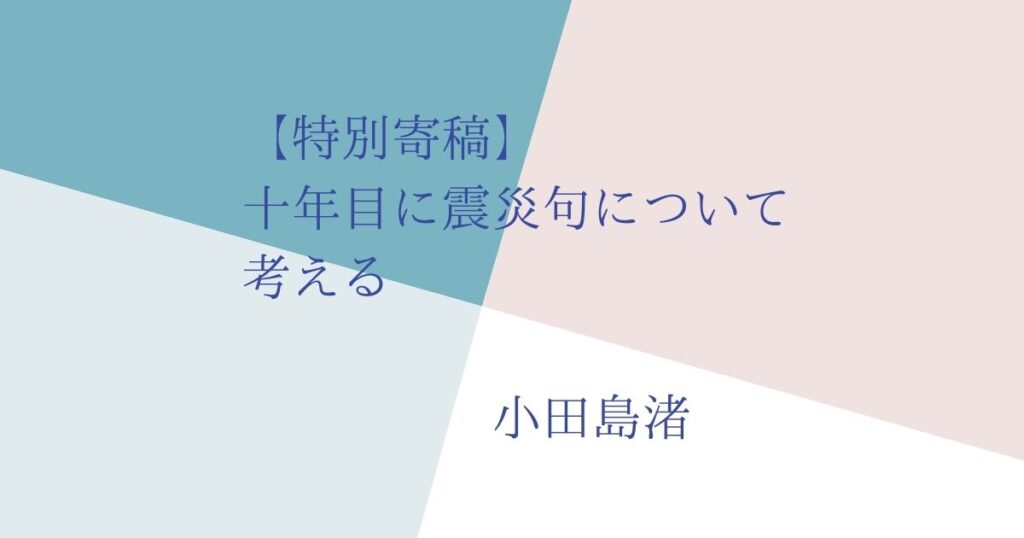
【特別寄稿】
十年目に震災句について考える
小田島渚(「銀漢」「小熊座」)
1 震災体験を語るということ
東日本大震災当時、宮城県仙台市内にいたが、その個人的体験のほとんどをいまだ書く気になれない。
いただいた支援や励ましの言葉の数々が前に進む原動力となった光のような面の裏側に、悲しみというより苦みを伴う惨めさや悔しさであったり、不条理への怒りを通り越しての無力感であったりと一概には伝えられない影の面が多々あるからかもしれない。
メディアでは、3月11日からたいして日も経たないうちに競うように様々な報道がなされた。被災地の、今まさに目の前にある凄惨な現実がどこか物語として消費されていくような違和感も影の面の一つである。
2 句集『赫赫』について(1)

2021年2月、現代俳句協会青年部による勉強会「句集リレー」のなかで取り上げらた、渡辺誠一郎氏の『赫赫(かっかく)』(2020年・深夜叢書)は、『地祇(ちぎ)』(2014年)に続く第4句集で、発表者を吉沢美香氏、聞き手を樫本由貴氏が担当された(以下、敬称略)。
俳句のレトリックに議論が傾きやすい近年だが、震災の句、戦争の句、小さい生き物を詠んだ句、大きい生き物を詠んだ句、家族を詠んだ句の5つに分類した句について、一句一句、自身の感じたままに丁寧に言葉をつないで鑑賞した吉沢の発表には、俳人の心がどう句に読まれたのかを考えさせられた。
震災の句として引かれたのは次の6句である。
三月の海が薄目を開けるとき 『赫赫』
春の水さびしき水は加わらず 同
春の限り炉心の底の潦 同
原子炉を遮るたとえば白障子 同
狐火もて見るやメルトダウンの闇 同
原子炉はキャベツのごとくそこにある 同
3句目以降は、「炉心」「原子炉」、「メルトダウン」から震災詠であると多くの人が感じるだろう。1句目は、震災句として見れば薄目を開ける海が不気味だが、海がゆっくりと目覚めるうららかな春の景と見ても差し支えない。2句目は、「春の水」がややキーワード的で、「さびしき水」は汚染水の暗喩とも読めるが、死に水のような普遍的なものも感じる。
続く聞き手の樫本は、震災句を多く含む『地祇』との比較、あとがきの「震災への体験を、少しでも内面化に努めるようになった」という言葉を軸に、吉沢と対話しながら俳人の震災からの精神的回復を読み取った。海をキーワードにした『地祇』と『赫赫』の句の対比は納得できるものであり、40分間のなかで発表者と聞き手の対話としてもよくまとまっていた。
しかし、あえて言えば、よくまとまっていすぎではないかと思ってしまう。それはメディアに物語として消費されていく震災にもどこか似ている。樫本は、自身のレジュメに、「社会詠とその誤解が生じさせるかもしれない分断をどう考えていくか」という問いを立て、批評時に注意したい言葉や構図として、「人間と自然」、その人間の中においての「東京と被災地」と図示したように、むしろ句集および震災句に、わりやすい構図を持ち込み、復興や希望、再生などの物語を安易に見てしまわないように十分に注意していたに違いない。そうでありながら、発表時点では句集全体を少し震災に傾けすぎた印象を与えてしまったことは否めない。
飛花落花その一枚は赤き舌 『赫赫』
勉強会後の参加者も自由に発言できるオンラインの時間に、樫本からの吉沢に対する質問でもあった、震災句とみた基準は何かをあらためて質問した。吉沢は〈飛花落花〉の句に震災を感じたが、個人的感想にすぎず、震災句として第三者に伝わるか疑問に思ったと言う。樫本は、感想と鑑賞の難しさがあり、鑑賞の場合、ある程度の裏付けが欲しいと考えると補足した。
確かに、掲句の一枚の舌には、ピカソの「ゲルニカ」の女性が突き出した舌のような得も言われぬ悲痛さがあり、震災句ともとれる。しかし、花びらに赤い舌をみるのはいかにも渡辺らしい幻想的な妖艶さが漂う。結局、震災句であるかどうかは、どのみち読み手の個人的な感覚に大きくよるものなのであり、その判断は句作品の成否における判断の要素の一つにはなるが、すべてとはならない。
震災句において、俳句が社会をどう捉えるか、逆に俳句が社会へどう影響を及ぼすかや、その表現方法、当事者性などは、俳句をとりまく論点となりうるだろう。
被災者であるか否かの作者の当事者性について少し掘り下げれば、百年後はそもそも経験者がほぼいなくなり、戦争と同じように、震災未経験者が句の作り手、読み手となる。また、作り手は経験だけを詠むわけでなく、読み手も体験をもとに共感を感じることだけが俳句の読みではないことを考えれば、表現における当事者性とは表現しようと思ったときから作者に有するものなのではないかと思う。
いずれにしても、震災句を巡る議論は、俳句作品自体や俳句をとりまく論点より震災が抱える社会問題の議論に収斂していくことが多い。もちろん、そのことも文学がなしえる世界への問いとして意義はあるだろう。しかし、本稿も震災特集という括りで書いている点で矛盾しているかもしれないが、震災に焦点を当てることは、ときに俳人および句集の本質を見失うことになるのである。
したがって、先の発表において、もし比較するとすれば、『地祇』以前の『余白の轍』(1997年)、『数えてむらさきに』(2004年)からも考察することが必要ではなかったかと思う。
3 句集『赫赫』について(2)
『赫赫』において、渡辺誠一郎の俳句はまず「渡辺誠一郎」という分類で考えたい。

当たり前ではないかと言われるかもしれないが、出発点に震災句あるいは震災句集としての分類分けが入れば、それは震災物語として回収されやすいというのは前述してきたとおりである。その当たり前にとどまって考えたとき、渡辺が向き合った「震災への体験の内面化」というのは単に震災を示すにとどまらないことに気づかされる。
『赫々』と同年に出版された『俳句旅枕 みちの奥へ』(コールサック社)は、盛岡、津軽、飛島、いわきなど東北各地を巡った紀行文で、角川「俳句」に2017年2月号から2年にわたって掲載された連載を加筆再編成したものだ。これについて、渡辺は小熊座誌(2021年3月号)上で、相馬京菜氏と対談をしている。
渡辺 角川「俳句」の編集部からは、現代の歌枕を巡るような注文でした。しかし誌面の限定や取材時間等を考えると、限られます。帯文にもあったように、芭蕉、子規らの足跡を辿ると同時に、東日本大震災後のみちのくを改めて巡りたかったことです。その地を、過去の様々な記憶、古層まで辿り、その上で、大震災の記憶を確認し、私なりの物語を紡ぐことができないのかということでした。それはいわば、震災の記憶を加えた、新たなみちのく論です。
渡辺は宮城県塩竈市に生まれ、現在も在住である。その東北は、常に中央から虐げられ搾取され、自然災害と飢餓、貧困にさらされてきた。もともと土地に歴史的な崩壊が幾重にも積み重なっていたが、震災によって現実的に目の前で崩壊した。それは、産土に築き上げてきた自身のアイデンティティの崩壊でもあったかもしれない。
『俳句旅枕』では、東北の地を自らの足で歩き、つぶさに調べ、渡辺にしかできない幻想性を見出し、震災物語として消費するのではなく、東北という物語をふたたび構築していることがわかる。掲載されている渡辺の道中吟は30句ほどあるが、『赫赫』に収められた句もある(( )内は『俳句旅枕』の掲載地名及び頁、『赫赫』掲載頁)。
北奥に耿然とあり大冬木 (八戸,96p 61p)
潮びたるごとき葬列秋の風 (津軽,131p 65p)*句集では秋黴雨
炎天の風を巻きたる塩屋崎 (いわき,239p 89p)
心平の細目は二つ行々子 (いわき,253p 90p)
鵺啼くや櫛田民蔵のインク壜 (いわき,254p 91p)
ここで気をつけたいのは、その新しく紡がれた物語は震災から始まったのではなく、第一句集から継続してこの俳人が向き合い、闘い続けている創作の過程の延長にすぎず、さらに言えば、俳人となる以前からの、自身とは何か、その自身を作り上げるこの東北の地とは何かという問いが起立しているということである。
みちのくの春は荒縄泥のなか 『余白の轍』
秋夕焼父断層のごと斜め 同
蝙蝠を抱けば性愛微かなり 同
阿弖流為は群魂であり籾殻火 『数えてむらさきに』
昼過ぎて東京そっと落花せり 同
陸奥の常闇畳む酢牡蠣かな 同
あわれとは水飲みにくる菊人形 『地祇』
夕べには水を立たせる花あやめ 同
ぎやまんのような海鼠を差し出され 同
『赫赫』からあらためて句を鑑賞する。
国よりも先に生まれし田螺かな 『赫赫』
国は民を統べるために権力を使う。しかし、その前に民は存在しているのだ。国のために民が生まれているわけではない。自明のことだが、それはいつも忘れられ、名もその声も残さずに消されてしまうその他大勢が歴史の中に埋没している。掲句にある田螺は、その他大勢でも自尊を持ち力強く見える。
生きものは泥から生まれ夕薄暑 同
魚類から両生類あたりの生物の進化論を詠んだようにも思えるが、人がそのまま泥から生まれるようにも感じる。その泥は生暖かくとても懐かしい。
一滴の血もこぼさずに竹を刈る 同
竹に血管はなく、どんなに切っても血は出ないだろう。一方で、どれほど人間たちは血を流してきたかという批判がある。一滴も血をこぼさない世界は、竹を刈るように簡単ではないかもしれないが、そうと望めば出来ないわけではない。
無人駅にひとり青鹿の匂いして 同
どこの無人駅だろうか。青鹿の匂いがするという一人降り立つ者は青年のように思われる。都会から来たのか、思慮深く洗練された立ち姿だが、それは人ではないような気がしてくる。歩くうちに次第に青鹿という精霊となって、山の暗がりへと駆け上って消えていきそうである。
真葛原姉の壊れた土人形 同
土人形は、素焼きに胡粉をかけて泥絵具で彩色をした人形で、東北であれば堤人形が有名である。姉は霊的な先見と強固な意思を感じさせ、土人形は欠けたのか、ひび割れたのか、呪術の占いのようである。真葛原が覆うその一帯は何か不穏な空気を帯びている。幻想的なイメージに儚さや脆さはなく、読み手の体内をざわつかせながら、イメージの強度が増していくのは渡辺俳句の特徴である。
吾いつか蟻に曳かれる夕山河 同
あり得ないが蟻に曳かれるほど小さくなった遺体が見えてしまう。自身の屍が虫けらのように蟻に曳かれるのは惨いことかもしれないが、なぜか大らかな快哉という気分がある。虫けらと書いたが、虫けらの地面すれすれの視座こそ尊いと言われている気がする。
ここに描かれた「夕山河」は渡辺が築いた新たなみちのくの姿であろう。草むらに沈み込んだ低い視点から見上げるそのみちのくに包まれるからこそ、抗い難きことを受け入れられる豊穣ともいえる境地がある。
4 「内面化」とは何か
-1024x768-1.jpeg)
『赫々』のあとがきにあった「内面化」について、立ち話程度になったが、渡辺氏に質問すると、「祈りだ」という言葉が返ってきた。その時、塩竈マリンゲート近くにある東日本大震災モニュメントの慰霊碑が思い浮かぶと同時に、『俳句旅枕』に掲載された30句ほどだけではないであろう道中吟が、氏によって東北各地に建てられた十七音の慰霊碑のように思われてきた。しかし、それは震災への祈りにとどまらないだろう。東北の地に幾重にも折り重なる古層に沈み込むあらゆる生き物の命への祈りである。(写真=塩竈市東日本大震災モニュメント=2013年建立。仙石線本塩釜駅から徒歩3分=筆者提供)
そして、ランドマークのように東北各地に散らばっているその十七音を点として線で繋ぎ、数多出来た線上に面を立ち上げ、東北の古層と今へ新しい層を重ねた、それが『赫赫』なのである。
5 筆者自身の震災句を振り返る
この10年に作った震災句と思われる筆者の自句はわずかである。津波にも原発事故にも遭っていない。だからではないが、作ろうとも作りたいとも、作りたくないとも思わなかった。
自句をいくつか振り返ってみる。〈今は只静かなる海蝶生る〉は、傍観者的で綺麗すぎると思う。〈被災地に来い春の宵もう一度〉は、街に春の宵の艶やかさが確かにあるのに、開いている店はほとんどなく人影もまばらで、春の宵とは人々がいてこそと思った心情はありありと思い出せる。しかし、ややスローガン的で気恥ずかしい思いがする。〈声上げず泣きてゐし子にやがて雪〉は実景に心情を込めた句で、当時味わった無力感がこみ上げるが、まだ直截な表現で詩として昇華しきれていない。
むしろ、筆者にとって震災句と思えるのは、次の2句だろうか。
〈あたたかや近所の猫に会ひにゆく〉は、震災の年の春に見た近所の庭先に集まっていた猫を思い出し、その一年後に見に行った句だ。猫に会いに行けるのは自分が生きているから、そして会いに行った猫も生きているからである。〈皆顔の違ふこけしや春障子〉は全部倒れて処分せざるを得なくなったこけしの思い出と被災地に住む人々を被災者として一括りには出来ない、一人一人違うということを暗に思っている。しかし、震災句とは読まれないだろう。
原発についての句は、〈魚の目しやぶりてゐたる原爆忌〉が浮かぶ。
未曽有の原発事故への対処が水をかけるしかないということに呆然としたが、その汚染水を貯める場所がなくなって海に流すと聞いたとき、唯一の被爆国であるこの国がすることだろうかと眩暈がした。その一方で、原発事故は被害者と加害者という簡単な対立図式を描けない。抗議の矛先は自らにも向くのではないかと思われたときの句である。
6 再び「内面化」とは何か
-3.jpg)
震災から8年目の9月頃だろうか。ふと毎日の入浴時に震災のことを思い出さなくなっている自分に気がついた。髪を洗うときには目を閉じるからか、さまざまな思いが去来していた。入浴のときに思い出すのは震災時しばらく風呂に入れない時期があったからかもしれない。自分の中でも風化がはじまったのかと思った。
しかし、『赫赫』のあとがきにある「内面化」という言葉を筆者自身に借りれば、毎日思い出さなくなったのは風化ではなく、「内面化」したのではないかと思う。いわば、震災はときどき思い出すような過去ではなく、日常のすべて、さらには言葉のすべてから剥がそうとしても剥がせないものとなったのではないだろうか。(写真=仙台の街中、2011年3月17日=筆者提供=)
震災はそこだけ切り取れるような非日常ではなかった。目の前のいわゆる日常であった。その日常の地続きに今があり、それは明日という日常へつながっている。その言葉で作る句すべての奥底には震災が沈み込んでいると言えるだろう。だがそれは筆者にとって、希望でも復興でも再生でもない。ただそれだけのことにすぎないのである。
髪洗ふたび三月の雪が降る 渚
【執筆者プロフィール】
小田島渚(おだしま・なぎさ)
「銀漢」「小熊座」所属、仙臺俳句会(超結社句会)運営、第44回宮城県俳句賞。
【セクト・ポクリット管理人より読者のみなさまへ】
