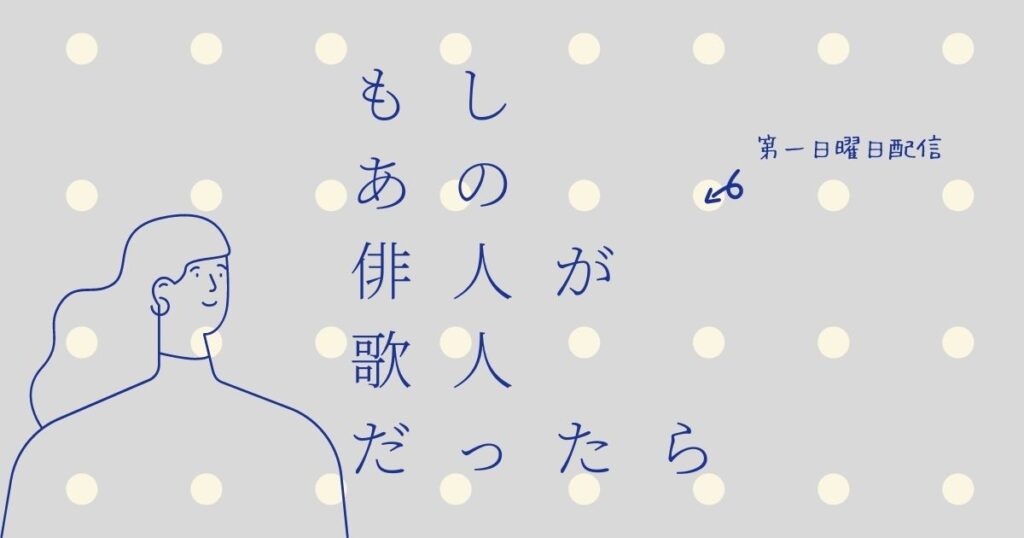
【連載】
もしあの俳人が歌人だったら
Session#12
このコーナーは、気鋭の歌人のみなさまに、あの有名な俳句の作者がもし歌人だったら、どう詠んでいたかを想像(妄想)していただく企画です。今月取り上げる名句は、石田波郷の〈初蝶やわが三十の袖袂〉。今月は、ユキノ進さん・野原亜莉子さん・鈴木美紀子さんの御三方にご回答いただきました。
【2022年3月のお題】

【作者について】
石田波郷(1913-1969)は、愛媛県生まれ。10代の終わりに、同郷の水原秋桜子が刊行した句集『葛飾』に惹かれて上京。長男誕生の1943年に召集。病気のため兵役免除となるが、死去まで手術と入退院を繰り返しつづけた。1946年に江東区北砂町に転居し、休刊していた主宰誌「鶴」を復刊。現代俳句協会の設立にも尽力。1969年、清瀬市の国立療養所東京病院(現・国立病院機構東京病院)にて死去。清瀬市は、2009年から「30歳以下」を対象とする「石田波郷新人賞」で若手俳人の顕彰に努めている。
【ミニ解説】
俳句では四季それぞれに「蝶」にまつわる季語があります。夏は「夏蝶」、秋は「秋蝶」、冬は「冬蝶」あるいは「凍蝶」。そして「蝶」といえば、それだけで春の季語となります。高野素十には、竜安寺で詠んだとされる〈方丈の大庇より春の蝶〉という句があるのですが、一般的には「春の」は不要です。
3月上旬から中旬は、暦の上だと「啓蟄」。土の中で縮こまっていた虫(=蟄)が穴を開いて(=啓いて)動き出す日のことで、一般的にもよく知られた二十四節気のひとつですね(俳句には「地虫穴を出づ」という季語もあります)。3月下旬になれば「春分」。いよいよ春らしさが増してくるころです。
蝶は、冬のうちに蛹となります。寒い時期に「休眠」をしないと、強い個体とならないそうで、気温も上がって日照時間も増え、あちこちに綺麗な花が咲き始める時期に合わせて、蝶は成虫となって飛び立ちます。ひらひらと暖かな日差しを舞う蝶は、春を代表する風物であり、とりわけ最初に見た蝶のことを俳人は「初蝶」として讃えます。

さて、掲句の石田波郷は、3月18日生まれ。まさにそんな初蝶のシーズンが誕生日であるわけですが、波郷が数えで「30歳」を迎えたのは、1942年のことでした。周囲の計らいで、吉田安嬉子と出会い、結婚するのもこの年のことで、秋櫻子が主宰する「馬酔木」を辞して、俳句結社「鶴」の運営に専心します。
15歳で学を志し、30歳にしてみずから立つ――。この「志学」から「而立」にいたる論語の道すじは、まさに波郷の前半生をあらわしているかのようです。和装の「袖袂」は、角までぴんとまっすぐと伸ばされているイメージ。ひらひらと飛ぶ「初蝶」の動きとは対照的でありながら、「何かがはじまる」イメージが共有されています。
さらりと「秋櫻子が主宰する「馬酔木」を辞して――」と書きましたが、モダニズム系の(いわゆる「新興俳句」系の)俳人とも付き合いのあった波郷は、新興俳句弾圧事件の黒幕とされる小野蕪子からの圧力を受けて、「馬酔木」を辞さざるをえなかったようです(田島和生『新興俳人の群像—「京大俳句」の光と影』)。波郷は20代の最後に、当局の「ブラックリスト」入りをしていたわけで、実際に――今風にいえば「忖度」によって――俳句を続けていくにあたって寄って立つ場所を奪われた、と。
時局を少し振り返っておくなら、前年12月、真珠湾攻撃によって太平洋戦争がはじまり、日本文学者会(仮称)が結成されたのが、1943年2月1日のこと。この翌月である3月からは、「馬酔木」の編集後記に波郷の署名消えています。ちなみに妻となる安嬉子と初めて会ったのも、同じ3月のこと。
同年6月、波郷は「馬酔木」から脱退。この月には、国策団体である「日本文学報国会」が結成され、日本文学者会は同会に吸収合併されることになったのは偶然ではないでしょう。さらに同月27日九段軍人会館にて吉田安嬉子と結婚挙式。失職同然であった波郷は、同門の石塚友二(1906-1986)の協力を得て、日本文学報国会に就職。5月には長男が生まれるも、9月に召集令状が届くという激動の1943年……
29歳から30歳にかけての波郷の「袖袂」の奥に隠されているのは、古典に耽り新しい古典俳句を書き記そうとする手であり、一生を病と付き合いながら過ごすことになる肉体を奮い立たせる手であり、愛する妻や子を愛撫する手であり、本心を偽りながらも国策機関の仕事に従事するための手でもあるのかもしれません。
ちなみに、波郷の選集である『初蝶』(2001年、ふらんす堂)の栞には、佐佐木幸綱さんが文章を寄せておりますので、興味ある方は、ぜひご一読ください。幸綱さんは『石田波郷読本』にも「波郷のプロ意識」というエッセイを寄稿されています。
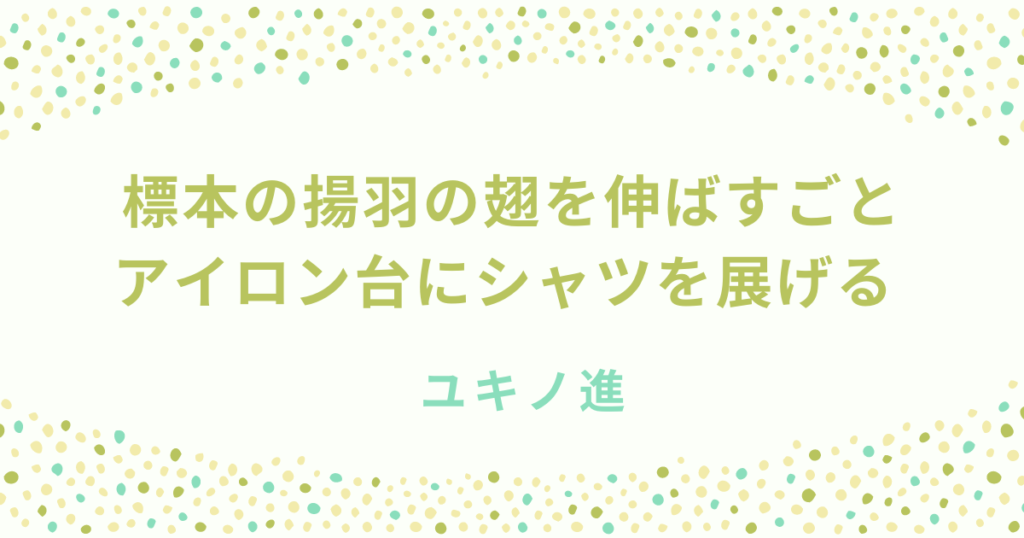
家事の中でいちばん好きなのはシャツの洗濯とアイロン掛けだ。クリーニングに出すのをやめて自分で洗濯するようになってからずいぶん経つ。週末の朝シャツを洗い、夜音楽を聴きながらアイロンをかけるのがひとつのルーティーンになっている。
襟や袖の汚れやすい部分はウタマロ石鹸でゴシゴシこすってから洗濯機に入れる。ウタマロ石鹸は奇蹟のようにこの世の穢れを落としてくれる。洗い終わってからはカラカラに乾かないように部屋で陰干し。そして右の袖から順に、ボタンの横の小さな部分や肩の丸まった場所などもしわを残さないように慎重にアイロンをかける。金曜の夜によれよれだったシャツがきりっとした姿に変わっていく様はとても気持ちがいい。そして平日の仕事でくたびれた自分自身が再生されていくようにすら感じるのだ。
コロナでリモートワークが中心になってからは毎日Tシャツで仕事をしているのでアイロンの必要がない。リモートによって毎日の通勤がなくなり、週末のアイロンがなくなった。区切りや再生の機会を逸しのっぺりした日常が続いている。
(ユキノ進)
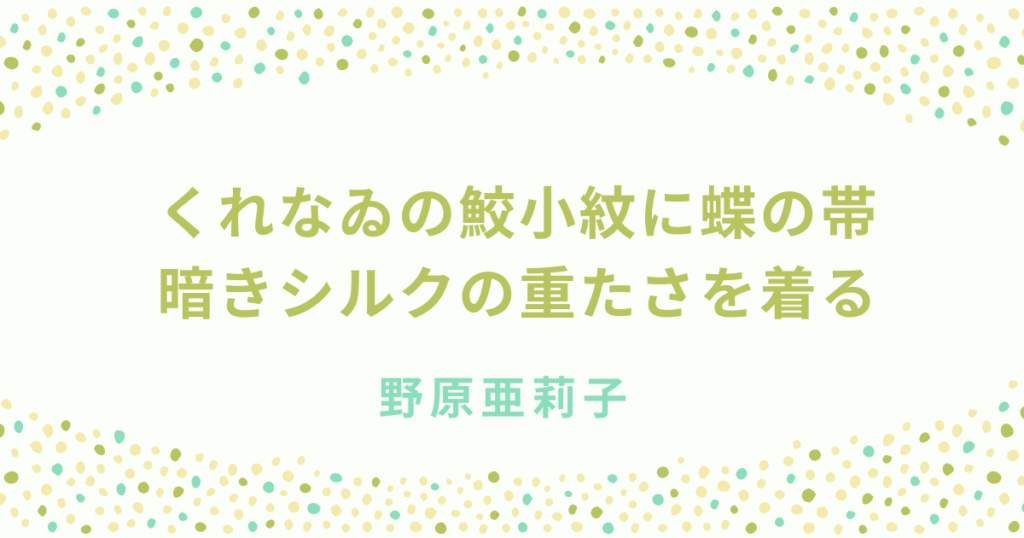
今年こそは着物を着よう。毎年そう思うのにちっとも着られない。夏は暑く冬は寒い。雨の日は汚れる。着るのに時間がかかり、徐々に着崩れてくる。荷物も持てない。着物特有の制約も多い。
にもかかわらず着物はやはり素敵だ。洋服だとできないような柄と柄の組み合わせを楽しんだり、派手な色にも挑戦できる。花が咲き蝶が舞う豪華絢爛な柄はまるで絵画のようで、全身に美しい布を纏う喜びを実感する。
着物は短歌や俳句に似ていると思う。制約があるからこそ自由に自己表現ができる。季節を先取りした花模様、袂からチラリと覗く襦袢の色、遊び心のある帯留め。微かな気配を繊細に捉えてきた先人たちの知性を感じる。
お出かけの機会も減り、zoomだと肩から上しか映らないが、それでも着物を着よう。ファッションとは誰かに見せるためのものではなく、自分をご機嫌にして楽しく生きるためにあるのだから。
(野原亜莉子)
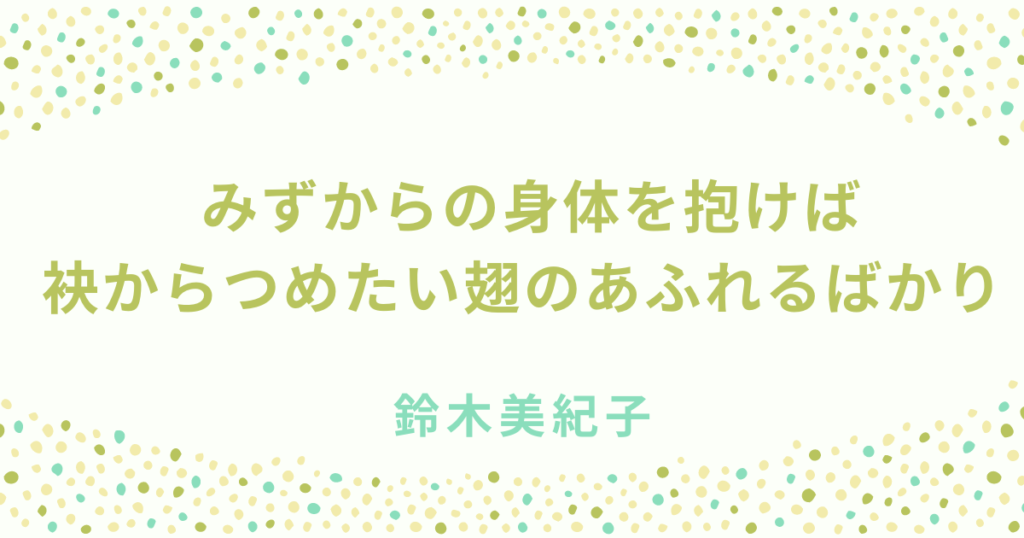
30歳のとき、わたしの身体はわたしのものではありませんでした。わたしの身体は、わたしの中に芽生えた小さな命に囚われていたからです。周囲の人から「もう、あなた一人だけの身体じゃないのだから大事にしなさい」と言われるたび、妊娠の喜びよりもその責任の重さに心細くなるばかり。授かった命のために自分の身体をまるごと明け渡すような日々が続き、想像を超える痛みを耐えぬいた出産後もわたしの身体はわたしの元へ戻されることはありませんでした。〈母親〉というスノードームの中に閉じ込められてしまったからです。昼となく夜となく泣きぐずる赤ん坊をひたすら抱き宥め揺らし続けた挙句、手首の腱鞘炎に。自らの意思ではなく、赤ん坊の泣き声に反応し母乳が滴る乳房は、赤ん坊のしもべに。この身体はわたしのものではない。わたしの身体はどこにいってしまったんだろう。わたしは何を失くしてしまったんだろう……。これがわたしのほろ苦くて冷たい30歳の頃の記憶です。
あれから年月が経ち子供も成人した頃、ちょっとした気まぐれでピアスをしたくなり美容クリニックを訪れました。痛みなんて大したことないと高を括っていたのですが、ファーストピアスの針に耳たぶを刺しぬかれた瞬間、思いがけない感情が溢れ出してきたのです。それは「この身体はわたしのものだ」というごくごく当たり前の認識からくる感傷でした。クリニックを出た後も耳たぶは熱を帯びジンジンと痺れていましたが、わたしはその痛みを甘受し味わい愛しむことができました。わたしのためだけの痛みが、わたしに自らの身体を取り戻させてくれたのです。耳たぶに開けた小さなピアスホールの痛みは深く遠くへ続いていて、スノードームに揺蕩っていた30歳の頃の身体をそっと繋ぎ留めてくれているのかもしれません。
(鈴木美紀子)
【ご協力いただいた歌人のみなさま!】

◆ユキノ進(ゆきの・すすむ)
1967年福岡生まれ。九州大学文学部フランス文学科卒業。2014年、第25回歌壇賞次席。歌人、会社員、草野球選手。2018年に第1歌集『冒険者たち』(書肆侃侃房)を刊行。
Twitter:@susumuyukino

◆野原亜莉子(のばら・ありす)
「心の花」所属。2015年「心の花賞」受賞。第一歌集『森の莓』(本阿弥書店)。野原アリスの名前で人形を作っている。
Twitter: @alicenobara
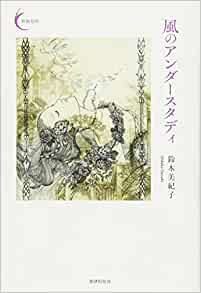
◆鈴木美紀子(すずき・みきこ)
1963年生まれ。東京出身。短歌結社「未来」所属。同人誌「まろにゑ」、別人誌「扉のない鍵」に参加。2017年に第1歌集『風のアンダースタディ』(書肆侃侃房)を刊行。
Twitter:@smiki19631
【セクト・ポクリット管理人より読者のみなさまへ】


