
【連載】
もしあの俳人が歌人だったら
Session#14
先月より第3日曜日にお引っ越し。気鋭の歌人のみなさまに、あの有名な俳句の作者がもし歌人だったら、どう詠んでいたかを想像(妄想)していただくコーナーです。今月のお題は、田中裕明の〈大き鳥さみだれうををくはへ飛ぶ〉。服部崇さん・鈴木美紀子さん・野原亜莉子さんの御三方にご回答いただきました。
【2022年5月のお題】

【作者について】
田中裕明(1959-2004)は、大阪府出身の俳人。1983年、角川俳句賞を当時史上最年少の22歳で受賞。波多野爽波の主宰誌「青」に拠ったのち、「ゆう」を創刊・主宰した。伝統をふまえつつも詩的な句風で、俳壇のニューウェーブとして活躍したが、白血病により早世した。没後、夫人の森賀まりらによって、田中裕明作品を語る「静かな場所」が創刊。2009年、45歳以下の若手俳人を顕彰するための俳句賞「田中裕明賞」(ふらんす堂主催)が創設された。
【ミニ解説】
五月から「夏」。中旬にもなると、「今年の梅雨入りは?」と天気予報などもそわそわし始めますよね。1951年以降の平均でいうと、沖縄の梅雨入りが5月10日ごろ、近畿地方や関東甲信越が6月6・7日ごろ、そして東北北部が6月15日ごろ。「桜前線」が通過していった日本列島には、「梅雨前線」が到来することになります。
「さみだれ」は「五月雨」。これは旧暦5月に降る長雨のことなので、現在の5月に降る雨のことではありません。梅雨がその時期のことを含むのに対し、五月雨は雨のことだけを指します。
歌題としては「長元八年関白左大臣頼通歌合」が早い用例があり、その後「堀河百首」、そして「金葉集」以後の勅撰集で多く立てられ、夏季の代表的素材となりました。
掲句は、「さみだれうを」という造語が独自です。景としては、いちにち降り止まぬ雨のなかを、魚を咥えた鳥が飛んでいったということでしょうか。鳥だって雨の日はたいへんです。翼が重たく濡れて、不自由でしょうから。
この雨がしとしとと降る梅雨なのか、それとも激しく降る雨なのかは、読者の想像に任せられています。魚がいるのですから、海か湖か川なのでしょうが、その鳥がどんな鳥なのかもまた、想像に任せられています。
五月雨にもの思ひをれば時鳥夜深く鳴きていづち行くらむ 紀友則(『古今集』巻3-0160 夏歌)
「長雨→眺め」からの連想で「もの思ひ」の情景と重ねられてきた五月雨ですが、和歌で登場するのは「ホトトギス」という小さな山鳥。ホトトギスは口の中が赤く、血を吐いて鳴いているようにも見えることから、正岡子規が俳号に子規、雑誌名に「ホトトギス」をつけたのは有名はおはなし。
この「大き鳥」は、海であれば大きなカモメ、湖や川であれば白鷺などでしょうか。しかし具体的な鳥の名前は、ここで重要ではありません。というよりも、「大き鳥」でなければなかったのでしょう。唐突さと大掴みさ。そしてその鳥が咥えている魚を「さみだれうを」と名づけることで、この一句はけっして絵には書けない、散文的にも説明できない、凝縮された言葉の奥行きだけに生まれるイメージを獲得したのだと思います。
もし、これが〈さみだれのうをくはへ飛ぶ大き鳥〉であったなら、言葉はもっとゆるやかな流れになり、結果として末尾の「大き鳥」に驚きは生まれせん。それに「さみだれのうを」、それなら誰にでも書けそうです。
この句における「五月雨」は、ほとんど観念になっているようにも感じられます。つまり、「さみだれ」という言葉が入っているからといって、雨が降っているとは限らず、さすがにピーカン晴れではないかもしれないが、しかしもう長雨のやんでしまったあとの海(湖)かもしれない。それもこれも「さみだれうを」という造語のもたらす効果です。
気づけば、この景色から、鬱陶しい長雨の暗さや重たさではなく、雨がやんで一筋の光明が差し込んできたような、そんな海の命のかがやきと軽やかさが感じられてくるから不思議です。
この句は、1985年に刊行された第二句集『花問一壺』所収。裕明20歳代前半の句です。

「心の花」の伊藤一彦さんにこんな歌がある。
おとうとよ忘るるなかれ天翔ける鳥たちおもき内臓もつを 『瞑鳥記』伊藤一彦
これを読んで以来、鳥を見るたびにその内臓の重さを考えてしまう。鳥の内臓と、粘土で作った人形とではどちらが重いだろうか。人形だって立たせるのは大変だ。重心を考え、左右対称にきちんと作らないと自立できない。
目に見えている世界は氷山の一角に過ぎない。見えていないものについて考えるのが大切だと思う。人形を作る時はあらゆる方向からよく見てよく考える事にしている。
軽々と飛んでいるように見える鳥も重たい内臓を抱え、必死で雨の中を飛んでいる。冷たい水に飛び込み、生きている魚の命を奪って生きるのは辛いだろう。生きているすべてのものは生の重さを持っている。だからすべての人に優しくしたいと思う。人はみんな泣きながら飛んでいる鳥なのだから。
(野原亜莉子)

グンカンドリを間近に見たのはガラバゴス諸島を巡ったときだった。ガラパゴス諸島では島ごとに違う鳥が生息している。グンカンドリがいたのはノースセイモア島だった。グンカンドリが木の枝の上で体を丸くしながら赤い喉袋を大きくしていた様子は今でも鮮明に記憶に残っている。喉袋を赤く大きく膨らませるのは雄鳥による雌鳥への求愛行動のようだ。グンカンドリは海鳥だが、泳ぎは得意ではない。カツオドリなど他の鳥が採った魚を奪って食べたりする。体は大きいが、餌の捕り方に関してはなんとも情けない鳥である。掲出句の「大き鳥」のかっこよさから、私はグンカンドリのことを思い出したのだが、あまりふさわしい連想ではなかったかもしれない。田中裕明がこの句を作った際には彼はグンカンドリではない鳥のことを思い浮かべていただろう。自ら「さみだれうを」を見つけて自ら捕まえることができる大きな鳥を。私は、グンカンドリの情けなさが好きである。
(服部崇)

もし、わたしが魚だったなら死の間際に一瞬だけでも自分の暮らしていた海や川を空から眺めてみたい。初めて見下ろす川や海の水面の美しさに嘴が食い込んだ身体の痛みさえ忘れてしまいそうな気がします。水の中の世界しか知らない穏やかな生活。水に守られ育まれ、閉ざされていたことに気づきもしないで終える生涯。それを幸せと呼ぶことにためらいはありません。それでも心のどこかで「大き鳥」がわたしを見つけ、空という未知の世界へ連れだしてくれることを切に願ってしまう自分がいます。命と引き換えに見下ろしたこの世界はわたしの眼にどんなふうに映るのでしょう。世界がわたしを失うとき、わたしは世界を手に入れる。その証として見下ろした水面は束の間、眩いほどの乱反射を見せてくれるはずです。
(鈴木美紀子)
【今月、ご協力いただいた歌人のみなさま!】

◆服部崇(はっとり・たかし)
「心の花」所属。居場所が定まらず、あちこちをふらふらしている。パリに住んでいたときには「パリ短歌クラブ」を発足させた。その後、東京、京都と居を移しつつも、2020年まで「パリ短歌」の編集を続けた。歌集『ドードー鳥の骨――巴里歌篇』(2017、ながらみ書房)。
Twitter:@TakashiHattori0

◆野原亜莉子(のばら・ありす)
「心の花」所属。2015年「心の花賞」受賞。第一歌集『森の莓』(本阿弥書店)。野原アリスの名前で人形を作っている。
Twitter: @alicenobara
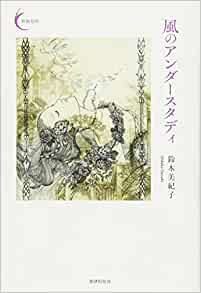
◆鈴木美紀子(すずき・みきこ)
1963年生まれ。東京出身。短歌結社「未来」所属。同人誌「まろにゑ」、別人誌「扉のない鍵」に参加。2017年に第1歌集『風のアンダースタディ』(書肆侃侃房)を刊行。
Twitter:@smiki19631
【セクト・ポクリット管理人より読者のみなさまへ】
