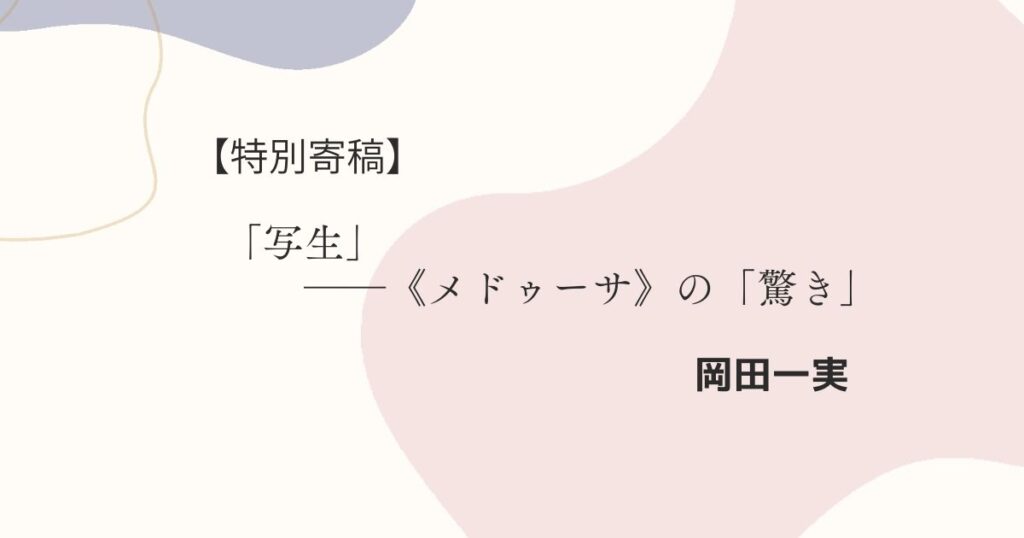
【特別寄稿】
「写生」──《メドゥーサ》の「驚き」
岡田一実
くもの糸一すぢよぎる百合の前 高野素十
桔梗の花の中よりくもの糸 〃
素十俳句における「客観写生」とは、「第三者的視点で書く」ということではない。対象に向かい、深く観照した先に得られる選択的な直感を、人間的でウエットな情の直接的叙述から距離を置いて叙することで、一般性や普遍性を獲得してみせる試みだったと思われる。ロマン主義的な「文学的意義深さ」に分け入らず、寸前で留まることで、通俗的で陳腐な情感から逃れようという試みだ。素十は「客観」を、膠着的でコンスタンティヴなものではなく、創造的で類推的でパフォーマティヴなものとして捉えていたのであろう。故に自由な闊達さがある。
前句、客観的ではあるが、美的に構成的な緊張感が宿る。対して、後句は構成的であからさまな作者の意図から脱し、理想美からもメッセージ性からも遼遠なる、ある種不気味で非理想的で非調和的な世界である。素十の書き方の多くは、水原秋櫻子が「文芸の真」と対置した「自然の美」などではなく、本質から大胆に書くものである。つまり書き方の技巧の極致だ。しかし、「写生」としてより不穏でノイジーな現実を捉えたのは、むしろ技巧が際立たない、後句のような句である。
書き方において、構成的と言われる山口誓子はどうか。
電柱のみな明るむや月に向き 山口誓子
泳ぎより歩行に移るその境 〃
一般的に、認知は、道具的価値、つまり、おそらく生存に役立つ概念を、点から点に移るように自然に背景化している。実在は点と点の間にも続いているのに意識されない。その点と点の間を言葉によって意識化させ、現前化してみせることで、新鮮な感覚を呼び覚ます。中期以降の誓子の試みは、むやみに点と点の間を埋めるのではなく、驚きという情動の到来を感受する閾値を下げて、構成的でありながら、只事すれすれにミクロの崇高を見出す、という志向だったと思われる。誓子は「即物非情」と言い表したが、理想世界から零れ落ちた事象を拾得する点においては、「写生」との交差を見出せる。
柳元佑太は、〈現実の「オブジェクト(=物)」が完全無欠なものであり、イデアであってそれに対して言葉がいくらかの欠損を抱えつつも近づいている。客体そのものに詩的源泉を求めている。それを言語においてどれだけ再現できるか〉が「写生の方法の裏付けの一般論」であると言う。その上で、写生句の価値の本質は「オブジェクト(=物)」ではなく、「書き方」であり、作者と読者のあいだで、過去の写生の語りとの近似を確認し合う営為こそが写生という営みである、と論じた(「翔臨」95号)。
「イデア」とは道具的で調和的な理想世界のオブジェクトのことで、雑駁で、ノイズで溢れ、多層的なこの環世界のことではない。事態に対し言態は易きに寄る。平凡な「写生」句は道具的で調和的で親和的な理想世界から逸脱することはなく、予定調和は打破されない。
子規が目論んだ「写生主義」には既に理想世界への批判的な視座があった。
《画の上にも詩歌の上にも、理想といふ事を称へる人が少くないが、それらは写生の味を知らない人であつて、写生といふことを非常に浅薄な事として排斥するのであるが、その実、理想の方がよほど浅薄であつて、とても写生の趣味の変化多きには及ばぬ事である。(中略)理想といふ事は人間の考を表はすのであるから、その人間が非常な奇才でない以上は、到底類似と陳腐を免れぬやうになるのは必然である。(中略)これに反して写生といふ事は、天然を写すのであるから、天然の趣味が変化して居るだけそれだけ、写生文写生画の趣味も変化し得るのである。写生の作を見ると、一寸浅薄のやうに見えても、深く味へば味はふ程変化が多く興味が深い。》(子規「病牀六尺」)
彌榮浩樹は柳元に呼応するかたちで、優れた「写生」句はリアリズムではなく、シュルレアル、つまり、現実離れした現実なのだと論じた(「翔臨」99号)。彌榮による「シュルレアル」は現実でありながら現実を超えた強度をもつ、ヘンな、オドロキのある現実のことである。
チューリップ花びら外れかけてをり 波多野爽波
柳元論と彌榮論の双方で取り上げられている爽波の代表句である。この句は本当に彌榮のいうシュルレアル的な「写生」俳句として全く問題のない句なのだろうか。
この句の内容は、季題「チューリップ」であるにも拘わらず全き姿ではなく、花びらの落ちかかっているさまの描写にある。花は「散る」ものであるにも拘わらず「外れ」と言語把握し直されている。確かに、「外れ」という把握・語彙選択は、「散る」の持つ儚げな印象にはない、チューリップの花びらの重量感をよく伝えている。しかしながら、この「にも拘わらず」の発想は、理想世界の単なる裏返しではないか。句の伝える「驚き」の源泉に、はからいによる理屈が垣間見える。
《振り返る途中で切落とされて叫ぶその顔を見るとき、私の顔にもその驚愕と恐怖がうつる。(中略)見る私の動きはメドゥーサの顔の動きに巻き込まれ、メドゥーサの情動と共鳴し始める。メドゥーサの顔は、見る私を先取りするようにして私の顔と「韻」を踏み、 歪んだ鏡となって私の未来を奪う》平倉圭『かたちは思考する』(東京大学出版、2019)
《メドゥーサ》は絵画表現で、驚愕の表情そのものだ。言語表現である「写生」俳句において、それを為す動機となる非調和的でノイジーな「驚き」が読者に伝染するように書くこと、そして、読者が書かれた俳句に「韻」を感じ取り〈未来が奪われる〉、そこに「写生」俳句の醍醐味がある。はからいなどの夾雑物が混じると作者と読者の間に距離が差し挟まれ、深く伝染しにくい。
爽波の「チューリップ」句がもつ魅力は、偶然性・一回性による異化よりも、時間性にある。〈外れかけてをり〉の中途経過のぐらつきが、gif動画のように動的に放置され、リフレインする。不安定で不確定なまま打ち遣られている動的な蕩揺にこそ、〈現実を超えた現実〉の不穏さが漂う。読者が一句全体を読み下す時間と花びらの蕩揺が「韻」を踏むことで、現実にあって現実を超えた不思議さを読者は得るのだ。
人間のもつ感覚には身体的・認知的共感がある。「驚き」にも法則性があり、共感を得やすい一方で、類型化しやすい。現実を揺らすような非調和的でノイジーな「驚き」ならば、際限なく開拓が可能なのだろうか。些末主義が加速していき、読み味の乏しさが募るばかりではないのか。そして、「書き方」の問題が再度立ち上がる。
かほの絵の服を着てからゆらゆらす 鴇田智哉(『エレメンツ』素粒社、2020)
鴇田は広義の「写生」の方法を採るが、現れ(appearance)の抽象度を高め、物の価値/知覚の重み付けを相対化し、メッセージ性を剥がし、象徴性を高める。「驚き」さえも相対化された世界が不穏に漂う。ここに「オブジェクト」に頼らない「書き方」のひとつの到達点がある。三橋敏雄が提唱した「驚きを書かず、書いた俳句に驚く」と方向性を同じくしつつ、現象に軸足があるのが鴇田の特徴だ。
竹中宏は写生派俳人には「近代的な意識主体が考える、あるべき価値が、人間を窒息させるという考え方がある」と喝破した(竹中宏「写生の『中味』」 愛媛大学写生写生文研究会京都研究会 第一部・基調講演、2012.2.4)。写生句の価値の本質が「過去の写生の語りとの近似を確認し合う営為」であるならば、「あるべき価値」の範囲での対話であり、やはり窒息は免れない。
われわれは、過去の俳句のみならず、重なり合いつつ個々に異なったデータベースをもつ。「データベース的に全き読者は存在しない」という事実が、作者にとって、読者個々の参照を期待できるかもしれない。「写生」は本来的に作者本位の語であり、作者の振る舞いであり態度のことだ。読者は知識や経験則(heuristics)、形而上形而下両方を参照しながらそれを読んでいる。作者・読者は双方ともに多様性と多元性を有している。「言語」には免れ得ない「抽象性」、即ち、細かく綿密に言語的に描写しても、それは「写実」ではなく「情報の多い抽象」なのだという記号性がある。まずはそれらを軸とする。そして、韻律表現的行為を等閑視するような、情報の報告を句の表面に「写す」ことを目的とした「写生」観から離れ、「驚き」を含めた身体的・認知的共感を類推し、読者の脳裏にそれをうち鳴らすように刻み書く(「伝染させる」)。「作者である私が書く『天道虫』と読者であるあなたが想起する”天道虫”は別のものだが、ありありと新鮮に飛ばせてみせましょう」という、「写生」から謂わば転倒した、読者の想念のなかの身体的・認知的共感を先取りする韻文的試行がいわゆる「一%の写生句」となり得るのならば、その方法にはまだ可能性は閉ざされていないように思われる。
翅わつててんとう虫の飛びいづる 高野素十
(『現代俳句』2023年3月号初出を加筆修正)
【執筆者プロフィール】
岡田一実(おかだ・かずみ)
第3回芝不器男俳句新人賞にて城戸朱理奨励賞。第32回現代俳句新人賞。第11回小野市詩歌文学賞。第42回現代俳句評論賞。句集に『境界ーborderー』(2014)、『新装丁版 小鳥』(2015)、『記憶における沼とその他の在処』(2018) 、『光聴』(2021)「鏡」47号より入会予定。