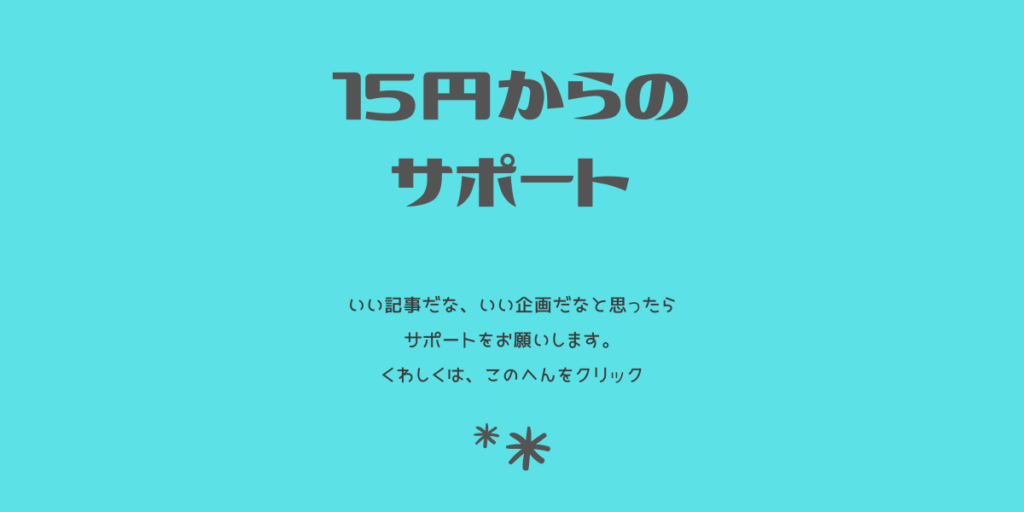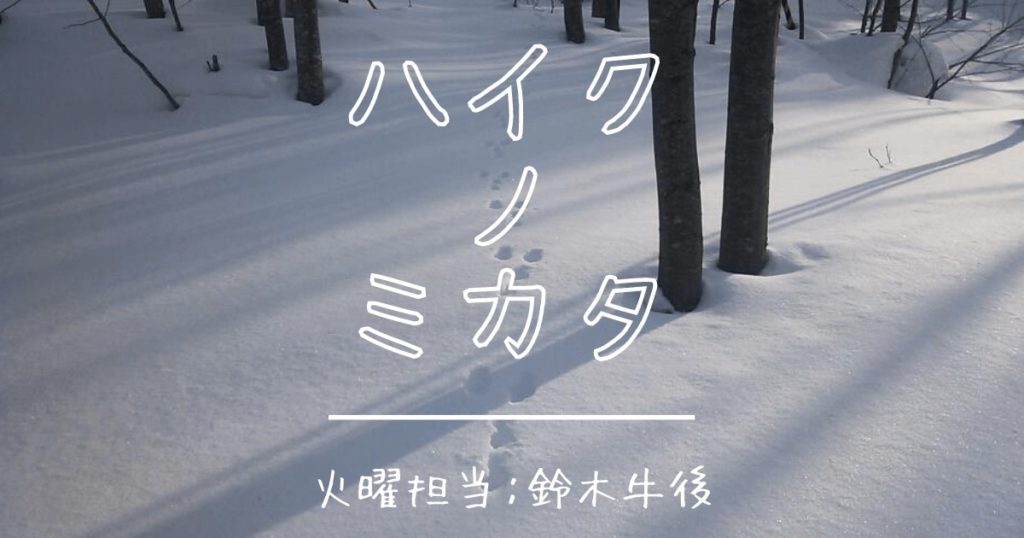
流氷は嘶きをもて迎ふべし
青山茂根
今年も流氷が到来した。気象台から流氷がはじめて目視できた日をいう「流氷初日」は紋別で1月26日。昨年の紋別の「流氷終日」は3月13日だったから、2か月近く居座ることになる。
流氷は春の季語ということになっている。流氷期の大半は立春以後ということだからかもしれないが、北海道ではやはり流氷=真冬という感覚が強い。それは、流氷が来ると寒さがいちだんと厳しくなるという体感から来ているので、それを払拭することはなかなかできないからだ。
虚子編「新歳時記」でも流氷はすでに春の季語となっているが、この「流氷」には、春になって川に氷が流れることも含まれているようで、実際に《草ともに氷流るゝ野川かな 蝶夢》の例句もある。
実は「新歳時記」の戦前版には樺太や大陸の、大きな河川やその河口付近の氷のことが多く書いてあったということを、以前橋本直さんから伺ったことがある。戦後版はそれを削除したので、流氷といえばオホーツク海沿岸に寄せて来るものに限られるようになったようだ。現在の歳時記は、単に虚子が春に置いたことを踏襲しているだけということなのかもしれない。
流氷は嘶きをもて迎ふべし
流氷には静と動の両方の面がある。静はびっしりと接岸して隙間なく海を埋めた風景。動は、ぎしぎしと音を立てながら陸に近づいてくるダイナミズムだ。俳句では両方詠まれるが、掲句は後者のイメージだろう。
高く低く夜の底に物の怪が呻くような音を立てながら近づく流氷。そこには海陸がせめぎ合うエネルギーの迸りがあるようにも思える。それを迎えるには、それ相応の生命力が必要だ。そこでもってきたのが馬の嘶き。
実は流氷と馬には共通点がある。流氷は、モンゴル高原に源を発するアムール川から、大量の淡水がオホーツク海に流れ込むことによって海表面が凍ってできる。馬は古墳時代に朝鮮半島から日本にもたらされたものと言われるが、もともとは西ユーラシアからモンゴルにかけての草原で広く飼われていたものだ。
そう考えると、馬が嘶きをもって故郷を同じくする流氷の到来を迎えること、それがとてもふさわしいことに思えてくる。作者はこの一句によって、流氷の軋む音と馬の嘶きとの共鳴を、流氷で埋め尽くされたオホーツク海に響き渡らせようとしたのだ。
(鈴木牛後)
【執筆者プロフィール】
鈴木牛後(すずき・ぎゅうご)
1961年北海道生まれ、北海道在住。「俳句集団【itak】」幹事。「藍生」「雪華」所属。第64回角川俳句賞受賞。句集『根雪と記す』(マルコボ.コム、2012年)、『暖色』(マルコボ.コム、2014年)、『にれかめる』(角川書店、2019年)。
【セクト・ポクリット管理人より読者のみなさまへ】