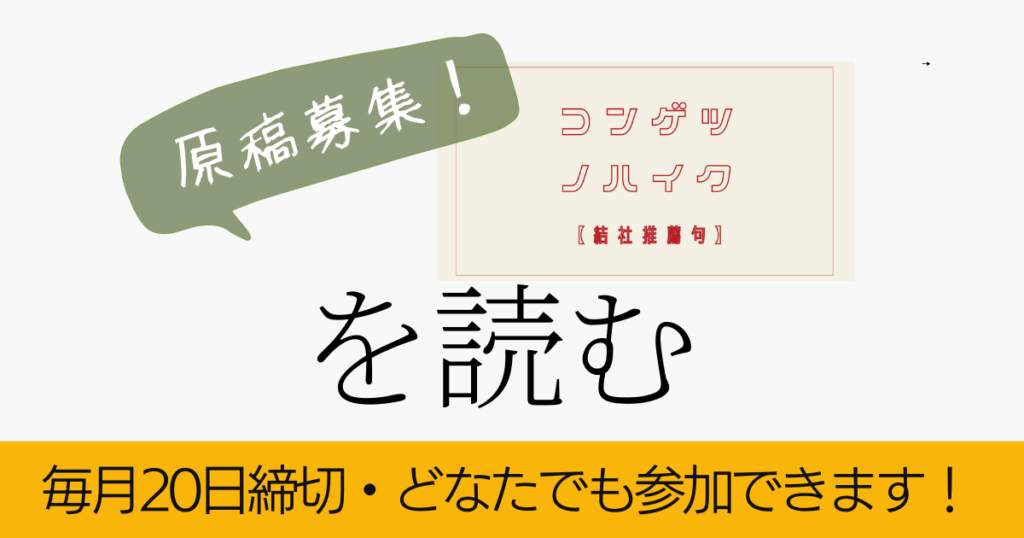【読者参加型】
コンゲツノハイクを読む
【2022年7月分】
ご好評いただいている「コンゲツノハイク」は毎月、各誌から選りすぐりの「今月の推薦句」を(ほぼ)リアルタイムで掲出しています。しかし、句を並べるだけではもったいない!ということで、一句鑑賞の募集を行っています。まだ誰にも知られていない名句を発掘してみませんか? 今回は7名の方にご投稿いただきました!(掲載は到着順です)
軽やかに光を配る風車
政元京治
「鳰の子」2022年6月・7月号より
のどかな田園風景がひろがる日本の原風景。都会の方なら誰もがというくらいに憧れる景色。その中に畑が広がっている。農夫だろうか?畑の中で作業をしている方がいらっしゃる。その方は、せっせと畑仕事をしているのだが、その畑には風車がたっていて風を流してくるくると回っている。もぐら避けの為に畑に風車がたてられているのだが、気持ちいい風の中に日差しがさしていて、その日差しのひかりをまるで春の陽気のように流してくれている。その流す様子を配ると表現され見事に描写され1句に纏めあげられている句である。
(杉森大介/「ホトトギス」)
くうるりとなほる逆子よ春隣
吉田祥子
「磁石」2022年5・6月号より
妊娠中は予想外のできごとが多くあり、逆子のそのひとつ。逆子と言われてもあまり心配しすぎず、自然となおってくれるのを待つしかない。この句は「くうるりと」のオノマトペが楽しく、前半のひらがなだけの表記にのんびりとしたやさしい雰囲気がある。そして季語「春隣」に希望を感じる。わたしも妊娠中や産後はさまざまなマイナートラブルに悩み、一日中ネットで情報を漁っては暗い気持ちになっていた。もっと気を楽にして大丈夫と言ってくれるようなこの句を、当時の自分に教えてあげたい。
(千野千佳/「蒼海」)
書くうちに出てくるインクヒヤシンス
依田善朗
「磁石」2022年5・6月号より
あれっ、書けない、インク切れかな? と思ったペンでも、ぐりぐりと線を引いているうちにインクが出てくる。今までの人生で何度も体験した筈のそんな現象を、しかし私は俳句にしようとは思わなかった。なぜか。鈍感だったからである。ペンはインクが出て当たり前、出なければ役立たず、という「常識」に囚われ、出ないペンが出るペンに変わる瞬間に感動があること、そしてそれが俳句になり得ることに思いが至らなかった。この句の作者の繊細さを見習いたい。
(西生ゆかり/「街」)
ぶらんこの降り方愛の屠り方
黒澤麻生子
「磁石」2022年5・6月号より
言わずと知れた三橋鷹女の「鞦韆は漕ぐべし愛は奪うべし」の本歌取り。この句は戦後の若い世代の女性達を鼓舞する句であったとか。それもあってか戦後七十年を経て昨今は女性から告白するケースが多いと聞く。さて掲句。そんな現代にあってむしろ愛は終わらせ方が難しいと教える句と読んだ。しかもお互いに冷え切って合意の上で分かれるのではなく、一方的に「屠る」難しさ。ぶらんこも完全に静止してから降りるのは簡単だが、揺れているまま降りるのは難しい。ひょいと気楽に飛び降りると着地に失敗して思わぬ大怪我をする。含蓄のある現代の名句。
(種谷良二/「櫟」)
花冷や揃へてたたむ木偶の指
日野久子
「南風」2022年7月号より
舞台を終えた人形を箱に仕舞おうとしているのだろう。丁寧かつ慎重な取り扱いが要求される存在で、とくにその指はもっとも注意を要する部位といってよいかもしれない。「揃へてたたむ」から作中主体が人形をいたわりつつも細心の注意を払っている様子がうかがえる。「花冷え」の季語は、前述の内容に加えて人形の指の繊細さや冷たい質感を思わせ、また舞台上でのいきいきとした様子とそのあとの沈黙ぶりといった想像を喚起させるうえで有効に機能していると考えられる。
(光本蕃茄/「澤」)
セーターの肘当の押す夜の扉
さとう独楽
「蒼海」2022年16号より
みんなが触るところにはなるべく触らないようにして久しいですね。ドアノブなど、回さなければならない場合は仕方がないですけど、押すだけの扉なら肘で押す人が多そうです。そこに注目して現在の状況が現れています。夜の扉、からは、外へ出る扉を思いました。出かけるところだとしたら、マンションの入り口でしょうか、それとも雑居ビルなどから出て帰宅するところでしょうか。肘あて付きのセーターということで、若干ラフな外出かな、とも想像できます。
(フォーサー涼夏/「田」)
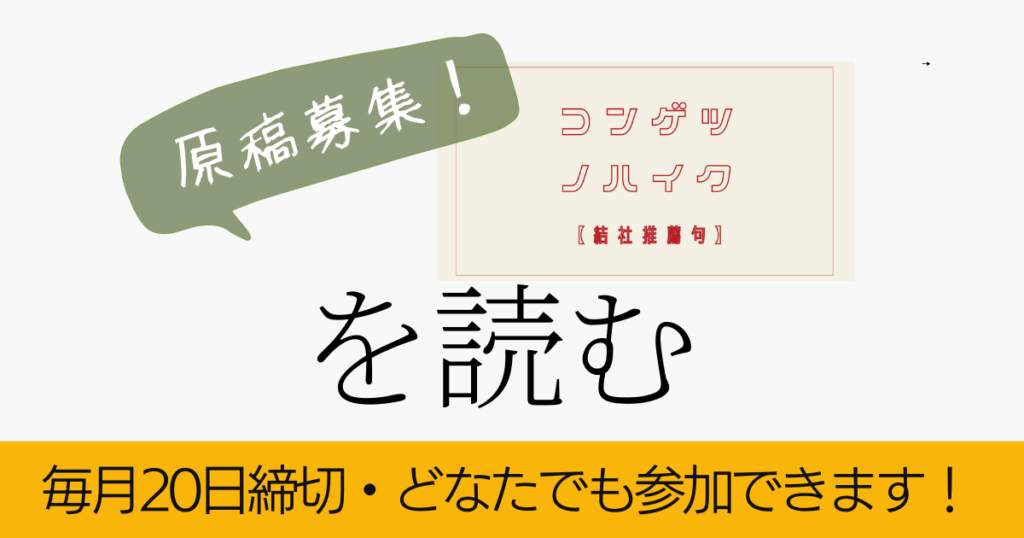
惜春を置いてきぼりに試着室
塚本一夫
「銀漢」2022年7月号より
春から夏へと人の心が移りゆく様を「試着室」という空間に託す。やや非日常を感じる「試着室」はしかし確かに現実と地続きであり、感傷のみが先走ることはない。
春の終わり、ファッションの勉強中である友人と買い物へ行った。試着室に持ち込み切れないほどの服を薦められ次々と着替えていると、やって来る次の季節への期待が自然と膨らんだ。試着室を出るとき、何か忘れ物をしているような気がして何度も振り返ったことを掲句から思い出した。あの時、私が置いてきぼりにした「惜春」は今も試着室に残されたままだろうか。
(笠原小百合/「田」)
→「コンゲツノハイク」2022年7月分をもっと読む(画像をクリック)
【セクト・ポクリット管理人より読者のみなさまへ】