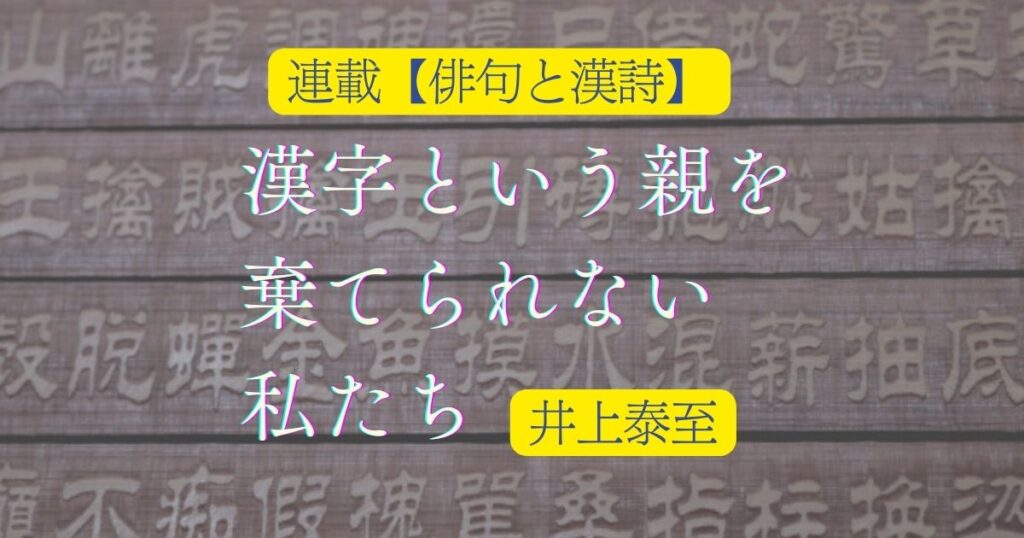
【連載】
漢字という親を棄てられない私たち/井上泰至
【第5回】
漢語の気分
句会で、漢詩由来の漢語を使った句を出して見た時のこと、
「気取ってますね」
と言われた。即座に
「品を良くしようとしただけなんですよ」
と脳裏には浮かんだが、「貴方は下品だと」という含意を以て受け取られる怖れもあり、呑み込んだ。
「小川軽舟さんという同世代を代表する俳人がいますがが、あの号も漢詩由来のはずで、あの方のことも「気取っていますね」と切るもりですか?」
とますます穏やかではない台詞が浮かび、十年経ってもその記憶は残り、今こうして思い返して書き付けている執念深さは、我ながら始末に悪いと思う。私の学生時代のあだ名の一つに、「モニター」というのがあった。
さて、蕪村の有名な、
牡丹散りて打ち重なりぬ二三片
という句がいい例だから、漢詩由来の詩語は、「気取り」なのか「品格」なのか考えてみよう。
牡丹のようなゴージャスかつ、華麗な花を正面から詠むのは、俳句の短さから言って無理がある。そこで、蕪村は、腐っても鯛ならぬ、散っても牡丹と変化球を投げてきた。これは俳句の本道である。しかし、視点の意外性だけで蕪村は満足するような小物ではない。牡丹本体の色気を出すべく、女性が服を脱いでそれが重ねてうち敷かれているような表現を中七に持ってきた。平安朝の十二単(ひとえ)の色襲(かさね)を連想させる言葉で、ここからは濃厚な色気が漂ってくる。
そこで蕪村は、上五に字余りの「牡丹散りて」、下五に「二三片」と、共に漢語調を持ってきて句を引き締め、凛とした品格でくるんだ。こういうのを「気取り」の一言で切ってしまうなら、最上級のパティシエのスイーツを、その辺の饅頭の感覚で判断するようなものであろう。
現代で、このような繊細な句作りをされるのは、片山由美子さんだと思う。
花の色とはうすべにか薄墨か
仮名と漢字の表記の使い分け、句またがりのリズムによる揺蕩う感じ。漢語ではないが、漢字のイメージたる「薄墨」が下にくるから、「うすべに」の色気が引き立つのだ。漢語系は、俗になりそうな題材を詠むとき、それを緊張感のある言葉やイメージで引き締め、そのことが俗を美に磨き上げるのだ。
蕪村は、芭蕉の弟子でも、都市系の俳諧を率いた其角の流れに位置する。地方は、芭蕉の「かるみ」を見たまんま俳句にすり替え、マニュアルや人生教訓書まで作って「結社」を組織していった支考が制覇してゆく。近代ならこの両方をうまく使い分けたのが、虚子ということになる。
俳句の歴史は、常に大衆化と先鋭化のせめぎ合いである。そして、先鋭化に寄与した文学的資源としては、漢詩文そのものか、漢詩文的なるものが必ず数えられる。
【執筆者プロフィール】
井上泰至(いのうえ・やすし)
1961年、京都市生まれ。上智大学文学部国文学科卒業。同大学院文学研究科博士後期課程単位取得満期退学。博士(文学)。現在、防衛大学校教授。著書に『子規の内なる江戸 俳句革新というドラマ』(角川学芸出版、2011年)、『近代俳句の誕生ーー子規から虚子へ』(日本伝統俳句協会、2015年)、『俳句のルール』(編著、笠間書院、2017年)、『正岡子規ーー俳句あり則ち日本文学あり』(ミネルヴァ書房、2020年)、『俳句がよくわかる文法講座: 詠む・読むためのヒント』(共著、文学通信、2022年)、『山本健吉ーー芸術の発達は不断の個性の消滅』(ミネルヴァ書房、2022年)など。
【バックナンバー】
◆第1回 俳句と〈漢文脈〉
◆第2回 句会は漢詩から生まれた①
◆第3回 男なのに、なぜ「虚子」「秋櫻子」「誓子」?
◆第4回 句会は漢詩から生まれた②
【セクト・ポクリット管理人より読者のみなさまへ】
