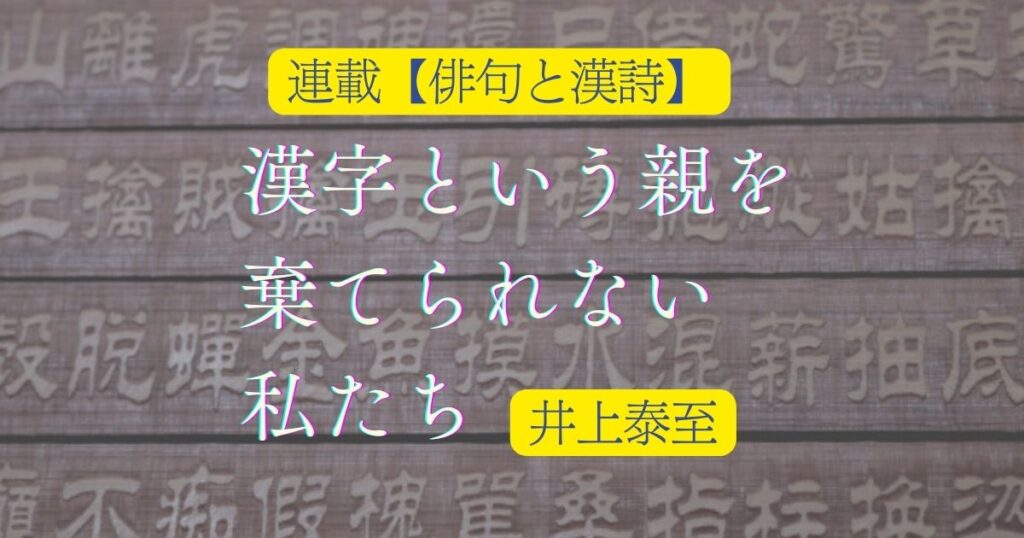
【新連載】
漢字という親を棄てられない私たち/井上泰至
【第1回】
俳句と〈漢文脈〉
漢詩はほぼ死に絶えた文芸だ。今年七月亡くなられた、この道のオーソリティで、自身漢詩を詠まれる石川忠久先生の授業に、院生時代出たことがある。『唐詩選』が全部頭に入っておられ、漢詩の評釈の最後には、先生一流の節回しの朗詠をされ、再度中国語で吟じ終えて、「いい詩だな」で決めるのがお定まりだった。まあ、「いい思想だな」とはならないよね、と授業の後に、悪友とまぜっかえした覚えがある。
Amazon.co.jp: 漢詩の稽古 : 石川忠久: 日本語書籍
明治の作家のペンネームが、鷗外・漱石・子規・露伴等々、漢詩文にルーツを持つものだったのに対し、大正になると、芥川龍之介・高村光太郎・萩原朔太郎と変貌する時点で、漢詩は生きた文学ではなくなったことがわかる。漢詩の投稿欄が新聞から消えるのは大正期だ。
俳句界に眼を転じれば、この手の大正風の俳号を使いだしたのは、中村草田男であったことが見えて来るし、本人に漢詩の教養がなくても、4Sの俳号はまだまだ漢詩の匂いが漂う。俳句は周回遅れの文学と言う面は否めない。
さらに言えば、星野立子・上野泰・清崎敏郎といった昭和に入っての虚子門の実名作家が、今の先駆けであったことも見えてくる。ただし、高浜年尾は漢詩人でもある子規の命名なので、扱いは難しい。そう言えば、立子も虚子が数えで三十歳の時の生まれに際し、『論語』の而立から引いた男っぽい命名ではある。
父がつけしわが名立子や月を仰ぐ 星野立子
つまり、意識・無意識に日本語が背負う〈漢文脈〉に眼を向けた時、そこには幾多の発見があることが予想されるのだ。連載はそういうものにしたい。漢文は言文一致以降、衰えたのか、日本文化の基盤として生き続けているのか。そういう二項対立は一旦おいて、古い文体としてではなく、現代に活かす古典の知恵だけでもない、「もう一つのことばの世界」としての〈漢文脈〉の眼から、俳句を見つめ直してみようと言うのである。
Amazon.co.jp: 漢文脈と近代日本 (角川ソフィア文庫) : 齋藤 希史: 日本語書籍
そもそも漢詩文によって構築された、日本語の中の表現、その背景にある文化の体系の問題抜きに、短詩型文学、特に俳句は語れない。芭蕉の正風が、漢詩文の引用をする実験時代を通して生まれたことや、蕪村の修辞や発想が漢詩から来ていることは常識の世界だし、生涯漢詩を詠んだ子規の革新もまた、漢詩文抜きには語れない。
俳句は短歌と違って、下五から逆転して詠むことが可能だし、そういう読み方を要請するものが多い。特に俳諧の時代の、切れの強い発句はその色が濃い。芭蕉の
古池や蛙飛び込む水の音
にしても、「水の音」を読んでから、自ずと上五・中七を反芻するものだから詩として成り立っている。外山滋比古が『省略の詩学』で、俳句は本質的に漢詩文に近いと見切った発言をしているのは、慧眼なのである。
Amazon.co.jp: 省略の詩学―俳句のかたち (中公文庫) : 外山 滋比古: Japanese Books
【執筆者プロフィール】
井上泰至(いのうえ・やすし)
1961年、京都市生まれ。上智大学文学部国文学科卒業。同大学院文学研究科博士後期課程単位取得満期退学。博士(文学)。現在、防衛大学校教授。著書に『子規の内なる江戸 俳句革新というドラマ』(角川学芸出版、2011年)、『近代俳句の誕生ーー子規から虚子へ』(日本伝統俳句協会、2015年)、『俳句のルール』(編著、笠間書院、2017年)、『正岡子規ーー俳句あり則ち日本文学あり』(ミネルヴァ書房、2020年)、『俳句がよくわかる文法講座: 詠む・読むためのヒント』(共著、文学通信、2022年)、『山本健吉ーー芸術の発達は不断の個性の消滅』(ミネルヴァ書房、2022年)など。
【セクト・ポクリット管理人より読者のみなさまへ】



