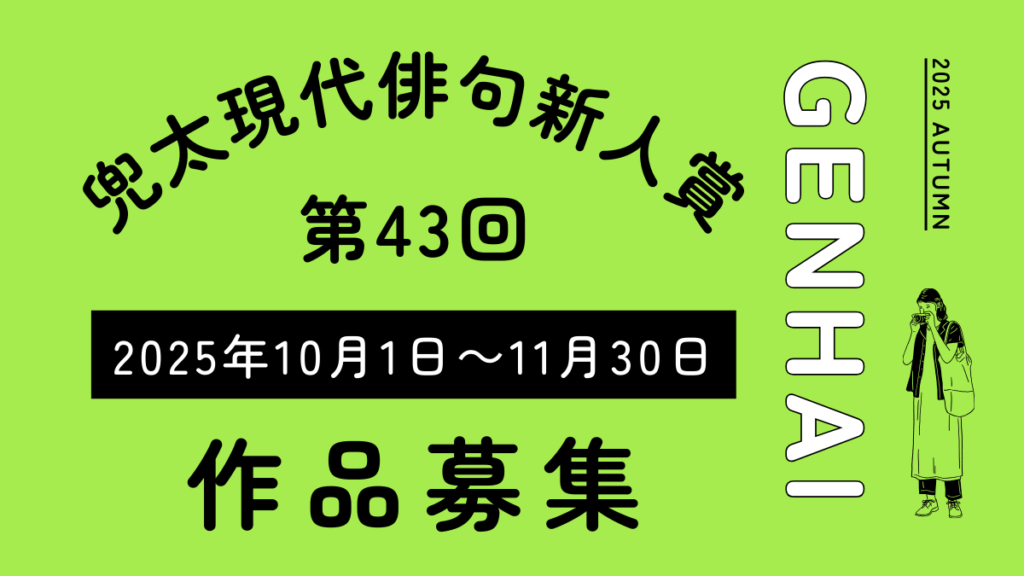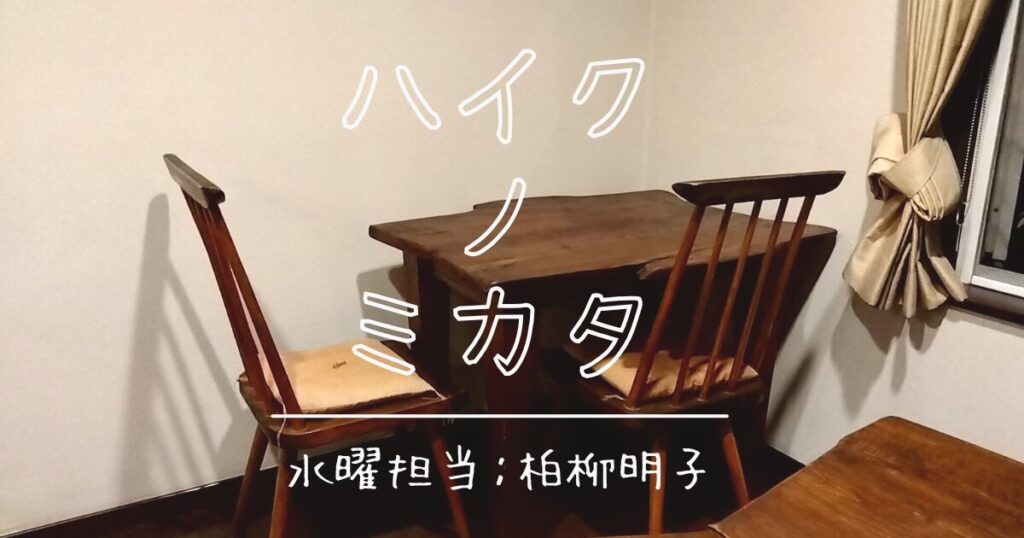
凍つるなり宇宙の闇が窓にまで
奥坂まや
冒頭「凍つるなり」の強い響きにドキリとする。アンデルセンの「雪の女王」ではないが、世界全体が凍りついてしまったかのように。続く中七下五の畳みかける言葉のとその迫力から身ひとつで真空へ放り出された感覚に陥る。暗黒の中の恐ろしいほどの孤独。おのれの存在および生命自身と対峙せざるをえないほどの。
「宇宙の闇」とあるので夜だということはわかる。しかし、「宇宙の」と冠することで闇は無限の空間と時間をもつ存在として読者の胸にのしかかってくる。だとすると、時間帯は深夜なのだろう。何もかもが眠りについた世界の片隅で、静止したような時間の中で、凍てつく寒さに震えつつ窓の外の闇に己が心を浸している作者。それはただ夜空を見上げているだけでなく、何か、誰かを追悼しているような祈りの姿にも見えてくる。
そういえば、掲句の入った句集には以下の句がある。
冬銀河頬杖つけば死が親し
物思いにふけったり、何かを思い出すとき得てして人は「頬杖をつく」という動作を取ることが多いが、季語と下五「死が親し」が共鳴しあうことで「生き残ってしまった自身」を実感し途方に暮れている映像と心情が伺えるようだ。その意味で、この句と掲句はどこか兄弟句のように筆者には見える。
だが、冬銀河の句に対し掲句は「宇宙の闇」とあることからおそらく星すら見えないのだろう。もしかすると、その闇はビッグバン後の膨張と冷却の表情を伴って作者には見えたのかもしれない。宇宙の始まりであるビッグバン。大爆発の後の宇宙の膨張、そして冷却しつつ銀河が生まれ、地球が生まれ、現在の我々までつながっていく。約138億年前から続く空間と時間はまさに「闇」であろうし、「凍てつく冬の夜」だからこその実感がこの句を作者の裡より呼び寄せたのではないか。物理学では現在も宇宙は膨張を続けているという説が有力とのことだが、宇宙から見れば塵にも満たぬヒトと地球の存在、そして時間を体感している作者の内面を示すには「凍てつく」の表現こそが相応しい。
2024年に「量子もつれ アインシュタイン 最後の謎」「チ。-地球の運動について-」、2025年に「3か月でマスターするアインシュタイン」と宇宙や天文に関する科学番組が立て続けにNHKで放送された。どの番組も、普段の生活や自分では想像もつかぬ途方もないスケールの世界・宇宙や時間・空間を伝えるとともに、物理学者や天文学者たちが一つずつ解明してきた理論と歴史を紹介していた。
領域は異なるが故・相棒は物理学の専門家だった。(「この説明が入っていないのはおかしい」という呟きを時には交えつつ)彼に言わせるとどの番組もわかりやすかったらしいが、バリバリ文系の私には正直毎回「?」だった。でも、自分にはそれまで縁のなかった時空間の在り方と原理を垣間見ることができたような気がして、観ながら解説してもらうたびにワクワクした。
特に印象的だったのが、3か月で出てきた「(9+1)次元ブラックホール」で「1は時間を意味する」という話だった。「どういうこと?」と訊く私へ「時間に対する概念がある時点から物理学の世界で変わった。それはとても革新的で大事な瞬間だったんだよ」というようなことを相棒は言っていた。もっときちんと聞いて内容を覚えておけばよかったとも思うが、それ以来、夜になると宇宙(闇)がより身近になったような気がする。特に最近は「宇宙が始まったときの揺らぎを相棒は今、実際に感じているのかな」と思う。そんなとき、暗黒の凍てつく闇は果てしない距離ながらも不思議に少し懐かしく、生と死は等しい重みをともなって私という個(孤)を包んでくれる気がするのである。
(柏柳明子)
【執筆者プロフィール】
柏柳明子(かしわやなぎ・あきこ)
1972年生まれ。「炎環」同人・「豆の木」参加。第30回現代俳句新人賞、第18回炎環賞。現代俳句協会会員。句集『揮発』(現代俳句協会、2015年)、『柔き棘』(紅書房、2020年)。2025年、ネットプリント俳句紙『ハニカム』創刊。
note:https://note.com/nag1aky
【2025年11月のハイクノミカタ】
〔11月1日〕行く秋や抱けば身にそふ膝頭 太祇
〔11月2日〕おやすみ
〔11月3日〕胸中に何の火種ぞ黄落す 手塚美佐
〔11月4日〕降誕の夜をいもうとの指あそび 藤原月彦