
【連載】
「震災俳句を読み直す」第2回
その「戦場」には「人」がいる
―角川春樹『白い戦場』・三原由起子『ふるさとは赤』・赤間学『福島』
加島正浩(名古屋大学大学院博士課程)
震災直後に発表された「震災句集」において、最も注目を集めたのは長谷川櫂の『震災句集』であるが、角川春樹の『白い戦場』(文學の森、2011年10月)も言及されることが多かったように思う。ただし、長谷川櫂の句集同様、『白い戦場』も肯定的に読み直すことは難しいように思う。
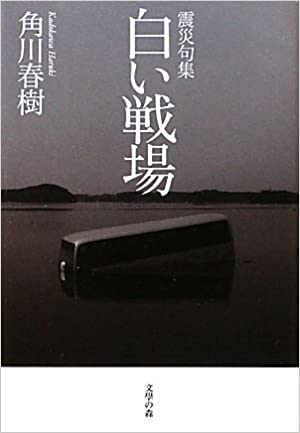
前回、高野ムツオと照井翠を取り上げ、高野は死者の声を聞こうと試み、照井は死者の声を聞いてしまっていると述べた。
では角川春樹はどうかというと〈遺棄されし海市に骨の笛が鳴る〉などと詠むが、その音をおそらく聞いてはいない。もちろん、遺棄された骨の音を聞いて「鳴ってるねー」と、祭りのお囃子を聞くような態度で完結させられる俳人であるのなら別であるが、さすがにそれはないだろう。というよりもそれで完結させられるなら、やはり「聞いて」はいない。他にも〈たましひの犇めく海の朧かな〉のように「かな」を用いて余韻を響かせるように、死者(の声)を詠むこと(挙げていけばきりがないが〈春暁のしづかな雨や被曝の地〉〈原発忌見えざるものを怖れけり〉〈ぞろぞろと人なき街の仔猫かな〉などにも似たような印象を抱く)や〈いづれみな還りゆくなり春の沖〉と津波の死者を一般的な人間の死のなかに回収していくような詠み方にも違和感がある。俳人に震災を詠まなければならないとするような切実さが感じられないのである。
誤解を生まないよう付言するが、それは震災を経験していない局外者が震災を詠んではならないと主張したいのではない。ただ震災を必ずしも詠む必要はない(俳人のみならず言語芸術に携わる者は、同時代の社会的事件に必ず反応しなければならないということはない)にもかかわらず、震災を「詠む」俳人の動機を知りたいとは思うのだ。
17文字で構成しなければならない俳句という形式が、社会的事件を扱うのに適しているかどうかを議論できるほどの知識は私にはないのであるが、少なくとも「最適」ではないだろうと思う。(それは「文学」も同じであろうと思う)しかしそれにもかかわらず、「詠んでしまう」俳人に私は関心があり、また震災に「反応してしまう」(させられてしまう)局外者の心の動きに、ひとつの可能性があると考えている。本来「無視」してしまえばできなくもない人々が、そこに関わろうと「してしまう」心の動き―つまり主体的な意志ではなく、受動的に「巻き込まれてしまう」こと―に私はひとつの可能性を感じている。(照井は「聞いてしまう」からこそ、詠まざるを/書かざるを得ないのである)
しかし『白い戦場』には、そのような「反応せざるを得ない」俳人の心の動きは感じられない。その点で私は肯定的に読み直せる句集であるとは考えていない。角川は〈地震狂ふ荒地に詩歌立ち上がる〉、〈瓦礫より詩の立ち上がる夕立かな〉と詠んではいるが、彼自身が、「地震」や「瓦礫」から歌を立ち上げているとは思えないのである。
ただそれでも、今回取り上げるのは「白」と「戦場」という、ふたつの「イメージ」が気にかかるからだ。
白い戦場となるフクシマの忌なりけり
鳴りつぱなしの赤い電話やフクシマ忌
なぜ「白」なのか、なぜ「戦場」なのか、そのイメージで福島を詠むことが適切であったのか、ということが気にかかる。
「赤い」電話と「フクシマ忌」を対比させ、〈原爆忌チューブの赤を絞り出す〉と広島の被爆は赤と結びつけ、福島を白と結びつけ、〈フクシマや向日葵すらも日に叛き〉と(向日葵がセシウムを吸収するという話が広がり、一時期向日葵を植える動きが起こったことを踏まえてだとは思うが)上記の句を踏まえて黄色い向日葵が福島に叛く句を読むと、福島から色が消えたような印象を俳人が持っているように思える。
確かに、原発「事故」直後の福島を色彩豊かに彩ることは難しかったであろうと思う。丸木美術館で4月10日まで開催されていた山内若菜「はじまりのはじまり」展に3月20日にうかがったところ、たまたま山内さんが在廊されており、色々お話させていただいたのだが、最初の頃は福島を描く際に色を使えなかった。ただ次第に福島の人々にモノクロの絵を観ていると「事故」のこと、辛いことを思い出すと言われ、色を使えるようになったとおっしゃっていたのが、非常に印象的であった。
(ちなみに3月17日に開催された立命館大学主催のシンポジウム「東日本大震災。百年経ったら―記憶・継承・忘却―」にて、大友良英さんが、震災/原発「事故」直後はメロディ(物語)が書けなかったが、次第にコメディが必要だと思うようになり、それが『あまちゃん』につながっていくというお話をなさっていたのだが、相似形を成す話であると思う)
『白い戦場』が福島を色鮮やかに詠まない(詠めない)ことは、理解できる。しかし、「白」は「戦場」と結びつくのである。そのため福島が「雪国」だから「白」と詠んだということではないだろう。
(付言すれば、福島第一原発に近い地域の浜通りは太平洋側の気候で、雪はあまり降らない)
おそらく、防護服が「白色」だからだろう。「戦場」は見えない放射性物質との戦いということなのであろう。俳句としては理解できないこともない。ただ仮に福島や福島第一原発に近い相双地区が「戦場」であったとしても、そこには人が生きており、「事故」以後に(強制避難、区域外避難は関係なく)住んでいた場所を追われた人々が生きていたのである。「白い戦場となるフクシマ」と俳人が詠むときには、そこに人の姿が見えない。

歌人の三原由起子は、福島県双葉郡浪江町に生まれ、原発「事故」により実家が強制避難区域となったのち、2013年4月1日に浪江町の区域再編により、実家は避難解除準備区域に振り分けられる。(三原が〈また町が民が心が裂かれゆく区域再編はじまる四月〉、〈昔から二つに意見を分かつ町と言われし町を三つに分ける〉と詠むように、この再編で住民はまたさらに分断された。加えて三原は〈ふるさとにみんなで帰ろう 帰らない人は針千本の中傷〉という歌を詠んでいることも指摘しておきたい。現在でもTwitter上では、「帰らない」人、区域外避難を行った人への誹謗中傷は絶えない。)
三原の『ふるさとは赤』(本阿弥書店、2013年5月)は、彼女の16歳から33歳までの歌を集めた第一歌集である。彼女の歌は、自分の生活やそこで経験される感情を詠んだものが中心であり、浪江で生き、上京し、結婚し、実家が「事故」で住めなくなり、様々に思い悩まなければならなくなる人の姿が歌集からはみえる。
「事故」以前の三原にとっての浪江=故郷は〈ギターケースを開けば故郷の香りして心は過去に駆けてゆくなり〉、〈いちめんに広がる青田に守られて過ごしたこころのまま生きている〉と浪江を離れていても、確かな存在感を有して自らのなかに留まっているものとして捉えられていることがわかる。〈保守の強き地盤の上で生きている友の言葉に若さを探す〉、〈反対の意見はたちまち悪口に変換される伝言ゲーム〉などと保守的な空気を有する地域での生きづらさも詠われながらも〈福島と東京の間で揺れている心は青春地点で鈍る〉と詠まれるように、確かに福島、浪江は彼女を作り上げた「故郷」として存在しているのである。
そして震災後、歌人は〈われのこころひとつひとつを育みしふるさとのために生きていきたし〉と原発「事故」後の生きる指針を定め、〈いま声を上げねばならん ふるさとを失うわれの生きがいとして〉、〈ふるさとを失いつつあるわれが今歌わなければ誰が歌うのか〉と歌人としての悲壮な覚悟を固める。では原発「事故」後、歌人にふるさとはどのように捉えられたのか。
iPad片手に震度を探る人の肩越しに見るふるさとは 赤
阿武隈の山並み、青田が灰色に霞む妄想 爆発ののち
海沿いの広すぎる空広すぎる灰色の土地 それでも故郷
空がただ明るい真昼 真夜中が永遠に続くようなふるさと
やりなおしできない世界を覚悟して警戒区域はいつも真夜中
満開の桜、青空変わらずにある変わりしは人のさまざま
浪江町の本震の震度は6強であった。東京にいた歌人はまず、強い揺れを示す赤色でふるさとを見ることになる。原発「事故」が発生したのちは、その赤色も消え「灰色」と詠われ、「真夜中」と色が消えた世界として警戒区域内にあるふるさとが示される。
ただしそれはそこに生きる人が否応なく直面させられた変化なのであって、「事故」以後もふるさとは美しいことが、満開の桜や青空を通して示される。〈うつくしまふくしま唱えて震災の前に戻れる呪文があれば〉とも詠われるように「事故」によって福島は変わってしまい、「うつくしま」という言葉が持つ意味も変わり、三原の歌ではその言葉は悲しく響く。
しかしそれでも、福島は美しくありつづける。
そして次第に色彩をともなって福島は詠まれはじめる。

東日本太平洋側の施設や津波用の河川水門などを建設する土木技術者で、震災によって長年自分が手がけてきた建物が一瞬で崩壊し、大きな喪失感に襲われたと述べる赤間学の句集『福島』(朔出版、2018年11月)では色彩が見え始める。〈死者は彩鮮やかに盆の落雁〉、〈福島をじつと見てゐる万年青の実〉、〈冬すみれ被曝検査を受けにけり〉などがそれである。今もなお帰還困難区域の指定が続く福島県浪江町津島地区のことなどを考えたときに、色彩をともなって詠むことが適切なのか、まだ私には判断がつかない。山内若菜さんがおっしゃっていたように、色のない世界に耐えつづけることが人間にはできないようにも思える。山内さんの《牧場 放》(2020年)は色彩豊かではあるが、被曝し亡くなった動物の姿が描かれ、私は非常に悲しい絵だと感じた。白黒以外の色を用いて描くことがすなわち間違いであるという単線的な理解は全く成り立たない。個展は大変に素晴らしかった。
ただそのことをあわせても、赤間学『福島』には気にかかる句がある。
〈町捨つる人もありけり赤い雪〉である。
まず事実として「町を捨てた」人など一人もいない。三原の歌に戻れば、彼女は「ふるさとを失う」と詠んでいた。強制避難区域からの避難であろうが、その区域の外側からの避難であろうが、原発「事故」がなければ、「避難」は存在しなかったのであるから、誰一人として町を「捨てた」人などいない。三原が適切に詠むように町を「失った」のである。
そしてそのうえで、〈赤い雪〉は何を示すのか。私にはわからない。金子兜太に〈雪の海底紅花積り蟹となるや〉という名句があるそうだが(この句ではおそらくないと思うが)何か先行する名句を踏まえてのことなのか。そうであるなら、俳句の教養が一切ない私の問題であるのかもしれないが、なぜ〈赤〉なのか。
「白い戦場」から「赤い雪」へと転換しても、なお私が思うのは、〈町を捨つる〉と詠むこの句から、三原の歌のような人の思いが読めないというその1点である。「戦場」であろうと「雪」が積もろうと、そこには様々な思いを抱えて、人々が住んでいた/る町なのである。人々には多様な思いがある。もちろん衝突もある。三原は〈脱原発デモに行ったと「ミクシィ」に書けば誰かを傷つけたようだ〉、〈原発の話はタブーと注意する先輩はまだムラに生きおり〉とも詠んでおり、そこに住む/住んでいた人々の思いを歌/句に織り込むのは、非常に神経をつかう作業であり、難しいことも事実だ。しかしそこに住む/住んでいた切り落とされ福島が詠まれるのは、そこに住んでいた/る人々を切り捨てることに等しいように思う。多様な人の思いを「単色」で詠むことはできないのかもしれない。
【付言】現在「復興」の合言葉のようにも使われている「うつくしま」であるが、そもそもこの言葉を作り出したのは、福島県知事を「辞職させられた」佐藤栄佐久である。安孫子亘監督のドキュメンタリー映画「『知事抹殺』の真実」によれば、佐藤は東京電力に安全対策をするよう強く求め続け、安全が確保されるまでは原発を再稼働しないとして福島第一・第二原発の全機を停止させたためか、第一次安倍政権時に捏造された可能性が極めて高い収賄事件で辞職を余儀なくされた。佐藤の作った言葉が「復興」の合言葉に使用されているのは、大変に「皮肉」なことと思う。
【執筆者プロフィール】
加島正浩(かしま・まさひろ)
1991年広島県出身。名古屋大学大学院博士後期課程在籍。主な研究テーマは、東日本大震災以後の「文学」研究。主な論文に「『非当事者』にできること―東日本大震災以後の文学にみる被災地と東京の関係」『JunCture』8号、2017年3月、「怒りを可能にするために―木村友祐『イサの氾濫』論」『跨境』8号、2019年6月、「東日本大震災直後、俳句は何を問題にしたか―「当事者性」とパラテクスト、そして御中虫『関揺れる』」『原爆文学研究』19号、2020年12月。
【セクト・ポクリット管理人より読者のみなさまへ】
