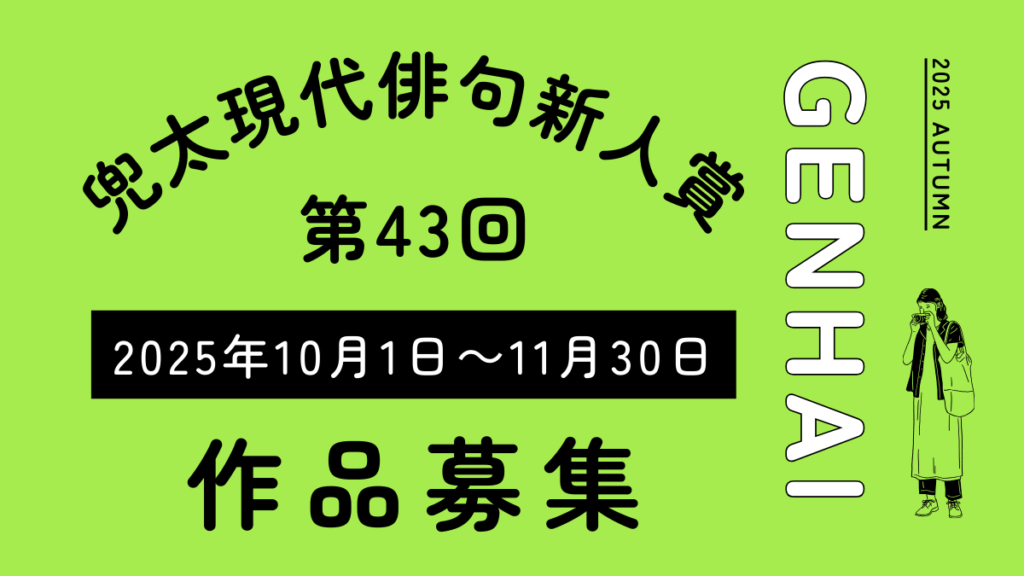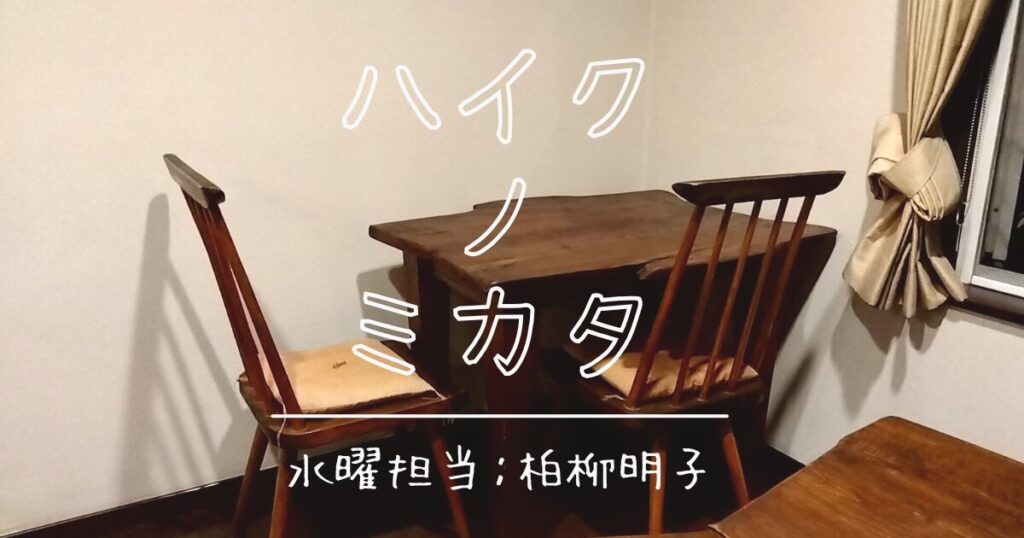
わが町の灯の匂ひ立つ日記買ふ
岡本眸
岡本眸の俳句作品を読んでいると、どの句も自分の日常や心情が切り取られて十七音として差し出されているような気がする。そういう印象をもつ方は私以外にもいるのではないだろうか。今日というささやかな時間を確かに生きたことを、自分の言葉と季語で明日へつなげようとする営み。だからこそ、彼女の俳句作品にはいつも実感と体温があり、時代を越え読者に共感をもって愛されるのだろう。「寄りそう魅力」。それは岡本眸の俳句作品の特質の一つと言えるかもしれない。
個性が無いようで、どの町にも表情はあると思う。それが普通の住宅街であったとしても、そこに住み、生活を築き、日々をおくる人々がいる。同じような生活でも、それぞれ少しずつ異なるから自然と町の表情も違う。掲句では「わが町の灯の匂ひ立つ」とある。灯とあるので、既に冬の夜に包まれた闇を明るく照らす家々の灯だろうか。あるいは、飲食店の賑やかな煌めきか。いずれにせよ、灯の向うに息づく人間の存在感が温もりと匂いをともなって読者に届く。また、上五「わが町」より、生活の土台である町への思い入れと普段の暮らしが隠し持つかけがえのなさがさりげなく強調される。同時に、吐く息が白いほどの寒さも作品全体より感じられる。それらのイメージが重なり合って町の灯はより美しく、親しげなものとして映る。どこか切ない郷愁にも似た感情を滲ませて。
その町の灯が「匂ひ立つ」。前述の家庭や飲食店の煮炊きおよび家々それぞれの生活の匂いでもあろうが、その町に住む人々の共有する感情や暮らしの表情を「匂ひ立つ」と言っているようにも感じられた。
現在、私は某商店街の近くに住んでいるが、引っ越した当初、まったく知らない人々が商店街を行きかう様子や行動に共通する生活感と親近感を覚えた。さらに商店街を行く人々の歩調が平日は忙しいのに休日はゆったりとしたテンポに明らかに変わっていた。だからだろうか。活気は変わらないが、人々の表情の影響を受けて休日の商店街もいつもと違う顔をしているように見えた。
それまでも別の町に住んだことはあるが、そんなふうに感じたことは初めてだった。、
そんな記憶があるからだろう。新しい年を記すための日記をその町で買い、そこでの日々を綴ろうという季語を借りた掲句の小さなエピソードに、作家自身の明日への、そして生きることへの前向きな意思を感じるのである。
掲句以外の俳句作品もそうだが、岡本眸は「今・ここで生きること」をずっと詠み続けた作家なのではないかと思う。慎ましくも凛とした意思を背骨に。
自身の家族の喪失を経験しながら、彼女はひとり、一足ずつ生活と時間の中を歩いていった。俳句という型、言葉、そして季語を用いて。あるときは空に、あるときは地に、今は亡き人々の面影を自然界と暮らしの中に映し見ながら。そうやって自身の今と生活を十七音として描くことで、岡本眸は現在、私たちが知る俳句作家となったのではないか。
彼女はとうにいないが、彼女の未来時間である現在を生きる私は俳句を始めたことで彼女の俳句作品と出会えたことに心から感謝している。これからも岡本眸とその俳句に励まされていくだろう。私も自分の暮らしを反映した俳句を紡いでいければ。そして、人生という有限の時間のうちで自分だけの表情と味のある俳句を少しでも多く作ることができますように。今年の終わりをかすかに感じつつある今、切にそう願う。
(柏柳明子)
【執筆者プロフィール】
柏柳明子(かしわやなぎ・あきこ)
1972年生まれ。「炎環」同人・「豆の木」参加。第30回現代俳句新人賞、第18回炎環賞。現代俳句協会会員。句集『揮発』(現代俳句協会、2015年)、『柔き棘』(紅書房、2020年)。2025年、ネットプリント俳句紙『ハニカム』創刊。
note:https://note.com/nag1aky
【2025年11月のハイクノミカタ】
〔11月1日〕行く秋や抱けば身にそふ膝頭 太祇
〔11月2日〕おやすみ
〔11月3日〕胸中に何の火種ぞ黄落す 手塚美佐
〔11月4日〕降誕の夜をいもうとの指あそび 藤原月彦