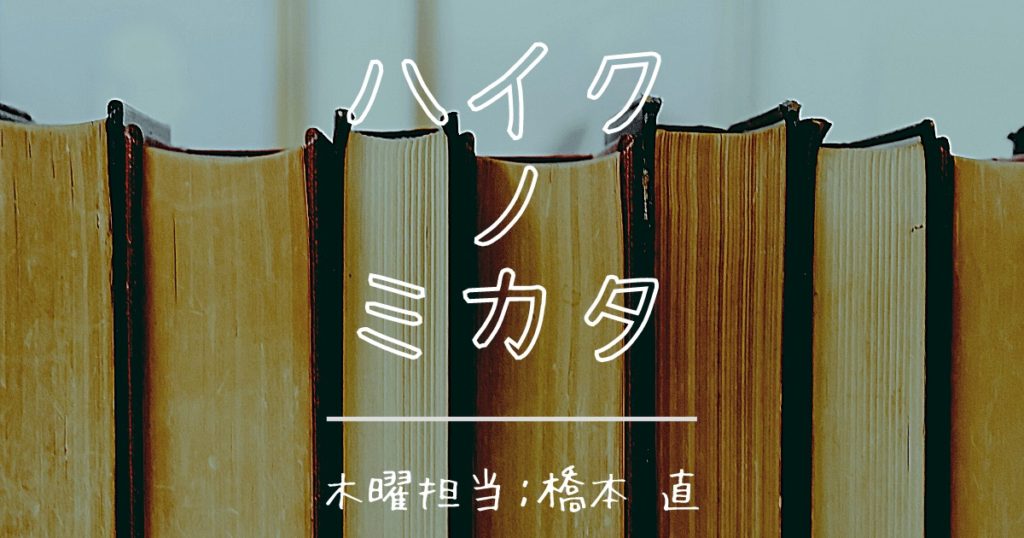
ビル、がく、ずれて、ゆくな、ん、てきれ、いき、れ
なかはられいこ
(「WE ARE!」第3号2001年12月)
平成の終わりにある俳句総合誌が「平成俳句検証」という特集を組んだ。普段この雑誌の特集は良いものが多いので気にしているんだけど、字の大きさに比例して情報量が少ないのが残念。それはさておき、特集中、「平成を代表する句」というアンケートがあって、私にも依頼がきたのであげたのが今回のなかはらさんの川柳です。
そもそも、平成時代を代表する、というほど同時代の読者にとって威力のある句があったろうか、と考え込んでしまう。もちろん、平成にも良い俳句はたくさん生まれているのだけれど、〈平成を代表する句〉と客観的に言われうるものがもしこの世にあるとするのなら、平成に生きた人間が皆いなくなった後にも残って、明治大正昭和の句とともに国語の教科書なんかに載っちゃうような句を言うのじゃないだろうか。すると私も本稿の読者もすでにこの世にはいないころにわかることになるはずだけれど。
思うに、昭和の後半から平成の俳壇は、一己の表現を突き詰めたはずの昭和(戦後)俳句の作家達が大家となって市民を啓蒙する側にまわって出来上がったのが大きな軸だから、根は内向きであるにもかかわらず、結社を中心としてその予備校のようなカルチャー講座や新聞投稿欄がある意味よく機能しており、俳句人口を千万の単位で増やし、そこから優秀な作家を組織的活動の枠の中ですくい上げてきた。同時に平成以後は東西冷戦の終結と情報通信技術の革新を背景としたボーダレスとその反動の時代でもあって、俳句で言えばいささか緩やかながら結社の枠の外で頭角を現す俳人が世に出てくるようにもなった。が、結果としてボーダレスは思ったほど進まず、それぞれが島宇宙のなかでよろしくやっている状況が主潮流で、それが平成無風なんて気色の悪い言葉が囁かれた由縁であろう。あいにく文芸批評も時代の波のなかで力を失い、枠の間を連絡したり総合したりする力は弱かった。見ようによっては豊穣である。だから当然というべきか、くだんのアンケートの結果はバラバラだったと記憶する。
1 / 2