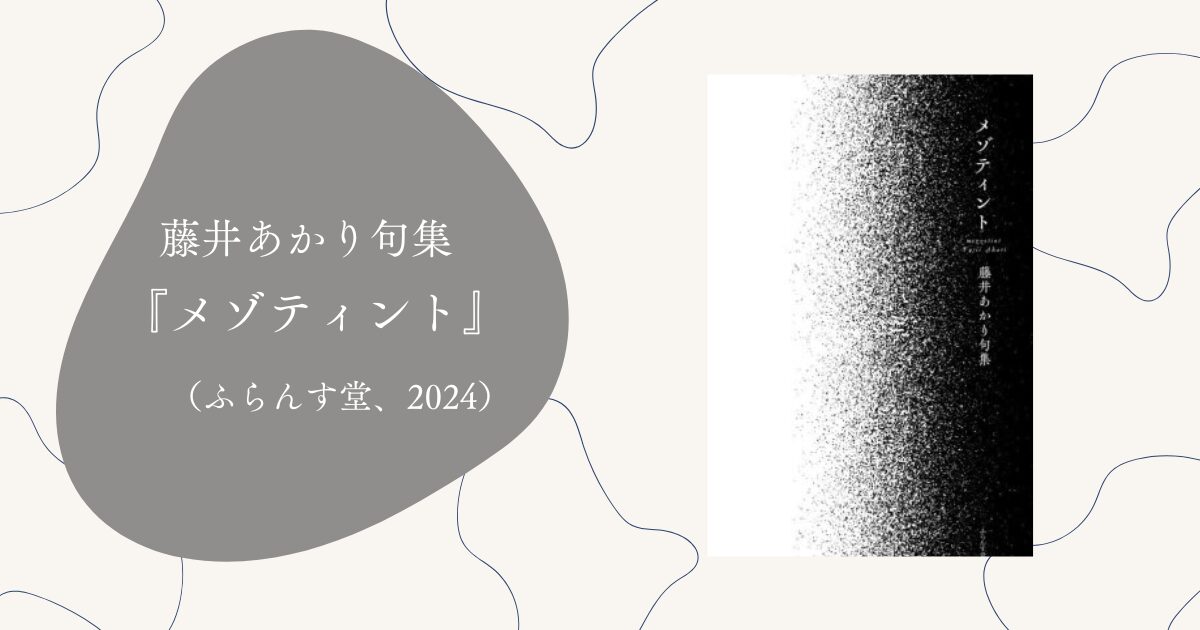グレーゾーンの言葉たち
──────────────────
藤井あかり『メゾティント』(ふらんす堂、2024年)
まず、タイトルがいい。『メゾティント』と聞いて、はてそんな音楽用語があっただろうか、と捏造された記憶をよすがにしつつ、頁をぱらぱらとめくっていくと、その言葉に出会わぬまま、一冊を読み終えている。冬の日の通り雨のような心地よい読後感に酔いしれつつ、どこかに読み落としたかと思ってめくり直すと、やはりない。しかしこの事実はさして気にならず、今自分が感じている読後感こそが「メゾティント」と名指されているものなのだと感じる。
野分中同じ気持ちでゐるといふ
雲の峰誰かを幸せにせねば
またの世は綿虫同士にて会はむ
君にまた初めて出会ひたき春野
『メゾティント』は、大人の恋の句集でもある。作者は1980年生まれで、2015年には第一句集『封緘』(文學の森)を出しているから、30代も後半にさしかかったころの恋であろう。〈雲の峰誰かを幸せにせねば〉の「誰か」は、隙がないほどの倫理性に貫かれており、その前後に〈傘貸してくれし縁や沙羅の花〉、〈婚約ののちの照り降り水葵〉、そして〈どこにゐても虹を教へてあげるから〉とつづくページが、前半のクライマックスである。直情を隠すことのない純粋さと、自身の生を祝福するようなものとしての花や草木。植物の季語は実景というより象徴と化し、作者の強い意思と感情が句集の通奏低音となる。
句集に章立てはなく、春から冬に向かう一年がシームレスに三度繰り返される。おそらくは厳密な編年体ではなく、たとえば2022年の角川俳句賞候補作(「目陰」)内の作は散らばっている。〈息白くカストラートのための歌〉は選考会で小澤實がその素材の新しみを指摘していたと記憶するが、〈薫風にダンパーペダル踏みかへる〉〈コンケラー・レイドに花冷を記す〉〈スワッグをがさりと吊し晩夏光〉など、厳選されたカタカナ語も持ち味のひとつ。VRを詠んだ〈汗ばみて仮想現実より戻る〉も面白い。〈汗ばみてをり自画像の私も〉という句もある。藤井さんは汗っかきなのだ。
後半に透かしみえる肉親の死、そして子育ての一筋ではいかなさ、そうしたプライベートを句材とした句群は、本書を単なる「大人の恋」の甘やかな句集としないには十分である。〈読み返す日記に躁や冬薔薇〉からは、コントロール不能な「情動」(感情や心理ではない)が「書く」こと(そして書かれる「言葉」)の根源にある作者であることが窺える。〈独りにも蟻殺すことにも慣れて〉は、この句集の後半のクライマックスにも思える。自身のことなのか、まだ幼い子供の行為かは不明瞭だが、しかし時折、見出される鬱的な──死を臨もうとする──情動が、別の角度から句集に強度を与えていることは、明らかだ。
『メゾティント』は、「章立てがない」代わりに、句の配置とリズムが徹底的に考えられている。点と点がつながって線となり、やがては面になる──そういう幾何学的な思考に裏づけられた句集である。一例を挙げれば、〈扉を叩くための拳や春北風〉からはじまる句集は、最後のページに〈いちにちに開く扉の数春隣〉で受けられている。また、「傘」の句が頻出するが、第一句集には〈青梅や傘畳むとは人悼む〉があり、第二句集には〈人悼むときのみぞおち青嵐〉がある。
第一句集の〈言の葉は水漬いてゆく葉冬の鳥〉や〈丁寧に書けば書くほど悴める〉といった「言葉」や「書く」ことの主題化も、シームレスに継承されており、〈紙が燃え字が燃えてをり春の暮〉〈はつなつの言葉は私を鳴らす〉といった、ともすれば観念的な句も混じる。〈口あけて己が言葉を待つ夜長〉は、交換可能な記号としての言葉ではなく、向こう側から到来するものとしての言葉であろう。だからそれを書き留め、文字となるときには、もう自分のものではなくなっている。音が鳴るのはピアノであって、楽譜ではない。
さて、こう書きながら「メゾティント」の句を探してみても、やはりない。と思ったら、藤井が角川俳句賞に同名の作を出品していたことを知る(いや、思い出す)。〈あかときの大向日葵はメゾティント〉。あった。立秋の句からはじまる50句作品の最後の句である。「メゾティント」は、音楽用語ではなかった。銅版画の凹版技法の一種なのであった(Photoshopの機能にもある)。つまり答えは、句集の表紙にあった。白と黒のドットから構成され、デジタル的に散逸していくような世界だ。
この句について、選考会の小澤實は「こういう銅版画の技法を持ち出さなくても描写できるんじゃないかな」と否定的だったが、銅版画の凹版技法なのではなく、デジタル的なドットの感覚だとすればどうだろう。『メゾティント』の表紙の中央を見てほしい。白でもなく、黒でもなく、その境界なき境界が主題化されていることに気づく。たとえば、躁でもなく鬱でもなく。ハーフトーンというよりは、文字通りのグレーゾーンである。このグレーゾーンは、おそらく作者にとっての世界そのものであり、彼女が求めているものも、そうした「グレーゾーンの言葉たち」なのかもしれない。〈爽やかにいつでも旅立てるやうに〉には、田中裕明の〈爽やかに俳句の神に愛されて〉も反響するが、その短い遺言のような純粋さが胸を打つ。
(堀切克洋)

◆藤井あかり『メゾティント』(ふらんす堂、2024年)
『封緘』に継ぐ待望の第二句集。
序句:石田郷子
◆作品紹介
花辛夷声出して喉取りもどす
五月病とも前髪の翳りとも
色見本この朝焼の色はなく
眩しくて見えぬが猫柳である
病室に春の野をそのまま飾れ
青葉木菟仮死から蘇るまでを
一面の白蛾と見えて壁白し
押し寄せてくる葉柳と後悔と
青葉騒栞の少し前から読む
山茱萸の実に触れて手の蘇る
冬館ランプは光から古び
胸に火の回る速さや冬河原
すれ違ふ秋風よりも颯と人
君にとつての雪が私の詩
歌ひをる喉を冬の泉とも