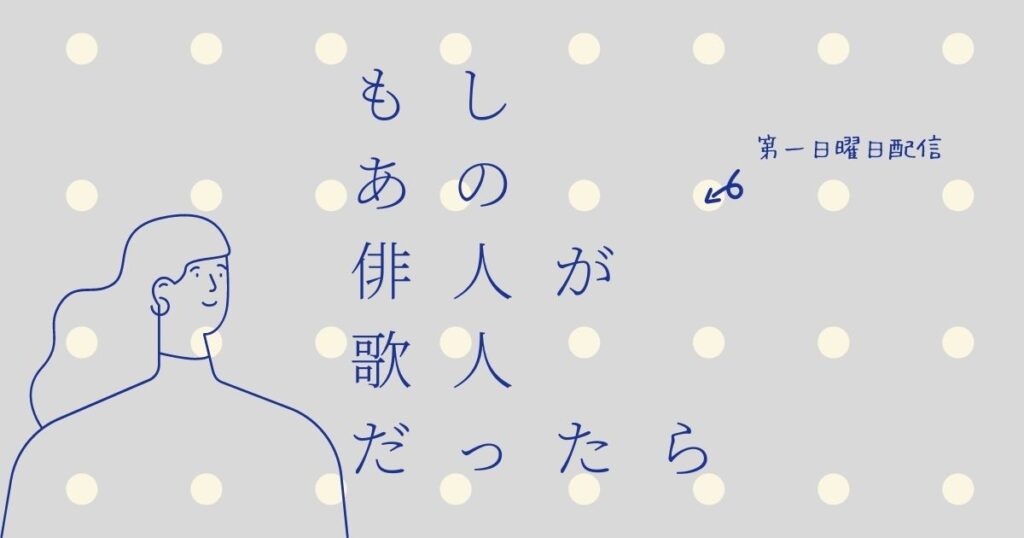
【連載】
もしあの俳人が歌人だったら
Session#5
このコーナーは、気鋭の歌人のみなさまに、あの有名な俳句の作者がもし歌人だったら、どう詠んでいたかを想像(妄想)していただく企画です。今月取り上げる名句は、宇多喜代子さんの〈八月の赤子はいまも宙を蹴る〉。この句を歌人のみなさまはどう読み解くのか? 俳句の「読み」の新たなる地平をご堪能ください! 今月は、上澄眠さん・鈴木晴香さん・三潴忠典さんの御三方にご回答いただきました!
【2021年8月のお題】
八月の赤子はいまも宙を蹴る
宇多喜代子
【作者について】
宇多喜代子(1935-)は、山口県徳山市(現:周南市)生まれ。10代の終わりに俳句をはじめ、35歳のときに「草苑」創刊に参加し、桂信子に師事、同誌編集長を務める。2004年、桂が没し「草苑」終刊後、「草樹」を創刊し会員代表となる。2006年から2011年まで、現代俳句協会会長。伸びやかなで作風のなかに、歴史性や社会性も顔を覗かせる。2001年、句集『象』にて第35回「蛇笏賞」、2012年、『記憶』にて第27回詩歌文学館賞俳句部門など受賞多数。
【ミニ解説】
日本の八月は、暦の上では立秋があるので「秋」となります(つまり、掲句では「八月」が秋の季語です)。この時期は、残暑でとても過ごしにくい地域が多いですよね。そしてその高温多湿な季節は、何といっても「お盆」と結びついています。
お盆の明確な起源はいまだわかっていないそうですが、中華文化では旧暦の7月朔日に「地獄の蓋」が開き、7月15日の中元節には「地獄の蓋」が閉じるという民間信仰が古来よりあったため、現在でも台湾や香港、華南を中心に現在でも中元節は先祖崇拝の行事として盛大に祝われます。これは旧暦1月(新暦2月ごろ)の春節/上元節に対応している、シンメトリックな区切りです。

一方で、日本の正月は新暦で祝いますから、そのような対称性はほとんど共有されていません。どちらかというと、日本での「8月」は、エアーポケットのような月。それは、何といっても「終戦記念日」が、8月15日であるためでしょう。
しかし、8月15日は「玉音放送」があった日に過ぎません。しかも電波状況が悪く、独特な抑揚と難解な漢語は、ライブで聞いていた人たちの理解を大きく妨げたことも想像されます。ポツダム宣言を受諾したのは前日の14日で、ミズーリ号での降伏文書調印は9月2日のことですから、いったいなぜ「8月15日」が「記念日」なのか(いったい何を「記念」しているのか?)というのは大きな疑問でした。その疑問に明快に答えてくれたのが、佐藤卓己『八月十五日の神話 : 終戦記念日のメディア学』(2005年初版、2014年増補版)です。
1930年代、当時の最先端のメディアであったラジオでは、朝は「盂蘭盆会法要」が、昼間には甲子園、そして夜には盆踊りが中継されていました。つまり戦前から、8月15日は「ハレ」の日でした。日中戦争勃発後の1938年大会からは、甲子園の「黙祷」もまたはじまりました。そうした慣習を背景に、戦後にさまざまな政治的思惑から「敗戦=占領」(9月)から「終戦=平和」(8月)へのシフトが行われてきたのではないかというのが、佐藤卓己さんの行った問題提起のひとつでした。

宇多喜代子は1935年生まれ。つまり終戦時に10歳でしたから、敗戦=占領のことも身をもって知っている世代です。そして、戦後の平和思想とともに時代を歩んできた世代でもあります。しかし、それが単純なメッセージに陥っていないのは、体が重くなる「八月」の重力にあらがうように、それを吹き飛ばすように、赤ちゃんの生命力が描かれているからでしょう。
ところで、この句の〈いま〉に対応する〈むかし〉とは、いつのことでしょうか。自分が小さかったころ(戦時中)でしょうか? それとも、自分が「母」の年代になったころ(戦後)でしょうか?
宇多自身がこの句をつくったのは、2002年のことですが(『記憶』所収)、後年、東日本大震災のとき気仙沼の被災者に、「元気に手足を上げて」家の近くで死んでいた赤子の話を聞いて、彼女はそこに中東の惨禍を伝える報道写真や、戦争中の記憶を重ね合わせています。いったい、なぜ赤子は死んでもなお宙を蹴っているのかと。つまりこの句の〈いまも〉は、作者の記憶のなかで蘇る死んでいった子供たち、そして〈いまも〉どこかで死にゆく子供のことを包み込んでいる言葉だということです。
それが人類の繰り返してきた営みだからこそ、その非業さを写しとる作者の目は、過去とも現在とも未来ともつながっています。そして同時に、この赤子の脚力は、何かにあらがうことがもたらす希望のようなものも、含んでいます。生と死、過去と現在(未来)、絶望と希望が、まったく矛盾しないかたちで一句に詠まれているという点で、この句は二十一世紀の名句としてこれからも語り継がれていくことでしょう。
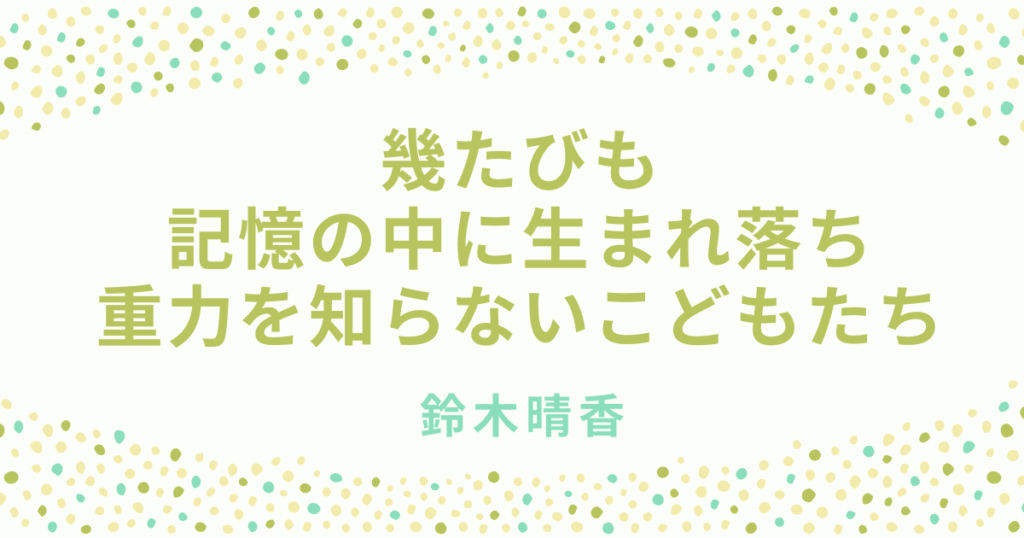
八月。パリで、日傘を買うのに苦労した。
雨でも傘をさす人が少ない街で、日傘なんてもってのほか。人々はサングラスをかけて、それ以外の体の部位はこれでもかと陽に晒している。長かった冬の夜の恨みを晴らすように、公園へ、テラスへ、みんな太陽を探しにゆくのだ。
それにしてもその夏の暑さは酷かった。さらに恐ろしいことに、もっと暑いローマに行く予定だったのである。これは、無理だ。
大きなデパートで探してみても、日傘がない。一本もない。パニックだ。すぐに検索。傘を手作している老舗があるらしいと誰かが教えてくれる。ブロガーありがとう。四方の壁に傘が飾られたそのお店に入り、パラソルはありますか、と聞くと、店主は3本の日傘を出してきた。何百本もある中で、たった3本である。でも助かった。白地に青い鳥の柄を選んだ。
あの傘屋の主人は、私の心の中でいつでもそこに立って、傘を差し出している。いまも。
(鈴木晴香)
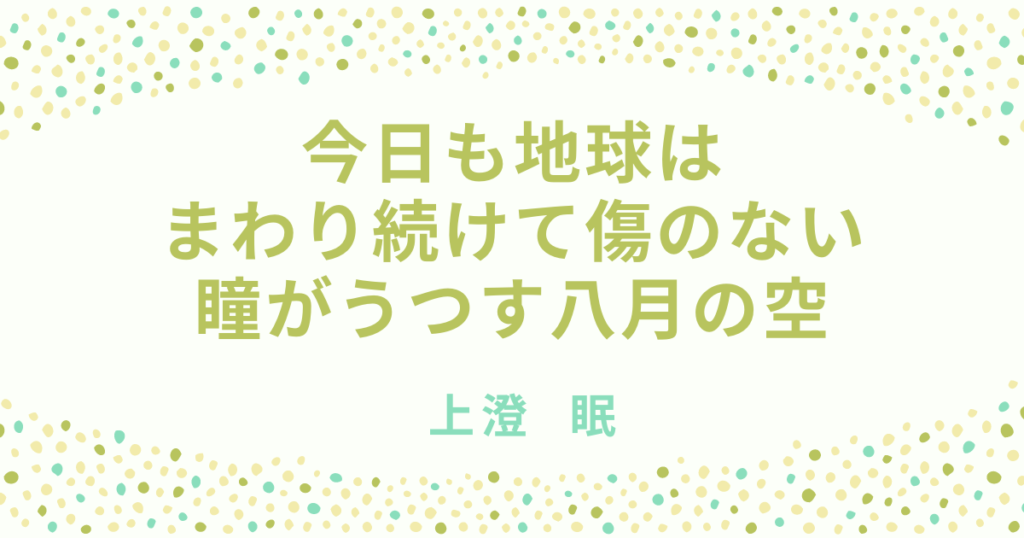
八月六日の八時十五分、広島ではサイレンが鳴る。大人になって広島で暮らすようになるまでそのことを知らなかった。寝起きのぼんやりした頭に、サイレンは、うわんと大きく出現して尾を引いて消えていく火の玉のようだった。
原爆ドームまでは一時間かからずに行くことができた。平和記念公園や平和記念資料館に行く時はもちろん、路面電車がその前の橋(原爆投下の際に目標になったとされる相生橋)を通るので、橋の向こうの町に行く時はいつも原爆ドームが目に入る。異様な存在感を持ったまま、風景の一部のように車窓を流れていく。まるで日常の一部のように。
終戦からあと、この町で生まれた子どもたちにも、この風景はそう見えるのだろうか。
生きようとするエネルギーのかたまりのような赤子の瞳に映る風景を思う。まだ意味を知らないものが、意味を持って彼らの中に立ち現れるまでの時間のことも。
(上澄眠)
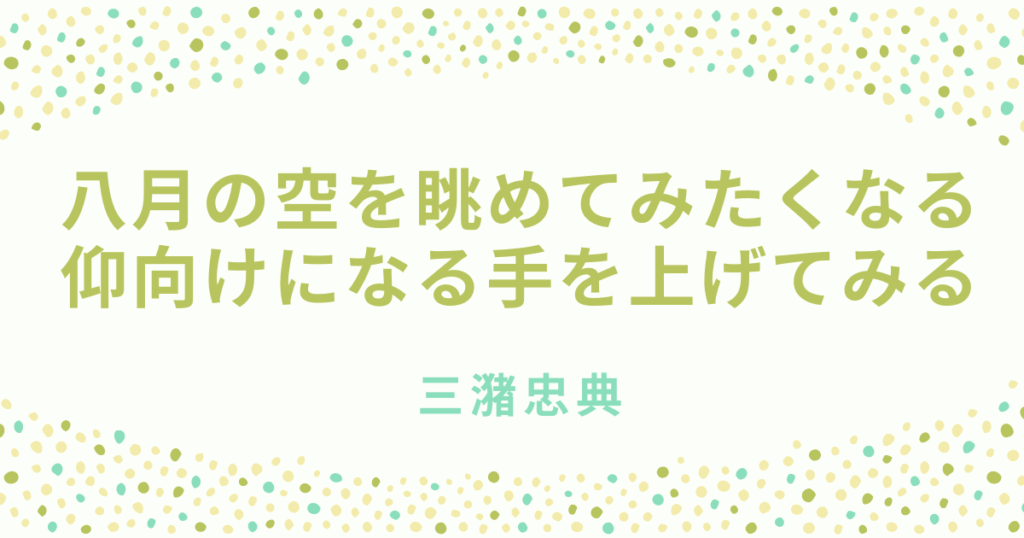
いつからか仰向けで寝るようになった。小さい頃は起きたときに180度回転しているくらい寝相が悪かったので、好きな姿勢で寝ていた。学研の科学の本あたりで、胸の上で手を組んで寝ると悪夢を見るという話を読んで、胸の上で手を組んで寝る練習をしているうちに、仰向けで寝る習慣ができた。組んだ手の重みで胸が締めつけられるという理由らしい。実際に悪夢を見ることはできたが、寝ている間に胸の上で手を組む癖が直らなくなり、毎晩のように悪夢にうなされることとなった。
ちなみに私は八月生まれ。数年前に誕生日が祝日に制定された。天皇陛下のようで光栄だと思っていたが、昨年と今年はオリンピックの都合で別日に変えられている。一握りの人間の思惑によって、八月に悪夢が繰り返されてはならないと切に思う。
(三潴忠典)
【ご協力いただいた歌人のみなさま】

◆鈴木晴香(すずき・はるか)
1982年東京生まれ。慶應義塾大学文学部英米文学専攻卒業。塔短歌会所属。雑誌「ダ・ヴィンチ」の連載「短歌ください」への投稿をきっかけに短歌を始める。歌集『夜にあやまってくれ』(書肆侃侃房)。Readin’ Writin’ BOOKSTOREにて短歌教室を毎月開催。第2歌集『心がめあて』(左右社)が今月発売!
Twitter:@UsagiHaru

◆上澄 眠(うわずみ・みん)
1983年生まれ。神奈川出身。心のふるさとは広島。四月から島根県民になりました。塔短歌会所属、「まいだーん」に参加。
歌集『苺の心臓』(青磁社)。
Twitter:@uwazumimin
◆三潴忠典(みつま・ただのり)
1982年生まれ。奈良県橿原市在住。博士(理学)。競技かるたA級五段。競技かるたを20年以上続けており、(一社)全日本かるた協会近畿支部事務局長、奈良県かるた協会事務局長。2010年、NHKラジオ「夜はぷちぷちケータイ短歌」の投稿をきっかけに作歌を始める。現在は短歌なzine「うたつかい」に参加、「たたさんのホップステップ短歌」を連載中。Twitter: @tatanon
(短歌なzine「うたつかい」: http://utatsukai.com/ Twitter: @utatsukai)
【来月の回答者は野原亜莉子さん、上澄眠さん、鈴木美紀子さんです】
【セクト・ポクリット管理人より読者のみなさまへ】
