
【第2回】
お茶と水菓子―「わび」の実際
柳行李片荷は涼し初真瓜 芭蕉
夏のフルーツと言えば、今ならサクランボや桃であろうか。かつては真桑瓜だった。メロンほどの糖分はないが、さっぱりとして食後にいい。中国ではかつてスイカもそうであって、ジュースなどいきわたらない時代、水分補給の意味もあった。
夏は水の季節であり、水の果物と言えば、まず真桑瓜だった。瓜から生まれた瓜子姫のイメージも、夏に異様に成長を遂げるこの水の果物の上品な甘さがヒントであったか。夏の風物詩として、「瓜売り」の語も残る。スイカやメロンほど大きくない真桑瓜は、行商に向いていたことだろう。
初真桑四にや断ん輪に切ん 芭蕉
縦横どちらに切ってもいいが、皮に近い方は味が薄く、芯に近づくほど甘い。その点柿とは全く逆である。「ん」の繰り返しは、夏の楽しみの到来を喜ぶ気分が横溢している。
ならはしの塩茶飲みけり瓜の後 其角
塩を入れた薄茶は、二日酔いに効くとされた。其角は、一斗酒百篇とうたわれた李白同様、呑むほどに酔うほどに秀句を吐いた酒豪俳人である。なにしろ少年時代から、呑んでいたのだというから、二日酔いの処方も心得ていたろう。瓜で口をさっぱりして水分を補給した後、温かい塩茶で、胃腸を休め、塩分も補給するのだから、理にかなっている。
和食のフルコースである懐石は、最後の茶と水菓子がポイントになる。江戸時代、接待用のレシピを小説化した粋な趣向の作品がある。井原西鶴の『万の文反古』である。書簡体といえば、ルイ16世時代の貴族の不倫を描いたラクロの『危険な関係』が思い浮かぶが、西鶴も読ませる。
巻1の4「来る十九日の栄耀の献立」は、ある呉服屋の手代が提案した接待の計画に対し、接待を受ける側の旦那の手代が接待の内容に修正意見を述べた形の手紙となっている。書面の過半は料理の献立が占める。茶道家でもある石塚修さんの解釈(『近世文藝』100号)に従えば、この献立は本膳料理のそれであるという。
一般に現代では、懐石(会席)料理とひとくくりにされるが、本来、武家がお客をもてなすための膳に載せた本膳料理、茶会で提供される軽い懐石料理、現代における宴会料理たる会席料理は全くの別物である。本膳料理こそが、日本料理の根元なのである。例えば、服部家は室町時代に確立した料理の家元である。芭蕉も若き日藤堂家に仕えた折は、料理番だったという伝えもあるから、俳句との関係では要注意なのだ。貴族階級の儀式性の高いフルコースの伝統を引く本膳料理を、豪商とはいえ町人の接待に出すところが「栄耀」なのだろう。
問題は、締めの水菓子とお茶である。献立の指示は、現大阪府河内長野市日野の真桑瓜に砂糖をかけて出せとある。今の感覚から言えば、真桑瓜だけでは質素な茶懐石の水菓子に思えるが、当時砂糖が大変な貴重品だったことを思えば、やはりこれは本膳料理のデザートなのである。私の母方は鹿児島だが、奄美・琉球とアクセスしていた薩摩の薩摩揚げは甘い。それは大変な「栄耀」でありお国自慢であったのだ。祖母はよく砂糖をかけて食べていた。さんざん贅沢な食事と酒を楽しんだ挙句、素朴な真桑瓜で口をすすぎ、水分を補給したのである。接待は旧暦六月、今なら梅雨明けの酷暑の時期の舟遊びの折のことである。
さて、お茶の出し方の指定である。お茶は菓子なしに出せとあるから、一見すこぶる簡素に見えるが、これは真桑瓜と同じで見せかけである。次に一服ずつ「たて切り」にせよとある。これは茶碗を共用させないことを意味し、この料理が茶懐石でなく本膳料理であることの何よりの明かしだということになる。逆に言えば、茶碗を共用する利休たちの「わび」茶がいかに革命的であったかが、わかろうというものだ。
芭蕉は自分の俳諧を、利休の茶にも精神的につながるものだとした(『笈の小文』)。貴族・武家の文芸であり、儀式とも絡んでいた和歌・連歌に比べて、俳諧は利休茶だというのである。豪華な会席料理の起源である本膳料理と「わび」しい茶懐石を混同するというのは、俳句を和歌・連歌同様の格式ばったものとして一緒くたにしてしまう「伝統」観と同じ倒錯そのものである。
前回虚子が、俳句が月並化してマニュアルだけの宗匠が蔓延ったように、茶道も形式だけにとらわれると「わび」の精神がなくなると示唆したのはこの点にある。現代の俳句で言えば、機械的に古典文法を規範化して創作に持ち込む態度は、後世から「月並」と批判される危険性がある。
文法の基本的なルールは残さないと俳句ではなくなるが、もしルールだけになって「心」が失われたら、それは形骸化した悪しき「伝統」だと虚子は言っているのである。虚子は、古典にない古典らしき文体まで編み出していたし、文法は謡曲などを通して体得していたが、文法破りを確信犯として時にやっていたことは、堀切克洋さんとの共著で解き明かした(『俳句がよくわかる文法講座』)。
虚子は、子規の設計図を基に、近代俳句の中身をつくり、臨界点を意識しながら実験をした自負があった。季感の薄い熱帯季題俳句など、その典型であろう。残すべき基礎的ルールとしての「季題」と「写生」、それに古典的言い回し。しかし、そこにだけとどまった時、形骸化は始まる。ただしい「伝統」とは、守るべきものを自覚しながら、挑戦しつづけることだったのである。
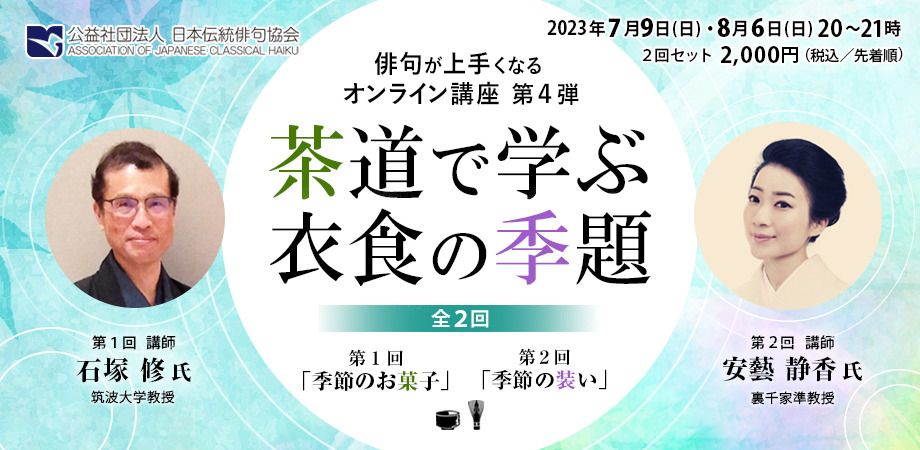
【執筆者プロフィール】
井上泰至(いのうえ・やすし)
1961年、京都市生まれ。上智大学文学部国文学科卒業。同大学院文学研究科博士後期課程単位取得満期退学。博士(文学)。現在、防衛大学校教授。著書に『子規の内なる江戸 俳句革新というドラマ』(角川学芸出版、2011年)、『近代俳句の誕生ーー子規から虚子へ』(日本伝統俳句協会、2015年)、『俳句のルール』(編著、笠間書院、2017年)、『正岡子規ーー俳句あり則ち日本文学あり』(ミネルヴァ書房、2020年)、『俳句がよくわかる文法講座: 詠む・読むためのヒント』(共著、文学通信、2022年)、『山本健吉ーー芸術の発達は不断の個性の消滅』(ミネルヴァ書房、2022年)など。
【井上泰至「茶道と俳句」バックナンバー】
【井上泰至「漢字という親を棄てられない私たち」バックナンバー】
◆第1回 俳句と〈漢文脈〉
◆第2回 句会は漢詩から生まれた①
◆第3回 男なのに、なぜ「虚子」「秋櫻子」「誓子」?
◆第4回 句会は漢詩から生まれた②
◆第5回 漢語の気分
◆第6回 平仮名を音の意味にした犯人
【セクト・ポクリット管理人より読者のみなさまへ】
