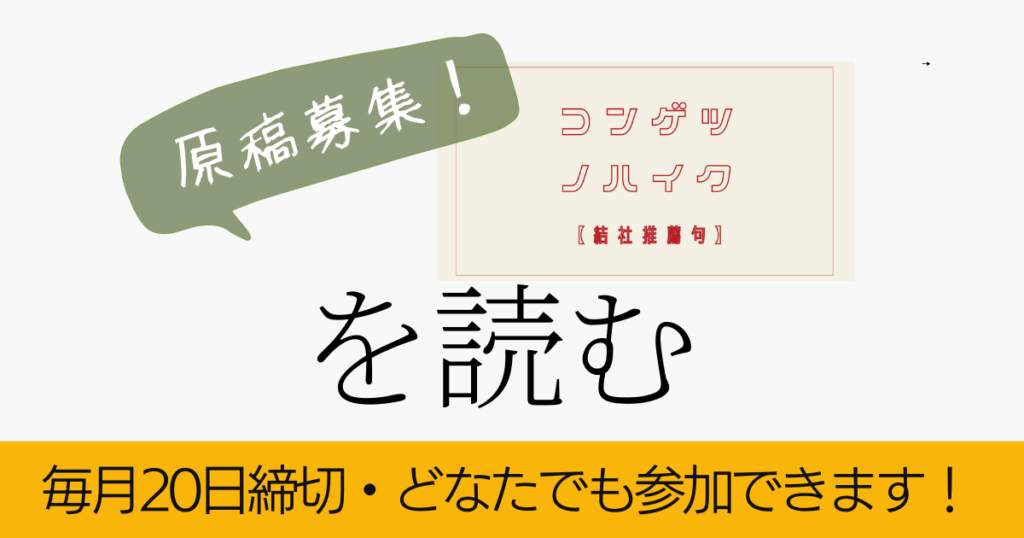【読者参加型】
コンゲツノハイクを読む
【2022年2月分】
ご好評いただいている「コンゲツノハイク」は毎月、各誌から選りすぐりの「今月の推薦句」を(ほぼ)リアルタイムで掲出しています。しかし、句を並べるだけではもったいない!ということで、一句鑑賞の募集を行っています。まだ誰にも知られていない名句を発掘してみませんか? 今回は12名の方にご投稿いただきました!(掲載は到着順です)
花野描く花野の端をすこし出て
田村祐巳子
「香雨」2022年2月号より
モーパッサンが嫌いなエッフェル塔を見たくないあまり、エッフェル塔のレストランをしばしば利用していたという話がある。逆に、よく眺めたいのならばその場所から離れなければならない。花野にいても花は描けるけれど、「花野」全体を描くのならばやはり「端を少し出」ることだ。「花野」と「端」の「は」・「端」と「少し」の「し」のリズムが小気味よく、描いている最中に心が躍っている感じが伝わってくる。「すこし」の平仮名の表記も、一歩二歩きっちり出ている感じではなく、だいたいこのへんかな、という気安さが感じられた。(榊原遠馬)
ぱつとせぬ虫の来てをり花八手
小笠原黒兎
「炎環」2022年1月号より
八手は冬に白い花を咲かせる。花の少ない時期なのでその蜜を求めて多くの虫が集まってくる。花は地味なものだがその蜜は極めて濃厚とか。しかしもとより冬。揚羽蝶のような大柄で美しい虫はとうに死に絶えている。勢い集まる虫の多くは越冬する蝿や虻。ポンポンのような花に蝿が群がっている悍ましい図になる。掲句はそんな虫たちを「ぱつとせぬ虫」と一刀両断。確かに揚羽蝶と比べれば蝿や虻は「ぱつと」しない地味な虫。しかしそれは人間の勝手な尺度であって皆懸命に生きている命。作者が掲句で揶揄嘲弄したかったのはこんな人間の勝手な差別意識なのだろう。(種谷良二/「櫟」)
着膨れのはみ出してゐる屋台かな
高木宇大
「雪華」2022年2月号より
冬のおでん屋台の長椅子に、三人の客の背中が見える。元より小さな屋台だから客は三人が上限なのだが、全員が着膨れているのでどんなに詰めて座っても、両側の二人の体は屋台の幅をはみ出してしまっている、というユーモラスな句。「着膨れ」から発信された、外気の寒さ、木枯らしの冷たさ、息の白さ、おでんの温かさ、燗酒の熱さは、かなりリアルだ。この屋台には行ってみたくなる。というか、読み手は既にそこにいて、三人の背中を見ている。(松村史基/「ホトトギス」)
肘つけばおでんの屋台ぐらぐらす
鳳佳子
「澤」2022年1月号より
子どものころ、食事中に肘をついてはいけないとよく言われた。そんなことも今はすっかり忘れて、愉快に飲み食いを楽しんでいる感じがよい。おでん屋というところがまた、ざっくばらんで気取らない印象だ。それにしても、いくら移動式の屋台だからといって、肘をついただけで全体がぐらぐらするというのはいささか心許ない。酔いも回ってきた時分だろうか。大人の情けないような、それでいて楽しいようなところが出ている。(斉藤志歩)
いとどの足はづれて太しそれも掃く
加納燕
「澤」2022年1月号より
いとど、は、昆虫のカマドウマのことだそうだが、そう言われても、馴染みのあるものではなかった。あるとき、家の中に現れた一匹に驚かされて、それがカマドウマだと知った。簡単に潰せると思ったのだが、その瞬発力、ジャンプ力に圧倒されてしまった。この句からは、その虫の強さ、大きさが感じられる。はずれて太し、という表現にも賛成。その処理に慣れているらしい作者の暮らしぶりも想像できる。対象物と作者、状況が一体になって、17音のドラマが成立していると思った。(フォーサー涼夏/「田」)
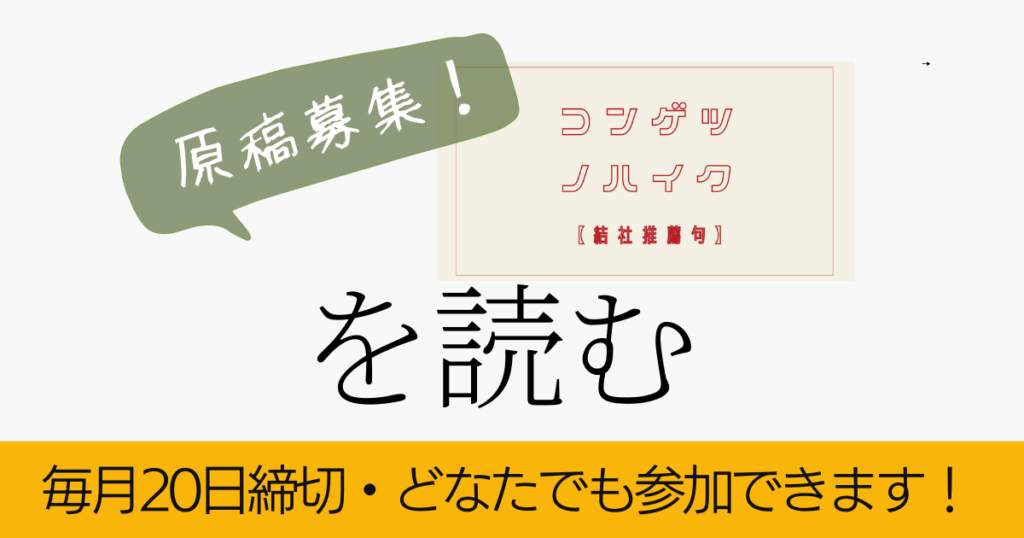
月待ちてあんぱんの臍おしかへす
横山泠子
「橘」2022年1月号より
あんぱんに臍(穴)を作るのは膨らんだ時に空洞が出来無いようにする為らしいが、臍は穴なのでそれ自体が膨らむことは無い。つまり出臍にはなら無い。ならば臍を押返すというのはどういう事か。人間が外側から開けた臍に対してあんぱんが内側から押返している、膨らんでいるという事ではないだろうか。人同様あんぱんも月を待ち、月と呼応して膨らんでゆく。月の引力とあんぱんの膨らむ力。当然潮汐のイメージも重なる。月待ちて、で軽く切れ、臍おしかへす、の後に「力」が省略されていると読んだがどうだろう。因みに満月に小豆を食べるのは理に適っているのであんぱんお薦めです。(田中目八/「奎」)
伝へたき言葉あるやう帰り花
山田 茜
「田」2022年2月号より
花木が花を咲くきっかけは、日照時間と温度らしい。要するに、きっかけが与えられるまでは辛抱強く待ち、きっかけが与えられればすぐにでも咲いてしまう。そんな生命の強さが帰り花にはある。しかし人間はどうだろう。例えば初恋の相手だとか、伝えたい言葉があるのに、何かきっかけ/勇気がなかったために伝える事が出来なかった事を、誰しも経験した事があるのではないだろうか。掲句を読むと、逆説的にあの頃のあどけなく、いたわしい感情が思い起こされるようだ。(北杜駿/「森の座」)
雀化し蛤つひに碁石にも
戸矢一斗
「銀漢」2022年2月号より
七十二候の季語。筆者は「二十四節気俳句生活」というブログを持っていることもあり、当然「七十二候」も長年の課題として(時間のある時に)作句に取り組んでいますが、音数の長い季語が多く「雀蛤となる」だけで十音。傍題の「雀化して蛤となる」では十三音。これは俳句になりようがないな、と思っていましたら、高級碁石の素材に見立てて、雀→蛤→碁石とピッタリ十七音に仕上げたのは見事です。また歳時記の解説ではこの場合の「雀」は賓客のことらしいので、高級碁石に転生して棋戦に使われるような想像もできて楽しい。脱帽です。(鈴木霞童/「天穹」)
流れゐる水あたらしき屏風かな
対中いずみ
「秋草」2022年2月号より
藝への讃歌であり、お伽噺のようでもあり。屏風に描かれた水が見るたびに新しく見える、ということを簡単に淡淡と表現して、お見事と感服いたします。面白みの急所は、〈ゐる〉という言葉遣いに宿っているようです。絵は動く筈もない。絵に込められた気韻が動いている。そこを感じ取るのは人の心の働きであって〈流れゐる〉。ぴったりな表現ですね。省みて、俳句という藝もまたかくあるべし、と、ごく自然に連想が繋がりもしましょう。(平野山斗士/「田」)
丸まりて茸も猫も地の色に
篠崎央子
「磁石」2022年1月号より
猫も茸も確かに丸くなる。掲句では丸まることを強調したいためか、語順を逆にしている。思わず頷いたのも語順を逆にしたインパクトのためだ。もう一つは、下五の「地の色に」だ。読み手の想像を膨らませるようにされている。恐らくは山のふもと、ふもと近くの公園だろうか。偶然見つけた茸の近くでゆるりと猫が休んでいるのだろうか。誰もいない公園でのワンシーン。和やかな印象を僕は受けた。茸の傘の下にゆっくり猫が休んで茸も猫も地面の色に同化しているかのようで、癒される一句でした。(紀宣/「天塚」「篠」)
十三夜見送りもせず帰したる
山田美恵子
「火星」2022年1月号より
こどものころ、見送りをされることが苦手だった。ていねいな見送りは優しい心持ちと育ちの良さの表れだと、大人になってから気がついた。いつも見送りをしてくれるひとがしないと、客人はびっくりするだろう。そして「だいぶ怒っているかも」と思う。でももしかしたら客人は見送りの有り難さも理解できない無粋なひとだったのかもしれない。そして十三夜という満月の二夜前の欠けた月を愛でるこの風流もわからないひとだったのかもしれない。じつに繊細な感性の一句だ。(千野千佳/「蒼海」)
それぞれの宝のありか小鳥来る
吉岡簫子
「ホトトギス」2022年2月号より
一読して句の持つ明るさに惹かれた。小鳥は食べきれない餌を隠す習性がある。「宝」とはその隠した餌のことだろうか。何気ない雑木林にもたくさんの「宝」が眠っていると思うと楽しい気持になってくる。「それぞれ」「宝」「ありか」と具体性を持たせないことで「小鳥来る」という季語のみが明確な事実として浮き立っている。また、取り合わせの句として鑑賞するのも面白い。小鳥も私たち人間も「それぞれの宝のありか」がある。小鳥はどこに餌を隠したのか忘れてしまうことも多いようだが、私たちはなるべくなら覚えていたいものである。(笠原小百合/「田」)
→「コンゲツノハイク」2022年2月分をもっと読む(画像をクリック)
【セクト・ポクリット管理人より読者のみなさまへ】