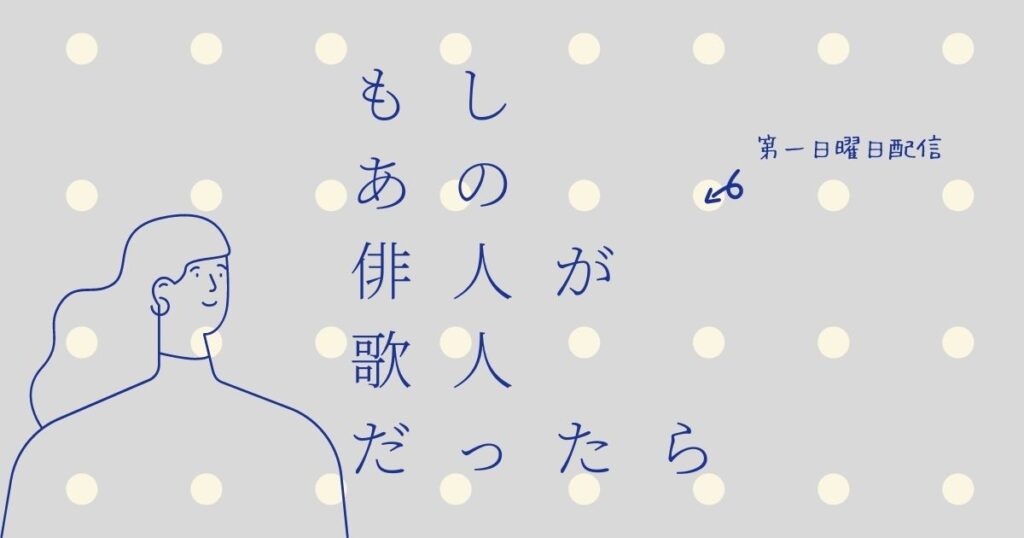
【連載】
もしあの俳人が歌人だったら
Session#8
このコーナーは、気鋭の歌人のみなさまに、あの有名な俳句の作者がもし歌人だったら、どう詠んでいたかを想像(妄想)していただく企画です。今月取り上げる名句は、尾崎放哉の〈咳をしても一人〉。この句を歌人のみなさまはどう読み解くのでしょうか? 今月は、服部崇さん、野原亜莉子さん、三潴忠典さんの御三方にご回答いただきました。
【2021年11月のお題】
咳をしても一人
尾崎放哉
【作者について】
尾崎放哉(1885-1926)は、鳥取市生まれ。『層雲』の荻原井泉水に師事。種田山頭火らと並び、自由律俳句のもっとも著名な俳人の一人である。東京帝国大学法学部を卒業後、東洋生命保険(現・朝日生命保険)に就職し、大阪支店次長を務めるなど出世コースを進んだエリートでありながら、突然それまでの生活を捨て、無所有を信条とする一燈園に住まい、俳句三昧の生活に入る。その後、寺男で糊口をしのぎながら、最後は小豆島の庵寺で極貧のなか、ただひたすら自然と一体となる安住の日を待ちながら俳句を作る人生を送った。
【ミニ解説】
この句からは、先月の〈秋深き隣は何をする人ぞ〉にも通ずるような、死を覚悟した人間の孤独が、あるいは自己との対話のドラマが立ち上がってくるようにも思えます。『層雲』を創刊して自由律俳句をリードした荻原井泉水は、歪められた松尾芭蕉の俳の精神を正しい道に引き戻そうとしました。たとえば、こんなふうに言っています。
「よく人は、俳句の内容と俳句の形式といふことをいふ。だが、俳句の内容よりも俳句のエスプリといふものを捜さなければならず、俳句の形式よりもリズムといふものを解しなくてはならない。私が思ふのに、俳句のエスプリを生かす為には、在来の俳句形式ではいけない。もつと自由なるリズムを用ひなくてはならない。さうして、其リズムに於て俳句的なるものがある以上、それは形式的にみて、いかに在来の俳句と違つて見えようとも、やはりりつぱな俳句として成立する。いや、それこそ新時代の俳句である」(『芭蕉・蕪村・子規』)。
しかし、放哉にしても山頭火にしても、彼らの提示した短い言葉の数々は、「頭の中で言葉をこねくりまわして定型に当てはめた」のとは違う、瞬間性が、あるいはナイーブさが感じられます。おそらく、彼らにとって定型とは社会そのものであったのでしょう。大学を出て、就職をして、家庭をもち、子育てをする。俳諧とは「かぶきもの」の遊びだったはずなのに。官僚が、医者が、文学者が、大学教授が俳句をこしらえる。それが当時、虚子の主導していた「ホトトギス」の商業戦略のひとつでもありました。
そこには句会があり、師がいて、そして何よりも句友がいます。いまのように、TwitterもInstagramもない世界ではありますが、彼らはけっして孤独ではなかった。一般に、孤独では俳句はつくれないのです。もちろん、放哉も『層雲』という雑誌に所属していましたが、彼は社会という定型のなかで自己が埋没していくことが、恐ろしかったのかもしれません。ヴェーバーが『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』(1904〜1905)のなかで批判した、人間は交換可能とみなす官僚システムへの、体を張った抵抗。趣味や風流ではなく、命懸けの<わび・さび>。
せきをしてもひとり。
しなくてもひとり。
でも社会は、ひとりになることを許してくれません。戸籍を通じ「家」ベースで国家に把握され、徴兵と納税をすることのバーターとして、市民として生きることを許可される。同様に、定型は、自由になることを許してくれません。定型と季語と、場合によっては文語や切字を使うことで、初めて俳句であると認定される。では、ひとりになるには、自由になるにはどうしたらいいのでしょうか。
ちょうど同じころ、20世紀初頭のフランスの社会学・人類学者のマルセル・モースは、代表作『贈与論』を執筆しました。それがのちにレヴィ=ストロースのシステムとしての「交換」に影響を与えたことは、周知のとおり。そこで登場するポトラッチ(蕩尽)とは、金持ちになった者が、尊敬を得るために、全財産を散財する(他者にあげたり、燃やしたりする)ことで一文無しになるという「文化」が紹介されています。まさに放哉そのものですね。
ちなみに、「咳」は冬の季語ですが、本当に寒々しいのは、システム化されてしまった「冷たい社会」のほうだともいえます。つまり単に冬に風邪をひいて、頼れる人もいないまま、咳き込んでいるのではなく、一種の社会批評にもなっているというわけです。
深読みでしょうか?
そんなことはないでしょう。昨年からのコロナ禍で部分的にでも医療崩壊を起こしてしまった日本は、肺を病んでいた一定数の人々が、保健所に事務的な対応をされたり、救急車を呼んでもこなかったり、病院に受け入れを拒否されたり、ワクチンの予約がなかなかできなかったり、誤った方法でワクチンを摂取させられたりしたのですから。
この句を「孤独」という言葉で鑑賞しているのをよく目にしますが、放哉は淋しかったわけでも、孤独だったわけでもなく、ただ「ひとり」だっただけなのではないでしょうか。もちろん淋しさを感じることもあったでしょう。でも、孤独ではない「ひとり」というのが、人間にあるのだし、許されるのではないでしょうか。同句集『大空』に収められた彼の句を詠んでみれば、いかに「孤独」がバズワードかがよくわかる気がします。
足のうら洗へば白くなる
お祭り赤ン坊寝てゐる
なんと丸い月が出たよ窓
よい處へ乞食が来た
雪積もる夜のランプ
霜とけ鳥光る
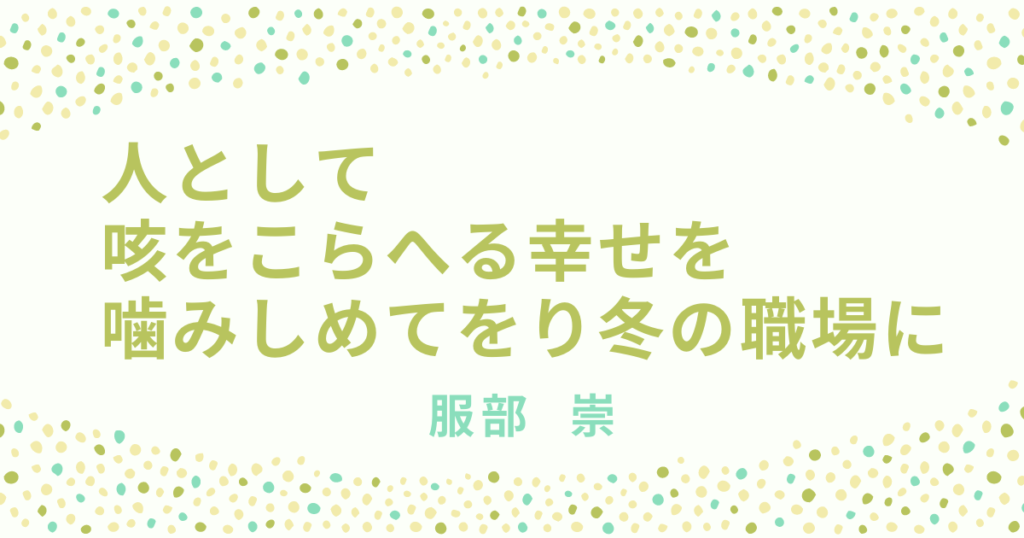
新型コロナウイルス感染症の蔓延防止の観点から全国的にテレワークが推奨されているが、ときには職場に出勤せざるを得ないことがある。その際には、従来以上に職場で咳をするのがためらわれる。あるとき、咳をするのがためらわれるのは周りに人がいる職場だからだと気が付いた。
放哉の生涯に古代インドにおける「四住期」の理想を思う。「四住期」では人生を学生期、家住期、林住期、遊行期の四期に分ける。家族や社会のために働く家住期を終え、家族や社会を離れて修行や瞑想に浸る林住期に至る。やがては死地をみつめる遊行期に入る。
日本では孤独死が社会問題となっている。コロナ禍の渦中で問題は悪化しているようにも見受けられる。一部では、孤独死を孤立死、孤高死との言い換えが試みられているが、実質は変わらない。人は一人では生きていけない。人は一人でしか生きていけない。人は一人では死ねない。人は一人でしか死ねない。生き死にを咳をこらえながら考える。
(服部崇)
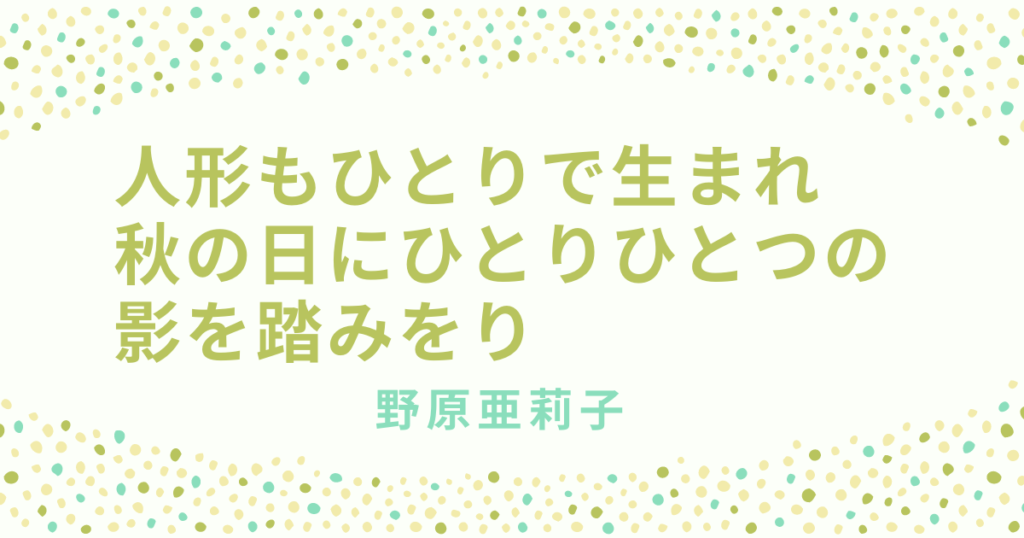
独身で人形なんて作っていると「一人でさみしいでしょう」とよく言われる。ところが私には「さみしい」という気持ちがよく分からない。これでは恋愛のスタートラインにさえ立てないような気がする。
そういえば人形もひとりだ。雛人形など男女ペアの人形もあるが、大体どこの国でも女の子の人形が単体で販売されている。顧客である女性は感情移入しやすい同性の人形を好むからだと思う。生物はペアになるべきなのだろうし、それが嫌だという訳ではない。ただ、人形の女の子たちが華やかに凛々しく人形店に並んでいる様子を見慣れているせいか、ひとりというのがより自然な選択に思えてしまう。
人形は「自分」と「他人」の間のちょうどよい中間地点に居る。2次元と3次元の間、現実と空想の間。一人と二人の間の曖昧で優しい世界の心地よさは、たぶん他の何者にも代え難い。
(野原亜莉子)
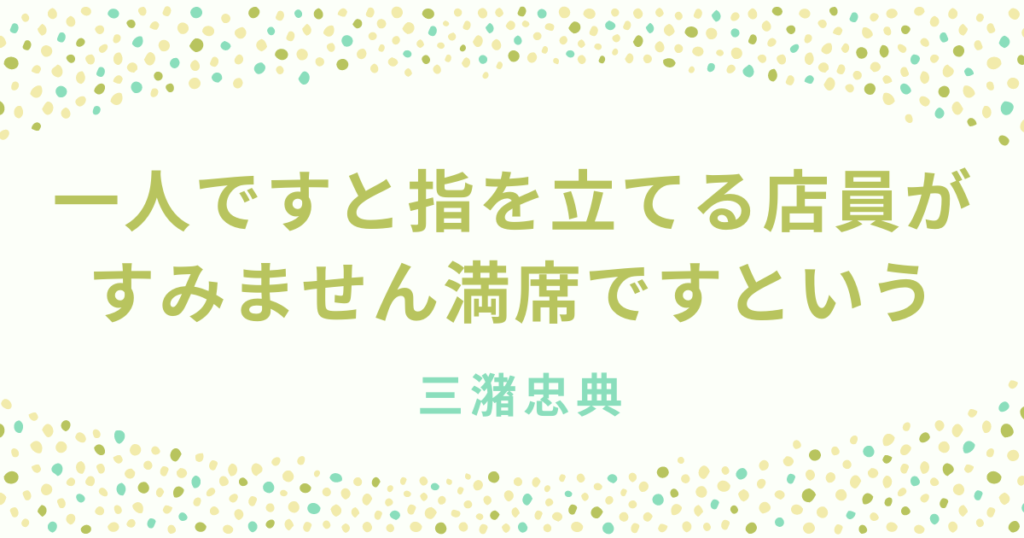
また前のようにみんなで集まれるとよいですね。最近よく耳や目にするようになり、本当にそう思う。一方で、自分はそんなに集まることを求めていたかな、と疑う部分がある。
前のように、という言い回しに引っかかる。そもそも心から楽しい集まりなんてそんなになかった。付き合いや義務的な集まりがほとんどで、居心地が悪かったことが少なくない。今後は願わくは、楽しい集まりだけに厳選して参加させていただきたい。決して集まること自体が嫌いな訳ではないのだ。
一人でいるのが好きで、今でもそれは変わらない。協調性なんて元来無かったが、仕事を続けるために、無理矢理後付けした。ところが協調性がないために、幸か不幸か協調性がないと思しき面々から共感を受けやすいようで、仕事でもプライベート(のかるたの仕事)でも厄介な場面での調整役を期待されるようになってしまった。なんということだ。
(三潴忠典)
【ご協力いただいた歌人のみなさま】

◆服部崇(はっとり・たかし)
「心の花」所属。居場所が定まらず、あちこちをふらふらしている。パリに住んでいたときには「パリ短歌クラブ」を発足させた。その後、東京、京都と居を移しつつも、2020年まで「パリ短歌」の編集を続けた。歌集『ドードー鳥の骨――巴里歌篇』(2017、ながらみ書房)。
Twitter:@TakashiHattori0

◆野原亜莉子(のばら・ありす)
「心の花」所属。2015年「心の花賞」受賞。第一歌集『森の莓』(本阿弥書店)。野原アリスの名前で人形を作っている。
Twitter: @alicenobara
◆三潴忠典(みつま・ただのり)
1982年生まれ。奈良県橿原市在住。博士(理学)。競技かるたA級五段。競技かるたを20年以上続けており、(一社)全日本かるた協会近畿支部事務局長、奈良県かるた協会事務局長。2010年、NHKラジオ「夜はぷちぷちケータイ短歌」の投稿をきっかけに作歌を始める。現在は短歌なzine「うたつかい」に参加、「たたさんのホップステップ短歌」を連載中。Twitter: @tatanon
(短歌なzine「うたつかい」: http://utatsukai.com/ Twitter: @utatsukai)
【セクト・ポクリット管理人より読者のみなさまへ】
