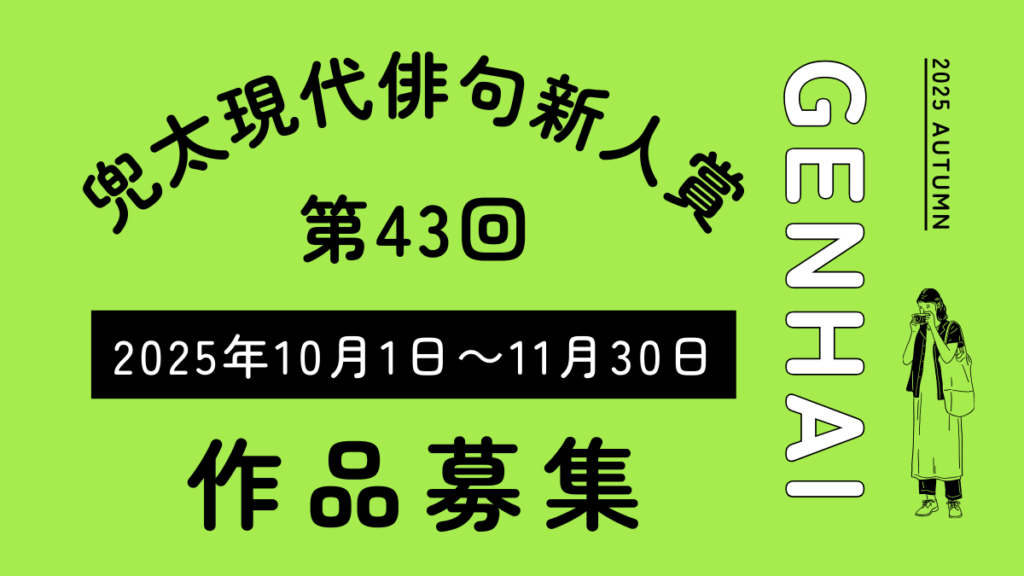まんまるくなりたるままの氷なり
室生犀星
この句は、世界を把握しようとする意志よりも、見てしまう・気に入ってしまう といった反射的な快感を前面に押し出している。
「まんまるく」は、形状の説明であると同時に、判断を含んだ言葉でもある。「まんまるく」には「整っている」「愛らしさ」といった判断が自然に含まれており、対象を意味の体系へ回収する前に、反射的な好ましさが立ち上がる。これは、「かわいい」ものに出会ったときの反応とよく似ている。かわいいとは、何かを理解した結果ではなく、理解する前に反射的に感じてしまうものやから。
氷は比喩として回収されることもなく、ただそこに「まんまるく」存在する。
視覚・聴覚の両方において重ねられた「ま」「なり」により、変化や物語は遮断され、氷が氷としてそこに「まんまるく」あることだけが残される。この句のなかで、氷は溶けないし、壊れないし、何かを暗示することもない。「まんまるくなりたるまま」であること以上のことは語られない。ここでは俳句がしばしば担わされる発見の要素も、世界を求められることもない。
また、この句は俳句の視覚詩としての側面を利用し 、我々を「遊び」へと誘う。
縦書きで読まれる俳句という形式において、「ま」「なり」が視覚的に縦に落ちていくとき、言葉は意味以上に配置とリズムを帯び、視覚的な縦書きの一行詩、として立ち上がる。この縦方向への落下は、この句の方向、つまり遊びと遮断、について身体に近い(縦型で、節のある、空洞の)感覚として訴えかける。
我々は矛盾を抱えたこの(俳句)形式を続けていくにあたって、永続的価値を見出そうという不毛で必敗の戦いを求められる。形式は本来、世界が一瞬立ち上がると同時に消え去るべきものであり、 それにもかかわらず、我々は俳句という形式に囚われる。この句は、必ず敗北する戦いであることを隠さず、なおその敗北のなかで遊んでいる。
氷はただの氷としてそこに留まり続ける。不毛さに向き合い、戦いながら、それでも、快感を得てしまう。この句の快感とは、初めに述べた「かわいい」と同じように日常の小さな反射的快感のことである。このとき俳句は、勝利のための表現ではなく、敗北のまま続けることができる遊びとなる。把握しきれない世界を前にして、意味の回収を諦めつつ、それでも関係を結ぼうとする態度がある。
この態度がこの句の強度に繋がっているのではないだろうか。
(雨霧あめ)
【執筆者プロフィール】
雨霧あめ(あまぎり・あめ)
2002年生まれ。滋賀県出身。会社員。
よろしくお願いします。