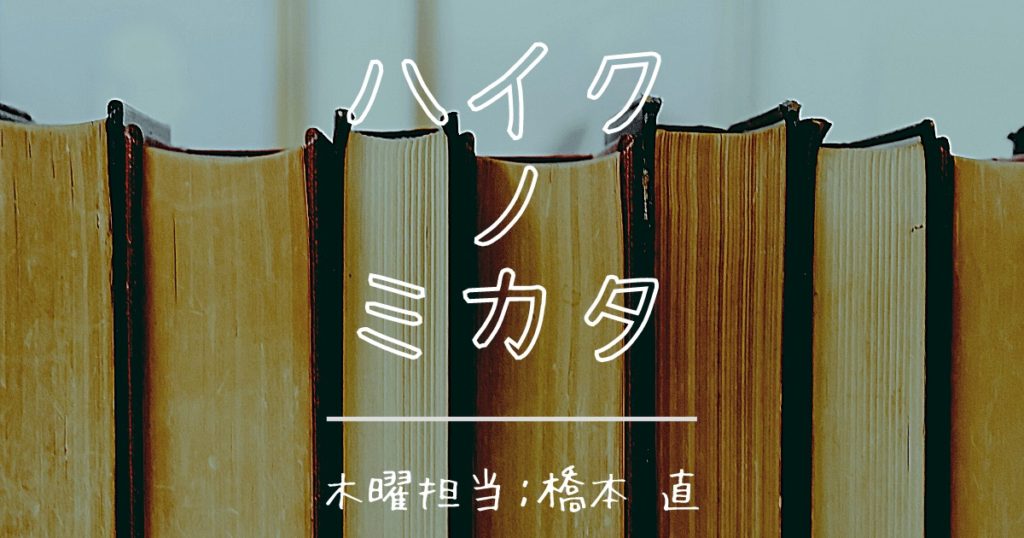
同じ事を二本のレール思はざる
阿部青鞋
(「ひとるたま」1983年 現代俳句協会)
阿部青鞋はおかしな句を詠む人だというイメージがあって、しかし句集を読み出すと、案外に普通だったりもする。普通というのは、「夕方のはうれん草のひたしかな」や「家庭にて羊の毛皮よごれけり」のような、だからなんやねん、的なツッコミをいれたくなる句とか、「笹鳴きのふんが一回湯気をたて」のような古川柳に片足をつっこんだような意味で勝負する句のことを言う。特に三つ目は、句集の巻頭を飾っていて、この俳人はなかなか人を食ったことをする、と思う。句集タイトルの「ひとるたま」は漢字を当てれば「火取玉」。この玉が集めた光のおこす煙が自分の句であると作者は後記で言う。
さて、基本意味の連結で文脈を構成する作家なのだけれども、「冷蔵庫に入らうとする赤ん坊」、「いくつ鳴るつもりの柱時計かな」、「はりがねがたうとう海になつたのだ」あたりの軽くホラーっぽい句でその奇妙な句柄の片鱗を見せ、「てのひらをすなどらむかと思ひけり」、「食パンを買ひきしのちの別の時間」、「左手に右手が突如かぶりつく」、「うつぶせになればいまだに若きわれ」あたりの句になると、もはや我が身と心は我一人のみのものにあらずという風情でいろいろなものが内部で同居していそうある。そんな句の中に掲句が置いてあると、この二本のレールも、もはやただの物体ではなく、この作家(あるいは作中主体)の身体の延長線上に延びゆく物としてあるような気さえしてくる。多くの句が一見擬人法のような詠み方なのだけれども、それによって人の枠(境界)の曖昧さを露出させているようにも見える。言い換えれば、擬人法で擬人法が壊されてゆく、ということになろうか。もちろんそれは、人のあり様とはいかなるものかを問うことになるのだろう。
(橋本直)
【執筆者プロフィール】
橋本直(はしもと・すなお)
1967年愛媛県生。「豈」同人。現代俳句協会会員。現在、「楓」(邑久光明園)俳句欄選者。神奈川大学高校生俳句大賞予選選者。合同句集『水の星』(2011年)、『鬼』(2016年)いずれも私家版。第一句集『符籙』(左右社、2020年)。共著『諸注評釈 新芭蕉俳句大成』(明治書院、2014年)、『新興俳句アンソロジー 何が新しかったのか』(ふらんす堂、2018年)他。