
【第10回(最終回)】
「さび」しくなって心を見つめる
武将の処世と茶の湯
墨染めの夕べや名残り袖の露 細川幽斎
織田信長の追善供養の為に、細川幽斎は本能寺の焼け跡に仮屋を作り、百韻連歌の興行を行った。その発句である。「露」は和歌連歌では、儚さと涙の象徴である。幽斎は信長を討った明智光秀とは、その娘玉(ガラシャ)を息子の忠興の嫁に迎えるほど昵懇の間柄だったので、多くの武将は、本能寺の変に対して幽斎がどのように対応するかを見守っていただろう。
しかし、幽斎は髪を下ろして僧形となり、信長公の追善供養をする意志を表明し、光秀の反逆には一切荷担しない姿勢を公にした。この幽斎の対応を知らされて光秀は非常に動揺したらしく、卑屈とも言える協力要請の書状を再度幽斎に送っている。
発句は、光秀派だった幽斎が生き残るための、大掛かりな演技だった、と光秀贔屓の司馬遼太郎は『国盗り物語』のラストで触れている。幽斎は、足利義昭を皮切りに、信長・秀吉・家康と主を代え、細川家は江戸時代には熊本藩52万石の太守として残った。幽斎はまた、当代一の歌人であり、古今伝授を受けていて、関ケ原の戦いで危うく西軍に滅ぼされるところ、宮中から使者が来て調停が入り、一命をとりとめたほどである。茶会も重ねた。利休の弟子である。
私の大学時代の恩師の一人に、細川幽斎研究の第一人者だった土田将雄先生がいる。大学院時代は、幽斎一座の連歌講読のゼミに参加したり、細川家の史料集『綿考輯録』の翻刻をお手伝いしたりした。
一番覚えている先生の言葉は、こうだ。
「戦国武将は、常に命のやりとりの場にさらされるから、茶を愛したんだと思うよ。」
主従の裏切りは無論、親子兄弟夫婦でも殺しあう戦国の転変を知れば、むべなるかな。戦国時代の軍記を研究し、歴史学の方々と仕事をご一緒していると、ますます土田先生の言葉は重く思い出される。
利休が茶に求めた「道」の世界と、信長や秀吉が茶会を開くことを一種のステータスシンボルとし、そこで披露される「名物」の茶道具を一国一城以上の価値としたこと、あるいは茶席を密談の場にして、政治に利用する姿勢とは、原理的に全く逆ベクトルのもののはずだ。利休は芭蕉と違って、生々しい面がつきまとう。だからこそ、利休の死は芸術上の死だったという解釈も出てくるのだ。
俗の極みから咲く「さび」の花
ただし、聖なるものと猥雑なものをひっくるめて、戦国の頃に確立された茶の湯というものは、多くの武将たちから愛好されたのも事実だ。それはなぜだったのか?こんな問いが生まれるのも、俳句の世界で、利休同様、聖俗双方を併せ呑んだ生き様をしたのは、他ならぬ虚子だったからである。
明易や花鳥諷詠南無阿弥陀 高濱虚子
自分の求めた俳句世界をこのように信仰告白してみせる一方、虚子は経営者としても成功している。虚子門には、俳句そのもので才能を開花させた者たちだけが集ったのではない。華族の本田あふひ、三菱地所の会長でホトトギス発行所を丸ビルに迎えた赤星水竹居、逓信次官で東大俳句会を創始した富安風生、初代海上保安庁長官の大久保橙青等々、綺羅星のごとく名士が数え上げられる。確かに、虚子と利休は似ている。利休は自分の死後を見通して、生前に分家を作り、茶道の保存に務めた。その辺も虚子とは通い合う。
我々江戸文学研究の大家中野三敏氏の言葉に、「貧乏人が金持ちの気分を味わうのがゴルフ、その逆が茶道」(『緑雨警語』)というのがある。これほど利休や芭蕉、ひいては虚子の「さび」を言い当てたものはない。
茶の湯はたいてい、主人と数人の客しか入れない狭い茶室で行なわれる。茶室の入口にあたる「にじり口」は、とりわけ小さくつくられており、刀を帯びていては、中に入れない。そこで刀は外の刀掛けに置き、主人も客も丸腰で向き合う。
簡素なしつらいと静寂の中、主人の心づくしのもてなしを受けるひと時。それは外の世界と隔絶された、静かな人と人との交流の時間である。
戦国武将たちは、一歩外に出れば、命を失うかもしれない、「博打」の連続である。次の合戦で生きて戻れる保証などどこにもない。片時も油断できない、常に己の「死」と隣り合わせに生きる日常において、茶の湯のもてなしは、一瞬心を穏やかにし、安らげるひと時だったに違いない。たいていはふやけた今の世襲政治家や、責任を逃れる言い訳ばかり考える官僚やサラリーマン社長と違い、虚子門の成功者たちは、戦国武将同様、実力でのし上がった、斬った張ったの者たちが多いのである。
これよりは恋や事業や水温む 高濱虚子
一橋大学の前身、高等商業学校卒業生への餞の句である。東大閥が仕掛けた専攻部廃止の文部省令や、東大による合併の動きに対し、全学生が抗議、総退学まで決議して抵抗、文部省令撤廃を勝ち取り、母校を残した猛者たちである。学生は当然男子だけだ。虚子の句を、今の「優しい」大学生の、ひ弱げな卒業式・謝恩会のイメージで捉えたら、とんでもない誤解となる。
戦士の休息という大人の俳句
「わび」とは、友達ができなくて寂しい、などどいう「うつ」の気分とは訳が違う。虚子のこの句は、独立自尊して、切磋琢磨した「サムライ」たちの、戦士の休息としての「水温む」なのである。ここで、生温い、中途半端な、あるいは啄木の亜流のような世を恨み、拗ねた若者までを想像してはいけない。
一度でも我に頭を下げさせし人みな死ねといのりてしこと 石川啄木
10年ほど前、最初に日本伝統俳句協会の全国大会に参加した時の事である。一泊二日の数百人の句会というのも、今や昔話だが、今でも忘れられない思い出がある。帰りのバスで、見知らぬ老紳士が、「お若い方がめずらしいですね。成績はいかがでした?」と隣に座って話しかけてこられた。
「男性は仕事でくたびれていますから、そうでもないですが、女性、特に主婦で俳句にのめり込む人の競争心や嫉妬心には、気を付けられた方がいいですよ」
この老紳士は、かつての「戦士」だったと思う。十数年を経て、俳句界を見回した時、この元「戦士」の言葉が、いよいよ思い出される。今や「戦士」に男女の区別はない。家で、仕事場で、戦っている人にもはやそんな区別は無用だ。むしろ問題は、男女の別なく、中途半端に俳句での名声や小さな富を得ようとする人間による、俳句の矮小化や、後付けの理論だけである。
富安風生は、俳句の「芸」の側面を忘れてはならないと言い続けたし、晩年の角川源義はこれを応援し続けた。「芸」とは、実世界で充実した、あるいは充実しすぎた時を送っている/送っていた人間の、心の「余裕」というものであろう。
最近サラリーマンとしても十分に生きてこられた、同世代の小川軽舟さんが、蛇笏賞を受賞する慶事があった。サラリーマンを生きて来たからこその俳句だという受賞の弁には、快哉を叫んでいる。軽舟さんの近年の句業に見られる、「余裕」や「俳諧師」的世界を、「俗」だと評する向きもあるが、それは「俗」ではなく、俳句の伝統の現代的再生なだけだ、と言っておきたい。文学だから、いろんな世界があっていいが、実世界でしのぎを削ってきた「戦士の休息」の文化を、削いでしまうような俳句界なら、そこから「大人」は消えて、俳壇そのものも、やせ細ってしまうことだろう。
(了)
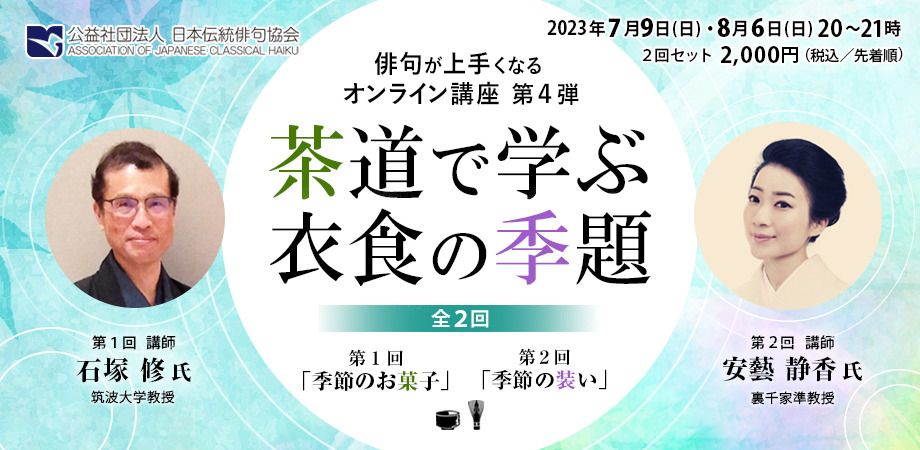
【執筆者プロフィール】
井上泰至(いのうえ・やすし)
1961年、京都市生まれ。上智大学文学部国文学科卒業。同大学院文学研究科博士後期課程単位取得満期退学。博士(文学)。現在、防衛大学校教授。著書に『子規の内なる江戸 俳句革新というドラマ』(角川学芸出版、2011年)、『近代俳句の誕生ーー子規から虚子へ』(日本伝統俳句協会、2015年)、『俳句のルール』(編著、笠間書院、2017年)、『正岡子規ーー俳句あり則ち日本文学あり』(ミネルヴァ書房、2020年)、『俳句がよくわかる文法講座: 詠む・読むためのヒント』(共著、文学通信、2022年)、『山本健吉ーー芸術の発達は不断の個性の消滅』(ミネルヴァ書房、2022年)など。
【井上泰至「茶道と俳句」バックナンバー】
◆第1回 茶道の「月並」、俳句の「月並」
◆第2回 お茶と水菓子―「わび」の実際
◆第3回 「水無月」というお菓子―暦、行事、季語
◆第4回 茶掛け―どうして芸術に宗教が割り込んでくるのか?
◆第5回 茶花の心
◆第6回 茶杓の「天地」―茶器の「銘」と季語
◆第7回 集まる芸の「心」と「かたち」
◆第8回 人の「格」をあぶりだす夏服
◆第9回 茶の旬
【井上泰至「漢字という親を棄てられない私たち」バックナンバー】
◆第1回 俳句と〈漢文脈〉
◆第2回 句会は漢詩から生まれた①
◆第3回 男なのに、なぜ「虚子」「秋櫻子」「誓子」?
◆第4回 句会は漢詩から生まれた②
◆第5回 漢語の気分
◆第6回 平仮名を音の意味にした犯人
【セクト・ポクリット管理人より読者のみなさまへ】
