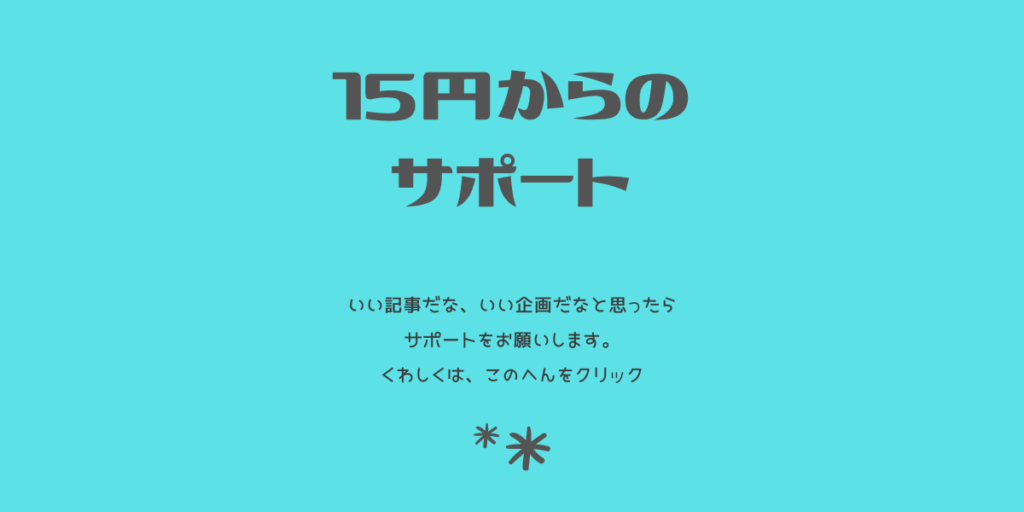【春の季語】春泥
【ミニ解説】
ほかの季節の「泥」が季語認定されないのは、やはり「春の泥」は特別だということ。つまり、そこには喜びがある。うれしい泥、それが「春の泥」。
雪岸叢梅發 春泥百草生
と言ったのは、唐代の詩人・杜甫でした。「雪の岸辺には梅が咲き、春の泥には草が生える」くらいでしょうか。つまり、凍てがゆるんできてこその春泥。
【春泥(上五)】
春泥に子等のちんぽこならびけり 川端茅舎
春泥になほ降る雨のつばくらめ 西島麦南
春泥に押しあひながら来る娘 高野素十
春泥にうすき月さしゐたりけり 久保田万太郎
春泥に月の轍を引き重ね 野見山朱鳥
春泥のまつくらやみに迷ひをり 星野立子
春泥に歩みあぐねし面あげぬ 星野立子
春泥になやめるさまも女らし 今井つる女
春泥の葛西にたゝむ見舞傘 石塚友二
春泥を来て大いなる靴となり 上野泰
春泥を桂馬に跳んでたのしまず 上田五千石
春泥やくもり硝子にうつる花 細見綾子
春泥にさへも決断力不足 後藤比奈夫
春泥へ並べ丸太の裸体なる 小原啄葉
春泥の位牌をすすぐ雨水溝 小原啄葉
春泥をあぶな歩きに犬の主 鷹羽狩行
春泥にとられし靴を草で拭く 稲畑汀子
春泥をこゑごゑ撥ねてゆきにけり 水内慶太
春泥を踏んで重心浮きにけり 西山睦
春泥を帰りて猫の深眠り 藤嶋務
春泥のもつとも窪むところ照り 山西雅子
春泥の道にも平らなるところ 星野高士
春泥に贔屓の穴を作りけり 山田耕司
春泥にひとり遊びの子がふたり 下坂速穂
春泥を泳ぐ東北の零度ばかり 橋本直
春泥を握れば人の髪まじる 堀下翔
【春泥(中七)】
幻影の春泥に投げ出されし靴 星野立子
かの旗を靴もて春泥にふみにじらんか 長谷川素逝
売られゆく牛春泥をつけしまま 阿部寿雄
戰勃るか春泥に釘ばらまかれ 八田木枯
棟上げや春泥をくる祝酒 鶴田恭子
乗り入れて馬場の春泥匂ふかな 西村和子
武蔵野の春泥重く歩きけり 上林暁
八つ手葉に春泥のとび散つてあり 岸本尚毅
牛乳を零し春泥おいしそう 近恵
くちづけのあと春泥につきとばす 松本てふこ
生まれ日の春泥ひかりごと跨ぐ 堀切克洋
【春泥(下五)】
乳母車の車輪がつけて行く春泥 細見綾子
飛ばさるは事故かそれとも春泥か 岡田史乃
【セクト・ポクリット管理人より読者のみなさまへ】