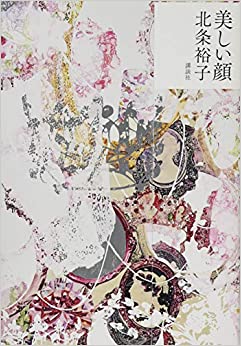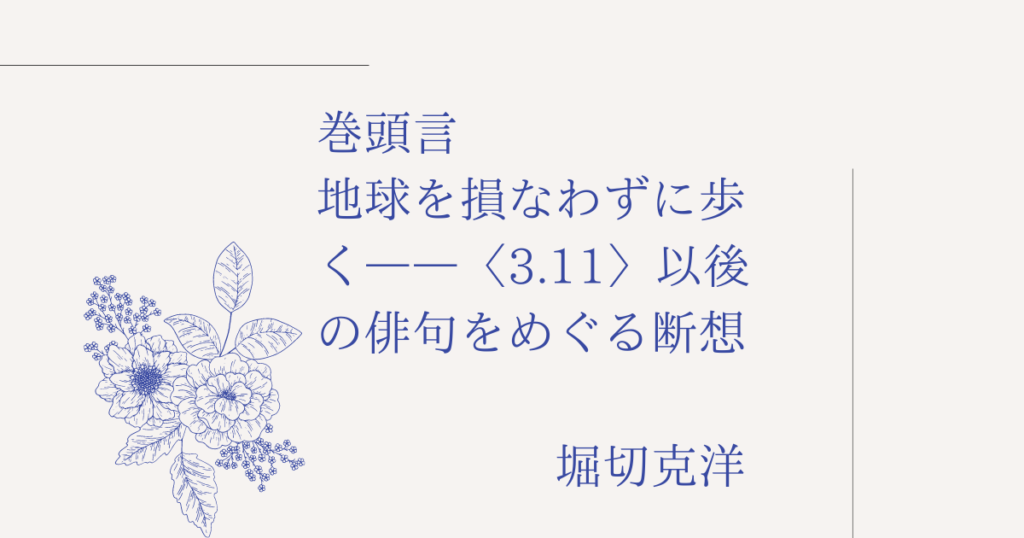
【巻頭言】
地球を損なわずに歩く――〈3.11〉以後の俳句をめぐる断想
堀切克洋(「銀漢」同人)
東日本大震災(2011年)を、その他多くの震災と一緒にすることができないのは、言うまでもなく、たちまち街を瓦礫の山にしてしまった大津波と、それに伴って引き起こされた福島の原発事故のためである。
1. 自然を再=考する――「原発問題」から「気候変動問題」へ
東電内で津波による災害が予見されていた以上、原発事故は「人災」であり、津波や地震による物理的被害は「天災」である。東電に損害賠償を求めた集団訴訟のいくつかでは現在のところ、東京高裁が東電のみならず、東電に対する規制権限を行使しなかった国も「違法」であると結審しているが、最終判断は最高裁まで先送りとなるだろう。同様の集団訴訟は全国に30件あるが、そのすべてに決着がつくのはまだまだ先のことである。もちろん、国にも法的に認められた権利はあるが、それを行使することで「先延ばし」にする態度は、ことの重大さと緊急性を考えれば誠実さを欠くと言わざるをえない。
もっとも、原子力技術が生んだ悲劇は、スリーマイル島事故(1979年)、チェルノブイリ事故(1986年)など、いくつもある。日本でも東海村JCOの臨界事故(1999年)が起こっていたことに加え、東京電力の隠蔽体質が地元で話題となっていたころ高校生だったわたしは、地元(福島県)のテレビのニュースで「MOX燃料」「プルサーマル計画」といった言葉を当然のように知っていた。とはいえ、それが、世界史的にどのような意味を持つのかどうかは、正直にいって真面目に考えてこなかったし、まさか福島がこんなに有名になるとは思っていなかった。少し盛っていうと、東京に出てきてから福島出身だというと、かなりの確率で福井、福岡と間違えられることがあったほど、福島はマイナーな県だという自己認識があったからである。
その1990年代末の話、当時都知事だった石原慎太郎に対し、プルサーマル計画にきわめて慎重な態度を示していた時の福島県知事が「東京に原発をつくってみたらどうか」と提案し、一笑に付されたという話が残っている。そのように国策と命懸けで対峙してきた首長が突然逮捕され、「収賄額0円」という奇妙な容疑で起訴されたのは、今から思えば悲劇の予兆だったようにも思える。そのあたりの事情については、『知事抹殺 つくられた福島県汚職事件』(2009年)に詳しいが、わたしが学生時代を送った1990年から2000年代にかけては、文化(表象)のダイレクトな関心ではなくなるほどまでに、制度的に硬直してしまっていた主題だったということだ。
つまり政治的に見れば、地方自治体が国=官僚機構と政治家(の支援を受けた企業)に対して抵抗することが、非常に困難だという「おなじみ」の話として表象されていたということである(先日、予定されていた広島県の大規模PCR検査が「官邸の意向」で先送りとなったように)。とりわけ原発に関しては、歴史的にはアメリカの影響が大きいため、沖縄をめぐる諸問題と似た構造をもっていることは、哲学者の髙橋哲哉が、それを「犠牲」の構造であると論じている(『犠牲のシステム 福島・沖縄』集英社新書、2012年)。これは戦後の歴史を振り返ってみれば、そのとおりだろう。福島をめぐる問題と類似しているのは、広島・長崎ではなく、むしろ沖縄なのである。
もちろん、広島・長崎の原爆投下があったからこそ、アメリカ中央情報局(CIA)の協力者のひとりであった正力松太郎の「尽力」によって、「原子力の平和利用」という建前で戦後日本が核技術を保持したという面が、歴史的に見れば確かにある。朝鮮戦争によって緊張する東アジア情勢のなかで、日本がアメリカにとっての防波堤となった帰結が、福島の事故であるというのは「歴史の皮肉」であるといわざるをえないが、しかし「歴史的な必然」でもあるのだ。原発政策がおおよそ国内問題に集約できないのは明らかで、そこがどうにも面倒な話なのである。
福島の原発事故以後、EU諸国を中心とするヨーロッパは、安全コストの悪すぎる原発への依存度を低める方針を共有するようになったことは知られている通りだ。それは「気候変動対策」や「脱炭素」の産業の中心を確保することで、経済的なプレゼンスを高めようとする方針と見るのがリアリスト的な視線だ。世界的に見れば、エネルギー需要は増加している。アジアでも台湾や韓国は脱原発の方針を打ち出しているが、そのなかで中国は、「原子力はクリーン」と主張しながら(!)、原子力需要のある中東・南アジア地域への輸出を国策としている(もちろん中国でも、福島原発事故後、原子力産業は深刻な打撃を受けたが、2019年より再開している)。加えて、アメリカとしては(1979年のスリーマイル事故以降、新設はされてないが)、中国・ロシアに原子力技術をリードされることはただちに安全保障上の問題となるから、手放しにくい面がある。10年後には中国が世界一の原発大国になることが想定されているとはいえ、「核をもたせてもらった」日本としては、単独の判断で「原発ゼロ」にはなかなかできないというポストコロニアル的状況をまずは理解しておく必要がある。
現政権は昨年10月に「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」を打ち出したが、このなかには原発の再稼働・新設が盛り込まれている。日本国内に54基ある原発のうち、再稼働したのは9基で、うち6基は停止中である。原発の発電量は現状でも全体の6%程度で、原子炉等規制法では「原発の運転期間は原則40年」とされているから、新設をしなければ黙っていれば「原発(ほぼ)ゼロ」になってしまう。だからこその「新設」が盛り込まれたわけだが、いままでのところ首相の答弁は、この点を正しく解き明かしていない。そのため、いまのところは経産省主導の「脱炭素=原発再稼働・新設」という方向性が、メディアでは表立って批判されてはいない。
したがって、福島のこと、原発のことを考えるには、まずもって「気候変動」のことを考えなければならない――ということが、この10年でいちばん大きく変わったことではないだろうか。つまり単に安全保障上の問題として、米中との軍事的関係においてのみ、「原子力政策」を考えなくてよくなったことが、日本にとっては「朗報」ともなりうるほど、大きな変化だったのではないか。 昨日3月10日から12日かけて、「原発ゼロ」に加えて「自然エネルギー100」を訴えるオンライン会議「原発ゼロ・自然エネルギー100世界会議~福島原発事故から10年~」が行われている。緻密なコロナ対策で日本でも有名になったオードリー・タンや元首相の小泉純一郎ら、100名を超える識者による世界会議だ。

もし、昨年12月に亡くなった有馬朗人(「天為」主宰)が生きていたら、その点を訊いてみたかったところだ。かつて東大総長・文科大臣を務めた有馬は、産業界や学界の有志が組織する「エネルギー・原子力政策懇談会」の会長として、2013年に安倍政権に緊急提言を行っているが、それはあくまで原発をベース電源として捉えたうえで安全確保を求めるものだったからだ。当時、有馬は「世界各国で原発導入が進む現実をみても、正面から向き合うことが大事だ」と語っていたが、自然エネルギーへのシフトが行われている現在の流れのなかでも、考えは変わらなかったのかどうか。ともかくも「産業界」の意思が、市民にとって問題であることは、指摘しておいてもよい(それらは事故直後から「ムラ」であると形容されてきた)。
しかしながら、俳人にとってまず考えるべきは、政治的ふるまいをするかどうかではなく(それは各人の思想・信条の自由である)、いかにして俳句の問題として捉えることができるか、ということである。
衝撃的なデータが公表されたのは、2019年のことだった。現在、昆虫の3分の1が絶滅危惧種であり、ハチやアリ、カブトムシなど、世界に生息する昆虫の4割が夥しいスピードで減少しているという調査結果が発表されたのである。主な要因としては、農業や都市化、森林伐採などで生息地を奪われたこと、世界中の農業で使われる肥料や殺虫剤の影響や化学物質による汚染、病原菌などの生物学的要因、そして特に熱帯地域で大きな影響を与えている気候変動があるという。こうした問題が、人間にとって対処可能であるかどうか、正直心許ないところだが、有機的な食品を選ぶ、殺虫剤を使わないなどの行動は、しておいても損にはならないだろう。
俳句は季節や自然と深いかかわりをもつ詩であり、それは部分的には『万葉集』にまで遡ることも可能かもしれないが、しかしそのように(長い歴史として)捉えられてきた時間幅を支えていた自然観を、近代(ざっくりいえば、産業革命+資本主義)以降の社会システムは変えてしまうところまで来てしまっている、ということだ。ライフラインがインターネットに依存し、電気使用量はこれからますます増加していくなかで、地球規模の生態系の変化を「見殺し」にする可能性があることを、俳句にかかわる者はもっと真剣に議論してもいい。季語の多くが、100年後にはもうなくなっているかもしれないのである。
この点について、「俳句四季」3月号の特集に小文を寄稿したところ、岩岡中正氏がさっそく毎日新聞の時評に引いてくださったのは、ありがたいことだった(「毎日新聞」2021年3月1日付)。繰り返しになるが、個人的な政治心情はさておくとして、俳人にまずできることは、自然の哲学を再考/再興することである。そうした試みは、山本健吉、オギュスタン・ベルク以降、あまりなされてこなかったように思えるからだ。俳句が「世界文化遺産」を目指すくらいなら、まず地球規模で自然を捉えるべきか、という議論まで踏み込んでおくべきではないか。
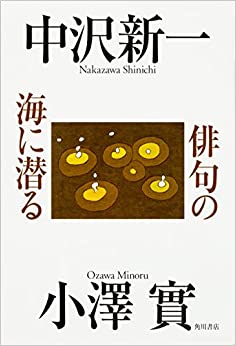
この点で、この10年のうちに触れた本のなかで、わたしにとって興味深かったのは、小澤實と中沢新一による『俳句の海に潜る』だ。わたしが〈3.11〉以後の10年間で、俳人からの問題提起としてもっとも示唆に富んでいたのは、この本である。中沢の芸術人類学(ことに「アースダイバー論」)を下敷きにして俳句の古層に迫っていく対談は、なかなかにスリリングな文化論だった。俳句の批評は、あまりに作家論や本質論に傾倒しすぎているが、これはまさしく自分にも跳ね返ってくる課題なのであって、わたし自身としても、次の10年の課題としなければならないと思っている。ハンナ・アレントがかつて語ったように、芸術作品は本来、人間にではなく、世界に向けて発せられるものだ。それは批評もまた同じだろう(『人間の条件』)。
2. 「議論」なき国にいるということ――無季をめぐる喜劇
それにしてもこの10年の間、俳句に起こったことを振り返るとき、あまりにもニッチな、あまりにも瑣末な事象が浮かんできて眩暈がするというのが、偽らざる思いだ。いや、もちろん狭義の「文学性」について議論をすることが無駄とはいわない。しかし、前節に述べた問題に対してどれだけ効果的だったかといえば疑問だし、そもそも狭い枠組みのなかでさえ、きちんとした議論が行われたかいえば、そうでもなかった。むしろ議論を避けて、各人の立場から語るという「立場主義」が徹底されていた。そのような議論に対する憎悪は、先の原発をめぐる議論と通じるところさえある。そう、わたしはいま、「季語」をめぐる議論、「有」と「無」をめぐる、あの神学論争のことを思い浮かべている。

ことは、高柳克弘の第二句集『寒林』(2016年)に〈瓦礫の石抛る瓦礫に当たるのみ〉という句が収められていたことが発端だった。第40回俳人協会新人賞の候補作として選考の土俵にあげられたこの句集をめぐって、選考委員が選後評において、無季の句について「心から惜しまれる」「俳人協会の賞の対象範疇を逸脱している」という言葉を残したのである。問題なのは、その言葉の意味するところが、結局のところ、明らかにならないまま現在に至っている、ということだ。
まず大前提として、俳人協会という団体(わたしも加入している)は、「有季定型」と呼ばれる俳句を作る作家が圧倒的多数を占めている。つまり、17音という定型のなかに季語を入れて俳句を作る人が多い。外国語であればいざしらず、日本語という言語の内部においては、自由律や無季の俳句は作らない人が多いということだ。しかし、俳人協会定款(根本規則)では無季を排斥してはいないのである。筑紫磐井は、つぎのように見解を述べている。
俳人協会は有季の作家が圧倒的に多い。にもかかわらず、俳人協会定款(根本規則)では無季を排斥してはおらず、むしろ無季排除はその時々の会長の政策と見るべきかも知れない(俳人協会会員の林翔、岸田稚魚らはアンケートで無季容認と回答している)。例えば、松崎鉄之介会長時代は、有志作家による形で、俳句教科書出版社に対し無季俳句を教科書に載せないように強く要請している。
「俳壇観測188」『俳句四季』2018年9月号
もちろん、団体設立の由来を考えれば、「冷戦」下での圧力団体として機能した面もあっただろうが、かつてのような党派性は薄れ、俳人協会の設立と深くかかわっている角川書店(俳人協会の本部である俳句文学館は、角川源義の貢献が絶大に大きかった)が発行する「俳句」にも、現代俳句協会(無季・自由律容認)、伝統俳句協会(有季定型遵守)の作家が寄稿するようになって久しい。したがって、『寒林』をめぐる震災詠は、本来であれば、そのような「冷戦」以後の微温的な関係に一石を投じるべき問題だったにもかかわらず、今のところ公的な議論がなされた形跡がないのは、ある意味では「日本らしい」現象であるともいえそうだ。
仮にも、俳人協会が「無季」の句を認めないとして、それは「季語を入れても瓦礫の荒廃は詠める」という意思表明を意味するのか。おそらく違うだろう。そのような断定をできる根拠がないからだ。では、そもそも無季になるような「瓦礫の荒廃は詠むな(作っても発表するな)」ということなのか。つまり、協会としての俳句の定義に関わるものなのか。その可能性は高い。しかし、長く俳句をやってきて、目の前の荒廃――「季語」のない世界、情緒的共同体からかけ離れた現実――をまのあたりにしたとき、それでもなお、定型詩として表現をしたいという欲求に対し、禁止を求める根拠はどこに求められるのかと問うならば、これはなかなかむずかしい。本来、この問題はその点を検討すべきだったはずなのである。
あるいは、もっと世俗的、表層的に「(賞を獲りたいのなら)瓦礫であろうがなかろうが、無季の句は入れるな」ということだったのかもしれない。しかしそれならば、やはり応募要項にその点を明記しておかなければ、フェアではないだろう(石田波郷新人賞では、そのように明記してある)。しかも無季俳句をめぐっては、とある俳人が「無季の句を詠むなら脱退せよ」と(俳人協会所属の)同人誌から追われるという一件もあったので、どうも「もやもや」が残っているのだ。わたしの知らないところで解決してくれていることを望むばかりだが、もしそうならば、どなたかぜひ教えてほしい。
今さら蒸し返して恐縮だが、先の問題の当事者である大塚凱は、自身のnoteに「そもそも、俳人協会の会員は『有季定型のよい句』を目指して詠まなければならないのか?」と問題提起し、次のように答えている。なお文中の「櫂さん」は、長谷川櫂ではなく、櫂未知子のことを指す。
「有季定型が中心・重視される」というのは自明だし、組織として明確・明瞭な方針を打ち出すことは重要だ(第一、そういうもののない組織は組織の体をなさないだろう)。とはいえ、規則に無季禁止と明示されているわけでもない、協会賞・新人賞等の傾向と選評から推定されるだけの言から、理事たる櫂さんが「無季禁止」と我々会員に強いることには、僕はやっぱり納得できない。
そもそも俳人協会の設立に関わった西東三鬼の無季句はどうなってしまうのか(そのころには有季定型に回帰していたとはいえ)。っていうか、優れた有季定型一物仕立ての句って、限りなく無季俳句に漸近しませんか?
「「群青」2月号から考えた:絵は踏めない」(2018年2月21日更新)
大塚自身、この直後で「誤解を恐れずに言えば、俳人協会新人賞選考会での高柳克弘『寒林』の無季俳句問題の再燃に過ぎない」と述べているが、それはその通りだし、「内部でなんらかの協定があるのなら、公表したほうがみんな幸せだろうと思う」ということにも賛同する。つまり大袈裟に言えば、ここに露呈しているのは、議論を避けるという結果、生まれている「権力性」の問題と言ってもいい。かつて福島県知事が、政治の場から「強制退場」させられた一件とまったく同じことが、ここでは起こっているのである。これは、官僚制というシステムの孕んでいる、わりと社会に普遍的な問題である。
一方で、上記の問題と高柳の一件を完全に重ね合わせることができないのは、『寒林』の一句は、未曾有の震災の句だったということだ。つまり、空想や思想においてではなく、自然界のなかに季語の循環的世界を凌駕してしまうような光景があったとして、その「自然」をどのように詠むべきか、あるいは捉えるべきかという問いは、自然の詩である俳句にとっては、単に有季・無季というデジタルな違いを超えて、わりと根本的な問題だからである。ひとまず、この句についての高柳自身の言葉を引いておこう。
それは、編年体で編んでいたので、2011年の東日本大震災を詠んだ自分の句として、句集に入れておきたかったからです。外すほうが不自然でしょう。「文藝春秋」の「崩れし『おくのほそ道』をゆく」と題した企画で、芭蕉が旅で訪れた地が震災でどう破壊されたのか、単身訪ねてまわって、句をまじえたレポートを書いたんです。「瓦礫」の句は、名取川流域の閖上地区で、瓦礫の山の他は何もなくなっている大地を見て詠んだもので、季語を入れて作ったのでは、この荒廃を表現できないと思った。俳人協会が無季の句を認めていないというのは分かっていたんですけれどね。
「スピカ」2017年8月11日、高柳克弘インタビュー
句集に無季の句を入れたのは、作者の意図によるものであるが、そもそも、高柳が所属する「鷹」の歳時記(『季語別鷹俳句集』、ふらんす堂、2014年)には、「無季」の句が末尾に章立てられている。飯島晴子にも、〈南朝のこと書くもえぎ色の鉛筆なり〉のような無季の句があるし、後述の高野ムツオはある文章のなかで、無季か有季かなんてどうでもいい、という晴子の言葉を引いている――「俳句が、どうしても有季定型であるべきか、そうでなくともよいものか、考てみれば、そんなことは、わたしにはどうでもよいことである」(「てんとう虫だましのサンバ」大岡信編『定型の魔力』河出書房新社、1992年)。
しかし、そういうことではないのだ。問題は、季語的情緒、あるいは日常性とカタストロフの「相性の悪さ」にある。子規以前であれば、ナマの現実を詠むこと自体が文学的行為であるとは見做されなかったから、自然災害を詠んだ俳句は作られてこなかった(ただし、近代以降でも虚子の系譜は「極楽の文学」を主張し、そのようなリアリズムを徹底的に排除する)。一方で、俳句という文芸(あるいは花鳥風月的な価値観)が、いわばフィクショナルな装置としての(たとえば春先に咲くはずの「福寿草」を正月の季語とし、「ぶらんこ」を春の季語とするような)季語体系を超えて、ナマの現実の「写生」に接近しようとするとき、季語や定型といった形式性は批判にさらされることになる。これは何とも既視感のある光景ではないか。
3. 毎日がカタストロフ――新興俳句の再評価、「アウトロー俳句」、ネオ人間探求派、戦争回顧
〈3.11〉以後の俳句に起こったこととして、象徴的な事例をひとつあげておくなら、ひとつは神野紗希らが中心となって編纂された『新興俳句アンソロジー 何が新しかったのか』(2018年)が刊行されたことである。これは20代、30代の比較的若い年齢の俳人が、基本的には師系とは関係ないであろう新興俳句の(場合によってはほとんど知られていない)作家をコンパクトに論じた本であり、現代詩との関係や政治的文脈など論点は多岐にわたっている好著である。しかしこの流れで、別のポイントを解き明かしておけば、何よりもまず新興俳句は、〈都市的なもの〉ないしは〈近代的なもの〉をどう捉えるか、ということと深くかかわっている。この本の捉え方につて、わたしはこのように書いたことがある。
〈平成〉を通じて崩れていった「一億総中流」という共同幻想は、俳句業界でいえば、1970年代以降の「俳句ブーム」という幻想性と重なりあっている。具体的には、カルチャーセンターの隆盛、俳句入門本の出版などであるが、こうした言説のなかで、俳句におけるモダニズム運動である新興俳句は、戦後の前衛俳句の終焉とともに古臭いものとして見なされていった。しかし半世紀が経過して、バブル崩壊後の経済停滞がもたらした社会不安が再びそこに目を向けさせている――というのが、一般的な説明だろう。(中略)しかしこれが、「個性」ないしは「マイナーであること」への期待が改めて強まっている証しなのだとすれば、若干の留意が必要だろう。大衆化社会では、ニーチェの超人思想のような極私的な自己に近く努力がしばしば肯定されるが、こうした「自分探し」の言説と資本の論理の相性のよさは、〈平成〉を通じて反省的に学ぶことになったものだからだ。
「新興俳句とは何だったのか」『俳句四季』2019年8月号
つまり「前衛俳句」が退潮した(社会党の力が著しく後退した=新自由主義的な方向へ歩み出した)1970年代以降、俳句における「伝統」が復権し、いわば類想と定型の内部で「小さなズレ」を楽しむという言語ゲームが数の上ではメインストリームを占めてきたことへの反動が、その「内部」から起こってきたということである。そこに通低しているのは、自然ではなく人間あるいは社会(つまり〈都市的なもの〉)への興味である。安定的な生活を基盤として俳句という「虚」に遊ぶという行為は、生活の安定性に不安を抱えている人間にとってみれば、違和感の対象でしかない。そもそも、その描かれる世界のいったいどこにいまの〈わたし〉はいるのか、と。
今後どうなるわからない世界のなかで、信じられるのはいまの〈わたし〉だけである、というのは、まさにデカルトの方法的懐疑みたいなものだ。そもそも、季語的に循環する世界に対する猜疑心。それは、さきほどの高柳の瓦礫の句と同一の地平にあるといっていい(そもそも高柳は「虚」に遊ぶタイプの作家であることにも注意されたい)。この素朴なまでの現実主義は、どうしてこんなに世界は悲惨なのか、あるいは自分とそりが合わないのか、という個人的な嘆きに傾きやすい。
フィクションとしての自己、フィクションとしての季語への対抗馬としての「リアル」な、「ありのまま」の自己、そこでは当然、季語も等身大でなければならないが、「ありのまま」といえば、日本でも2014年に公開された『アナと雪の女王』のことを思い出す。この映画に対し、アイドル評論家の中森明夫は、主人公のエルザ(アナの姉)を雅子妃と重ね合わせていたことが印象的だ。この中森の論は『中央公論』に掲載を拒否されたことで話題にもなったが、しかし実際に、元号が令和にかわって公務に復帰したときの言語能力の高さには、誰もが舌を巻いたはずなのである。

この10年のうちに展開した「ありのまま」といえば、〈3.11〉以後のもうひとつの大きな事象として、北大路翼の「アウトロー俳句」がある。最新の句集では、過去のような露悪的な作は抑制されているが、第一句集『天使の涎』、2015年、邑書林)、第二句集『時の瘡蓋』(2017年、ふらんす堂)、『アウトロー俳句 新宿歌舞伎町俳句一家「屍派」』(編著、2017年、河出書房新社)、『生き抜くための俳句塾』(2019年3月、左右社)あたりまでは、いわばサバルタンとして可視化されていなかった人々を「アウトロー」というハードボイルド性とともに可視化し(しかし実際には女子高生や身体障害者などもいて多彩な面々だ)、社会的にも大きなインパクトを与えた。こういってよければ、彼らの生においては「毎日がカタストロフ」なのであり、それゆえに俳句は「生き抜くため」の道具なのである。
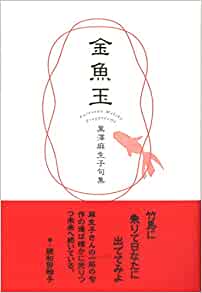
北大路翼は「人間探究派」といわれる加藤楸邨の師系であるが、もうひとり「ネオ人間探究派」とも呼ぶべき作家を挙げておくなら、黒澤麻生子にも触れておかなければならない。在宅高齢者を支えるケアマネージャーとしてはたらく作者の代表句、〈金魚玉むかしのことは生き生きと〉は、高齢者もまた劇的に事態が好転することのない「終わりなき日常」のなかで刺激を求めつづけていることを描く。そういえば現在、最高齢の俳人のひとりである深見けん二が、夫婦で施設に入居して空想の吟行とともに「むかしのことは生き生きと」吟じていることを思うと、ここにも「生き抜く道具」としての俳句という側面が見出しうる。
このように戦争の影がちらつく新興俳句、あるいは「終わりなき日常」のなかで死と向き合う「ネオ人間探求派」という傾向とともに、もうひとつ指摘しておかなければならないのは、戦争体験の振り返りが顕著になったことだ。昨年、亡くなった小原啄葉(「樹氷」名誉主宰)は、2012年に『黒い浪』(角川書店)を刊行し、どこか自分の過去と向き合うように、瓦礫の中で戦争体験を語り始めたのだった。戦場で人の肉を食べたかもしれないこと、国際法に違反する化学兵器の製造にも関与していたこと、など。多くの人々が一斉に亡くなり、東北の一部が瓦礫の街と化してしまったことが、どこか戦争体験を呼び起こしたのである。小原が公的にそれを語ったのは、『文藝春秋』誌上のことで、いまから見ればまだ震災「直後」であった2012年8月のことだった(「大震災と中国戦線を俳句に託して」)。栗林浩によるインタビューは、一部が彼のブログで閲覧できるようになっている(「昭和・平成を詠んで(1) 今、書かねばならないことー小原啄葉」)。また後述の菊田島椿による「私信」は「週刊俳句」で読むことができる(「小原啄葉句集『黒い浪』恵贈への礼状」)。
つらなれる目刺もおなじ日に死せる 小原啄葉
帰る雁死体は陸へ戻りたく
時の日の時計をはづす遺体かな
冒頭で、安倍政権に緊急提言を提出した有馬朗人も同様に戦争について語っている。有馬のロングインタビューが読売新聞に掲載されたのは、振り返ってみれば、急逝する4か月前のことであった。「終わらぬ夏<5>迫る戦闘機 顔が見えた…物理学者・俳人 有馬朗人さん(89)」と題されたインタビューのなかで、有馬朗人が語るのは、浜名湖の近く、飛行機部品の工場に勤労動員されていたときのこと、度重なる空襲を受けたという敗戦直前のことだ。海軍兵学校予科を教師から勧められるも、ラジオ作りが大好きだった有馬少年は「科学者になり国のために働きたい」と断り続けたという。一方で戦後の授業は、墨塗りをする教科書すらなく、奥の細道などを暗記しながら進んでいったとも。新型コロナウイルスで社会が混乱するなかでも、新入生に向けて「白熱授業」を展開していたという有馬のひたむきさには、胸が打たれるものがある。ただし、「原子力の平和利用を進めるべき」という意見は、この時点では変わらなかったようだ。
4. 震災詠に季語は「邪魔」か?――無季をめぐる誤解
このような俳句は原則としてみな、〈わたし〉が生きていること、そこにいたことを証言するものとしてある。いわばアリバイとしての俳句であり、信仰告白としての俳句である。読者は、句集に収められた句を通じてフィクショナルに作者を想像する。あるいは、そのフィクショナルな作者が見た景色や体験したことを想像する。それはわたしたちが小説を読むときと同じように、日本語に特徴的な視点の成り代わりを通じたアイデンティフィケーションによって成立しているようなコミュニケーションである。
小難しいことはさておき、要は、俳句が〈いま〉の〈わたし〉を詠むものであるという規範性が強くなっているということだ。そうなると、先ほど言ったように、一回的な経験が大事にされ、ことばは季語という約束事、場合によっては定型という約束事から、逸脱していく。たとえば、高柳克弘の瓦礫の句は、いうまでもなく日常の延長にある体験ではない。そこには日常との断絶があるのであり、だからこそ新鮮であり、言葉にしなければならないという思いが湧き上がってきたのだろう。
それはけっしてめずらしいことではない。たとえば、〈3.11〉をきっかけとして、明らかなかたちで社会的評価を獲得した俳句作家に高野ムツオがいるが、その高野が震災当日のことを詠んだ句のなかに、〈四肢へ地震ただ轟轟と轟轟と〉〈天地は一つたらんと大地震〉〈地震の闇百足となりて歩むべし〉などがある。とくに一句目は人口に膾炙している。三句目の「百足」が季語として扱われるかどうかには議論があろうが、三月のことだから、作者自身は季語としては使っていない。この点について、たとえば一句目の高野自身による「絵解き」はこんな具合である。
地震が起きた直後、仙台駅の句です。句の形になったのは約一週間後でしょうか。念頭にあったのは季節感はいるだろうか?ということです。「春の地震」とか「春の津波」など、そんなよそよそしいことは言えません。季語はありませんが、季節感は邪魔をします、地震そのもの、津波そのものを俳句にしようとしました。
第35回現代俳句講座(講演:高野ムツオ)後編(2011年6月11日)
伝統俳句系の結社では「季題」といわれるように、俳句における季語は「題=モチーフ」である。主題ではないのだから、必ずしも季語を入れて震災を詠むことが原理的に不可能であるというわけではないだろうが、しかし長年かけて取捨選択されてきた季語は、このような「非日常」は想定していないがゆえに、困難さは否定しがたい。もっぱら「日常」のために使われてきた情緒的な語彙をもって「非日常」を語ることの難かしさ。それは、和食中心の生活のために買い溜めてある食品で、洒落たフランス料理をつくる困難さに似ている。
私が無季俳句に関心を持ったのは十代である。四十歳で上梓した第一句集『陽炎の家』一八六句の前半、三十二歳までの作品のほとんどは無季であった。季語の情緒が作者の実感以上のものを表現してしまうのではないかと怖れてもいた頃だった。無垢の感受が伝わる句を作りたかった。そのわずかな可能性を大震災の時も持ち続けていた。
(「シリーズ季語を考える シリーズの終わりに」『俳句あるふぁ』2020年冬号、141頁)
高野ムツオの「詩」において重要なのは、彼自身という「個」であり、その肉体を通じて得られる「無垢の感受」である。それは徹底的に主観的なものであり、ヴィトゲンシュタイン的にいえば「私的言語」、つまり、けっして言葉では伝えることができないとされるものかもしれない。いずれにしても、俳句においては季語という共同性を「殺す」ことが、「私的言語」に接近するためのひとつのアリバイとなりうる。いいかえれば、それは季語の再解釈と、自身の体験、イメージを通じて句を読解していく「読み」の共同体とは異なる共同体をつくりあげる、いわばヒッピー的な(?)発想である。
では逆になぜ、有季定型の俳人は「有季」にこだわるのか。それはゲームの「ルール」だからである。それはなぜ野球選手はバットにこだわるのか、とか棋士は二歩にこだわるのかというのと同じである。二歩をしたら「負け」になるし、バットをもたなければ打席には立てない。これは高野が季語は「決まりや約束ではない。(…)季語以外にも重要な俳句の言葉は存在する」と述べているのと、実に対照的な考え方である(同書、138頁)。
ただし実際のところ、有季定型の俳人は「季語を入れる」だけでは満足しない。つまり、季感が大事だとか、本意が大事だとか、比喩で使ってはいけないとか、季語の使い方にも細かい注文がついてくる。ということは、「季語をどう扱うか」を考えるのが「有季定型」の真の意味ということだ。とすれば、無季俳句は「季語をどう扱うか」を考えていない、ということになるだろうか。先の高柳克弘の例は、季語のことを考えたうえでの無季だったのではないか。
高柳が〈瓦礫の石抛る瓦礫に当たるのみ〉という句を作ったとき、瓦礫の石の周りには、風も光もあったことだろう。それは言葉にはなっていないが、17音の外側に排除されることによって、この一句が成立している。とすれば、この句はじつは「季語のない有季定型」なのである。オール・オア・ナッシングで考えるから、なんだかややこしいことになる。神学論争になる。
しかし、「季語のない有季定型」としては捉えきれない17音詩もある。それは川柳であり、標語であり、童謡の歌詞であったりするが、そのひとつが俗に言う「無季俳句」から「季語のない有季定型」を取り除いたものがあるとは言えないか。たとえば、以下のような句である。
フクシマの弔旗でありぬ黒牛は 渡辺誠一郎
冤霊に列す原発関連死 正木ゆう子
燃え残るプルトニウムと傘の骨 曾根 毅
現実をテーマとして目の前に〈見えるもの〉を描こうとするとはちがって――正岡子規が唱導した「写生」は散文のロジックであり、季節感などとはいっさい関係がない。それは〈電線にあるくるくるとした部分〉(上田信治)は十分に写生的だが、季語はない――、〈見えないもの〉を描こうとすれば、高野というように季語は「邪魔」になる。季語は、存在している現実物であるからだ。これらは、想像的な現実(観念やイマージュ)を扱っているという点で、上で見たような「ありのまま」を描いた無季俳句とは本質的に異なっているのだ。
わたしたちがもっとも〈見えないもの〉とは、なんだろうか。それは、「死」だ。あるいは、死の予感(不安)だ。死、死者、あるいは不安やメランコリーが主題になるとき、季語が入っているかどうかは重要な問題ではない。情緒的共同体を離れて、〈個〉が発するようなシュールレアリスティックな17音の定型詩になる。
現代詩・紫雲英・眩暈・原子力 神野紗希
このような句の場合に「有季定型」の俳人は、「紫雲英」という季語が入っているから問題ない、とすんなり引き下がるとは限らない。「げん」からはじまる四つの言葉遊びのなかで読み手に起こっているのは、イマージュの遊びである。そしてその遊びのなかで、黙示録的な、あるいは幻惑的な不安が立ち上がってくる。これは、先ほどの高柳のような「季語のない有季定型」と対照するならば、「季語のある無季定型」なのではないだろうか。
しつこく繰り返すが、重要な分かれ目は、〈見えないもの〉を描くか、〈見えるもの〉を描くか、もうひとつは回帰する〈日常〉を描くか、一回的な〈非日常〉を描くかということである。震災がもたらしたものは、一回性の〈非日常〉であった。それを描こうとすれば、さらに〈見えないもの〉を描くか、〈見えるもの〉を描くかという選択が待っている。あるいは、〈日常〉を描きつづけるという選択肢がある。
季語は〈見えるもの〉であり、かつ〈日常〉である。だから基本的には、〈非日常〉を描こうとすれば、季語が不協和音を響かせるような句、あるいは逆にとても凡庸な観念句にならざるをえない。震災や火災や洪水はこれまでにも数多くあったにもかかわらず、俳句のなかではそれが描かれてこなかったのは、そういう理由だろう。しかし、それでもなお、破局の予感や底無しの不安を17音で表現したいという人間の欲望は、否定することはできない。誰かに伝えたいという欲望は、俳句のみならずあらゆる表現の基本にあるものだろう。
そのような形式を「俳句」と呼んでいいかどうかは議論の分かれるところだが、しかしカタストロフィをどう表象するかという問いを前にしたとき、季語があるかないかなんて表面的な話は、飯島春子ではないけれど、はっきりいってどうでもいいのである。といいながら、長々と書いてしまったわたしは「ムキ」にはなっているのかもしれない、という冗談はさておくとして。
5. 喪と忘却――正しく〈忘れる〉ために
正直にいって、現実は重苦しい。お金のこと、メンタルのこと、人間関係のこと、家族のこと、性のこと、いろいろ考えなければならない。そのうえで、政治のこと、住む街のこと、海外で起こったテロのこと、気候変動のことを考えなければならない。本当に重苦しいことばかりだ。
もっとも、それは今にはじまったことではない。その時代には時代の「重苦しさ」があった。なにせ虚子が「花鳥諷詠」を主張した時期は、日本が戦争に進もうとしていたまさにそんな時期だったのである。重苦しいからこそ、軽くいきたい、という考え方だってある。昔からそれはあったし、今もあるだろう。
しかし実際に、大切な人を失ったときは、どうしたって「重苦しさ」はのしかかってくる。日常的にも、わたしたちは死者の生前を偲び、弔い、そして喪に服さなければならない。
これ――この「重さ」――は、人間にとって大切な「仕事」であり、しばしば「喪の作業」や「喪の仕事」などと呼ばれるものである(フロイト「喪とメランコリー」)。もしその作業が不徹底であれば、心の遺恨を残すことになりかねず、表面的に「忘却」したとしても心のなかに「もやもや」が残ってしまう。その意味で、わたしたちは「正しく〈忘れる〉」努力をしなければならない。
「喪の作業」のプロセスを簡単に説明すれば、以下の四つの段階にまとめることができるだろう。すなわち、感覚や情緒が低下し、危機的状況に陥る――愛着の強さの反動から、後悔や罪悪感など、ネガティブな感情によって現実の否認を行う――事実を受け入れながらも絶望し、孤独になる――あたらしい環境のなかで感情が回復し、物事を肯定的に捉え始める――という、さまざまな物語が辿る順路である。つまり、時間の経過は必要だが、わたしたちには死を受け入れ、そして生活を回復するための「物語」が必要だということだ。
すべての死は、計画的に予定通りやってくるわけではない。交通事故、心臓発作、殺人のように、不意に訪れる死もある。それらと震災による死を分け隔てるものは、基本的にはない。
双子なら同じ死顔桃の花 照井翠
だがこれは、まだ誰も読んだことのない「物語」だった。小さな小さな物語であるが、しかし双子の遺体が同時に安置されているという状況は、それが事実かどうかにかかわりなく、震災前には到来しなかった想像力=現実だったということだ。
もちろん、そこに「桃の花」を配することによって、双子がいたいけな少女であることが思われることの了解可能性を指摘することはたやすい。しかしこの句に対し「桃の花」以外の季語を提案することもまた、それ自体として倫理な問いを含むだろうし、何よりもこの句は読者に津波禍のいたましさを想像させ、被災していない人までも「喪の作業」のスタートラインに立たせたという点は、否定しえないだろう。
関悦史は、この句が収められた句集『龍宮』の達成と限界を、「大災害の表現不能性に直面することではなく、涙を誘う程度には理解・受容の可能なものへと震災をスケールダウンしていくことにひたすら奉仕して」いる点に求めた(「俳句形式の胸で泣く」「週刊俳句」2012年12月16日更新)。おそらく、「アウシュヴィッツ以後、詩は書くことは野蛮である」というアドルノの文句や、ランズマンの『ショアー』における「表象不可能性」の議論を前提としているものなのだろうが、しかし『龍宮』に収められた句を「泣ける俳句」というコンテンツに「スケールダウン」するのは、「喪の作業」のプロセスをあまりにも消費文化的に捉えすぎているように思われる。
そもそも一冊の句集のなかで、関がいう「表現の臨界を越えた地震・津波・原発事故という三重の超巨大災害をそのままのスケールのものとして」描くというのは、どういう事態を指しているのか、わたしにはうまく理解できない。はたしてそれは可能なのだろうか。もちろん、表象は一種の暴力である。しかしだからといって、「表象不可能性」に開き直ることが「正義」なのではないだろう。少なくともわたしの考えでは、季語や定型という「制度」を破壊すること、了解可能性を否定すること、沈黙に徹することなどが、逆に「文明的」なふるまいだとは必ずしも思われない。
重要なのはまず、この作者が津波の甚大な被害に遭った地区で生活しながら、俳句を詠みつづけたという事実そのものである。それは彼女自身がこの句集を「鎮魂句集」であるというとおり、まずもって心に傷を負った人々に対する「喪の作業」だったからである。実際に震災後、照井は手作りのホチキス止めの句集を支援者などに配布して回ったという。しかしそれは、支援者にとってというよりもむしろ、照井本人にとって不可欠な作業だったのかもしれない。それはけっしてハートウォーミングな「泣ける話」などではない。ここでもまた、俳句は「生き抜く道具」なのである。
忘れてはならないことは、照井が想定しているのは遠く離れた「俳壇」などではなく、まずは目の前の破局的な経験を言葉にできずにいる「ふつうの人びと」だったということである――『龍宮』が蛇笏賞の最終選考に残ったとはいえ、である。そのような仕方で俳句が誰かに差し出されるということは、そうそうあることではない。そのことをまず前提にしなければならない。つまり、わたしたちは「誰に向けて」俳句を書くのか、ということだ。俳壇に対して、ましてや俳句史に対して、書いているのでは、ない。
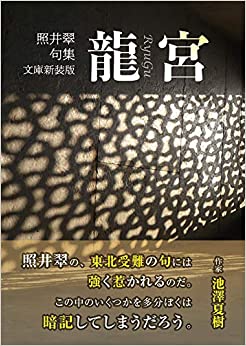
照井が描く蕭条たる景は、加藤楸邨のひんやりとした戦争詠と通いながらも、情動の崩壊をぎりぎりのところで回避しながらも、しかし回復の難しさを「物語」として提示している。先のプロセスでいえば、現実の否認であり、とくに発災直後の句は生々しい現実が、俳句の虚と混じり合っているともいえる。それはしばしば、内面告白のための口語体として表象され、俳句表現(=言葉の「芸」)にぎりぎりのところで踏みとどまっているようでもある。
在るはずの町眼裏に雪が降る
喉奥の泥は乾かずランドセル
三・一一神はゐないかとても小さい
春は壁乗り越えなくていいですか
照井が今年1月に刊行した『泥天使』は、「震災十年目の鎮魂句集」として上梓された第六句集だが、海外詠・コロナ詠を後半に置きながらも、全体としては津波禍のことを、とりわけ「泥」をライトモティーフとして、編んだ句集である(同時に版元のコールサック社からは絶版になっていた『龍宮』が文庫化された)。時系列を保っていた『龍宮』とはやや対照的なように思われるのが、『泥天使』においては、現実の時間がたびたび神話的な、宗教的な、あるいはカタストロフの記憶と結びつき、作者の死生観を色濃く漂わせている点である。ここでは、明らかに俳句が差し出されている相手が、『龍宮』とは変化している。
春の底磔のまま漂流す
瓦礫より舌伸べ雪を舐めたるか
花置かばいづこも墓場魂祭
ガス室の冬天の穴閉ぢきらる
死なば泥三月十日十一日
肺白く芽吹き人類滅亡す
死ねば天国に行くのではない。地獄に行くのでもない――「泥」になるだけである――というのが、照井の提示する世界観だ。そこには、泥と化した世界というものの正体を言葉で再構築していこうとする意思が感じられる。いつか人類が滅亡する日を夢見ながら、アダムのように泥から生まれ、やがて土に還りゆく自分を想像しつつ、泥になった人々を慈しむ――句集そのものが、ひとつの死生観の提示になっているという点で、『泥天使』という句集がまず差し向けられているのは、まず照井自身なのだともいえるだろう。
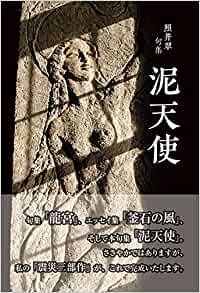
照井の「喪の作業」は、わかりやすくいえば、「死を日常化する」ということであるだろう。死はそこにある。照井なりのメメント・モリ(=「死を想え」)である。そのため震災の経験は、人間の死という体験一般へと敷衍され、虐殺や疫病という苦しみへとリンクしていく。正直にいえば、わたし自身はその「加速度」についていくのがかなり難しかった。しかし言われてみればなるほど、現在の日本社会にはあまりにも難題が多すぎて、「喪の作業」は震災というフレームのみで完結するような話ではなくなりつつあるのかもしれない。
6. 「なりすまし」のススメ――北条裕子「美しい顔」から考える
しかし、照井のような壮絶な体験をしていなければ、俳句を作る「権利」はないのだろうか。あの日、東京に住んでいた人々――福島での発電を享受していた人々――は「帰宅難民」となり、しばらく「計画停電」を余儀なくされたし、テレビから流れる警報に眠れなくなったりしただろう。被災地からの距離は、そのまま実害の程度の差になるとはいえ、東京に住んでいる人々もある程度は「被災者」だった。
しかしその「被災者」が、〈わたし〉の〈いま〉を詠もうとすれば、俳句としてはどうしたって「嘆き」に陥りやすい。代表的な例を挙げれば、正木ゆう子の句集『羽羽』に収められた次のような句がすぐに思い浮かぶ。
真炎天原子炉も火に苦しむか
鼻綱なき自由もあはれ爆心地
断崖に身を反りてわが列島は
セシウムのきらめく水を汲みたると
絶滅のこと伝はらず人類忌
ビニールシートこれをしも青といふか春
予震予震本震余震余震予震
冤霊に列す原発関連死
正木ゆう子の震災以後をテーマとした句は、「あはれ」「伝はらず」といった主情的な措辞や「か」という呼びかけを特徴としており、一言でいえば「憂い」あるいは「嘆き」の歌となっている。あるいは、メランコリーとしての俳句である。つまり、陰鬱(メランコリック)という気分が漂っていることが、これらの俳句ではポイントになっている。社会的なメランコリーの表明の背景には、もちろん災厄の外側で俳句をつくりつづけること、諷詠しつづけることへの抵抗感があったかもしれない。
このような行為は、あの当時のありふれた気分を「代弁」することでもあったはずだ。いったい日本は、世界はどうなってしまうのか。そのような絶望は、ある種の「空気」であった。しかし、嘆きを俳句にするということの意味は、たんに悲観を増幅させること以外の役にたったのかどうか。「嘆く」ことによって社会的に「正しい」振る舞いをするということ――震災直後に反射神経的に詠まれた震災詠・原発詠の多くは、そのような批判を免れない。それが最初に差し向けられたのは、長谷川櫂の『震災歌集』『震災句集』だったはずだが、皮肉にも正木ゆう子の蛇笏賞受賞時の選考委員のひとりが、長谷川であった(ついでにいえば、『龍宮』を蛇笏賞にひとり推しつづけたのも彼であった)。

上記の句のなかでいえば、〈セシウムのきらめく水を汲みたると〉という句が唯一、そのような嘆きのモードから離れている。川などのセシウム量を計測するために水を汲むという場面を読むことで、「無=症状」の水のきらめきが、悲しくも美しいという事実を読者は知るからだ。「汲みたると」と伝聞形式にしたのは、たとえば「汲みにけり」だと、主体が作者自身であると誤って判断されかねないことを危惧したものだろう。しかしこの句を読むとき、作者も読者も調査員や作業員の姿を思い浮かべるのだから、いっそのこと伝聞を捨ててしまうという手もあったかもしれない。
ここには実は微妙な問題がふくまれている。それは、作者が作中主体とイコールであるという通念と深くかかわるものだ。俳句が日常の現実を素材とする以上、その通念は免れることはおそらくできず、そうではない俳句がいくら可能であったとしても、「作者と作中主体は別ものである」というテーゼを原理化することはおそらくできない。そのときに出てくるのが、最初の問い――「照井のような壮絶な体験をしていなければ、俳句を作る「権利」はないのだろうか」である。この問いを前に思い出したいのは、「群像新人文学賞」を受賞作した北条裕子の小説「美しい顔」のことだ。
この小説は、母を津波で失った女子高生と弟の物語である。作者は被災地に一度も足を運ばず、ノンフィクションのルポなどを参照しながら、執筆したことで少なからず話題になったことは記憶にもあたらしい。受賞後、初出で明らかにしていなかった参照元の存在が発覚して謝罪と訂正を余儀なくされたものの、それでも驚くべきは、この若い作者が、直接的な経験の外部でおそるべきディティールの作品を執筆しえた、ということだ。
経験が大事であることは、俳句でも小説でも同じである。しかし、当事者固有の(究極的に個人的な)経験ばかりを重視することは、了解不可能性という檻のなかに閉じこもることになり、相互的なコミュニケーションは困難なものとなるというリスクを生んでしまう。また何よりもまず、当事者であることが、ただちによき表現者であることは意味しない。当事者であるかどうかは、言語のレベルにおいては、経験によって推し量られるべきではないという見方も、十分に可能なのである。大事なのは、「震災の辛さは被災者にしかわからない」と開き直る(=閉じこもる)のではなく、「震災の苦しみを想像的に共感する」ことなのではないか。
テレビやYoutubeでしか津波や地震を見なかった人も、それを俳句や短歌にしてもいい。被災地を訪ねなかった作家も、それを作品に描いてもいい。そしてそのようにして生み出された作品を、被災地の人も、それ以外の地域にいる人も、読めばよいと思う。
日比嘉高「「美しい顔」の「剽窃」問題から私たちが考えてみるべきこと」2018年7月11日更新
ここで日比嘉高が述べているのは、作者と作品を切り離して、純粋に作品の言葉から立ち上がるものを味わうという鑑賞のススメである。この点については、江戸時代に生きているわけでもないのに「絵踏」を詠まなければならず、場合によっては見たことも聞いたこともない植物や祭事について、さも体験した「かのように」詠むことを日常としている俳人には、それほど難しくない作業のはずだ。
にもかかわらず、このような議論がなされてこなかったのは、なぜなのか? それを考えるには、「作者=作中主体」という共同幻想が、なぜかくも強固であるのかを考える必要があるが、それは本論の射程を越え出ている。「震災の苦しみを想像的に共感する」よりは、あくまで作者個人の「立場」からオリジナルな言葉を紡ごうという近代の軛からいまだ脱却できていない、ということにいなるのかもしれない。それは、客観的で論理的な意見を出し合って、たがいに異なる意見の持ち主が「議論」するという手続きが苦手な、わたしたちの立場主義と、おそらくつながっているものかも、しれない。
今年、東京新聞は2015年から2017年にかけて一面掲載していた「平和の俳句」という企画を「東日本大震災10年」という枠組みで復活させた。これはもともと、『想像ラジオ』の著者でもあるいとうせいこうと、金子兜太が行っていた企画だが、兜太の死後(2018年)、黒田杏子があとを継ぐことになって、現在に至っている。ちなみに黒田杏子は、福島県文学賞俳句部門の選者のひとりである。
たとえば、北條の小説のようなケースを、審査員がどのように捉えるかは、とても気になるところだ。高校生が壮絶な戦争体験を語る俳句を出して入賞したとき、審査員は手放しでその想像力を称賛するのだろうか。いわば、「ネオ戦火眺望俳句」である。この企画で「なりすまし」を禁じているわけではない。俳人に問うてみたいのは、ヒトラーを主人公にして小説を書くことがそれ自体としては何の問題もないように、体験の外部を詳細に描く想像力もまた文学というの「芸」の力なのではないかということだ。
もし、それが俳句では倫理的に許されないのだとしたら、それは「結局のところ、人のことはわからない」という諦念に結びつきはしないか。先の当事者性の問題、立場主義の問題である。「自分は自分、人は人だから」という自他の切り離しは、勝手に他人の句に自分を重ねて解釈する俳句の読みの地平とは、むしろ逆をいくものではないのか。そうであれば、〈わたし〉ではなく〈ほかの誰かであったかもしれないわたし〉を俳句で詠むことは、そんなにいけないこと、なのだろうか。
7. 俳句大会は「広告」ではない
先ほど触れた、東京新聞「平和の俳句」は、また別の問題を含んでいる。それは、俳句が特定の思想や信条の、あるいは考え方の「広告」となっているのではないかということだ。よく知られているように、「平和の俳句」はいわゆる「9条俳句」問題に端を発して作られたものだ。
当時<梅雨空に「九条守れ」の女性デモ>という俳句が、さいたま市の公民館の月報に掲載を拒否された「九条俳句」問題を、2人は戦前の新興俳句運動に対する弾圧事件に重ねました。戦争に向かう時代の空気に抗おうと呼び掛けたのが「平和の俳句」でした。
わたしたちには思想・信条の自由、表現の自由が保障されているのだから、公共の福祉を害さない限りにおいて、いかなる政治的主張をもっていても不利益を被ることはない。実際にこの問題は2018年に最高裁で、さいたま市の違法性が確定している。そのことに異論はもちろんない。
だが、先の「梅雨空」の句を秀句と見なすかどうかは、俳句観の違いによる。この季語は、たとえば、先行きの見えない暗い時代の暗喩であるとも読めるため、それほど解釈に困ることはない。この「わかりやすさ」を川柳的であると非難する人がそれなりにいるだろうことは、たやすく想像される。
しかしこの句を「平和の俳句」という枠にはめてみたとき、「「九条守れ」の女性デモ」を俳句の素材として選んだそのこと自体が、作者の政治意識を物語りはじめてしまう。この句の作者が、「経済に戦争は必要だ」という主張を持ち合わせているとは、とても考えられないからである。屁理屈をこねれば、「経済に戦争は必要だ」という主張の持ち主には、それが地球全体を豊かにして、平和をもたらすと考える人がいてもおかしくはない。しかし、〈梅雨晴に最新ステルス戦闘機〉は、おそらく「平和の俳句」としては認められないだろう。たとえ作者が、「平和主義者」であったとしても、である。
人つねに平和を憎み春の泥 関悦史
わたしが「平和」という言葉で思い出すのは、戦間期ドイツの人々が「平和」を望んでいたということだ。つまり、歴史を見れば、「平和主義者が戦争を引き起こす」という側面が少なからずある、ということである。この発想を最初に知ったのはたしか高校のときに小室直樹を読んだときだったが、平和を望むのは個人の信条であって仕事ではない。しかし戦争は国際紛争の解決手段であり、「仕事」である。しかも、その内側に「平和」を含んでいる。戦争と平和はそれほど単純な対立ではないということ。だからこそ、平和主義運動が全土に広まったドイツが(ナチスでさえ当初は「平和」を主張していた)、好戦主義に一転したように、「平和」という言葉には危うさが含まれている。
「反戦平和」という左派的主張はただちに「反原発」へと直情的になだれ込んでいった。わたし個人としては、それほどそのような主張から遠いところにいるとは思っていないが、しかし客観的にみれば、そのような政治的主張の枠組みのなかで開かれる「平和の俳句」は、言うまでもなく、きわめてイデオロギー的を帯びている。それは、同じ思想の持ち主がコミュニティを形成するための有効な手段とはなるが、しかしその外部との交流は閉ざされているのではないか。なぜなら、コミュニティのなかでは、戦争や原発を必要としている人々や国家とは、いつまでたっても出会うことがないからである。この企画自体が、季語と同じように共感による情緒的な共同体をかたちづくってしまっている。
2021年3月1日
暁に東北に向き手を合わす 白沢弘介(79) 岐阜県各務原市
<いとうせいこう>まことに私たちの思いはこれだ。非当事者であっても祈ることはできる。耳を傾け、その先に行動することがある。
2021年3月2日
季語になぞなりたくなかった原発忌 曳地トシ(62) 埼玉県飯能市
<黒田杏子(ももこ)>広島忌・長崎忌・終戦日などは季語として定着。福島忌・原発忌も年々例句が増えています。安全神話崩壊の福島忌。
こんな具合に、3月1日からはじまった「平和の俳句」は、いまも東京新聞史上でつづいている。「私たちの思いはこれだ」と第一回目から言ってしまえるその「大胆さ」に、わたしは結構驚いている。一方で、黒田杏子の書きぶりは、「福島忌・原発忌」という季語が普及することが、すなわち「平和のためになる」と言わんばかりだが、果たして本当にそうだろうか。
しかし、それとは比べ物にならないほど「広告的」な俳句大会を見つけてしまった。復興庁が主催している「福島復興俳句コンテスト」である。こちらも「テーマ」が指定されているが、より限定的である。衝撃的なことが書かれているので、「閲覧注意」である。
テーマ「福島の農林水産物・観光地の魅力」
東日本大震災の発災、東京電力福島第一原子力発電所の事故から、令和3年3月で10年を迎えます。いまなお一部で福島に関する風評が残る中、福島の農林水産物・観光地を応援するため、その魅力を日本全国に伝えることができる句を募集いたします。
一言で言えば、ここで求められているのは「標語・コピー」のような句である。コンテストなんだから、と大目に見るべきという意見もあるだろう。だが、事実として、福島の農林水産物(桃・りんご・きゅうりなど)や観光地の魅力を伝えるものでなければならないというのだから、俳句の衣裳をまとったキャッチコピーの募集なのである。応募者と選者の「良心」に賭けるほかない。
そもそも福島に「観光地」など、そうたくさんあるわけではない。文化的施設であれば、鶴ヶ城や大内宿が浮かぶが、これらがあるのは会津地方であり、県内でも震災とおおよそ関係がない。猪苗代湖も位置的に微妙である。本当に、温泉かスキー場のような養護施設くらいしかないのだ。沿岸地域には、「スパリゾートハワイアンズ」と「アクアマリンふくしま」は、あるけれど、というのは福島県人の嘆きであるけれど、問題なのはこのように「文化的後背地」であるということそのものなのである(演劇を生業にしているものとしては、たとえば演劇の国立大学でも作ってほしいと思うのだが……)。
しかしさらに驚くのは、句の選び方である。応募要項には「選者による審査を基に、復興大臣、復興副大臣が参加した審査会にて、福島の魅力をより伝えるものを入賞作品として決定いたします」とあり、つまるところ、選者の審査は「予備選」であり、そこから入賞作を選ぶのは、俳句について造詣が深いわけでもない「復興大臣、復興副大臣」であることが示唆されているのである。ちなみに「選者」は「プレバト!!」でお茶の間のアイドルとなった夏井いつきと、「ふくしま」50句で角川俳句賞を受賞した永瀬十悟である。
そもそもの話だが、農業県福島の風評被害への懸念は当初よりきわめて大きく(当然である)、2011年以来、「最強の安全検査体制」を確保することで、信頼の回復に努めてきたはずだ。「緊急時環境放射線モニタリング調査」を行ってきた福島県農業総合センター(郡山市郊外)の社員は昨年末の記事のなかでこう証言している。
「事故直後は全然売れなかったが、だんだん安全性への信頼を取り戻している実感はある。科学的でなく、観念的に嫌だと思っている人が10%はいる。そうした人たちの理解を無理に求めるより、分かってくれる人たちに、福島県産品を安心して食べてもらう努力を続けたい」(草野部長)
野島剛「福島「風評被害」打破の最前線は「最強の安全検査体制」」2020年12月27日更新
このような現状のなかで、「福島復興俳句コンテスト」は何を達成しようとしているのか。「福島県産の農産物は安全だ」というのは科学的事実である(それでも不安だ、という気持ちはわからないではないが、この10年で各国の輸入制限は着実に解除されてきた)。しかもこのコンテストは、日本語圏のなかの話であるから、課題となっている台湾・韓国・中国ら5か国の輸入解禁には、それほど有益であるとも思われない。それにコロナ禍においては、観光地の魅力をアピールしたところで、別の問題が残っているだろう。
東京新聞の「平和の俳句」にせよ、この「復興俳句コンテスト」にせよ、共通する問題点は、俳句よりも上位の目的が設定されている、ということだ。もちろん、俳句の特色のひとつが「挨拶性」に見出される以上、そのようなメッセージ性は俳句から除外することはできない。地域の魅力を伝える絵葉書のような俳句も、平和を希求する善意の俳句も、やはり形式的にみれば俳句である。だが、その内容に目をむけてみれば、意味内容が一元的なメッセージへと還元されてしまう句は、一般的には秀句であるとはいえないだろう。重要なのは、このような大会が開催されたという「事実」であり、それは主催者の活動実績に資するだけである。参加者にも読者にも利益とはならないのだ。
その意味で、2016年に第一回がはじまり、今年で第6回を迎える「復興いわき海の俳句大会」は理想的な大会運営を行なっている点が注目に値する。

比較的小規模な大会ではあるが、福島の沿岸地区(浜通り)に関心を集め、人の流れを作りだすという意味でも、具体的な貢献をしている。この企画には土肥あき子、中田尚子と「絵空」を立ち上げた山崎祐子(いわき市出身)が立ち上げに関わっており、20年以上にわたって東北沿岸地域で開催されてきた「気仙沼海の俳句全国大会」を理念的に継承したものである。昨年は新型コロナウイルス感染対策のために、事前投句のみとなったが、例年はここに当日の俳句大会が加わる。
蝶の羽化見とどけ授業再開す 千葉喬子
着ぶくれてシーラカンスに会ひに行く 西山逢美
原子炉の沖はるかより梅雨の雷 山名美千子
子が父となりふくしまは豊の秋 伊東澄子
母の日の波打ち際に来てをりぬ 森羽久衣
ヨツト行く海一枚を切り分けて 赤松曙子
ここには、〈震災〉を示す言葉はそれほど多く見られない。よくも悪くも「ふつうの俳句」が並ぶ。こう言ってよければ、〈海〉を詠む句に福島かどうかである必要もないのだ。入選句のなかに「沖縄忌」の句が入っていたりもするのが面白い(さりとて強い政治的主張があるわけではない)。それぞれがそれぞれの生活を、海を、日常を詠むことによって、読者と「どこかにある現実」を分かち合う。そしてこうして評価を受けた句が、また誰かへと伝えられていく。〈海〉は、多くの人々の生活を奪ってしまったが、やはり多くのものを人々に与えてくれる存在なのだ。海は広いし、大きいのだ。
海は恐ろし海は懐かし今朝の秋 菊田島椿
これは、先の俳句大会にも関わっていた、気仙沼の俳句結社「蛙鳴会」の代表を務めている菊田島椿の句である。「復興いわき海の俳句大会」とは直接的には関係がないが、〈気仙沼―いわき〉という太平洋沿岸の都市が俳句を媒介にして繋がれたことで、日本にとっての〈海〉とは何かという問いを共有する契機が生まれたともいえるだろう。
〈海〉が抱える問題は、漁業、汚染水、マイクロプラスチックなど、多岐にわたっている。俳人のすべきことは、原発や津波という偶発的な出来事から〈海〉を考えることではない。逆に〈海〉そのものを考えるのと「並行して」、原発や津波、あるいは漁業やプラスチックのことを考えていけばいいのだ。そもそも〈海〉は俳人の占有物ではない。そうであれば、いろいろな人をどんどん巻き込めばいいのだ。そうした「社会」とのかかわり方と、先のように直接的に平和や嘆きを17音のなかに窮屈に押し込める方法とでは、果たしてどちらが「対話」を生む効果があるだろうか。
結びにかえて――あらゆる句は震災句である
季語は単なる記号的な「言葉=観念」であると同時に、きわめて身体的な、あるいは情緒的な「言葉=感覚」でもある。根源的な対立は、無季か有季かにあるのではない。そして数の上でいえば、圧倒的に多くの俳人が、後者のような季語観を有している。そのとき、カタストロフ的な〈非日常〉は「邪魔」なものとなる。
だから圧倒的に俳人の多くは、震災も原発も(少なくとも直接的には)詠んでこなかった。積極的に詠もうとしてきたのは、ごくごく一部の人々である。むしろ、生活の上では不安を感じずにはいられないからこそ、俳句という「虚」に逃げ込んだという人も少なくないだろう。ああ、こんなときに俳句があってよかった、と安堵して〈日常〉の「極楽の世界」を満喫した人もたくさんいたはずなのだ。警報のアラームの音に怯えながら暮らしていたころは、とくにそうだった。それも俳句の効用である、と声を大にして行っておかなければならない。これもまた「生き抜くための道具」である。
しかし、いうまでもなく、そのこと自体が責められるべきではない。むしろ、震災や原発をダイレクトに詠むことが、必ずしも真摯であるわけでも偉いわけでもない。本論でとりあげた「海の俳句」を例として、わたしたちは〈震災以後〉の世界のなかで、ひきつづき自然=〈日常〉と向き合って暮らしていなければならないのである。そして、平和のなかに戦争が含まれているように、日常のなかに含まれているものが非日常である。〈日常〉に安住することは、かならずしも現実から目を背けることではない。
牛死せり片眼は蒲公英に触れて 鈴木牛後
かぶとむし地球を損なわずに歩く 宇多喜代子
第64回角川俳句賞受賞した鈴木牛後は、北海道で酪農を営む俳人であり、この句の描く情景も福島とはまったく関係がない。しかし、わたしはこの句で避難区域で野垂れ死していった牛たちの姿を思わずにはいられなかった。ここには震災以前からつづいてきた世界が、震災後のまなざしによって見直されるという事態が起こっているのかもしれない。生の現実は、照井翠のリアリズムと同様に、日常のなかの非日常のありかを教えてくれる。
宇多喜代子の句は震災後に、総合誌に出された東日本大震災のテーマ詠である。この句もまた、震災という一回的な出来事に限定されない普遍的な世界のイメージを読み手にもたらしている。おそらくすでにこの句は、震災という文脈を離れて歩きだしているだろう。季語という日常の世界で、目をこらすこと――それもまた、「愚かな人間」を愛しつつ、破局の予兆を描くことにつながる。その意味では、あらゆる句は震災句であるともいえる。
もちろん、これからも震災をどこかに念頭においた句は、詠まれつづけるだろう。たとえば、震災当時、大学入学を控えた春休みだったという浅川芳直は、直接的に震災を詠むことができなかったが、「10年いろいろ考えて、自分がいまいる場所をちゃんと押さえて詠むことの大切さを学んだ」と語る。浅川は、平成生まれの東北に縁のある若手俳人に声をかけ、同人誌『むじな』を創刊。2017年に生まれたこの雑誌は、今年で第5号を迎える。
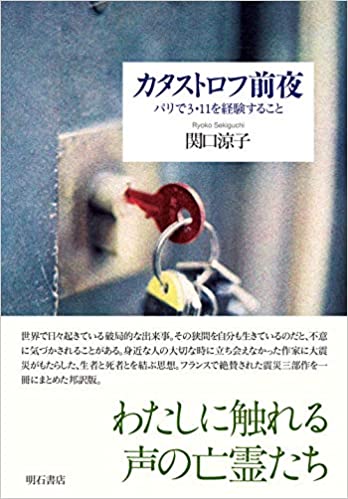
同誌では、東北ゆかりの俳人に目配りをするなど、歴史的にも一枚岩ではない〈東北〉を思考することの意味を投げかけている。〈一本は海に吼えたる黄水仙〉。これは浅川が4号に発表した句。いい句だと思う。いつだって忘れてはならないのは、フランスに住む詩人、関口涼子の言葉だ。わたしたちはつねにカタストロフ「以後」にいるか、そうでなければ、「カタストロフ前夜」にいるのである。
【執筆者プロフィール】
堀切克洋(ほりきり・かつひろ)
1983年生まれ。「銀漢」同人。第一句集『尺蠖の道』にて、第42回俳人協会新人賞。第21回山本健吉評論賞。2020年9月より、ウェブサイト「セクト・ポクリット」を立ち上げる。
【セクト・ポクリット管理人より読者のみなさまへ】