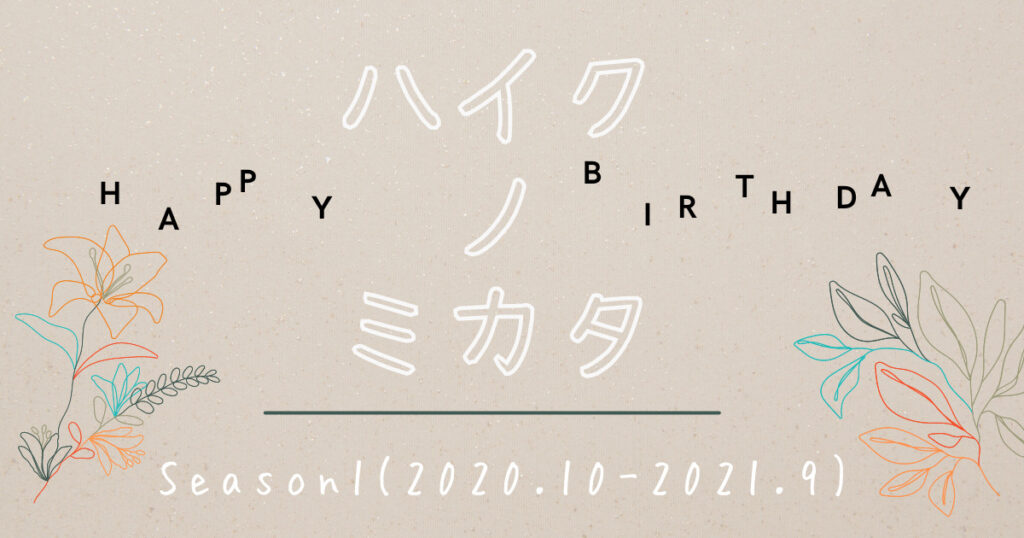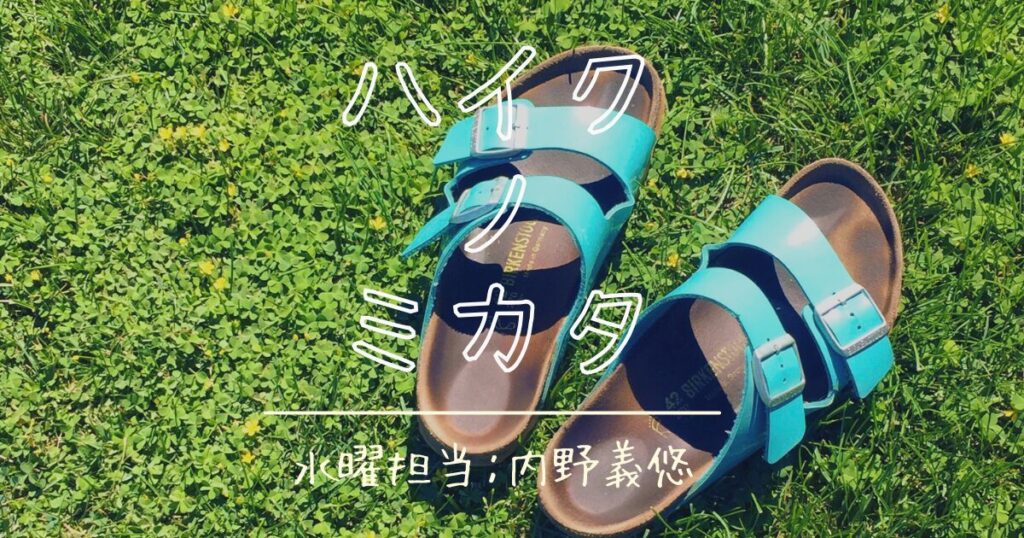
帰省せりシチューで米を食ふ家に
山本たくみ
(天秤第二号『上京』より)
幼少のころから「帰省」というものに憧れがある。
父方の祖父母は隣家に住み、母の実家も隣の隣町だったぼくは帰省先らしい帰省先を持たない子供だった。
それはまだ幼かったぼくにとって一つの旅行機会の喪失でもあったし、お盆の時期の帰省ラッシュのニュースなどで新幹線のホームや空港のロビーでインタビューを受けている家族の子供たちが羨ましくて仕方がなかった。(その頃の反動が、今の放浪癖に繋がっているようにも思える。)
「帰省」という行為は「帰るべき場所」を持った上で、今はそこを離れているからこそ成立するものであり、長い移動を伴うものだ。
そこにはやはり先述したとおり「旅」に通底するものがあるだろうし、一方で目的地が自らが生まれ育った「実家」であるという点において純粋な「旅」とは似て非なるものでもあるだろう。
でも結局、帰省をしたことのないぼくにはその感慨の実際は永遠に理解し得ない。
そんなことを考えている時に、とある「帰省」句に出会った。しかもそれは同じ俳句同人誌の仲間の作品であった。
その句は帰省という行為の本質的感慨をとらえているようにぼくには思えたので、やや手前味噌ではあるが、今回は「俳句同人リブラ」で活動を共にしている句友・山本たくみの俳句を鑑賞してゆきたい。
帰省せりシチューで米を食ふ家に 山本たくみ
リブラが発行している同人誌『天秤』第二号で、新作十句の内の一つとして発表されたのが初出。一読、たくみ句らしいクスッとさせられるユーモアにあふれた句だ。
倒置を用いた句型で、まず帰省の景が大映しになる。完了の「せり」の後に入る軽い切れ。この切れの間に、無事帰省を果たしてほっと一息ついた作中主体の姿が浮かんでくる。
忙しない都会での生活を離れての束の間の安息。懐かしい実家の匂い。少しずつ緊張がほぐれ、いつしか「この家の子としての自分」へと戻ってゆく。
そしてふと思い出す。そういえば最近シチューかけご飯食べてなかったな、と。
どんな家にも一つくらいは、独自に育まれた「文化」や「マイルール」のようなものが根付いているものだろう。
それは外から一見すると奇異な習慣に見えたり、かなりユニークな営みに感じられるかも知れない。しかし、その家で育った人間には極めて自然なことであり、代々受け継がれたその文化こそが、彼/彼女の価値観の礎ともなり得る。
この句の作中主体にとっては「シチューで米を食ふ」行為こそが実家の象徴であり、彼/彼女が飾らない素の自分へ戻るためのトリガーなのだ。
と同時に、作中主体は既にこの家を出て外の世界=社会に身を置いている者でもある。上五で軽く切れたひと呼吸の後に、「この家はシチューで米を食ふ家だったなぁ」と改めて認識しているように感じられるあたりには、この作中主体が実家の文化とそこに育った自分を俯瞰し、少しずつ客観視するようになった様子も垣間見える。
いずれにせよ、実家という「帰るべき場所」の存在は、親から独立しての社会生活というある種の「長い旅」のさなかにある者にとって、唯一安息を得られる宿のベッドのようなものなのだ。
さて、山本たくみという俳人は決して句歴が長いわけでもなく年齢もようやく三十路に足を踏み入れたほどの若さであるが、長い修練を経て習得したようなその諧謔性は、たくみ俳句の大きな魅力であり特徴となっている。
そしてまた彼の俳句には「虚」の要素はさほど多くないのではないかとも思う。
どの句を見ても決して飛躍しすぎることなく、地に足のついた自身の仕事や生活を通して実際に経験したことや目にした景色に、程よい匙加減でユーモアを加えたり或いは引き出してきたりする。
掲句にもその特徴は如実に顕われているが、他にも次のような句になんとも言えないリアリティとおかしみを感じられる。
(筆者注:下記引用句はいずれも連作構成句。鍵括弧内は連作タイトル。)
臨海学校パンツを部屋に忘れけり 山本たくみ 『着席せよ』
薔薇のジャム開けてと避暑の宿の人 同 『のり弁』
どちらもたくみが仕事・プライベート、それぞれの立場で実際に足を運んだ旅の中の一場面だと思われる。
ただ面白がれる俳句というだけではなく、「人間」という生き物をよく見ているなと思う。
「酔ふ人」という連作には昨夏にぼくたちリブラが行った俳句合宿の中での旅吟がいくつか含まれているのだが、この句群を見てもぼくたちがどれだけ観察されて「句材」になっているかが良く分かる。
甘酒やここらで宿を探しつつ 同 『酔ふ人』
東京を軽く貶して夏の湖 同 『酔ふ人』
月涼し隙あらばよき旅と言ひ 同 『酔ふ人』
こうしてみると結局、山本たくみという俳人は誰よりも「人間」が好きなのだろうと思えてくる。
そして、そんな憎めない男が束の間でも「社会生活」という長旅を離れ、帰省してうれしそうに頬張る実家のシチューはまず間違いなく美味しいに決まっているのだ。
(内野義悠)
【執筆者プロフィール】
内野義悠(うちの・ぎゆう)
1988年 埼玉県生まれ。
2018年 作句開始。炎環入会。
2020年 第25回炎環新人賞。炎環同人。
2022年 第6回円錐新鋭作品賞 澤好摩奨励賞。
2023年 同人誌豆の木参加。
第40回兜太現代俳句新人賞 佳作。
第6回俳句四季新人奨励賞。
俳句同人リブラ参加。
2024年 第1回鱗kokera賞。
俳句ネプリ「メグルク」創刊。
炎環同人・リブラ同人・豆の木同人。
俳句ネプリ「メグルク」メンバー。
現代俳句協会会員・俳人協会会員。
馬好き、旅好き。
【2025年5月のハイクノミカタ】
〔5月1日〕天国は歴史ある国しやぼんだま 島田道峻
〔5月2日〕生きてゐて互いに笑ふ涼しさよ 橋爪巨籟
〔5月3日〕ふらここの音の錆びつく夕まぐれ 倉持梨恵
〔5月4日〕春の山からしあわせと今何か言った様だ 平田修
〔5月5日〕いじめると陽炎となる妹よ 仁平勝
〔5月6日〕薄つぺらい虹だ子供をさらふには 土井探花
〔5月7日〕日本の苺ショートを恋しかる 長嶋有
〔5月8日〕おやすみ
〔5月9日〕みじかくて耳にはさみて洗ひ髪 下田實花
〔5月10日〕熔岩の大きく割れて草涼し 中村雅樹
〔5月11日〕逃げの悲しみおぼえ梅くもらせる 平田修
〔5月12日〕死がふたりを分かつまで剝くレタスかな 西原天気
〔5月13日〕姥捨つるたびに螢の指得るも 田中目八
〔5月14日〕青梅の最も青き時の旅 細見綾子
【2025年4月のハイクノミカタ】
〔4月1日〕竹秋の恐竜柄のシャツの母 彌榮浩樹
〔4月2日〕知り合うて別れてゆける春の山 藤原暢子
〔4月3日〕ものの芽や年譜に死後のこと少し 津川絵理子
〔4月4日〕今日何も彼もなにもかも春らしく 稲畑汀子
〔4月5日〕風なくて散り風来れば花吹雪 柴田多鶴子
〔4月6日〕木枯らしや飯を許され沁みている 平田修
〔4月8日〕本当にこの雨の中を行かなくてはだめか パスカ
〔4月9日〕初蝶や働かぬ日と働く日々 西川火尖
〔4月10日〕ヰルスとはお前か俺か怖や春 高橋睦郎
〔4月11日〕自転車がひいてよぎりし春日影 波多野爽波
〔4月12日〕春眠の身の閂を皆外し 上野泰
〔4月15日〕歳時記は要らない目も手も無しで書け 御中虫
〔4月16日〕花仰ぐまた別の町別の朝 坂本宮尾
〔4月17日〕殺さないでください夜どほし桜ちる 中村安伸
〔4月18日〕朝寝して居り電話又鳴つてをり 星野立子
〔4月19日〕蝌蚪一つ落花を押して泳ぐあり 野村泊月
〔4月20日〕人體は穴だ穴だと種を蒔くよ 大石雄介
〔4月22日〕早蕨の袖から袖へ噂めぐり 楠本奇蹄
〔4月23日〕夜間航海たちまち飽きて春の星 青木ともじ
〔4月24日〕次の世は雑木山にて芽吹きたし 池田澄子
〔4月25日〕ゆく春や心に秘めて育つもの 松尾いはほ
〔4月26日〕山鳩の低音開く朝霞 高橋透水
〔4月27日〕ぼく駄馬だけど一応春へ快走中 平田修
〔4月28日〕寄り添うて眠るでもなき胡蝶かな 太祇
〔4月29日〕造形を馬二匹駆け微風あり 超文学宣言
〔4月30日〕春の夢遠くの人に会ひに行く 西山ゆりこ
2020年10月からスタートした「ハイクノミカタ」。【シーズン1】は、月曜=日下野由季→篠崎央子(2021年7月〜)、火曜=鈴木牛後、水曜=月野ぽぽな、木曜=橋本直、金曜=阪西敦子、土曜=太田うさぎ、日曜=小津夜景さんという布陣で毎日、お届けしてきた記録がこちらです↓